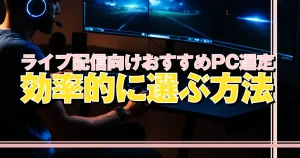Apex Legends向けゲーミングPCを初めて組む人が参考にできる目安

CPUはCore i5世代かRyzen 5で実用的に動くのか
私の実体験を踏まえて率直にお伝えすると、フルHDで遊ぶ分にはCore i5やRyzen 5といったミドルクラスのCPUで十分です。
正直、最初は「もっと高性能なものが必要ではないか」と心配していましたが、実際に使ってみると大きな不満はありませんでした。
あ、意外とこんなもんで大丈夫なんだな、と拍子抜けしたくらいです。
ただし、リフレッシュレートの高いモニタを存分に活かしたい人には事情が違います。
例えば144Hzや240Hzを本当に安定して叩き出したいとなると、CPUの余裕が効いてくるのです。
私は普段から撃ち合いの僅かなタイミングを逃したくないタイプなので、この点は身をもって体感しました。
FPSはわずかなカクつきが勝敗を左右してしまうからこそ、滑らかで安定した映像は何よりも価値があるのです。
一方で、ゲームだけでなく配信や裏作業を重ねるような使い方になると、ミドルクラスCPUでは限界を感じるシーンが増えます。
実際、私は配信をしながら複数のブラウザを立ち上げたときにフレームが揺れるような不安定さに遭遇しました。
その瞬間の感覚は、会社のオンライン会議中に回線が不安定になって声が途切れ途切れになるあの焦燥にそっくりです。
「やばい、持ちこたえられないかも」という嫌な汗をかいたのを覚えています。
快適さと同時作業の両立、これが難しいんですよね。
それでもCore i5やRyzen 5の良さは、扱いやすさにあります。
私は長年PCを組んできましたが、この気楽さに何度も救われました。
特に水冷クーラーのホースでケースの中をゴチャゴチャさせたくない私にとっては、このシンプルさが嬉しい。
動作も安定しているし、設置も手間がかからない。
安心感があります。
ただ忘れてはいけないのは、ApexにおいてCPUはあくまで基盤にすぎないという点です。
主役はGPU。
結局のところ、CPU以上にグラフィックカードの性能が快適性を左右します。
私自身、GPUに優先的に投資したほうが結果として満足度が高かったという経験を何度もしています。
だからCPU選びは舞台裏に近い感覚。
つまり裏方のさじ加減で全体の調和が決まるわけです。
その象徴的な出来事が、RTX 5070とCore i5の組み合わせでプレイしたときでした。
フルHD環境で平均180fpsを維持し、配信をしなければ十分すぎるくらいでした。
しかし同じGPUをRyzen 7と組み合わせて試した際、フレームが200を超えて操作感が目に見えて滑らかになったんです。
射撃訓練場での照準の追従が段違いでした。
「なるほど、ここまで差が出るのか」と思わず唸りました。
ではその差に価値を感じるかどうか――これはプレイヤーそれぞれの価値観に委ねられる部分です。
コスト面で考えると、やはりミドルクラスCPUの魅力は大きいです。
ApexはCPUの進化にそこまで依存していないため、わざわざ高価なCPUを選ばなくても快適に遊べる。
社会人の私にとって、このコストバランスは本当にありがたいと感じています。
給与や家庭の予算をやり繰りするリアルな生活の中で、ゲームにすべてを費やすわけにはいきません。
だから「必要十分」という言葉がしっくりくるんです。
現実的な判断ですね。
その一方で、数年先を考えるなら悩みは深くなります。
新しいゲームやアップデートがどういうCPU性能を要求してくるかは読めません。
私はそう考えて、時に余裕を持った構成を選んだことがあります。
未来への備えという意味で、上位CPUは安心材料です。
でもApexのみに集中するなら、Ryzen 5で十分戦えるのも事実。
この選択は未来志向か、今志向か。
突き詰めればその分かれ道なんです。
最終的に私の答えは「Apexを快適に楽しむだけならCore i5やRyzen 5で十分。
でも配信や複数作業も同時に安定させたいなら上位CPUを選んでおいたほうがいい」になります。
つまり、自分の生活スタイルや優先順位に照らして選択するしかないのです。
私は「自分の余裕」と「PCの余裕」を重ね合わせて判断してきました。
そのおかげで、構成を決めるたびに納得のいく選択になりました。
後悔しない決断。
これが、私が伝えたい一番のポイントです。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 42923 | 2462 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42678 | 2266 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 41712 | 2257 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41007 | 2355 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38483 | 2075 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38407 | 2046 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37176 | 2353 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37176 | 2353 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35552 | 2194 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35411 | 2232 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33667 | 2205 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32811 | 2235 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32445 | 2099 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32334 | 2190 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29174 | 2037 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28462 | 2153 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28462 | 2153 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25380 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25380 | 2172 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23022 | 2209 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23010 | 2089 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20797 | 1857 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19452 | 1935 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17682 | 1814 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16001 | 1776 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15246 | 1979 | 公式 | 価格 |
グラボはRTX 3060 TiとRX 6700 XT、扱いやすさで選ぶなら?
グラフィックボードを勧める場面で、私が最終的に人に選んでほしいと思うのはRTX4060 Tiです。
理由はとても単純で、安定して長く使えることが自分の生活と相性が良いからです。
性能の高さだけではなく、機材に触れるたびに余計な不安を感じずにすむ安心感が、年齢を重ねるごとにどれほど大切かを実感しています。
実際、このボードでプレイしているときには心が落ち着きます。
最新のアップデート後も動作が不安定になることがほとんどなく、ゲームを始める時点で「今日は調子はどうかな」と余計な心配をする必要がありません。
日々の仕事が忙しく、せっかく確保できた数時間をゲームに充てるときに、予期せぬトラブルで気持ちを削られるのは想像以上に負担になるのです。
今日は純粋に楽しもうと思っているときほど、安定感が全てを左右する。
もちろん、RX 7700 XTも優秀なカードであることは確かです。
WQHD環境でも高めの画質設定がしっかり動き、映像の表現は実に豊かです。
私自身、一時期このカードを使っていましたが、夜中に大きなモニターで美しい景色を映した瞬間、思わず声に出して「これはすごい」と言ったこともあります。
12GBのVRAMが示す余裕はやはり頼もしく、画質にこだわりたい人にとっては強い武器になるはずです。
それでも、困った思いをしたこともありました。
ある更新直後のことですが、数日間フレームレートが不安定で、楽しみにしていた休日の時間がどこか満たされない感覚に終わってしまったのです。
冷静に考えれば一時的な問題に過ぎません。
ですが限られた自由時間で心置きなく遊びたいと思っている時に、微妙な違和感が続くのは予想以上にストレスになるんです。
この気持ちは、若い頃なら「まあそのうち直るさ」と笑って流せたかもしれません。
でも今は違う。
だからこそ、RTX4060 Tiに戻したときに感じた静かな安心感は忘れられません。
最新機種と比べれば確かに性能的には一歩劣ります。
でもDLSSによるフレーム補完が効いて、戦いの一瞬に助けられることが少なくないのです。
仕事帰りの短時間のプレイでも、気持ちを切り替えて集中できる。
この違いは本当に大きい。
価格についても一言触れたいと思います。
RX 7700 XTは時折お買い得に販売されることがあり、私自身「これで十分かな」と心が揺らいだ頃もありました。
数千円、数万円の価格差は確かに魅力です。
しかし今振り返ると、それ以上に大切なのは毎度安定して動いてくれることでした。
安く済ませたのに後で悩むくらいなら、少し余裕を持たせて安心感を優先する方が、結局は心地よい日々に繋がるのだと身をもって学びました。
もちろん誤解しないでほしいのですが、RX 7700 XTが悪い製品というつもりは全くありません。
じっくり映像を楽しみたい人にとっては最高の相棒になるでしょう。
例えばストーリー性が強いタイトルや、広大な景色を眺めながら歩くタイプのゲームなら、このカードでしか得られない豊かさがあります。
ただし私の場合、例えばApexのように勝敗がはっきり分かれるタイトルを遊ぶときには、一瞬の判断のために安定性を最優先に考えたい。
そうなるとやはり選びたいのは3060 Tiなんです。
派手な映像や高画質の演出も素晴らしいですが、結局のところ勝ち負けの瞬間を支えてくれる環境の方が今の自分には大切だと考えています。
つまり、選択の基準は「安定感を重視するか」「映像の鮮やかさを重視するか」。
それだけです。
私は前者を選びました。
だからRTX4060 Tiを勧める。
実際に生活の中で小さな安心を積み重ねていくと、大げさに聞こえるかもしれませんが気持ちの余裕まで違ってきます。
趣味の時間は短い。
RTXに手を伸ばす。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 48533 | 101751 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32047 | 77933 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30055 | 66640 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 29978 | 73293 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27075 | 68805 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26420 | 60131 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 21879 | 56698 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19855 | 50392 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16507 | 39301 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 15942 | 38131 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15805 | 37909 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14592 | 34857 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13699 | 30804 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13160 | 32303 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10787 | 31685 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10617 | 28534 | 115W | 公式 | 価格 |
初心者がつまずきやすいパーツ同士の相性問題
私はこれまで何台も自作してきましたが、若いころはその重要性を甘く見て、何度も痛い思いをしました。
電源ボタンを押しても画面が真っ暗のまま、途方に暮れたあの瞬間は今でも鮮明に覚えています。
「あぁ、やってしまったな」と膝から崩れ落ちたことがあります。
その体験以降、私は必ず最初に相性を疑うようになりました。
それほど根深く学ばされた出来事だったからです。
特にCPUとマザーボードの組み合わせは、どうやっても避けられない最初の課題だと思います。
新しいCPUが出るたびにソケットやチップセットが変わり、何も考えずに差し込んでも当然動いてくれません。
私は何年か前に、最新のRyzenを手に入れて意気揚々と作業を始めたのですが、マザーボードが古い世代で完全に非対応でした。
返品や買い替えで数日を無駄にし、余計なお金まで失い、心の中では「なんで最初に確認しなかったんだろう」と自分を責めました。
だから今では、CPUとマザーを真っ先に調べることが、自作の第一歩だと思っています。
メモリも落とし穴が多いんです。
DDR5が登場して選択肢が広がったのはいいのですが、速度や容量ばかりを見て買ってしまうと、マザーボードが対応していないという事態に簡単につながります。
私は一度、そのせいで丸一日無駄にしました。
買ったばかりのメモリがどうしても認識されず、何度も抜き差しして試したり、ネット掲示板を読み漁ったり…。
「あぁ、俺はまだまだ浅はかだな」と苦々しい気持ちになったのを覚えています。
転ばぬ先の杖、です。
グラフィックボードの大きさ問題も見過ごせません。
最近のハイエンドGPUはとにかく巨大で、カタログスペックをにらんで「性能は十分」と考えていても、いざケースに入れようとすると物理的に入らないことがあるんです。
私も実際にそれをやらかしました。
RTXを差し込もうと手を伸ばしたら、あと数センチでつかえるという残酷な現実。
結局ケースを買い替え、開封したばかりのケースを泣く泣く倉庫にしまうハメになりました。
だからこそいまはケースの対応サイズを必ず確認しています。
地味ですが、意外と一番効果的なんです。
冷却パーツでも似たような過ちを繰り返しました。
背の高い空冷クーラーを選んでみたけれど、ケースの天井にぶつかってしまい、フタが閉まらない。
あの瞬間の徒労感といったら…。
水冷クーラーではチューブの取り回しが厄介で、閉じようとしたサイドパネルがどうしても閉まらず断念しました。
やっぱり「入らないものは入らない」という現実には勝てません。
冷却性能だけではなく「設置できるか」が最重要だと私は何度も思い知りました。
冷却を軽んじると、ゲーム中に突然フリーズしますからね。
あれは本当に腹が立つんです。
ストレージに関しても意外な壁があります。
高速なPCIe Gen.5 SSDは確かに心躍る性能ですが、発熱がすさまじく、専用ヒートシンクが必須になります。
そのヒートシンクが、グラフィックボードと干渉してしまい、結局組み立てを断念したことがありました。
あの時はさすがに声をあげてため息をついてしまいましたね。
結局私はGen.4のSSDを使っています。
十分すぎる速度だと思うし、安定性の安心感の方が大事です。
性能の高いパーツを搭載したにも関わらず、電源容量を削る人が意外と多い。
でも、それは本当に怖い落とし穴だと思います。
私も600Wの電源で強引に組んで試合中、まさかの電源落ち。
二度と味わいたくない失敗です。
それ以来、私は電源容量にやや余裕を持たせるよう心掛けています。
「ここでケチるのは違う」と今は声を大にして言いたいです。
紙の上では完璧な構成に見えても、実際に組んでみると干渉や冷却不足、電源容量不足など現実の壁はいくらでも出てくる。
それを経験して初めて「自作の難しさと奥深さ」が身に沁みます。
私はBTOパソコンにも随分助けられました。
その一方で、自作をする楽しみも確実にあります。
自由に構成を考え、思い描いた通りの一台を自分の手で完成させる。
その達成感は格別です。
ただ裏を返せば、それは大量の相性チェックに膨大な時間を費やす作業であり、煩わしくも愛おしい工程でもあるんです。
では、どうすれば失敗を減らせるか。
CPUとマザーボードの組み合わせを確認すること、メモリは必ず対応リストを調べること、グラフィックボードとケースのサイズを把握すること、冷却パーツが収まる設計を選ぶこと、発熱しやすいストレージの干渉を避けること、そして電源に余裕を持たせること。
私は過去の失敗からこれを学び、何度も繰り返すうちに確信しました。
必要なのは派手な技術ではなく、地味な確認作業なんだと。
だから私が伝えたいのは、自作の魅力を味わいながらも、最低限この六つだけは絶対に抑えるということです。
これを守れば、大きな失敗はかなり減らせるはずです。
あなたのゲーム体験が中断されることなく、思う存分楽しめる一台になる。
そのとききっと、自分だけのPCを完成させた誇らしさを感じられる。
Apex Legendsを快適に動かすために意識したいPC性能のバランス

メモリは16GBで足りるか、それとも32GBにした方が安心か
Apex Legendsを本気で楽しもうと考えるなら、私の経験からすれば32GBのメモリを選ぶ方が安心できると思います。
正直、16GBでも動くには動くんです。
しかし一日の仕事を終えてホッとした瞬間、ゲームを立ち上げている裏でDiscordやブラウザを開くこともありますよね。
そんなときに少しでも遅延やもたつきを感じてしまうと、せっかくの日常のリフレッシュが小さなストレスに変わってしまう。
だから私は32GBを推します。
その頃は「まあ十分だろう」と思っていたのですが、いざ試合中にマップの読み込みで引っかかりを感じたり、ウィンドウを切り替えるたびに数秒のタイムラグが出たりして、地味に気持ちの中で積もっていったんです。
ちょっとしたことなんですが、「またか…」とため息が出る。
それが積み重なることで、楽しさに影がさしてしまいました。
ところが32GBに換装した瞬間、別物のように軽快に動いてくれるんですよ。
マップの切り替わりもスムーズだし、バックグラウンドで音声通話を続けながらでも気にせず戦える。
自分でも思わず「これだよ、これ!」と声が出たのを覚えています。
最近のゲーム環境を考えると、もう16GBでは余裕が足りない場面が増えています。
OSやアプリケーションが平然とメモリを食い潰すなかで、ゲーム専用に割ける領域はどんどん圧迫されます。
私のようにメールやスプレッドシートを横に開きながら遊ぶ習慣がある人は特に顕著です。
タスクを切り替えるたびに「カクッ」とするあの感覚、仕事中のPCフリーズと似たような居心地の悪さを覚えるんです。
本気で嫌になりますよね。
ただし、Apexだけを起動し、映像設定をほどほどにして純粋に撃ち合いを楽しむなら16GBでも成立します。
実際に私の後輩もその環境で何の不満もなく遊んでいます。
やはり余裕がある方が、集中できる時間が多くなる。
だから勧めるとしたら32GB。
これはもう自然な流れです。
特に印象的だったのは、新しいDDR5メモリに替えたときのことです。
G.SkillのDDR5-5600を試しに導入してみたら、数値以上の変化がありました。
フレームレートやロード時間より何より、プレイ中の「もたつき感」がなくなる。
この差に私は素直に驚かされました。
もちろんGPUやCPUに予算を回したい気持ちも理解できます。
私も散々そう考えました。
でもパーツは結局バランスです。
今後のApexはさらに重くなるはずです。
新しいテクスチャや要素が次々と増え、求められるリソースは大きくなるばかりです。
友人が最近eスポーツの大会に参加したのですが、彼の話では「32GBはもはや標準」になってきているとのことでした。
それを聞いたときに私は確信しました。
メモリは単なる部品ではなく、快適に遊ぶための大切なインフラなんだと。
まるで空調やネット回線のように、裏で働いて環境を支えてくれる不可欠な存在です。
増設が簡単だと思う人もいますが、実際はそうでもありません。
私の知人は16GBから増設しようとした際に同じ型番が市場からなくなっていて、仕方なく全て買い直す羽目になりました。
だからこそ、最初から32GBにしておけば安心なんです。
これは仕事で使う道具と同じ。
最初に少し背伸びしてでも、後々後悔しない選択をしておいた方がいいのです。
16GBと32GBの大きな違いは、数字以上に「気持ちの余裕」です。
私は16GBで「まあ動くけど少し心配」と思いながら遊んでいました。
でも32GBでは「よし、安心して全力で楽しめる」と胸を張れる。
この差は精神的にも大きいんですよ。
仕事を終えて一息つき、電源を入れるときに「今日は大丈夫かな」と考えなくていい。
あの安心感は本当に価値があるんです。
コストを抑えて最低限の環境で走り出すのも立派なスタートです。
でも長期的にストレスなく遊びたい人、配信や録画を考えている人、あるいは他の作業と並行したい人には、私は強く32GBを推したい。
余裕を持つことで得られる安心、その時間は何物にも代えがたいです。
安心感。
信頼性。
この二つを得られるからこそ、私は32GBを選ぶべきだと確信しています。
未来を見据えて快適な時間を担保したいのなら、間違いなくその方が賢い選択だと胸を張って言えるのです。
SSDはGen4対応が主流になりつつある?容量は1TBか2TBか
SSDを選ぶ際に私が強く伝えたいのは、ゲームを快適に楽しむためには「Gen4対応の2TB」を選ぶのが一番確実だということです。
数字や理論的な比較だけではピンとこないかもしれませんが、実際に使ってみると体感が違いすぎて、もう以前の環境には戻れないと痛感します。
だからこそ、容量が中途半端だったり、意味のないほどに高性能なものを盲目的に選ぶよりも、堅実で現実的な選択をすることが大切だと強調したいのです。
今の市場を見渡すと、PCIe Gen4 SSDはすでにしっかりと標準の位置を占めています。
BTOパソコンを探してもほとんどのモデルにGen4が搭載されていますし、実際にゲームを起動するとロードの短さに確かな違いを感じることができます。
ロードで待つ間にスマホを手に取る余裕すら消えてしまった、そう言えるくらいに。
これはあらゆる説明を超えたリアルな体験なんです。
例えばApex Legendsだけを考えれば1TBでも余裕があるように思えますが、アップデートでどんどん肥大化して100GBを軽く超えてくる。
そこへ別のタイトルや配信ソフト、チャットツールなどを入れていくと、1TBなんて瞬く間に埋まります。
そうなったときの「また整理しないと」という気持ちの重さは、正直かなりのストレス。
これが積み重なると、本来楽しむはずの時間が小さな容量管理の葛藤に取って代わられてしまいます。
私は過去に1TBで何とかやりくりしていた時期がありましたが、新作のゲームを2つ入れるだけで、すぐに綱渡りのような状態になりました。
朝起きたらゲームの再インストールがまだ終わっていない、なんて経験も一度や二度ではありません。
大げさではなく、ゲームそのものよりも「容量のやりくり」が主役になってしまうんです。
耐えられない。
その状況を変えるきっかけが2TBへの移行でした。
これが本当に大きな転機でしたね。
余裕のあるストレージを使い始めると、わざわざ削除や移行を考える必要がなくなり、新作タイトルを躊躇なくインストールできる。
わかりやすく言えば解放感です。
このひとことに尽きます。
もちろん今では性能面でさらに先を行くGen5も存在しています。
確かに動画編集や大容量データを日常的に扱う仕事をしている人にとっては強力な武器です。
発熱やファンなどの冷却問題も増え、価格も跳ね上がる以上、現状では実用性よりも話題先行の存在に感じられます。
だからこそ、現時点での最適解はあくまでGen4であり、ゲームに限れば迷わずそこに落ち着くのが自然だと思うのです。
ここで忘れてはいけないのが「余白」という考え方です。
SSDの容量がパンパンの状態でアップデートしようとすると、途中で止まってしまったり、再インストールを余儀なくされたりする。
そのときに背中に流れる冷や汗ときたら、もう二度と体験したくないものです。
中途半端な選択はアップデートのたびに余計な手間とイライラを増やしてしまう。
ゲームの楽しさは削がれ、気づいたら「また整理か…」と毎回ため息をつく羽目になるのです。
1TBでは無理があり、Gen5はコストも発熱もまだまだハードルが高すぎる。
だから現実的かつ快適に遊ぶための最適解は、間違いなくGen4の2TBだと断言できます。
これは机上の論理ではなく、自分が何度も経験して学んだことです。
使っていて気づくのは、容量に余裕があると気持ちまで余裕が生まれるということです。
予想以上の安心感が、日々の選択を軽くしてくれる。
急に新しいゲームを入れてみようかなと思えるし、配信に必要なソフトも余計な手間なく入れられる。
「よし、やってみるか」と自然に思えるようになる。
実はそのポジティブさこそ、ゲーム環境に投資する本当の意味なのではないでしょうか。
性能の高さや価格の安さだけに飛びつくのではなく、長期的に安定して楽しめる環境を選ぶ。
これが何より大切です。
仕事に追われ、家庭のことも背負いながら楽しみを大切にしている私たち大人にとっては、安心して続けられる選択こそがコストを減らす近道になる。
だから私は胸を張って言います。
Apexを長く快適にプレイしたければ、SSDはGen4の2TB。
ただそれだけで容量不足のイライラも、オーバースペックによる出費も避けられる。
経験から断言できます。
心に余白。
安心の快適。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R65V

| 【ZEFT R65V スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7800X3D 8コア/16スレッド 5.00GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R66A

| 【ZEFT R66A スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 8500G 6コア/12スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
| ケース | DeepCool CH170 PLUS Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60XV

| 【ZEFT R60XV スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850I Lightning WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60GU

| 【ZEFT R60GU スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R44CG

高速な実行力で極限のゲーム体験を支えるゲーミングモデル
直感的プレイが可能、16GBメモリと1TB SSDでゲームも作業もスムーズに
コンパクトなキューブケースで場所を取らず、スタイリッシュなホワイトが魅力
Ryzen 9 7900X搭載で、臨場感あふれるゲームプレイを実現
| 【ZEFT R44CG スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 7900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット MSI製 PRO B650M-A WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
冷却は空冷で十分か、それとも簡易水冷を選んだほうが安定するか
Apex LegendsをプレイするPCをどう整えるかを考えると、やはり冷却の話は避けられません。
私がこれまで実際に試してきた中で言えるのは、ゲームを軽快に楽しみたいなら冷却方式の選択は最初から真剣に考えた方がいいということです。
空冷で十分な場面も確かに多いのですが、より高い解像度やフレームレートを長時間維持したいなら水冷を選んだほうが安心できると感じています。
これは私自身が空冷と水冷の両方を経験したからこそ言える実感です。
空冷の魅力はシンプルさと安心感にあります。
実際、以前私はCore Ultra 7を空冷で動かしていました。
通常の作業や軽めのゲームプレイではまったく不満はなく、安定した運用ができていました。
ただ、真夏の夜にランクマッチを延々と回しているとき、ファンの音が「ブォーッ」と鳴り続けて集中力をじわじわ削がれる瞬間がありました。
小さなことかもしれませんが、いざという場面で気持ちを乱す。
これが地味にストレスになるのです。
思い切って240mmクラスの簡易水冷に切り替えたときの衝撃は忘れられません。
温度が10℃近く下がり、ファンの回転も穏やかになって部屋の空気まで落ち着いたように感じました。
「もっと早く変えておけばよかったな」と正直に思いました。
冷却の質が変わると、体験そのものが変わります。
静かな環境に包まれたとき、私はようやくゲームそのものに没頭できるようになりました。
もちろん空冷にも強みはあります。
大きなヒートシンクを備えたモデルは高い安定性を誇り、メンテナンスも楽です。
コストパフォーマンスを考えるならやはり空冷に勝るものはないと納得する人も多いでしょう。
最近のCPUは発熱が抑えられてきたこともあり、少し前より空冷で十分まかなえるシーンも増えてきています。
この変化は歓迎したい部分です。
一方で水冷の効果は冷却性能だけにとどまりません。
ケース内部のエアフローが改善され、構造的に整った印象が出ます。
しかも結果としてGPUの温度まで下がり、PC全体の安定性が底上げされる。
Apexのように一戦一戦が集中力を要するゲームでは、この違いが馬鹿になりません。
長丁場を戦い抜く力につながります。
ただ、気になるのはポンプの音です。
人によっては「ジーッ」とかすかな音が気に障る場合もあります。
そして大きな不安として残るのは寿命です。
あるとき私は、「本当に長く使えるのだろうか…」と心配になりました。
ただ、最近はメーカーも耐久性の改善に力を入れており、5年以上安定動作可能と公表する製品も珍しくありません。
知人が使っているNZXTの280mm簡易水冷も、すでに3年を超えて安定しています。
トラブルもなく「技術の進歩ってすごいな」と素直に思わされます。
冷却を軽く見ると、いつかしっぺ返しを食らいます。
あの瞬間は「やっぱり熱のせいだな」と苦笑しつつも悔しさが残ります。
どんなにストレージやメモリに投資しても、冷却がボトルネックでは活用しきれません。
だから冷却は見た目のオプションではなく、PC体験の土台だと私は感じます。
本当に土台なんです。
冷却方法の選び方はシンプルです。
フルHDでプレイするなら空冷で十分。
それが明確に言える指針です。
性能を引き出しつつ快適に続けるためには避けて通れない判断になります。
そして私は、軽く遊ぶなら空冷、本気でやるなら水冷。
そう心の中で線を引いています。
静かな環境。
集中できる時間。
どちらもゲームに没頭する上で欠かせない要素です。
自分が何を求めているのかによってベストな冷却方式は変わります。
普段のスタイルを振り返り、「自分はどんな遊び方をしたいのか?」と問いかけてみるのが第一歩です。
Apex Legendsをプレイしながら配信する人向けPCの考え方

録画や配信作業に必要なCPUの性能目安
私はこれまで何度か試行錯誤を重ねてきましたが、GPUひとつが強力でも、同時配信を始めるとCPUの限界が一気に露呈します。
瞬間的に映像がカクついて、観ている人の体験を壊してしまう。
あの瞬間の冷や汗は今でもよく覚えています。
正直、8コア16スレッドをひとつの基準にして選ぶのが現実的だと思っています。
普段のApexは意外に軽快です。
最新のCPUなら驚くほど滑らかに動きますからね。
ただ問題は配信ソフトが裏で常に動き、しかもエンコードし続けていることなんです。
シーン切り替えやエフェクトを追加した瞬間に負荷が高まり、「うわ、やってしまったな」と感じたことが何度もありました。
自分のプレイ画面は違和感がなくても、配信を見た人から「カクついていたよ」と言われると、胸に刺さるんです。
このギャップが厄介極まりない。
結局のところ、力のあるCPUを最初から選ぶしかないんですよね。
昔、Core Ultra 5のクラスを使ったことがありました。
フレームレートは140fps前後で快適そのものだったのに、録画を同時に開始すると配信のアーカイブに落ち込みが見られたんです。
GPUのNVENCに仕事を振っても、CPU負担はゼロにはならない。
そこで痛感しました。
「CPUは余裕を買うものなんだ」と。
挑戦する前は過剰投資に思えましたが、実際に体験してみたら考え方が一変しました。
苦い学びでしたよ、本当に。
最近16スレッド以上のCPUを触る機会があったのですが、あれは別次元でした。
配信を流しつつDiscordで仲間と通話し、録画をつけても微動だにしないフレームレート。
安堵。
それ以上の言葉は要りませんでした。
ただし注意点もあります。
単純にスレッド数だけ増えても十分ではありません。
16スレッドでもクロックが低ければ、結局エンコード時に遅延が起こるのです。
数と速さ、その両輪が必要。
どちらかを犠牲にすると、すぐに限界にぶつかります。
私は何度も「もう少し上のモデルにしておけば」と地団駄を踏んできました。
現実は厳しいものです。
そうなると、ただの配信では済まなくなります。
私も会議配信の場で処理が滞り、一瞬の音声遅延に「ラグってる」と視聴者に指摘された経験が忘れられません。
CPUの余裕が信頼に直結する。
これは企業でも個人でもまったく同じです。
信頼を欠いた瞬間、努力が台無しになるのです。
選ぶなら安全圏はCore Ultra 7 265Kあたり、あるいはRyzen 7 9800X3D以上。
やはりこのクラスのCPUは安心感が段違いです。
一方で録画をせず遊ぶだけならCore Ultra 5やRyzen 5でもやっていけます。
ただ、配信も同時にするなら明らかに不足します。
せっかくの高画質配信が「惜しかったね」で終わってしまう。
もったいないにもほどがあります。
私はそこに妥協はしないべきだと考えています。
私の実感を言えば、配信や録画も意識するなら8コア16スレッド以上で、しかもクロック性能もしっかり備えたCPU以外に選択肢はありません。
間違いない、と断言したい。
余力のあるCPUは快適な体験そのものですし、買い直しは結局コストも倍増します。
長期的な視点で考えるなら、最初から安定性を備えたCPUを選ぶべきだと強く思います。
「あのとき勇気を出して上のクラスにしておけば」と、何度呟いたか分かりません。
同じ失敗をしてほしくない。
年齢を重ねたいま、体験から学んだ確かな気持ちです。
贅沢ではなく堅実な選択。
それがCPUへの投資です。
だからこそ私は声を大にして言いたいのです。
配信や録画を考えているなら、どうかCPUだけは妥協しないでください。
そのための選択肢です。
高fps配信に適したグラフィックカードの候補
この思いを実現するには、間違いなくグラフィックカードの選び方が肝になります。
映像はカクつく、操作は遅延する。
真剣勝負の場面でラグが発生したときの悔しさは、本当に胃の底にずしんと響きました。
だからこそ、ここでは妥協できない。
私は自分自身の経験からそう強く感じています。
高fps配信を支えるGPUには明確な選択肢が存在します。
ひとつはNVIDIAのGeForce RTX 5070や5070Tiといった最新世代のモデル。
これらはDLSS 4やReflex 2といった先進機能を武器に、応答性をしっかり底上げしてくれる頼もしさがあります。
もう一つはAMDのRadeon RX 9070XT。
こちらはFSR4を軸にAIアクセラレーションを活かすアプローチで、以前は「配信するならNVIDIA一択」とまで言われていた差をかなり縮めてきました。
実際、ここ1、2年のAMDの進化は目を見張るものがあり、重たいシーンでも安定して動作することが増えてきたんです。
昔のイメージで見下していると、痛い目を見るかもしれません。
ただ、ベンチマークや数値よりも大切なのは「安定感」だと私は思います。
配信ソフトとApexという重量級のゲームを同時に動かすとfpsはどうしても揺れます。
そこをいかに制御できるかが重要で、結果として長時間安定して動いてくれるカードこそ一緒に戦える相棒になる。
私がGeForce RTX 5070Tiを評価しているのは、まさにそこです。
追加されたハードウェアエンコード機能はもう実用レベルにまで来ていて、OBSとの相性も抜群。
一度その安心感を味わうと、後戻りしたくなくなるんです。
とはいえ、コストを軽視するわけにはいきません。
そこに光るのがRadeon RX 9060XTです。
でもドライバ更新が頻繁に行われ、改善が日々見える。
価格と性能のバランス感覚はまるで若手が思い切ってレギュラーを狙っていくような勢いがあって、「おっ、このカードやるな」と思わず唸る瞬間があります。
私は何度も実機で触れましたが、堅実さと意欲を兼ね備えたカードという印象を強く持っています。
つまり、費用を重視する場面ならこの選択肢は決して悪くないんです。
それと忘れてはいけないのがメモリ容量とバス幅の問題です。
Apexというゲームは見た目以上にVRAMを消費します。
12GBは最低ライン、できれば16GB欲しい。
これは私が痛感した部分です。
以前、8GBのカードで3時間配信したとき、後半にfpsが急落しました。
だから、容量には妥協しない。
さらに冷却も見逃せません。
どれだけ高性能なカードでも熱暴走すれば一気にパフォーマンスが下がります。
クロックダウンした瞬間にfpsが落ち込み、快適さは台無しです。
熱が逃げきれず、せっかく買ったカードの性能を半分も活かせなかった。
あのときの虚しさを覚えているからこそ、消費電力と冷却設計を必ず一緒に考えるようになりました。
ここは絶対甘く見ちゃいけない。
私はそう強く言いたい。
最終的に私の考えを整理すると、高fpsも配信の快適さも両立させたいならGeForce RTX 5070Tiが鉄板です。
そして費用をさらに抑えたいならRadeon RX 9060XT。
実際、候補はこの三枚で十分だと思っています。
他を検討する理由はあまり見当たりません。
ある意味、とてもシンプルな選び方に落ち着きますね。
配信の質を上げ、同時に自分自身も快適にゲームを楽しみたいなら、回り道を避けることが近道になります。
5070TiかRadeonか。
この二択に集約されるのは決して大げさではありません。
悩みに悩んで出した私の結論でもあり、実際に試行錯誤してきた末の答えなんです。
だから、これから挑戦する人にも伝えたいのはただひとつ。
ゲームと配信は楽しむためのもの。
そう願っています。
自分らしさを出せる配信環境。
これがやっぱり大事なんです。
安心感。
私が本当に求めてきたものはそこでした。
録画データ保存はHDDよりSSDのほうが快適?
配信を快適に続けたいと考えると、やはり録画データの保存先はHDDではなくSSDにすべきだと私は強く思っています。
正直に言えば、私自身も最初の頃はコストを優先して大容量のHDDを使っていました。
当時は「容量さえあれば大丈夫だろう」と安易に考えていたのですが、いざ実際に配信をしてみると、映像がカクついたり音声が途切れたりして、そのたびに冷や汗をかきました。
視聴者にとってどう映っているのかを思うだけで気持ちが沈み、配信の楽しさがどこか半減していたように思います。
その経験から、SSDを使うことの意味を深く理解しました。
SSDの大きな強みは、やはり処理が驚くほどスムーズに進むことです。
HDDは内部の物理的な構造上、どうしてもシークタイムや断片化の影響を受けてしまい、結果として録画や配信に支障が出ます。
特に高解像度で高ビットレートの録画を重ねると、HDDではコマ落ちや引っかかりが頻発し、ストレスの原因になります。
そのたびに「またか」とため息をつく日々でしたが、SSDに切り替えてからはその悩みが一掃されました。
処理の速さと安定感は段違いです。
導入のとき、正直なところ「本当に値段分の差があるのか」と半信半疑でした。
しかし一度NVMe SSDを使ってみると、その快適さに驚かされました。
録画ファイルが積み重なっていってもゲームが重くなる感覚はなくなるし、配信中の小さなカクつきすら消えたのです。
「これだ」と。
もちろん、HDDが無価値になったわけではありません。
むしろバックアップやアーカイブのためには欠かせない存在です。
容量単価ではHDDに軍配が上がるのも事実です。
ですが少なくとも「配信を楽しみながら録画をスムーズに続けたい」という観点でいえば、HDD一本で臨むのは無謀だと痛感しました。
私は現在、録画データをまずSSDに保存し、後日まとめてHDDに移すようにしています。
これなら不安も減り、精神的に非常に楽です。
今ではPCIe Gen.4対応のSSDが普及し、価格も随分と下がってきています。
性能面の差は明らかですし、昔のように導入コストが高すぎるという印象もなくなりました。
2TBクラスのSSDがあれば1か月以上の録画データを余裕でカバーできますし、その後HDDへ移せば長期保存の問題も解消されます。
そのうえゲーム自体の読み込みも劇的に速くなり、再インストール時の待ち時間すら気にならなくなりました。
体感してしまうと「もう戻れない」と思いますよ、本当に。
一点だけ気をつけるとすれば、SSDは負荷が高まったときに発熱をしやすいことです。
ただしこれはヒートシンクを付けたりケース内のエアフローを工夫したりするだけで簡単に解決できます。
私自身、録画専用のSSDをOSから分けて設置していますが、この構成に切り替えてからは一切不満を感じていません。
それどころか余裕すらあり、配信中の安定性が以前とは比べものにならないほど高まりました。
大げさではなく「安心感がある」というのはこのことだと思います。
HDDは同時に複数の処理をすると速度が落ちてしまうのは避けられません。
結果として、ゲームと録画を同時にこなしても支障が出ないのです。
安定。
結局これ以上に大切なものはないのかもしれません。
さらに最近はBTOパソコンでもオプションで録画用SSDを簡単に追加できます。
自作に自信がない人でもショップ構成を選ぶだけで配信に適した環境を揃えられるわけで、この手軽さは魅力的です。
私も実際にBTOを利用しましたが、大きな手間をかけずに最適解を選べたのはいい体験でした。
「最初からこうすれば良かったな」と心から思います。
一方で、「大容量のHDDがないと不安」という気持ちも分かります。
長くパソコンを使ってきた人間として、それはごく自然な考えです。
ただ、配信用にSSD、保存用にHDDと明確に役割を分けるやり方を知れば、その不安も不思議と消えていくはずです。
役割を切り分けることでトラブル発生時の対応も早くなるし、作業全体が穏やかに回っていく。
これは本当に大きな違いです。
録画にはSSD、保存にはHDD。
この二本立てがベストの形だと確信しています。
導入が面倒に思えるかもしれませんが、実際のところ手間もコストもそれほど大きくなく、それ以上に得られる効果が大きすぎるのです。
なので迷う理由はありません。
私はもう録画用にHDDを選ぶことはありません。
Apex Legends対応ゲーミングPCを長く使うために考えたい拡張性


後からのアップグレードを見据えたケース選びの基準
Apex Legendsを長く快適に遊びたいなら、ケース選びを軽く考えてはいけないと私は思います。
ただの箱のように見えて、実際には将来の拡張性や安定した動作に大きく響いてきますから。
だから私は選ぶ基準を「長く使えるかどうか」に置くようになりました。
見た目だけで選ぶと、必ず後悔するんですよね。
過去に私も痛い経験をしました。
小さくておしゃれなケースを買ったものの、大型GPUを導入したいときに物理的に入らなかった。
結果、ケースごと買い替え。
出費と作業の手間、その時のストレスは今でもよく覚えています。
だから今では「先を読む」ことを徹底するようになったんです。
無駄な買い替えは本当に避けたいんですよ。
ケース内部の広さ、これはやっぱり大事です。
最近のグラフィックボードは年々巨大化していて、長さが30センチを超えるのは当たり前。
厚さも3スロットを占有するようになれば、小型ケースにはまず収まりません。
勢いで選んだら最後、泣きたくなる未来が待っていますよ。
さらにCPUクーラーを水冷に変えようと考えるなら、ラジエータ取り付け可否も最初に確認必須です。
これを後回しにすると自由度が一気になくなる。
まさに痛感しました。
冷却性能も無視できません。
Apexのような負荷の高いゲームを高リフレッシュレートで回すと、GPUもCPUもすぐに熱々になってしまう。
ケース正面や上部がメッシュ設計ならエアフローが確保され、安定性に直結します。
一見静かそうなのに内部温度が上がってゲームがまともにプレイできなかったんです。
「またやってしまったな」と頭を抱えました。
裏配線スペースやストレージの拡張性も大切ですね。
最近のNVMe SSDは高性能ゆえ発熱もすごい。
ヒートシンクだけでは処理しきれずに追加冷却が欲しい場面も出てきます。
ただ、ケースが狭いと何も置けないんです。
数センチの余裕があるかないかで未来の快適さは大違い。
私は一度、裏配線がまるでできないケースを買って失敗しました。
見た目は散らかり、管理も最悪で、最後には「もう捨ててしまおうかな」とまで思ったほどです。
数年前に流行りだしたピラーレスデザインは本当に作業が楽。
昨年Lian Liのケースに変えたとき、大型GPUの取り付けが見事にスムーズで、「もっと早くこれを選んでいれば」と思わず声が漏れました。
それまで閉鎖的なケースを無理に使っていた苦労を思い出すと、もう後戻りはできませんね。
外観デザインももちろん気になる要素です。
ガラスパネルで内部を見せて楽しむタイプや、木目調で家具と並べても馴染むデザインなど、魅力は多い。
ただ木製パネルケースは見た目こそ素敵でも通気性に課題があることが多い。
私は一度、本気で迷って購入寸前までいったのですが、最後に「道具はやはり使えなきゃ意味がない」と我に返りました。
外側に惚れても中が窮屈ならストレスしか残らない。
電源やファンレイアウトも意外な落とし穴です。
ハイエンドGPUを考えるなら850Wクラス以上の電源を見越す必要がありますが、電源サイズが大きいと内部スペースを削ってしまうケースもあります。
実際に配線が窮屈になって、メンテナンスのたびにイライラが積もった経験があります。
なので今では「柔軟に電源を格納できるかどうか」も大事な基準にしています。
これが地味に効いてくるんですよ。
要は、内部に余裕があって、冷却性能がちゃんと確保されて、今後のパーツ交換や追加にも柔軟に対応できるケースを選ぶこと。
それが一番大事なんです。
見た目や価格だけに釣られると、やがて大きな代償を払うことになる。
Apexを何年もプレイしたい人ほど、拡張性を最優先に考えないと後で痛い思いをします。
安心感がある。
納得が残る。
ケースは地味な存在ですが、その選択で未来の数年間が大きく変わります。
私は自分自身、これまで失敗と買い直しを何度も経験して、ようやく身に染みました。
だからこうして熱を込めて書いているのは、同じ失敗を誰かが繰り返してほしくないからです。
ケースはただの容れ物ではなく、未来の基盤。
その考えに行き着いたとき、やっと私は自分にとっての正しい投資を見つけられたと思えました。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z57A


| 【ZEFT Z57A スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H6 Flow White |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55IM


| 【ZEFT Z55IM スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5050 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55WI


| 【ZEFT Z55WI スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55DX


| 【ZEFT Z55DX スペック】 | |
| CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
電源ユニットの容量は750Wで十分か、余裕を見て850Wを選ぶべきか
Apexをやるなら電源はできれば850Wを選んだ方がいい、これが私の実感です。
もちろん構成によっては750Wでも何の問題もなく動きますし、私も最初はそう考えて組みました。
しかし、実際に使い続けていくと「数字上で足りている」と「安心して長く使える」は別物だと痛感しました。
最初にそこまで考えきれなかったのが正直なところです。
私の経験を言えば、Core Ultra 7とRTX 5070 Ti、そして750Wの電源という組み合わせで組んだ時は、快適に動作していました。
最初は青色の画面など出るわけもなく、日常使いも、ゲームも、問題なんて見えませんでした。
でもある日、SSDを追加し、冷却ファンも足しました。
すると突然、激戦の最中にブルースクリーン。
正直、心臓が止まるかと思いました。
やっぱり電源って土台ですから、余裕のない構成だとちょっとした拡張でも不安定さが顔を出すのだと、身をもって思い知らされました。
一方で、フルHDモニタとRTX 5060 Ti程度の構成、CPUもCore Ultra 5のクラスで、拡張もしないと決めているなら750Wで何も問題ありません。
むしろ効率を考えればちょうど良いと感じるくらい。
消費電力あたりの性能は最近かなり改善されているので、ゲームでも負荷が集中しても600W前後で収まる場面が普通にあります。
その場合は「これなら750Wで十分だ」と自信を持って言えるんですよね。
だから用途が絞られていれば750Wの方がコスト的にも環境的にも合理的なんです。
ですが、私が強く言いたいのは「余裕の有無」です。
Apexみたいに常にGPUもCPUもフル稼働しているタイトルでは、ギリギリの電源は本当に怖い。
突然のクラッシュや耳障りな音。
わずかでも不安を抱えながら遊ぶのは、純粋に楽しめないんです。
「次の瞬間落ちるかもしれない」なんて気持ち、できれば味わいたくないじゃないですか。
さらに世代が進んだGPUは一瞬で電力を跳ね上げる性質があり、計算上は余裕があっても現実では厳しい時があるんですよ。
笑えないトラブルです。
結局850Wに買い替えて解決しましたが、その間に無駄な出費と手間、そして気疲れを抱えていたのを間近で見て、私自身も「これは他人事じゃない」と強く思わされました。
安心。
それこそが私にとって一番大切です。
朝電源ボタンを押すときに「今日もちゃんと動いてくれるかな」と不安を抱く生活はもう嫌です。
余裕がある電源ならそんな心配も吹っ飛びます。
もちろん、用途次第では750Wで不便のない生活を送れます。
フルHDでやると決めて、何も増設しないと割り切っているなら750Wで必要十分です。
ただ私のように気づけばSSDを増やしたり、新しいパーツに手を出してしまうタイプだと、迷うくらいなら最初から850Wを選ぶのが精神的にもずっと楽。
経験上、余裕のある電源にして損したことは一度もありません。
予算重視で「少しでも抑えたい」と考える人なら750Wの選択に納得できるでしょう。
でももし心のどこかで「もうちょっと将来性があった方が安心かな」と思うなら、850Wを考えるべきです。
私は今なら間違いなく850Wを選びます。
小さな差額で大きな安心を手に入れる。
それが私にとっては最良の判断だからです。
余裕があると、不思議と心まで整う。
これが私の結論です。
長くPCを安心して使い続けたい。
そして、再び後悔したくない。
結局それを支えるのは電源だった??そう思っています。
DDR5メモリは後から64GBまで増設できるのかどうか
DDR5環境を考えるとき、一番大事なのは「後から64GBまで増設できるか」だと私は思います。
Apex Legendsを快適に遊ぶだけなら32GBで十分という意見もありますし、正直その通りなのですが、私の場合は仕事でも趣味でも同時に色々とパソコンを触ることが多いので、先々を見据えて余裕を残しておくことが本当に大切だと感じています。
結局、将来的に拡張できるかどうかが心のゆとりにつながりますし、安心感を左右するんですよね。
最初に確認すべきはマザーボードのスロット数です。
4スロットあれば安心ですが、2スロットしかないものを選んでしまえば後々かなり厳しい展開になります。
例えば16GBを2枚で32GB構成にしていたとして、後から64GBにしようとすると32GBモジュールを2枚買い直すことになり、結局それまでのメモリが無駄になる。
これほどもったいないことはないと、私は身をもって痛感しました。
というのも、過去にBTOで安価さだけに飛びついて2スロットのモデルを買ってしまい、その後に増設したいと思ったときに「しまった…」と頭を抱えたのです。
あの時の後悔はもう二度と味わいたくないと強く思っています。
次に考えるべきはメモリそのものの規格です。
現行のDDR5では1枚32GBのモジュールが一般的になっていて、4スロットのマザーボードと組み合わせれば最大128GBまで乗せられる。
つまり64GBを目指すくらいならむしろ余裕の範囲なんです。
だからこそ、最初は16GB×2で32GBを導入して空きスロットを残した状態でスタートするのが理想的。
将来的に必要になったら同じ仕様の16GBをもう2枚差すだけで済む、そのシンプルさが長期的な安心を生んでくれますね。
実際の例を出すと、私の同僚が使っている環境があります。
彼はWQHDモニターで配信と編集を同時にこなしているのですが、最初は32GBで十分だったのに、動画編集ソフトと録画配信を同時に回すと最近は急激にメモリ使用率が上がるようになったそうです。
結局16GB×2を追加して64GBにしたところ、「いやあ、こんなに違うのか」と本当に驚いた顔をしていました。
その表情を見たとき、やっぱり余裕を持つことの大事さを改めて実感させられましたよ。
以前のDDR5は高すぎてなかなか手を出せませんでしたが、今はかなり価格がこなれてきていて実用的な水準になってきました。
64GBにしても、トータルのPC予算を考える中ではそこまで重たい負担にはなりません。
今のBTOモデルは空きスロットが用意されているケースが多いので、事前に仕様書を確認しておくだけで、後から「足りない」と落胆せずに済みます。
このひと手間を惜しまないこと、これが実際にはものすごく大きな差を生みます。
Apex自体は64GBを丸ごと食いつぶすゲームではありません。
ブラウザを複数開きながら、録画ソフトを走らせつつ、加えて編集ソフトで同時進行。
そんな日常的な環境ではあっさり上限に近づくこともあり、私にとって32GBは意外と心許ない状況になる場面が多いんです。
プレイ中にちょっとしたもたつきを感じると、「やっぱり余裕が欲しいな」と痛感させられます。
だからPCを新調するなら、私は断然4スロット搭載マザーボードをおすすめしたいです。
最初は16GB×2で32GBにして、必要を感じたタイミングで同じブランドの16GBをさらに2枚追加。
この流れが最も無駄なく、堅実な構成であると考えています。
実際に増設の作業も拍子抜けするほど簡単で、互換性も最小限の心配で済むんです。
私は今でも忘れられない場面があります。
ゲーム中に突然カクつきが発生し、思うように動けずイライラしたあの経験。
たかがメモリ不足なのに、自分が小さな罠にはまったような無力感を覚えたのです。
その記憶があるからこそ、今の私は余裕のある環境を整えておくことを絶対に欠かせない準備だと考えています。
職場の仲間も同じように「どうせなら64GBにしておいた方が安心だ」と口を揃えることが多いです。
私はこう思います。
先を見通した拡張性。
これがあるだけで、PCライフは大きく変わります。
「後から増やせる設計にしておく」その工夫こそが、使う人の安心と余裕を確実に支えてくれると、心から信じています。
Apex Legends用PCでよく出る疑問


グラボがなくてもApex Legendsは起動できる?
もちろん、CPU内蔵のGPUでも「とりあえず動く」こと自体は可能ですが、それを快適と呼ぶのは違います。
動いた瞬間は「よし、これでも大丈夫かも」と希望を持つのですが、実際に試合が始まればカクつきが目立ち、相手よりも画面の遅延に意識を奪われてしまう。
つまり、ただ動くだけでは楽しめないのです。
私も過去に、仕事用のPCから一時的にグラボを外した状態でApexを動かしたことがあります。
正直に言うと起動したときは少し嬉しかったんです。
「あれ、案外プレイできるかもな」と。
しかし試合に突入した瞬間に現実を突きつけられました。
画面はカクつき、キャラクターの動きは途切れがちで、敵の動きを予測するどころか自分の視界にさえストレスを感じる。
敵の足音よりも画面の処理落ちに神経を集中している状況で、とてもまともな試合ではありませんでした。
それこそ、ただのストレス製造機です。
とはいえ、近年のCPU内蔵GPUは大きく進化し、軽いゲームであれば十分に遊べますし、資料作成や簡単な動画編集にも対応できます。
しかし、Apex Legendsのようなシビアなタイトルは話が別です。
ほんの一瞬でも相手の動きが途切れて見えれば、それだけで撃ち負けることもある。
悔しさしか残らない。
耐え難い体験です。
一秒間に数フレーム描写が遅れるだけでも、相手のキャラクターがまるで瞬間移動しているかのように見えてしまう。
暗い通路で敵がスライディングしてきたとき、その一瞬が命取りです。
自分としては正しい行動を取ったつもりでも、画面に映らなければ全てが無駄。
チームプレイにおける協力体制も崩壊しかねません。
結局は仲間にも迷惑をかけるんですよね。
ではどの水準のGPUが必要なのかと言えば、少なくともフルHD環境で戦うためには現行のミドルクラスが基準になります。
144Hzの高リフレッシュレートモニターを活かしきりたいのであれば、さらにワンランク上の性能がないと追いつきません。
WQHDや4Kを考えるならなおさらです。
内蔵GPUどころか、エントリークラスのグラボでも物足りない。
つまり、選択肢は狭まるのです。
私に強い印象を与えたのは知人の環境でした。
彼はRadeon RXシリーズの上位モデルを導入していて、実際にプレイ画面を見せてくれました。
240Hz近くを安定して出し続けるその映像はとにかく滑らかで、敵の細かい動きや弾道までもが綺麗に映し出される。
見た瞬間に「これが快適さか」と感心しました。
正直、羨ましさがこみ上げてきましたね。
あの没入感は反則レベルでした。
一方で、インターネット上には「設定を落とせばグラボなしでも十分」と主張する人もいます。
しかし冷静に考えてみれば、それは昔の軽いタイトルなら通じる話でしかありません。
Apexのように多人数が同時参加し、リアルタイムで高度なグラフィックス処理を求めるゲームとは根本的に違います。
苦笑いですよ。
私が強調したいのは、Apexにおける「グラボはいらない」という考え方は現実味がないということです。
確かに起動はするかもしれない。
けれど、それは本来の面白さを掴むための環境とは到底呼べない。
本当に集中して楽しむには、快適さと安定性、そして瞬時の反応に応えてくれるハードウェア、つまりGPUが不可欠なんです。
もしそこを軽視すれば、せっかく貴重な時間を費やした試合も疲労感だけが残ります。
40代の私だからこそ余計に感じるのですが、その差は心の余裕に直結します。
グラフィックボードの導入は確かにそれなりの投資です。
しかし決して無駄ではありません。
自分の楽しみに直結する出費なのですから。
快適な映像がもたらす爽快感は、遊びをただの遊び以上の体験に変えます。
それが積み重なれば「今日も一勝してやるぞ」と気持ちを切り替える力にもなります。
結局、私自身は二度とグラボなしの挑戦を繰り返す気はありません。
あの不便さで得られた教訓は忘れていません。
努力や作戦だけではなく、環境の差が試合を左右するという現実を痛感したからです。
そして今は自信を持って言えます。
Apex Legendsを本気で遊びたいなら、専用グラフィックボードの導入は避けて通れない。
これが大人の選択です。
本当に。
それがゲームを楽しむための最低限の責任です。
フルHDと4Kでは必要スペックにどれくらい差があるのか
Apex Legendsをプレイする上で、フルHDと4Kの差は単なる解像度の違いではなく、まるで別のゲーム体験をしているような隔たりがあると私は感じています。
結論から言えば、コストや安定性を重視するならフルHD、映像体験を最優先にするなら4Kを選ぶのが正解です。
けれどその選択に至るまでには、自分の財布や時間、そして快適さへの考え方を何度も問い直す必要があると痛感しました。
フルHD環境であれば、最新世代の中堅クラスのGPUやRyzen 5クラスのCPUでも十分に力を発揮してくれます。
実際、私もRTX 4060Tiクラスの構成で遊んでいた時期があり、その際には200fps前後を安定して出せていました。
描画が乱れたりカクついたりすることも少なく、プレイに支障を感じた場面はほとんどありませんでした。
今思えば、必要以上に機材に投資することもなく、冷静に楽しめる環境だったと思います。
加えて電源も650W程度で足り、冷却も標準的な空冷で済ませられたので、変に神経質になることもなかったのです。
いつまでも遊べる安心感。
これがフルHDの魅力でした。
ただし4Kに移行してからは、その感覚が一気に吹き飛びました。
4Kでプレイする場合はGPUもCPUもワンランク上が必要になり、例えばRTX 5080やRadeon RX 7900 XTXクラスが推奨されます。
Ryzen 7クラス以上のCPUでなければ、その性能を出し切ることが難しい場面が多くありました。
私が初めて4Kのモニタに手を出し、同じ構成のままプレイしてみたときのことです。
フレームレートは一気に60fps前後まで落ち込み、敵に照準を合わせても反応が遅れ、対戦中に「やってしまった」と思う場面が増えました。
正直、悔しかったですね。
努力で補える部分ではない現実の壁にぶつかった感じでした。
当然ながらメモリも要求が変わってきます。
32GBはほぼ前提で、少なく見積もっても16GBでは安心できませんでした。
加えて、高性能なGPUが発する熱量も想像以上であり、ケースの選び方も重要になります。
850W以上の電源も覚悟しなければならず、その時初めて「単なる解像度を上げるだけで、ここまで周辺環境への投資が増えるのか」と驚いたものです。
冷却をどうするか。
水冷に一歩踏み込むのか。
それとも静音性をあきらめるのか。
頭を抱える日々でしたよ。
しかし、それでも4Kの映像は圧倒的だった。
景色の美しさに思わずゲームを中断してスクリーンショットを撮ったことさえありました。
初めてApexを4Kで起動したとき、胸の奥がゾワッと震えました。
「やばい」って正直に思いましたよ。
圧巻の光景でした。
二度と元には戻れないかもしれない。
ただし美しさばかりではありません。
消費電力は確実に増し、部屋の中の体感温度が上がって夏場は特に辛い。
空冷ファンは爆音に近く、集中してプレイするにはストレスフルで、結局は大型の簡易水冷を導入してしまいました。
気づけば、電源や冷却といった周辺機器にまで手を広げざるを得ない。
ゲームを楽しむだけのはずが、生活環境にまで影響が及んでくるのです。
覚悟。
これが4K環境につきまとうキーワードだと思います。
最近のGPUはかなり効率を意識して設計されていると聞きますし、確かに昔に比べると消費電力は良くなったはずです。
それでも4K環境に身を置くと、フルHDに比べて余裕が全くないことを思い知らされます。
私も最初は「最新世代なら何とかなる」と軽く考えていました。
でも実際に使うと、冷却の足りなさ、電源からの供給不足、そして想像以上の出費という現実に直面しました。
幻想は早々に崩れ去ったのです。
結局、自分が何を大切にするのかで選び方は変わります。
競技的な有利さを最優先するのであれば間違いなくフルHDです。
余計な投資をせずに安定した高fpsを維持できますし、動作も滑らかなので安心して対戦に集中できます。
一方で、映像体験そのものを満喫したいのであれば4Kの存在感は唯一無二です。
大画面で楽しむ迫力、世界観への没入感。
そこに心が震えなければ正直もったいないと言えるでしょう。
平日は仕事終わりに集中して遊びたいのでフルHD。
休日や気分に余裕のあるときは4Kで世界に浸る。
そんな二刀流スタイルです。
それぞれにメリットとデメリットがあるからこそ、選びきれないのも本音です。
便利さと美しさ。
この間で揺れる気持ちは、きっと多くのゲーマーが共感してくれると思います。
振り返ってみると、フルHDと4Kの差は単なる数字の違いではありません。
はっきりとゲームスタイルを分ける「境界線」といっていいでしょう。
だからこそ、どちらを選ぶにしても、自分自身が心の底から納得できる覚悟が必要なのだと思います。
迷いながらも選び取った最終的な気持ちは、Apex Legendsを思い切り楽しむために欠かせないのは環境にふさわしい準備と腹をくくる気持ち。
この一点に尽きると私は強く実感しています。
心からそう思います。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R67S


| 【ZEFT R67S スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X3D 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Corsair FRAME 4000D RS ARGB Black |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 360 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z58C


| 【ZEFT Z58C スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster Silencio S600 |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z58W


| 【ZEFT Z58W スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
| ケース | Okinos Mirage 4 ARGB Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56AD


| 【ZEFT Z56AD スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R52O-Cube


ハイレベルゲームも快適に対応するパワフル・ゲーミングPC
高速32GB DDR5メモリと最新のSSDの極上のハーモニー
省スペースに収まる美しきコンパクト設計のマシン
Ryzen 7 7700の力強いパフォーマンスを体感せよ
| 【ZEFT R52O-Cube スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | INWIN A1 PRIME ピンク |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850I Lightning WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
ゲーミングノートでApex Legendsを快適に動かせるか
結局のところ、どちらが優れているかというよりも、自分がどんな環境で遊びたいのか、どんなスタイルでゲームを楽しみたいのかで答えが変わるのだと気づきました。
冷静に考えれば当たり前の話ですが、迷っている時はどうしても性能や価格の比較に目が行ってしまうものです。
だからこそ、最初に大事なのは「自分の生活にどう馴染むか」という視点だと思います。
私の周りでも「ノートで本当に大丈夫なの?」という声をよく聞きます。
特にApexのように瞬間の判断が結果に直結するゲームでは、不安を抱える人が多い。
それでも最近のゲーミングノートは確実に進化しています。
コンパクトな筐体に高性能を詰め込み、フルHDで144Hzという環境なら十分に対応できる実力があります。
私自身も半信半疑で買ったのですが、実際に使ってみた時は「いや、これは想像以上にやれるな」と正直驚きました。
どうしても薄型構造ゆえに冷却は弱点です。
長時間プレイすると内部温度がじわじわ上がり、ファンが勢いよく回り出す。
30分ほど経つ頃には背面から吹き出す熱気が強烈で「正直、このままじゃきつい」と思ったこともあります。
けれど最近の機種は横や背面に排気口をきちんと配置し、効率よく熱を逃がすように設計されています。
さらに冷却スタンドと併用すれば安定性は大きく増し、想像以上に快適に遊べる。
持ち運び可能な機材でここまでの環境が手に入るとは、少し前までは考えもしませんでした。
ノートPCならではの大きなメリットは「自由さ」に尽きます。
例えば出張先のホテルで遅い時間にふとゲームがしたくなった時、その場で電源とネットさえあればプレイできる。
これがどれほど気持ちを軽くしてくれるか、実際に経験してみないと分からないと思います。
移動続きの生活でも、いつもの環境を保ちながら遊べることがモチベーションの源になる。
これはデスクトップでは絶対に実現できない部分です。
ただし最高レベルの環境を求めるなら、話は変わります。
4K解像度で高リフレッシュレートを安定維持したい、本格的に大会を意識する、といったニーズにはノートでは応えきれません。
冷却やパーツ交換の自由度からして、デスクトップにだけ許された領域といえるでしょう。
大きな空冷ファンや水冷クーラーを積み込める拡張性が作り出す安定した動作音と温度管理。
深夜まで腰を据えて練習しても不安がない。
それこそがデスクトップの絶対的な魅力です。
私は最近、AIによる自動制御を搭載したノートにも触れる機会がありました。
負荷に応じてクロックや冷却ファンの動作を最適化する仕組みなのですが、それを実際に使ってみると想像以上に精巧で「いや、もうここまで来たのか」と心底驚かされました。
かつてはノートで高性能を求めるのは無謀だと考えていた私が、一瞬「ちょっと投資してみてもいいかもしれない」と思わせられたほどです。
技術の進歩のスピードは恐ろしいくらいです。
答えは意外とシンプルです。
その携帯性と扱いやすさこそが最大の価値になる場面も多いからです。
一方で、もっと上の映像体験や大会環境を視野にするなら、間違いなくデスクトップを選ぶべきです。
静音性も冷却性能も段違いですし、拡張性を考えると長い目で見て安心できます。
ここに優劣はなく、自分自身のプレイスタイルに合わせた適材適所というだけの話なのです。
私は外出が多い暮らしをしているので「同じ環境を持ち運べる」ことの価値がとても大きい。
だからゲーミングノートは私にとって欠かせない相棒のようになっています。
ただ友人の中には自宅で腰を据えて何時間もじっくり遊ぶ人も多く、そういった人には迷わずデスクトップをすすめています。
大切なのは「自分がApexをどんな場面で、どう楽しみたいか」という問いにきちんと向き合うこと。
軽快さ。
圧倒的な安定。
だからこそ実用性と憧れのバランスを考え抜いた上で、自分に合った選択をしてほしいと心から思います。
そしてその答えを見つける過程も、ゲームと同じくらいワクワクするのかもしれません。
結局のところ「どちらを選ぶか」ではなく「どう遊ぶか」で未来は変わる。
BTOと自作、コストパフォーマンスはどちらが良いか
BTOであれば、無駄な時間を費やすことなく、目的に合った性能を確保しやすいのです。
BTOショップというのは結局、仕入れの力がすごいんですよ。
メーカーや代理店とつながっていて、大量にパーツを押さえるから一つ一つの値段をグッと下げられる。
さらに在庫の安定性も持っているので、最新のGPUやCPUを手に入れるのに、自作より安く済む場合が大半です。
私も過去何度も価格比較をしてきましたが、グラボやメモリみたいに市場価格の上下が激しいパーツは、BTOがほぼ勝っているんです。
体感で言うと、自作であれこれ探し回って買い集める労力を考えたら、その差はもはや埋められないなと。
正直な話、値段差はバカにできません。
自作を推してきた自分にとって、その認識が揺れたのは最近のBTOモデルを見たときです。
20代の頃は「CPUクーラーは自分で吟味しないと性能を引き出せない」なんて本気で信じていました。
でも今は違います。
ミドルクラスのBTO構成ですら、冷却性能をしっかり意識したケースとクーラーを標準搭載していて、下手な自作よりよほど安心感を与えてくれるのです。
昔のように「自作じゃないと冷却不足が心配」という感覚は、ほとんど消え去りました。
信頼できる仕上がりです。
去年、BTOでオプション追加した2TBのNVMe Gen4 SSDが、同じタイミングで量販店や通販で単品購入するより7千円安かったんです。
7千円ですよ。
これ、パッと見では些細な差かもしれませんが、ゲームを1?2本買える金額ですから大きいです。
もちろん自作にしかない価値もあるんです。
好きなケースを選んでLEDを仕込んで、「自分だけの一台」を組み上げる楽しさは格別です。
実際、私は新しいRadeonのGPUが出荷された直後にわざわざ入手して、自作PCに即日組み込んだ経験があります。
発売直後に最新技術を触れたあの高揚感は、今でも忘れられません。
気持ちは完全に満たされました。
ただ、今考えると「その高揚感に見合う出費だったか」と問われると微妙です。
Apexのためと割り切るなら、そこまでお金を使う理由は正直ないんですよ。
Apexの快適プレイにはGPU性能とメモリ帯域が大事で、CPU依存度はそれほど高くありません。
要は144Hz以上で滑らかに動作すればそれで十分。
であれば、自作で拘るよりも、BTO構成でGPUとメモリに予算をうまく集中させたほうが合理的なんです。
素直にそう思います。
保証面の差も大きいです。
自作の場合、一つ不具合が出るとパーツ単位で検証して、販売店やメーカーにそれぞれ問い合わせ。
これが時間を食うんです。
社会人にとってその時間、ものすごく重い。
夜中に帰ってきてから配線を調べ直し、休日を修理で潰すとか、正直きつすぎます。
その点BTOなら窓口は一本化。
困ったらショップに連絡すればいい。
その安心感は心底価値があるものです。
電源や冷却設計についても一度痛い思いをしました。
自作で「余裕ある電源を積んでおけば安心」と考えたことがあるんですが、実際はケーブルが多すぎてケース内が散らかり見た目が最悪に。
要するに、過剰なこだわりが裏目に出た形です。
やってみて分かりました。
余裕って時に邪魔になるんです。
だから私は、Apexを快適に遊ぶPCを選ぶ状況なら迷わずBTOにします。
最新GPUやCPU、十分なメモリやNVMe SSDをバランスよく積んだモデルが、リーズナブルな価格で手に入る。
しかも保証がセットになっている。
その条件を超える選択肢は、率直に言って少ないです。
ただ、自作を完全に否定する気は毛頭ありません。
細部まで好みを反映して一台に愛着を込めたいなら、それはそれで大いに価値のあることです。
私もその楽しさは知っています。
でも「Apexを思い切り楽しむためにコストを抑えつつ性能を確保する」という一点に絞るなら、BTOを選ぶのが賢明だと断言できます。
その選択に後悔はないと、私は自信を持って言えます。
安心感。
納得感。
これが今の私をBTOに向かわせる理由です。
――仕事に追われながらも休日にApexで息抜きをしたい。