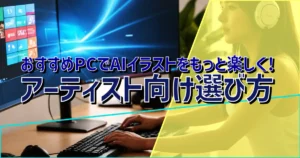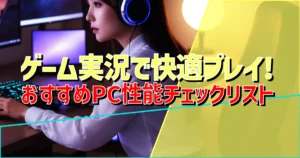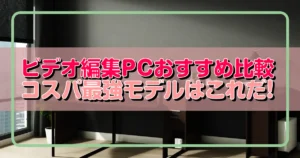4K環境でApex Legendsを快適に遊ぶためのGPU選び

RTX4060TiとRX7600XTを比べて感じた実際の差
実際にRTX4060TiとRX7600XTを比較していく中で、私がはっきりと確信したのは「安心して長時間没頭できるのはどちらか」という点でした。
数字だけ眺めている時には正直そこまで大きな違いはないと思っていましたが、実際に4K環境で遊んでみると想像以上に差が出てしまい、ただの数値遊びでは済まされない現実を突きつけられることになったのです。
特にRTX4060Tiの滑らかさは強く印象に残りました。
余計な不安を抱かずに自然とプレイに打ち込めるという点で、私はこの安心感をとても重視しています。
一方でRX7600XTも決して悪いカードではありません。
むしろ価格を考えれば奮闘していると感じます。
しかし、ふとした瞬間の引っかかりがプレイの流れを邪魔してくる。
ほんのわずかな違いに見えても、そのタイミングで負けに直結することだってあるんです。
小さな差。
でも実際には痛い差なんですよね。
私が強く実感したのは混戦の場面でした。
敵味方入り乱れる中で大量のエフェクトが発生すると、本来なら処理が重くなってカクつくことが想定されます。
しかしRTX4060Tiは崩れない。
逆にRX7600XTではカクッと止まる瞬間があり、その一瞬で判断が遅れて悔しい想いをすることがありました。
ゲームはコンマ数秒で勝敗が決まる。
だからこそ、この差は小さくありません。
RTX4060Tiには余裕があり、テクスチャ品質をそこそこ高めにしても心配にならない。
それに対して、RX7600XTでは重さを感じる場面が数度あり、そのせいで設定を落とさざるを得ませんでした。
映像表現の美しさを気にする私にとって、これは精神面へのダメージが意外と大きかったです。
綺麗な環境で遊べると純粋に楽しい。
だからこそ妥協を強いられる状況は心底惜しいと思いましたね。
ただ、コストの側面ではRX7600XTの良さも確かに際立ちます。
友人がPCを買い替える際「なるべく予算を抑えたい」という要望からRX7600XTを選んだのですが、実際の使用感を満足そうに話していた姿を見て、金額と性能のバランスこそが人によっては最重要なんだと改めて感じました。
「いや、これで十分楽しいよ」と笑っていましたからね。
この一言に説得力がありました。
一方で、私のようにApexを4Kでとことん楽しみたい人間にとっては答えはけっこう明快で、RTX4060Tiしかないなと思わされました。
設定をいじり倒して微調整しなくても、そのまま遊べてしまう環境を得られることは想像以上に気が楽なのです。
もちろん調整を突き詰める楽しさも理解できます。
ただ私は仕事で時間に追われることが多いからこそ、いち早くゲームの世界に入り込める方を選びたい。
その価値はかなり大きいんです。
信頼性。
ドライバの更新状況も両者の印象を分けました。
RTX4060Tiは長年のアップデートによってしっかり最適化されており、万が一トラブルが起きても修正が早い印象です。
この安心感は馬鹿にできません。
一方でRX7600XTも改善はされていますが、競技シーンのようにトラブルを1ミリも許容できない環境では頼りきれないと感じることがありました。
些細なことのように見えても、本気で取り組むと気になってくるのです。
特に気になったのがフレーム生成技術でした。
RTX4060Tiで使えるDLSSは、映像の滑らかさと反応速度をほぼ同時に確保しており、リフレッシュレートの高いモニターと組み合わせると驚くほど快適に動作しました。
正直「もうここまで来たのか!」と声に出そうになったくらいです。
それに対してRX7600XTのFSRは改善を重ねてきたのがわかるものの、本気で勝負が決まる場面ではまだ完全に信じ切れない印象がありました。
昔の翻訳アプリで意味が通じるけど違和感が残る、あの独特な感じに近いんです。
きっと今後の進化で良くなるのでしょうが現段階ではやや不安。
私は、4KでApexを快適に遊ぶ気持ちがあるなら迷わずRTX4060Tiを推すと思います。
RX7600XTで遊ぶことが不可能ではない。
ただ「快適」と言えるかと聞かれれば言葉に詰まってしまいます。
だから、心置きなく遊んでもらいたいなら断然4060Tiを薦めたい。
そして最後にまとめるなら、価格面で納得できればRTX4060Tiが現時点では最良の選択です。
特に4K環境においては代わりの効かない安心感があります。
その違いが最終的にどう影響するか。
確信しましたよ。
DLSSとFSR、4Kプレイでどこまで頼れる機能か
4K環境でApex Legendsをプレイするとき、私は今のところDLSSやFSRの恩恵を受ける以外に道はないと考えています。
昔は「ネイティブ解像度にこだわってこそ本当のゲーミングだ」と意地を張っていましたが、実際にプレイしてみるとフレームレートが不安定になる瞬間が多く、何度も集中力を削がれました。
その苛立ちや疲れを思い出すと、いまではAI技術を用いた補完の助けを素直に頼るのが一番だと心から感じています。
快適さが集中力を支え、勝敗を左右する――これはゲームという娯楽を超えた心理的な安心材料でもあるのです。
NVIDIAのDLSSは世代を重ねるごとに大きく進化していて、正直驚きます。
数年前までは文字の輪郭がぼやけたり、遠景の木々がざわついたりして「これはちょっとな」と躊躇しました。
しかし最新のDLSSを試したとき、特に人物描写や敵シルエットの鮮明さに感心しました。
四十代にもなって、思わず「おお、ここまで来たか」と感嘆の声を漏らすくらいです。
敵の動きを早く察知できるのは本当に大きなアドバンテージで、単なる画質向上ではなく勝負の結果を揺さぶる効果を実感しますね。
AMDのFSRも同じく興味深い技術です。
私はRX 9070XTを試した際にFSRを有効にしてみました。
そのとき、画面が一気に滑らかになり、120fps前後まで突き抜けた瞬間の感覚はいまでも鮮明に覚えています。
煙が重なるシーンや環境描写が負荷をかける場面でも大きな破綻がなく、素直に「これは楽だ」と思いました。
正直、40代ともなると集中力も若い頃のように持続しないので、この安定感はありがたいんですよ。
ただし便利な技術にも欠点はあります。
フレーム補完を有効にすると、どうしてもマウスを振ったときに「ん?」と思うくらいの遅延が顔を出します。
Apex Legendsのようにミリ秒単位で勝敗が変わる場面では、その一瞬が命取りになります。
数回プレイ中に引っかかるような感覚を覚え、「これは人によっては合わないだろうな」と思いました。
結局のところ、自分のプレイスタイルとのすり合わせが必要なのです。
私は便利さを優先しますが、それぞれの感覚次第でしょう。
それでも全体として見れば、DLSSやFSRを積極的に活用すべきだと私は断言します。
何よりも安定したフレームレートで遊べることのほうが、細かい映像の違和感より遥かに価値がある。
昔は鉄柵の斜め線が妙に歪んで見えたり、背景が揺らいで「おいおい」と突っ込みたくなる場面もありました。
最初にDLSSを導入したときは「なんだよこれ、でもすごいな」と複雑な気持ちになったものです。
ただそれ以上に、滑らかに映像が流れる安心感が勝ってしまうんですよね。
私は最近、BTOショップでRTX 5070TiとRX 9060XTを試したのですが、そのとき改めて強く感じました。
同じようなフレーム数が出ていても、DLSSを使った方が「敵を狙うときのブレが少ない」とわかるんです。
この見えない差が撃ち合いでは致命的な差になる。
逆にFSRは映像全体のなめらかさに優れていて、大画面テレビでのプレイに向いている印象を受けました。
環境によって感じ方が大きく違うんですよね。
忘れてはいけないのは、どんなに優れたアップスケーリング技術でも、GPUそのものの限界を超えられるわけではないということです。
RTX 5060TiやRX 9060XTのようなミドルクラスでは、フルHDやWQHDでの安定感は十分ですが、4Kで120fpsを維持しようとすると明らかに厳しい。
実際に知人が試した際、80fpsを割る場面が頻発して結局WQHDまで落とすしかありませんでした。
これは現実です。
理屈ではなく、実体験で突きつけられる現実。
だからこそ、もし本当に4K環境でApex Legendsに挑みたいのなら、最低でもRTX 5070TiやRX 9070といったモデルを軸にすべきです。
この選択がいま最も合理的だと私は強く思います。
ネイティブ4K映像自体は確かに美しい。
しかし自己満足にとどまる部分が大きく、結局のところ快適さを犠牲にするのは本末転倒です。
AIを使うのが当たり前の時代になった。
そういうことなんでしょう。
正直に言えば、まだ完璧ではない部分もありますよ。
細部の描写に不自然さを見つけると「やっぱりAIだな」と感じる瞬間もあります。
それでも手放せない。
安心して長時間没頭できる環境のほうが、自分にとっては圧倒的に価値があるんです。
結局、DLSSやFSRは妥協ではなく合理的な解です。
4Kという高い理想を現実に近づけるための橋渡し役。
年齢を重ねるほど、無理せず気持ちよく遊べる選択肢を大事にしたくなるんですよ。
今の自分にとって、それが一番しっくりくる表現なのです。
144fpsを狙うなら現実的に選びたいGPUはどれ?
144fpsでApex Legendsを楽しみたいのであれば、やはりGPU選びがすべてを決めると私は思います。
半端なスペックでは高解像度と高リフレッシュレートを両立させることは難しく、結局は余計な遠回りをしてしまう。
これは自分が構築を重ねて実感した率直な事実です。
4K環境を前提にした瞬間、それなりの妥協が許されない世界なんだと腹の底から思い知らされました。
最初に挑戦したのはRTX5070クラスでした。
導入した当初は意気揚々とプレイを始めたものの、実際に設定を落としながら4Kで戦ってみると、安定しないフレームレートにやるせなさを感じました。
WQHDでは問題なくても4Kになると一気にきつい。
数万円の差を惜しんだ自分を静かに責めていたのです。
その後、思い切ってRTX5080に切り替えた瞬間の衝撃は忘れられません。
設定を高にしてもフレームが落ち込むことなく、120fpsを割る気配すらない。
GPUのパワーがここまで心を楽にさせるのかと驚きました。
DLSS 4を併用することで条件次第では144fpsを超える。
初めてその数字を目にした瞬間、「これだよ、これを待っていたんだ」と声を出してしまいました。
一方で、Radeon系統についても無視はできません。
RX 9070 XTを触ったときには、正直に言って性能面では十分戦えると確信しました。
FSR 4のフレーム生成を使えば快適性に余裕が出る。
ただ残念だったのは発熱の傾向です。
特に夏場に長時間プレイをするとじわじわとケース全体が熱を抱え込み、思わず「こんなに暑くなるとはな」と愚痴が出ました。
エアフローやファンの配置が性能以上に実用性を左右するのです。
冷却を制したとき、そのカードは一気に真価を発揮する。
短期間ながらRTX5080で実戦に臨んだ際の印象は、一言で言えば「安定感」。
エフェクトが画面いっぱいに広がる混戦でもフレームは揺るがず、Reflex 2が遅延を抑え込んでくれるおかげで操作の違和感はまるでない。
夢にまで見た理想的な応答性。
これが本当に自分の環境で実現したのだと気づいたときは、年甲斐もなく胸が高鳴りました。
冷静に考えれば144fpsという数値は贅沢です。
しかし、この贅沢がゲーム体験を「格別」に変えるのです。
GPUの力だけで満足してはいけない。
CPUやメモリ、ストレージが調和してこそ全体が完成する。
私が組んだ際にはCore Ultra 7とRyzen 7クラスを候補に考え、メモリは32GBから妥協しませんでした。
ストレージもGen4のSSDを用意し、後で足を引っ張る要因にならないよう意識しました。
空冷でも十分とは思いつつも、静音を優先するとやはり水冷を選びたくなる。
ここをケチって性能を殺してしまうことは、自分にとって大きな後悔になると確信していたからです。
実際に4Kで144fpsを狙うというのは、突き詰めれば「楽しむための贅沢」だと思います。
ただ、その贅沢を選択した瞬間、もう後戻りできない種類の快適さを知ってしまう。
高リフレッシュレート対応モニタに投資しておきながらGPUを妥協するのは、宝の持ち腐れでした。
私は最初にその落とし穴にハマり、後悔を噛み締めました。
そして買い替える手間と追加の出費を冷静に計算したとき、最初からハイエンドを選んでおけばよかったと何度も思いました。
だから私は声を大にして言いたい。
Apex Legendsを4Kで144fps付近に安定させたいのなら、RTX5080かRX 9070 XT以上。
これが唯一の答えなのです。
そしてその力を最大限に活かすために、CPUやメモリ、ストレージの組み合わせもバランス良く配置すべきです。
中途半端を選んだときに待っているのは「やっぱり足りないな」という後悔でしかない。
だからこそ、その時間を最高の状態で味わうことが結果的に心の豊かさにつながるのだと感じています。
数万円の差に躊躇することもあるでしょう。
しかし、それを惜しんでは本来得られる喜びを取り逃してしまう。
私はもう妥協しません。
本気で選ぶ。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 48533 | 101751 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32047 | 77933 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30055 | 66640 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 29978 | 73293 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27075 | 68805 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26420 | 60131 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 21879 | 56698 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19855 | 50392 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16507 | 39301 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 15942 | 38131 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15805 | 37909 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14592 | 34857 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13699 | 30804 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13160 | 32303 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10787 | 31685 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10617 | 28534 | 115W | 公式 | 価格 |
4Kプレイに向けたApex Legends用CPUの考え方

Core i7とRyzen 7、使ってみてどちらがしっくりくる?
ただ、それ以上にCPUによって体験が思った以上に変わることを、私はこれまでの使用経験で痛感してきました。
数値データやベンチマークを見ればおおよその性能差は分かります。
しかし実際のプレイでは、カタログ上の数値以上に「気持ちよく付き合えるかどうか」が大切なのだと実感したのです。
安心して任せられるか、それとも瞬間ごとの切れ味に魅了されるのか――結局そこに尽きるのだと思います。
Core i7を長期間使ってきた私の印象は、とにかく堅実でブレが少ないという点です。
重たいシーンでも一歩引いた余裕のある処理をしてくれて、不安になる瞬間が少ない。
プライベートな夜に深夜までプレイしていても、ファンが急にうるさくなることもほとんどなく、静けさの中でゲーム世界に没頭できました。
静かな環境で遊べることがここまで心地よいのかと、40代になってから改めて気づかされたぐらいです。
一方でRyzen 7に切り替えてみると、気づかされることも多くありました。
特に驚かされたのは、処理の切り返しの速さです。
敵が不意に飛び出してきても、GPUとの連携で即座に反応する。
そのスピード感に胸が高鳴りました。
初めてビル内に突入したとき、ロードの軽さに「おお、これだ」と思わず声が出てしまったことを、いまでも鮮明に覚えています。
勢い。
ただ、Ryzenにも注意すべき面はありました。
配信や録画を並行して長時間回すと、発熱を意識せざるを得ない瞬間があります。
OBSを起動したまま数時間プレイしていると、いつの間にか温度が上がり、不安定さを感じることもありました。
最初にその状況になったときは「これは少し厄介だぞ」と苦笑した記憶があります。
対照的にCore i7では温度上昇の波が穏やかで、配信しながらでも長く安心して遊び続けられました。
安定して動き続ける大切さを、そこでしみじみ理解しました。
Ryzen 7の良さは、スピードだけにとどまりません。
ユーザーがプレイに没頭している時に、そのレスポンスが自然とリズムを後押ししてくれるのです。
次の日のことを考えて苦笑いしつつも、心の中では「やっぱりこの軽快さはクセになる」と思っている自分もいます。
ゲームがここまで気分を盛り上げるのは、Ryzen 7の俊敏さがもたらす、ある種の魔力かもしれません。
もちろん、私のように配信や動画編集も同時に行う使い方だと、Core i7に分があると感じる場面が多いです。
夜中に仕事終わりでゆったりゲームをする時間は、一日の終わりを整えるような大事な儀式のようなものです。
そのひとときに余計な不安を持ち込みたくない。
だからこそ、安定したCore i7の存在は信頼感に直結します。
頼れる同僚のように隣にいてくれる感じがするんですよ。
とはいえ状況次第で心がRyzen 7に揺れる瞬間は確実にあります。
特に仲間とわいわい遊ぶとき、あの俊敏さが爆発力となって盛り上げてくれるのを肌で感じることができます。
やはり「どちらが絶対に上」という結論にはどうしてもならない。
用途や気分によって揺れ動き、それこそが選択の妙なのだろうと思います。
最近はAIを動かしながら配信したり、ブラウザで複数のタスクを同時に処理することも増えてきました。
そのような場面では、やはりCore i7の余裕が光ります。
ファンが控えめに回るだけで、気持ちまで落ち着くのが分かる。
年齢を重ねるほどに、落ち着いた安定環境がありがたくなるのは当然なのかもしれません。
それでも、たまに「今日は勢いで勝負だ」と思う夜は、Ryzen 7を起動し、その切れ味に心を預けたくなるのです。
本当に結果を左右するのはGPU側であり、CPUはむしろ「プレイ時間をどんな性質で支えてくれるか」という違いに現れるのです。
つまり数字だけを見て悩むよりも、自分の遊び方や求める心地よさに照らして選べばいい。
そうやって選んだ方が、結局は自分の時間を豊かにしてくれるのだと思います。
安定した歩み。
切れ味のある瞬発。
私にとってはその両方に魅力があり、どちらか一方に決めきることはできません。
40代の自分にとって、その柔軟さこそが一番の贅沢なのだと感じています。
CPU使用率がフレームレートに与える影響を確認する
これは理屈だけでなく、自分が痛い思いをしてきたからこそ強く言えることです。
GPUだけを信じて選んだ結果、思うように動かない悔しさを何度も味わったんですよ。
昔の私は「4KならGPUが全てだろう」と単純に考えていました。
でも、いざ実際にプレイすると違った。
グラボ自体はまだ余力を残しているのに、CPUが引っ張ることで全体のフレームレートが上がらない。
あのとき「ああ、これがCPUボトルネックか」と頭を抱えました。
正直、机を蹴飛ばしてやりたくなるくらい悔しかったですね。
4K解像度ではGPU負荷が高まるからCPUは気にしなくてもいい。
そう思い込んでいたのも事実です。
ところが実際には、敵の行動計算や物理演算、環境処理など、目に見えない部分を担っているのは全部CPU。
ここが詰まるとGPUは遊んでしまい、結局「宝の持ち腐れ」状態になる。
高いお金を出して買ったグラボなのに、その力を引き出せずもったいない気持ちでいっぱいになりました。
特にApexのようなバトルロイヤルゲームではその弱点が露骨に現れます。
降下直後や複数部隊が入り乱れる銃撃戦の場面でCPUが一気に100%に張り付き、動きが止まった瞬間を何度も経験しました。
「なんで今なんだよ!」と声を荒げたこともあります。
夢中になっているときほど、その一瞬のカクつきで集中が削がれるのは本当に辛いんです。
一度こういう苦い経験をすると、次にパーツ選びをするとき考え方が変わります。
優先するのは「CPUに十分な余裕があること」。
数値のfpsがどれほど高くても、実際の体験がぎこちないなら何の意味もない。
私は数字より自分の感覚を信じる方が正しいと学びました。
いや、本当に痛感しましたね。
当時は「コストも抑えられるしバランスは悪くない」と自分を納得させていたけど、実際に遊ぶと敵が多い場面で処理落ちが顕著に出てくる。
フレームがガタガタと乱れた瞬間に「これ、本当に良い選択だったのか?」と自問自答しました。
答えは明らかに「ノー」。
あの失敗は今も鮮明に思い出せます。
最近ではCPUも確実に進化しています。
省電力性を意識しながら必要なパワーは確保し、冷却性能も向上していますし、静音性もかなり良くなってきました。
だからこそ長時間プレイしても安心して集中できる。
さらに将来的にGPUを買い替える場面が来ても、CPUがしっかり支えてくれる分だけ環境を長く活かせるんです。
それは大きな価値なんですよ。
ただし注意して欲しい点もあります。
CPUの平均使用率だけを見て「余裕がある」と誤解しないことです。
その時、表面上は安定していても裏で処理が追いつかず、カクつきとなって現れる。
これが厄介で、初めて遭遇した私もかなり戸惑いました。
だからこそ一瞬でもピークで余裕があるかどうかを見極める。
それが安定の鍵なんです。
でもそこを支えるCPUが不足していれば、その性能は眠ったまま終わってしまう。
だから私は今、同じようにApexを楽しみたい人へ「GPUだけに頼らず、それに見合ったCPUを選んでほしい」と本心から伝えたいんです。
妥協してはいけない組み合わせ。
これが唯一の答えです。
私は数年かけて遠回りをしましたが、その分強く言えます。
これから選ぶ皆さんには余計な後悔をしないように、安心して遊べる構成を初めから選んでもらいたいんです。
いや、ほんとに。
CPUを軽視していたあの頃の私に伝えたいですよ。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 42923 | 2462 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42678 | 2266 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 41712 | 2257 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41007 | 2355 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38483 | 2075 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38407 | 2046 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37176 | 2353 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37176 | 2353 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35552 | 2194 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35411 | 2232 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33667 | 2205 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32811 | 2235 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32445 | 2099 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32334 | 2190 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29174 | 2037 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28462 | 2153 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28462 | 2153 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25380 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25380 | 2172 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23022 | 2209 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23010 | 2089 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20797 | 1857 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19452 | 1935 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17682 | 1814 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16001 | 1776 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15246 | 1979 | 公式 | 価格 |
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R65V

| 【ZEFT R65V スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7800X3D 8コア/16スレッド 5.00GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R66A

| 【ZEFT R66A スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 8500G 6コア/12スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
| ケース | DeepCool CH170 PLUS Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60XV

| 【ZEFT R60XV スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850I Lightning WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60GU

| 【ZEFT R60GU スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R44CG

高速な実行力で極限のゲーム体験を支えるゲーミングモデル
直感的プレイが可能、16GBメモリと1TB SSDでゲームも作業もスムーズに
コンパクトなキューブケースで場所を取らず、スタイリッシュなホワイトが魅力
Ryzen 9 7900X搭載で、臨場感あふれるゲームプレイを実現
| 【ZEFT R44CG スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 7900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット MSI製 PRO B650M-A WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
配信や動画編集も考えるならCPU選びの基準はこう変わる
私も最初はそう信じ込んでいました。
しかし、配信や録画、さらに動画編集までやろうとした途端に、その甘い考えを後悔することになりました。
ゲームプレイだけでは気づけなかった負荷が、目の前に押し寄せてきたのです。
私は以前、推奨環境を満たしていれば問題ないと楽観して、手頃なCPUで配信を始めたことがあります。
最初は順調にスタートしたものの、数分後に映像が突然カクつき、OBSが止まり、視聴者から「止まってるよ?」というコメントが次々届く。
背中を汗がつーっと流れ、画面の前で固まった瞬間を今も鮮明に覚えています。
あのときの恥ずかしさと悔しさは忘れられない。
まさに配信事故。
その経験以来、私は確信しました。
マルチスレッド性能やエンコード性能があるかどうかで、全体の安定度はまるで違う。
Core Ultra 7やRyzen 7クラス以上であれば、ゲーム用の処理と配信用の処理を並行して走らせても、CPU使用率が急に跳ね上がることはずいぶん減ります。
慌てることなく、安心して作業に集中できる。
やはり余裕があるかどうかは精神面でも大きいと痛感しました。
もしここで、コストを抑えようとしてミドルレンジ以下を選んでしまったらどうなるか。
かつて私がそうであったように、「趣味のはずだった楽しみ」が逆に強いストレスに変わってしまいます。
楽しいはずなのに苦しくなる。
これが一番つらいのです。
さらに動画編集までを含めて考えるなら、シングル性能だけではとても足りません。
複数のエフェクトやレイヤー編集を行うと、マルチコアを搭載しているかどうかで作業効率がまるで違ってきます。
私は以前、Core Ultra 7からRyzen 9に乗り換えたことがありました。
するとレンダリング時間が三割以上短縮されて、本当に驚いたのです。
その差はしばしば数時間単位になり、仕事から帰っての限られた夜の時間を丸々別のことに使えるようになる。
だからこそ投資する価値は確実にあると実感しました。
冷却も軽視できません。
長時間配信をしていると夏場は特に顕著で、空冷では数時間経つうちにファンが全力で回り始め、部屋中にその唸りが響きます。
やかましさに気持ちが削がれてしまう。
すると静かで安定し、集中力を切らさずに済む環境を作れる。
快適さに直結するのは意外にもこうした細部であると痛感しました。
あのときの安心感は、今でも忘れられません。
一般的に「推奨動作環境を満たしておけば十分だ」と言われることは多いものです。
しかし現実には、ただプレイするだけと、配信や編集を含めて実行するのとでは世界が全く違います。
趣味にするにしても、本格的に取り組むにしても、やることが増えれば機材の要求水準も自然と上がる。
私は失敗を通じてようやく学びました。
安く済ませたい気持ちは理解できます。
私自身、同じ気持ちでスタートした過去がありますから。
ですがほんの少し上位モデルを選ぶだけで、後々のトラブルは見事に消え去ります。
不満を抱えない未来を手にできるのです。
あとから買い替えて後悔するくらいなら、最初から余裕を確保しておいた方がはるかに賢明です。
これはもはや鉄則に近い。
投資した分は必ず時間の節約と安心につながって戻ってくるのです。
CPUは単なる部品ではありません。
快適に遊ぶための土台であり、配信を通して人とつながるときの信頼の架け橋でもあります。
私が何度も失敗を繰り返したからこそ断言できます。
CPUを甘く見て妥協すれば、そのツケは必ず自分に返ってきます。
しかし逆に、余裕を持ったCPUを選んでおけば、時間も心の余裕も手に入る。
これは本当です。
CPUは妥協するな、と。
Apex Legends用ゲーミングPCのメモリとストレージ構成

DDR5メモリは32GBと64GBで使用感に違いはあるのか
4K解像度でApex Legendsを遊ぶ環境を整えるうえで、私が実際に32GBと64GBの両方のメモリ環境を試した経験から言えるのは、ゲームを主体とするなら32GBで全く問題なく、ただし動画制作や配信を並行するなら64GBの安定感はやはり魅力的だということです。
ゲームだけを考えるなら、フレームレートやロード時間で不満を感じる場面は32GBの環境でも一度もありませんでした。
普通に快適ですし、プレイ時にストレスを覚えたことはなかったのです。
率直にいって、純粋なゲーム体験では32GBが現実的な結論だと実感しました。
しかし私の使い方はそこまで単純ではありません。
仕事柄、録画をしながらプレイしたり、配信を同時に動かしたり、さらに裏で動画編集ソフトを起動することも珍しくないのです。
そうなると、32GBでは操作の切り替えに微妙な遅れが出始めて、「おやっ」と思わされる瞬間がありました。
ちょっとしたもたつき。
それが小さくても気になってしまうのです。
けれど64GBに切り替えた途端、その煩わしさが嘘のように消え、どの作業も人間の意識の流れに合わせるように即座に反応してくれた。
その軽快さに心底驚いたのをはっきり覚えています。
それでも「余裕」が与えてくれる安心感というのは、小さな違いの積み重ねとして確実に体感できるのだと思います。
アップデート後のイベントで32GB時に一瞬カクついた場面では、プレイ中に「また来るかもしれないな」と無意識に構えてしまいました。
ところが64GB環境では同じ場面でも不安がなく、純粋にプレイに集中できたのです。
これが私にとっては見過ごせない価値でした。
ただ当然のことですが、64GBへの投資は安くはありません。
BTOパソコンの構成相談を受けるとき、私はよく「その差額を冷却に回しませんか」と提案することがあります。
長時間プレイするなら適切な冷却と静音性を確保した方が、実は体感的に快適に直結するのです。
冷却にお金を掛けた方が、夏場の動作安定性やファンの騒音の少なさを実感できます。
だから「メモリは多ければ正義」という単純な話ではないのです。
私が64GBを推すのは、短期の快適さより長期利用を見越す方です。
私は数年単位でPCをアップグレードせずに過ごしたいと考えているので、この安心は大きいと思いました。
これが作業集中を邪魔しないのです。
「心の余裕」と言うと少し大げさかもしれませんが、日々の実感としてはけっこう大事な要素なのです。
逆にゲーム専用の方には64GBをおすすめしません。
私自身、ゲームだけなら32GBで困ったことは一度もなく、むしろ過剰だと感じました。
実際、CPUやGPUを強化した方が目に見えて効果を感じやすいですし、投資の満足度はそちらに軍配が上がるでしょう。
ゲームを快適に楽しみたいなら、32GBで十分以上に仕事をしてくれる。
それが私の正直な感想です。
最終的な判断は、どんな使い方を想定しているかという一点にかかっています。
Apexを4K高画質で快適に遊ぶだけなら32GBで問題はなく、予算はグラフィックカードや冷却に回す方が賢い選択になるはずです。
一方で配信や動画制作を絡めるなら、64GBの余裕が結果的に仕事や趣味の効率を大きく底上げしてくれます。
ゲームなら32GB。
振り返れば、選択に迷い続けた日々もありました。
けれど冷静に使い方を見直してみれば、答えは思った以上に単純でした。
つまるところ、自分がPCに何を求めているのか。
それを突き詰めて考えることが、後悔しない選択につながるのだと今では強く思います。
SSDはGen4とGen5、実際に体感できる差はある?
SSDの選び方で迷っている人には、私はまずGen4をおすすめします。
実際に日々の使い方を考えると、今のところGen4で十分困らないのです。
数字のスペック上ではGen5のほうが早い場面もあるのですが、ゲームをしているときに「ああ、ここでGen5じゃないと厳しい」と感じる瞬間はほとんどありません。
正直、ロード速度のわずかな差よりも、ゲーム自体の処理やサーバーとのやり取りで待たされる時間のほうが圧倒的に多いです。
つまり数字ではGen5が勝っていても、体感としての劇的な差は出にくいということです。
ただ、この話はゲーム中だけのこと。
実際にはゲームを起動する前から試練は始まっています。
Apexのようなタイトルはアップデートの容量がやたら大きく、数十GBものダウンロードと展開に毎回付き合わされる。
一度や二度なら我慢できますが、これが積み重なると心底疲れるんです。
私も深夜にアップデートが突如始まり、寝かせていたPCの前で「いつ終わるんだよ」とイライラしながら時計を睨んだ夜を今でも覚えています。
そのときにGen5の転送速度の速さは確かに助けになりました。
時間が縮まるだけで気持ちは大きく変わる。
小さな差ですけど、大事な部分です。
しかしGen5には忘れてはいけない弱点があります。
それは発熱です。
私が一番痛感したのは真夏。
システムドライブにGen5を入れて過ごしたら、気温の上昇に合わせてSSDの温度が90度近くまで跳ね上がり、気がついたら勝手に速度が落ちていました。
がっかり感というより、裏切られた気持ちに近かったです。
「せっかく高性能を選んだのに、まるで自分の環境がその性能を殺してしまっているじゃないか」と思いました。
性能を存分に発揮させるには、冷却や電力環境を真剣に考える必要がある。
それがなければ宝の持ち腐れです。
性能を追うこと自体が目的化すると、本当に大切なことを見失うんですよね。
一方でGen4は驚くほど安定感があります。
むしろ「これで十分だ」と自然に思える。
派手さはないけれど、地に足のついた選択。
それがGen4の大きな価値です。
もちろん未来への視点も無視できません。
新しいCPUやGPUは既にPCIe 5.0対応ですし、「せっかくだから全部Gen5で」という気持ちは理解できます。
でもよく考えてみてください。
本当に体験を変えるのは、GPUやネットワーク、あるいはAIによる最適化のほうなんです。
今この瞬間でGen5にしなければゲームが遅れるという事態にはならない。
私は実際に触れてみて、そう確信しました。
だからこそ焦って飛びつく必要はないのです。
実体験をもう一つ挙げます。
ですが私の体験談を伝えると、彼はGen4に変更しました。
そして完成したPCは静かで心地よく、アップデートも十分早い出来映えになったのです。
その笑顔を見たとき「現実的な判断こそ後悔しない選び方なんだ」と心から感じました。
背伸びせず、身の丈に合った判断をする。
まるで仕事の意思決定と同じだなと、自分の中でつながった瞬間でした。
加えて補足するなら、Apexを4Kで動かしたいのならSSDよりGPUとメモリを優先すべきです。
最新のGPUや大容量メモリを積んでいれば、SSDのGenによる差はほとんど気づかないでしょう。
優先順位をつけるならSSDは二の次。
ただしアップデートやデータ移動の待ち時間は意外に効いてくるので、そのバランスをどう取るかは人それぞれ判断が分かれるところだと思います。
私が行き着いた答えはシンプルです。
システムドライブにはGen4を選び、余裕がある人は追加でGen5をデータ用にしてみる。
発熱リスクを抑えつつ高速の恩恵の一部を味わえる。
冷静で堅実、それでいて遊び心を残した大人の選び方だと感じています。
選択肢を一つに絞らず、バランスを取ること。
それが結局もっとも現実的で納得のいく構成になるのです。
安心感が違うんです。
静かさが心を落ち着けてくれます。
失敗した経験を持っている分、余計に「後悔しない選択」をしてほしいと思うのです。
無理に最先端だけを追わなくても、日々気持ちよく付き合えるPCがあれば十分。
それが私の本当の実感です。
ではGen5はいらないのかと聞かれると、それも違います。
挑戦したい人にとっては価値がありますから。
最先端を手にしたときのワクワク感は格別で、実際に触れてみると胸が高鳴る瞬間もあります。
その気持ちはとても大切です。
ですから選択肢としてGen5を残すことは否定しません。
結局のところ、私は安定したGen4に信頼を置きます。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
ストレージ容量は1TBと2TB、どちらを選ぶと安心か
Apex Legendsを4Kで快適に遊びたい人にとって、結局のところ1TBよりも2TBのストレージを選ぶのが間違いのない選択だと、私は自分の経験から強く感じています。
もちろん1TBでも当初は十分そうに見えるのですが、それはあくまで「今だけの話」に過ぎません。
長い目で見たときに、安心してゲームや仕事を楽しみたいなら、容量の余裕は欠かせないのです。
私自身、最初に1TBを選んだのはコストパフォーマンスを考えたつもりでした。
安いし当面は足りると思ったし、とりあえずこれなら困らないだろうと軽く考えていたんです。
でも実際に運用を始めてみると、アップデートの大きさや新しいゲームの追加、そして録画データがみるみるうちに増えていって、気づいたときには空き容量が常にギリギリの状態。
毎回どのゲームを残し、どれを消すかで悩む日々は本当にストレスでしたね。
正直、もううんざり。
今のゲームは容量の食い方が本当に半端じゃありません。
最新の大作タイトルだと普通に100GBを超えてきますし、オープンワールド系やFPSなどは200GBに迫ることも珍しくない。
さらに私の場合は仕事でも動画編集をする関係で、プロジェクトファイルやキャッシュだけで数百GBが一気に消えることもありました。
そのたびに「また容量が足りない…どうしよう」と頭を抱えていました。
精神的にもしんどいし、何より時間の無駄なんですよ。
これではせっかくの趣味が台無しです。
遊びたいときにすぐ遊べないのは本当に痛い。
1TBの環境って、例えると目先の距離しか走れない短距離走のようなものです。
その瞬間は全力で走れても、持続力がない。
逆に2TBはマラソンランナーのように長期間安心して使い続けられる余裕を持たせてくれるんです。
録画データもまとめて残せるし、スクリーンショットやWindowsの更新ファイルなんかも全部受け止めてくれる。
これは大きな違いでした。
思い出すのは、1TBから2TBに換装したときのことです。
データ移行作業は正直面倒で、あのときは夜遅くまで作業に追われました。
終わったときにはヘトヘト。
それでもやってよかったと心から思えたんです。
翌日からは空き容量を気にする必要がなくなり、パソコンを立ち上げただけで心持ちが軽くなる。
なんだか解放感すらありました。
安心感って、思っている以上に日常に影響を与えます。
容量の余裕があるかないかで、パソコンに向き合うときの姿勢が全然違うんです。
以前は常に容量不足の警告や赤いゲージにビクビクしていましたが、今は構える必要がない。
ただ好きなように使える。
この小さな違いが積もり積もって、大きな気持ちの余裕につながっていきました。
2TBのもう一つの良さは、使い分けがしやすい点ですね。
私はシステム領域、ゲーム領域、そして録画用領域と大きく分けて使っています。
こうするとファイルが整理しやすいし、問題が発生したときに切り分けるのも容易です。
その安心感は地味ですが確実に効いてきます。
トラブルが起きにくい環境って、実際かなりのストレス軽減につながるんですよ。
もう、よけいな不安が減るだけで快適。
4TB以上のモデルはまだまだ高価で、BTOパソコンに組み込もうとすると全体のバランスを一気に崩してしまう。
だから私は今の時点で実用性とコスト、そして性能を考えたら、Gen4規格の2TBモデルが最適だと思っています。
スピードも十分にあり、容量のゆとりもある。
長期的に見ても後悔の少ない選択です。
たとえば休日に一日中撮影したプレイ動画を高画質で保存しようとすると、数十GBが一気に吹き飛びます。
これが続くと1TBなんてひとたまりもありません。
気がつくとストレージが真っ赤に染まり、起動するたびに容量チェックをしなければならない生活。
正直、もう二度と戻りたくないです。
一度余裕のある環境を味わうともう戻れない。
これは事実です。
だからこそ私は最初から2TBを選ぶことを強く勧めたい。
ゲームも仕事も楽しみ尽くすためには、容量に追われる生活から解放される必要があるからです。
安心して遊びたい。
ストレスを減らしたい。
余裕を持って仕事したい。
だからこそ2TB。
これが私の答えです。
Apex Legends向けゲーミングPCを安定させる冷却とケース選び


空冷と水冷、それぞれの特徴と選びやすいクーラー
Apexを4Kで安定して楽しむために冷却方法をどう考えるべきか、これは一見すると単純な性能比較の話に見えますが、私の実感としては「空冷と水冷のどちらを選ぶかは最終的に自分の性格や生活スタイル次第」だと思っています。
無理をせずに長く付き合える冷却方法を選ぶこと、それが結局は一番後悔の少ない決断だと確信しています。
空冷には古くからの安心感がありますし、取り付けも単純でわかりやすい。
正直言って、PCを触るときは「安定して動作して当たり前であってほしい」と思っているので、それを自然に実現してくれる点が大きな魅力なんですよね。
かつては夏場に熱暴走でソフトが落ちてしまい、作業も遊びも台無しになることがありましたが、大型の空冷クーラーに交換して以降はそうした心配が激減しました。
冷却が安定していると、それだけで気分まで落ち着くものですし、静かに遊べる時間の価値を改めて思い知らされました。
ヒートパイプやフィン構造が以前より明らかに工夫されていて、静音性も向上しています。
夜に作業やゲームを楽しんでいるとき、昔のように「ファンがうるさいな」と思うことはなくなりました。
私の家にも家族がいますが、余計な機械音が響かないというのは生活面で想像以上に大きなメリットなんです。
やっぱり静かっていいんですよ。
一方で、水冷は「冷える」という点で空冷を一歩リードしているのは間違いありません。
液体が効率的に熱を運ぶため、CPUやGPUの温度が見事に安定します。
その安定感に、思わず声が出ました。
「ここまで違うか」と素直に驚いたものです。
水冷の魅力はもうひとつあります。
静音性です。
昔はポンプの音が気になって仕方なかったのですが、今は随分と進化しました。
空冷よりも静かに感じることさえあるくらいで、日常利用でも使いやすさを実感できるレベルに来ています。
性能・安定性・静音性、この三つを求めるなら水冷が有力な候補であることは確かです。
私自身数年前に液漏れでマザーボードをダメにし、結果的に予想外の出費を強いられた経験があります。
そのときは本当に悔しかった。
「二度と水冷なんて入れるものか」とまで思いました。
けれど最近の製品は進化していて、その信頼性は格段に上がっています。
今ならあそこまで神経を尖らせる必要はないかもしれません。
全体を比較すると、空冷は堅実で手堅い選択、水冷は性能重視で攻めの選択、というイメージです。
どちらが正しいという答えはなく、やはり求める方向性に左右されます。
例えばPCケースによってはラジエーターが収まらないなど、物理的な制約も出てきます。
ここを見落とすと「買ってから入らない」という笑えない事態になりかねません。
冗談抜きで事前確認が欠かせない部分なんです。
私は普段の業務や生活の延長線上でPCを扱う以上、静音性と安定性を優先して空冷を選んでいます。
特に最近のCPUは発熱が以前ほど厄介ではなくなっているので、大型空冷を導入しておけば十分対応できます。
ただ、一方で少しでもフレームレートを高く維持し、最高の環境でゲームを楽しみたいという方には、水冷の存在が大きな支えになるでしょう。
実際に私も試した際には「なるほど、こういう世界か」と納得せざるをえませんでした。
最後に、私が伝えたいのは冷却は単なるスペック競争ではないということです。
長時間ゲームをしていてもシステムを信じて任せられること。
その安心感が心から嬉しい。
数字や規格の比較を超えた部分にこそ、本当に大切な価値が隠れています。
冷却を選ぶことは、単にCPU温度を下げるためだけでなく、自分の時間をどう過ごすかを決める選択でもあるのだと私は感じているのです。
安心という満足。
信頼できる相棒。
そして最終的に、空冷か水冷かという二択を決めるのは自分の心の中にある「納得できるかどうか」という基準だけなのだと私は強く思っています。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z57J


| 【ZEFT Z57J スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 245KF 14コア/14スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z58N


| 【ZEFT Z58N スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 235 14コア/14スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | LianLi A3-mATX-WD Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z58Q


| 【ZEFT Z58Q スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 235 14コア/14スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
| ケース | LianLi A3-mATX-WD Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN EFFA G09C


| 【EFFA G09C スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal North ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 360 Core II White |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52AH


| 【ZEFT Z52AH スペック】 | |
| CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake Versa H26 |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
エアフローを重視するケースと静音志向のケースの違い
もちろん人それぞれ価値観は違いますし、静けさやデザインの好みを大切にしたい方もいるでしょう。
でも、自分の体験を振り返ってみると、最終的にゲームの快適さを維持できたのは、冷却を重視した選択をしたときでした。
初めて高性能のケースを導入したときのことは今も鮮明に覚えています。
RTX40番台のGPUをフル稼働させても温度は安定し、戦闘中にカクつきもなく、画面は驚くほどなめらかに動きました。
いや、本当に「冷却が全てを支えているんだ」と心底納得した瞬間でした。
ただし、良いことだけではありません。
ファンの音はどうしても無視できない存在になります。
静音性と快適性のどちらを選ぶか。
これは実際の生活の中で悩まされる本気のテーマです。
静音重視のケースも試してみました。
分厚い遮音パネルと内部の吸音材の力で、動作中であることを忘れてしまうほど静か。
特に在宅勤務で会議をする際、人の声がはっきり聞こえ、相手に「PCの音がうるさいですね」と言われる心配もありません。
その快適さには感謝したい気持ちが湧いてきました。
集中できる。
落ち着ける。
このメリットは大きいです。
しかし残念なことに、GPUやCPUに本気で負荷をかけると熱が籠ってしまうため、長時間のプレイには厳しかった。
最初は気づかずにプレイしていたのですが、数時間を超えた頃、画面の動きに違和感が出て、それが温度上昇による性能の低下だと分かったのです。
「快適な静音環境か、それとも安定動作か」。
悩ましかった。
最近は両立を目指す新しいタイプのケースも出てきています。
私が試したものも、ガラスパネルの見た目が美しく、冷却力も十分に感じられました。
選択肢が少し広がったように感じ、これまでの「二者択一」という息苦しさが和らいだ気がしましたね。
それでも、私はあえて断言したいのです。
Apexを4Kで遊ぶには、エアフロー重視のケースが最も信頼できると。
静音性を求めつつ快適さも大事にしたいのであれば、別途冷却ファンや簡易水冷クーラーなどを追加する工夫が必要です。
そこを軽く考えると、すぐに性能が落ちる形でしっぺ返しが来る。
冷却不足はプレイの中断、集中力の乱れ、そして「やっぱり失敗したかもしれない」という後悔につながります。
私はかつて、大口径ファンを複数搭載したケースを導入し、真夏の週末に14時間プレイし続けた経験があります。
エアコンを切ってもGPUのクロックが下がらず、フレームレートは安定し続けました。
ふと時計を見た瞬間、「あれ、もうこんな時間か」と気づき、快適な環境が時間を忘れさせるんだと実感しました。
なので私の指針は明確です。
高負荷の4K環境でApexを本気でプレイする人は、迷わず冷却力を優先すること。
ただ、選び方に迷っているなら、答えは単純でいい。
「エアフロー重視」。
プレイを全力で楽しみたい人ほど、このシンプルな真理に行き着くはずです。
見た目にこだわってケースを選ぶときのチェックポイント
ケースを選ぶ上で、私が一番大切にしているのは「見た目と実用性の両立」です。
どちらか一方に偏ると必ず後悔するんですよね。
昔、デザインだけで気に入ったケースを衝動買いしたことがあるのですが、冷却性能をまったく考えていなかったせいで数か月で手放す羽目になりました。
当時は本当に自分の判断の浅さを痛感しました。
だからこそ今は、デザイン性と冷却性能の両方を必ず確認することを習慣にしています。
パッと見で格好良くても内部が熱地獄じゃ、話にならないんです。
強化ガラスのケースが流行り始めた頃には、私も人並みに惹かれていました。
RGBの輝きが全面に広がっていると、最初はそれなりにテンションは上がるんです。
でも実際に数時間ゲームをしたら、筐体の内側は高温で、ファンは全開、うるささと熱気で参ってしまった。
綺麗な見た目にだけ引っ張られた自分が情けなくて、あの時の失敗は本当に痛手でした。
だから最近は、まず空気の通り道がちゃんと設計されているか、吸排気のバランスが取れているかを最初にチェックしています。
特に気に入っているのは木製パネルを取り入れたケースです。
これは正直意外でした。
最初は「木なんてパーツと合うのか」と疑っていたのですが、実際に部屋に置いてみたら想像以上に溶け込みました。
私のワークスペース兼ゲーム部屋は無機質すぎる空間だったのですが、木目の温かみが加わることで空気が柔らかくなったんです。
派手な照明で気分を盛り上げるのも悪くないですが、40代になった今の私には落ち着いた環境の方が性に合います。
集中力も上がり、作業効率まで改善しました。
自分でも驚いたくらいです。
ただし、どんな場合であれ「見た目だけで選んじゃダメ」。
これは声を大にして言いたい。
とくに大型のGPUを活用してゲームをする人は要注意です。
サイズが入るかどうかの確認、設置後にグラボがたわまない設計か、補助の支えが入れられる構造か。
ここを甘く見ると本気で痛い目を見ます。
高価なパーツを壊してしまうリスクだってある。
怖いですよ、ほんとに。
最近はサイドパネルがガラスでフロントがメッシュ、いわゆるハイブリッド型のケースが増えてきていて、私はこれを強く推したいんです。
見た目の美しさと冷却性能を同時に確保できるから。
以前はケースの違いなんて誤差だろうと軽視していましたが、実際に温度モニタリングをしたら驚きましたよ。
同じ構成なのにケース設計だけで10度近く差が出るんです。
体感するともう後戻りできません。
内部設計も見逃せません。
電源カバーの有無や裏配線スペースがしっかり作られているかで、完成度が大きく変わります。
ケーブルをすっきり整えられるだけで、組み立てたときの満足感が段違いなんです。
細かいことですが、ここを軽視すると後悔します。
最近はRGBライティングの制御が最初からシステムに組み込まれたケースも増えていて、配線の煩雑さがだいぶ減ってきました。
最初に電源を入れたとき、鮮やかに統一された光がスッと点灯する瞬間は、やっぱりワクワクする。
「おっ、綺麗に揃ったな」なんて、独り言が出ましたね。
ただ便利さや派手さだけを追いかけると、必ずぶつかるのがファンノイズの問題です。
前面を完全メッシュにしたケースは吸気が最高で温度管理もしやすいのですが、その分どうしても音が漏れる。
夜中、静かな部屋で「ブーン」と響く音に苦しんだ経験は、今でも忘れられません。
24時間稼働するPCを傍に置く生活を続けていると、その小さなノイズが積もってストレスになるんです。
そのため、私は冷却と静音のちょうどいい着地点を見つけることを大事にしています。
印象的だったのは、木製パネルケースを導入したときです。
硬質な鉄とガラスのケースだけを使っていた頃は、どうしても冷たくストイックな作業空間になっていたのですが、木の温もりが見た目だけでなく心にも作用しました。
PCに向かうこと自体が自然とリラックスできる時間に変わり、長時間作業していても苦痛を感じにくくなったんです。
本当に目から鱗が落ちた瞬間でした。
最終的に私が強く伝えたいのは、ケース選びを侮ってはいけない、という一点に尽きます。
Apex LegendsのようにGPUに負担のかかるゲームを4Kで楽しむには、ケースの選択次第で快適さが大きく変わるんです。
ケースは外から一番目に入る部分であると同時に、内部のパーツを守り、性能を支える大切な器。
だからこそ「見た目が格好いい」か「冷却性能が優秀」だけでは足りない。
両方をちゃんと満たす必要があります。
私は若いころ、何度もケースを買い替えては後悔を繰り返し、ようやくこの答えにたどり着きました。
最新のハイブリッド構造や配線性に配慮したケースを手に入れたとき、感じた安心感と満足感は格別です。
昔の私に教えてやりたいですね。
「ケース一つでここまで変わるんだぞ」と。
つまり、見た目へのこだわりが強い人ほど、冷却や静音といった地味な要素を軽視しちゃいけない。
これが、今の私が腹の底から実感していることです。
そして心から皆さんに伝えたいことです。
Apex Legends用ゲーミングPC購入に関する疑問まとめ


4K環境でApex Legendsは実際どのくらいfpsが出るのか
いざ構築してみると、「結局ここに行き着くのか」と実感しました。
どちらか一方では満足できないのです。
私はRTX 5080クラスのGPUとRyzen 7 9800X3Dを組み合わせ、自作PCを構築しました。
その結果、平均で90fps前後を安定して出せたのですが、特に激戦区に降りた際でも80fps台までしか落ち込まず、カクつきは一切ありませんでした。
この滑らかさと映像美の融合は、自分の目で確かめるまでは正直半信半疑でしたが、実際にプレイ中に敵の動きを細かく捉えられる瞬間は、スペックに投資した意義を実感した場面でした。
やはり数字だけでなく体感こそ価値だなと痛感したのです。
ただし120fps以上を狙うなら、画質設定をある程度落とす覚悟が必要です。
私は「どこまで映像美を追求するか」と「どこまで勝ちにこだわるか」、この二つのバランスで悩みました。
毎回の戦績を突き詰めたいなら軽さ重視。
だから私は大げさではなく、100fps前後で映像美と戦術性が調和するところが最適だと考えました。
欲張りかもしれませんが、これが大人の楽しみ方かもしれません。
ストレージに関してはGen.4 NVMe SSDを使いました。
これが想像以上に効果的でした。
マップの切り替えが本当に一瞬で、ロード中にぼんやり待つ時間が激減。
特に連戦を繰り返すときには、ストレスレスな環境こそが集中力を維持する助けになります。
気持ちに余裕が生まれるのです。
ただし課題はやはりGPUです。
CPUを最高クラスにしてもGPUが足を引っ張れば結局fpsは頭打ち。
パーツの役割を理解しないと無駄な投資になります。
私もCore Ultra 7 265Kを以前試したときに、ApexがCPU依存度の低いゲームだと改めて納得しました。
空冷環境でも十分安定して動いたので、結局「程よいCPUと攻めのGPUの組み合わせ」が正解なのだと確信するに至ったのです。
これが要点。
メモリは必ず32GBを推奨します。
表面的には16GBでもなんとか動くのですが、実際に4K設定や配信を同時にすると差は歴然です。
単なる容量の数字ではなく、余裕のあるシステムは臨機応変に動き、ちょっとしたトラブルを抑えてくれる。
私は32GB環境にしてからゲーム中の不安感が一気に消えました。
冷却の重要性も外せません。
以前はデザイン性に惹かれてガラス張りピラーレスケースを選んだのですが、ゲーム中に熱がこもり、fpsも下がる場面が出てしまったのです。
驚きました。
そこで、思い切って前面からの高エアフローを確保できるケースに変えてみたら、安定性が見違えるように改善された。
正直少し悔しかったですが「やはりPCは見た目よりも性能」。
この経験は今でも忘れられません。
私が辿り着いた構成は、GPUは最新上位、CPUは堅実、メモリ32GB、ストレージはGen.4 NVMe SSD、そしてケースは冷却重視。
この組み合わせで、4K環境でのApexは極めて快適になります。
もちろんコストは安くありませんが、それでも私はこう思います。
払った額以上の価値はあった、と。
数字では測れない満足度が確かにそこにあるのです。
仕事が終わった一日の終わりに、ハイクオリティな映像で没頭できる。
戦場の緊張感に集中しながらも、同時に心のどこかで癒やされている自分がいるのです。
大人だからこそ、日常の中にこうした「ご褒美の時間」が必要なのだと実感しています。
忘れられない体験になったのです。
そして何より、4Kでのプレイはゲームと自分の距離を変えました。
時間が限られる40代の私にとって「やるなら妥協しない」という選択は、自分自身へのささやかな励ましでもありました。
贅沢かもしれませんが、そこにしか得られない達成感と安らぎが存在していたのです。
コストを考慮するとRTX4060Tiは買う価値がある?
理由は単純で、価格と性能のバランスがゲーム解像度によってあまりにも左右されてしまうからです。
普段からPCを使い倒してきた私としては、この割り切りが不可欠だと感じています。
実際に触ってみた経験もあります。
友人から頼まれてBTOのゲーミングPCに4060Tiを組み込み、WQHD環境で「Apex Legends」を試しました。
結果は快適そのもの。
設定をほんの少し調整するだけで、ハイリフレッシュレートのモニタともしっかりかみ合い、動作も安定していたので「これは良いな」と素直にうなずきました。
ところが4Kに切り替えた瞬間、雰囲気はがらっと変わります。
フレームレートの落ち込みが目立ち、動きが途切れる場面に直面すると、爽快感よりもストレスが先に来てしまい「これは厳しいな」と感じざるをえませんでした。
映像は確かに美しい。
RTX4070やそれ以上のモデルと比べると導入コストは抑えられますし、消費電力や発熱も控えめ。
だから電源容量や冷却能力に制約のあるケースでも選びやすいのは確かです。
けれど心のどこかで引っかかるのは「数年後、このカードはまだ戦えるのか」という思い。
長い時間軸で見れば、数万円上乗せして上位GPUを買っておいた方が安心だという勘がどうしても働くのです。
実際に甥から「Apexを始めたいんだけど、どんなPCがいい?」と相談を受けた時にも、このことを説明しました。
学生で限られた予算、当然ハイエンドGPUは非現実的。
そこで私は4060Tiを候補に挙げ、WQHDを前提に勧めたのです。
設定を落とせば200fps前後を狙えることも分かっていたので、価格と性能のバランスは今の彼に合っていると判断しました。
それを聞いた彼は「それならいけそうだ!」と顔を輝かせていました。
こういうケースでは間違いなくハマるカードだと断言できますし、若い世代にとってはちょうどいい落としどころなのです。
ただし、4Kを前提とする方には勧めにくい。
たとえるなら、ビジネスの重要なプレゼンの場面で、必要な資料を半分しか揃えずに挑むようなもの。
やれないことはないけれど、勝負を決定づける力は不足している。
実際、最近のゲームは軽量化されている部分もあるものの、全体的なリッチ化の流れは止まっていません。
4Kの設定となると必要なリソースは確実に跳ね上がり、長期的に楽しもうと思えばどうしても余裕のあるGPUを用意すべきだと痛感します。
正直に言えば、私たちの年代になるとゲームに使える時間は限られてきます。
仕事も家庭もある。
だからこそ、その短い時間をストレスなく遊べるかどうかは死活問題なんですよ。
安心して遊びたい。
これに尽きます。
これは年齢を重ねたゲーマーにとって非常に重要なキーワードだと思います。
せっかくの趣味なのに「性能の限界を気にしながら遊ぶ」という状況になれば、楽しさよりも後悔が残ってしまう。
だから私は、少し無理をしてでも余裕を持ったGPUを選んだ方が、最終的に「買ってよかった」と思えるのだと信じています。
一方で、現実的に「まずはPCを組んでゲームを始めたい」という人にとっては4060Tiは非常に有力なカードです。
特にフルHDからWQHDの範囲を前提にするなら、その性能とコストの釣り合いは素晴らしい。
万能ではありませんが、的を絞れば本当にバランスが良い。
私自身、これまで何台も環境を構築してきた経験があるので、そのポジションの安心感はよく分かります。
だから最終的な判断は単純です。
ただしどうしても予算を抑えたいが手元に4Kモニタがある、という方には、一時的なつなぎの選択肢としての価値はあるかもしれません。
しかし2年、3年と長く使うのであれば間違いなく物足りなくなり、結局は買い替えの必要に迫られる。
その時に悔しさが残る未来が想像できてしまうのです。
率直に言うと、安心して4Kを楽しみたいならRTX5070以上を狙うべきです。
4060Tiの価値は、あくまでWQHDを中心に考えた場合に輝きます。
役割を理解して正しい場に置くことで、このカードは非常に心強い存在になる。
つまり、自分の用途を冷静に見極められるかどうかがポイントです。
信頼の判断基準。
最終的にはここに落ち着くはずです。
RTX4060Tiは決して万能ではない。
しかし用途を見極めて選べば、非常に賢い選択になり、長く「良かったな」と思える。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R67S


| 【ZEFT R67S スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X3D 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Corsair FRAME 4000D RS ARGB Black |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 360 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z58C


| 【ZEFT Z58C スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster Silencio S600 |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z58W


| 【ZEFT Z58W スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
| ケース | Okinos Mirage 4 ARGB Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56AD


| 【ZEFT Z56AD スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R52O-Cube


ハイレベルゲームも快適に対応するパワフル・ゲーミングPC
高速32GB DDR5メモリと最新のSSDの極上のハーモニー
省スペースに収まる美しきコンパクト設計のマシン
Ryzen 7 7700の力強いパフォーマンスを体感せよ
| 【ZEFT R52O-Cube スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | INWIN A1 PRIME ピンク |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850I Lightning WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
長く使うことを考えた場合の現実的な構成とは
Apex Legendsを本気で4K環境で楽しみたいと考えたとき、やはり一番の鍵になるのはグラフィックカードだと私は思います。
いくらCPUが優秀でも、4K解像度で映像処理の大部分を担うのはGPUであり、ここが不足していると一気に全体の実力が引き下げられるのを過去に嫌というほど味わいました。
中途半端なGPUを選んで数年後に買い替えざるを得なくなった経験があるからこそ、今回は最初からしっかり上位モデルを選ぶと心に決めています。
とはいえ「GPUさえ良ければ安心です」と単純には言えないのも事実です。
CPUがある程度の水準に達していなければ、映像は滑らかに動かず、敵を目の前にして一瞬止まるような挙動が出ることがあります。
あのワンテンポ遅れる感覚はオンライン対戦では致命傷なんですよね。
ただ数年先までスムーズに戦えることを考えれば、結局は妥当な投資だったと自分に言い聞かせることになります。
私が実際に信頼しているのはCore Ultra 7 265KやRyzen 7 9800X3D辺りのクラスで、消費電力や発熱の面でも極端に神経質にならなくて済み、長期間でも安心して遊べた実感があります。
ひとことで言えば、安心感。
メモリは、16GBでもゲームは動きます。
通話アプリ、配信ソフト、ブラウザを同時に動かすと、すぐに限界を超えてしまった経験があります。
そのため、現実的には32GBが最低ラインだと思っています。
さらに余裕を確保するなら64GBを選んだほうが長い目で見れば確実に快適だと感じます。
余裕が生む気持ちの余裕。
使っていてカクつきが無いことが私にとって最大の価値でしたし、この感覚を知ってしまったら戻れません。
速い応答性に救われたことは何度もあります。
続いてストレージですが、これも後から容量不足に悩まされやすい部分です。
Apex Legends本体だけでも相当のサイズがあり、さらに大型タイトルを追加するともう1TB程度はすぐに埋まってしまう。
だから私は2TBを強く勧めたいと思っています。
流行りのGen.5 SSDは確かに速いですが、発熱対策や価格で躊躇してしまうんです。
私はあえて安定してコストバランスに優れたGen.4の2TBを選びます。
派手さを追わず、現実的にストレスの少ない選び方。
これが私自身にとっての正解でした。
正直、速度を追いかけすぎると財布が悲鳴を上げますし、そこに悩まされるのは本末転倒です。
冷却については、水冷が目立つ時代ですが私は今でも空冷派です。
水冷の静けさや見た目は正直魅力があります。
でも、数年後にポンプが壊れてしまったのを知人のケースで見聞きしてしまってから、私はどうしても不安を感じてしまうのです。
高品質な空冷クーラーは本当に壊れにくく、安心して長く使えました。
決して華やかさはないのですが、トラブルに怯えずに使えることの価値を痛感しました。
だから次に組むときも空冷です、と言い切ります。
ケースはつい見た目先行で選びがちですが、本当に大事なのはエアフローです。
空気の流れがしっかり確保されていないと、どれほど高性能なパーツも苦しそうに熱にあえいでしまうのを見てきました。
以前愛用していた無骨なケースは、正直デザイン的には退屈そのものでしたが、温度の安定感が抜群で長時間遊んでも全く心配がなかった。
やはり見た目より実用性でした。
電源も忘れてはいけません。
むしろここが全体の土台になる部分です。
過去に容量ギリギリの電源を使っていて、新GPUへ換装したときに起動さえしなくなり、慌てて買い替えた経験があります。
あの冷や汗はしたくない。
今なら、余裕のある750W以上を最低ラインにして、できれば850Wクラスを選んでおくのが正解だと断言できます。
余裕があると精神的にも余裕になるのです。
表向きには性能に直結して見えないのですが、ここを軽んじるのは危険です。
こうして全体を振り返ると、長い期間4K環境でApex Legendsを安定して楽しむには、GPUを核に据え、CPUはミドルハイ以上を選び、32GBから64GBのメモリを積んでおくこと。
そのうえでGen.4の2TB SSD、高品質空冷、空気の流れに配慮したケース、そして850Wクラスの電源。
この組み合わせが私の導き出した答えです。
もちろん最初に投資がかさみます。
ただ後から思わぬ買い替えに追われて無駄を重ねるより、安心して長く戦える構成を整える方が、結局はコストも抑えられ、気持ちも楽になるのを実体験で学びました。
無駄な迷いを削ぎ落とし、ただ純粋にゲームを楽しめる環境を作る。
BTOと自作、結局どちらの方がコスパが良い?
特に大きなポイントは、BTOショップの調達力です。
最近のようにグラフィックボードの値段が不安定に高騰している時期だと、5070やRX 9070XTといった最新カードを単品で買おうとすると本当に数万円単位で変わってしまう。
そこをBTOなら、まとめ買いのスケールメリットで安く収められる。
こればかりは庶民の私では到底太刀打ちできないんですよ。
さらに実感するのは「届いたらすぐ動く」という点です。
自作では、組み立てた後にBIOSをいじったりドライバーを入れたり、ちょっとした相性不良に頭を抱えたりと、数日は軽く飛びます。
平日の夜に時間を削るのは正直きつい。
だから「今日届いたパソコンで、その日の夜にはApexがサクサク動く」という事実が、私にとってはお金以上の価値になるんです。
疲れて帰ってきて、限られた時間の中で電源を押せばすぐ遊べる。
それが40代の私には一番ありがたいことだと思っています。
時間は本当にかけがえのない資産ですね。
もちろん、自作にしかない喜びを忘れたわけではありません。
私は過去にDEEPCOOLの大型空冷クーラーを取り付け、深夜でも静かに動くマシンを作ったことがあります。
あのときの満足感は代えがたいもので、友人のBTOマシンより静かだったときは妙な優越感すらありました。
しかし価格の問題は厳しい現実です。
最新のCPU――たとえばCore Ultra 7 265KやRyzen 7 9800X3Dといったモデルを単体で入手しようとして、その値段の高さに苦笑いしたことは何度もあります。
中価格帯のくせに結局は高止まりしている。
その状況を目の当たりにすると、BTOの価格メリットを認めざるを得ません。
BTOは標準で1?3年の保証がつき、修理や交換の対応窓口も一本化されている。
何かトラブルがあっても「ここに頼めば解決する」と思える安心感は大きいです。
私はこれまで自作で電源やメモリの相性問題に悩まされ、真夜中にフォーラムを探し回ったこともあるのですが、そうした不安を最初から避けられるのは大きな利点です。
さらに、最近では2TBのNVMe SSDが標準搭載なんて構成も珍しくなく、いちいちメーカーや型番を調べる手間を省ける。
あの面倒から解放されるだけで、正直かなり助かりますね。
ただし、自作機にしかない自由度の高さを否定はできません。
ケース一つを取ってみてもそうで、私は木目調のケースを導入したとき、部屋全体の雰囲気に溶け込んで「これはもう家具だな」と思ったくらいです。
心が躍った瞬間でした。
こういう体験はBTOではなかなか得られない部分だと思います。
冷却においても、自作はとことん突き詰められるのが面白い。
耳を澄ましても聞こえないNoctuaのハイエンド空冷に感動したこともあれば、360mmラジエータを組み込んで冷却を攻めたこともあります。
その自由度は極端に走れる分、確かに「趣味」としては最高の領域です。
やるなら徹底的に、という思いが実現できる。
とはいえ、最終的に「高画質で安定してゲームを楽しみたい」というシンプルな目的に立ち戻ると、やはりBTOの方が現実的なんですよね。
休日の限られた時間を無駄にせず、届いた瞬間から全力で遊べるのは何よりも大きな魅力です。
余計な調査やトラブル対応に悩まされず、保証に守られた環境で遊べることは安心感につながります。
安心感。
これが私がBTOを選び続ける理由です。
何台ものパソコンを触ってきましたが、趣味として自作に没頭するのも素晴らしい。
ただ生活の一部として定着させるなら、BTOが最適だと私は確信しています。
迷う余地はありません。
選択肢は自由ですが、ゲームを快適に楽しみたいだけなら、BTOを選ぶのが後悔しない道だと思います。
だから私はBTOを推します。