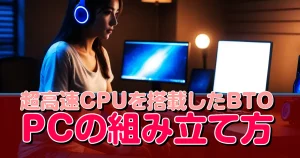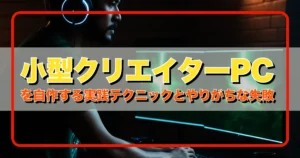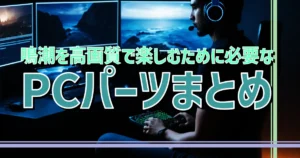原神をPCで快適に楽しむためのスペック目安

CPUはCore i5/i7とRyzen 5/7ならどちらが快適か
私の経験から言えば、Core i5やRyzen 5でも十分に遊べますし、ほとんどの場面で支障なく楽しめます。
ただ、それだけでは心の底から安心しきれなかったのも事実です。
やはり長く遊びたいとか、裏で別の作業を並行したいとか考えると、Core i7やRyzen 7といった上位のCPUにしておいたほうが後悔は少ない。
これは何度も実感しましたね。
当時はRTX 5060 Tiを組み合わせて、フルHDやWQHD環境で原神を遊んでいましたが、快適性はおおむね十分でした。
派手な戦闘エフェクトが画面いっぱいに広がっても、予想以上にフレームが安定していたんです。
その瞬間は「この価格でここまでできるのか」と感心してしまった覚えがあります。
ただ、冷静に考えるとこれはゲーム単体での話。
一度、仕事を終えた後に癒やしとして原神を起動しながら、裏で動画変換と画像処理を走らせてみたことがありました。
そのとき、CPUの余力不足というものが如実に表れました。
画面こそ大崩れはしないものの、快適さがわずかに削がれて集中できない瞬間があったのです。
そんな中で、たまたまRyzen 7を積んだPCを触る機会がありました。
その差は歴然でしたよ。
エンコードが平行で走っていようが、ゲーム画面は動じずにしっかり滑らか。
こういうときに「やっぱり余裕って大事だな」と痛切に感じました。
人によっては「自分はあくまでゲーム用途だけ」と割り切れるでしょう。
それならCore i5やRyzen 5で全く問題ないと思います。
むしろコストを抑えられる分、賢い選択とも言えますからね。
しかし、私はどうしても数年後の自分という存在を意識してしまうんです。
新しいゲームも触れたいし、趣味の動画づくりも続けたいし、時にはオンライン会議やビジネス用途とも兼用する。
そうなると、多少高くても余力を求めてCPUを上位モデルにしておいたほうが精神的に楽。
未来への先行投資というわけです。
最近のCPUはただパワーがあるだけでなく、省電力化や静音性でも一歩進んでいます。
夜遅くひとりで原神を遊んでいても、ファンが大きく回らないので余計な気を散らさず没頭できるんです。
この静かな安心感は、まるで頼れる仕事道具を新調したときのような気分を呼び起こします。
40代にもなると、道具への信頼性ってすごく大事なんですよ。
土台が弱ければせっかくのGPUの力を十分に引き出せない。
CPUは裏方の縁の下の力持ちですから軽く見てはいけない。
私はそう確信しています。
一方で、Coreは古い業務ソフトとの相性が良いケースが多く、仕事で兼用したい私にとっては安心材料でした。
逆にRyzenは価格性能比の点で優秀。
コストの割にパワフルでお得感を味わえる場面は少なくないんです。
最終的には本当に、自分が「安定を優先するのか」、「価格を優先するのか」というシンプルな問いに向き合うことで答えが見つかります。
迷ったときほど欲張らず、自分の本音に合わせて選ぶべきですね。
正直に言えば、私はかつてRyzen派だった時期があります。
家庭の出費を抑えつつ性能を確保したかったですし、当時はそれが最適解でした。
でも仕事や趣味の双方で同時多重タスクをこなすようになると、Core i7の安定性というものが非常にありがたく感じられるようになったのです。
これは単なる好みの問題というよりも、生き方や環境の違いによって導かれる答えの違いだと言えます。
安心できる。
もし今「原神をサッと遊べれば十分」という考えであれば、Core i5やRyzen 5を選んで何ら問題はありません。
ただし「何年も同じPCを使いたい」とか「動画制作にも挑戦したい」と思うなら、Core i7やRyzen 7が適している。
その差は最終的には手間やストレスを減らし、日々の心の余裕に直結します。
私は経験上、自分の余裕をお金で買うという感覚が非常に大切だと痛感しました。
これからPCを組む、あるいは買い替える方には、ぜひ今の使い方に加えて未来の自分を鮮明にイメージしてほしいです。
その姿を考えれば、自ずと「少し上のCPUを選んでおいたほうがいい」と気づく人も少なくないでしょう。
今財布が許すなら、未来の快適さに先回り投資しておくこと。
それはプレイそのものの快適さ以上に、大きな価値をもたらしてくれるんです。
最終的に私が学んだのは、CPUを選ぶ基準とは単なる性能比較ではなく、やりたいことと余裕のバランスをどう捉えるか、という点でした。
だから私はCore i7を選びました。
性能の高さももちろんありますが、それ以上にこれで安心だと思える信頼感を得たかったのです。
それが私の答えです。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 42923 | 2462 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42678 | 2266 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 41712 | 2257 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41007 | 2355 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38483 | 2075 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38407 | 2046 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37176 | 2353 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37176 | 2353 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35552 | 2194 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35411 | 2232 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33667 | 2205 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32811 | 2235 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32445 | 2099 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32334 | 2190 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29174 | 2037 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28462 | 2153 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28462 | 2153 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25380 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25380 | 2172 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23022 | 2209 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23010 | 2089 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20797 | 1857 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19452 | 1935 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17682 | 1814 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16001 | 1776 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15246 | 1979 | 公式 | 価格 |
グラフィックカードはRTX派?Radeon派?実際の違い
グラフィックカード選びで迷う人は多いですが、最終的に納得できる答えは、自分がゲームでどんな体験を本当に求めているかを突き詰めたときに見えてくると、私は思っています。
私は過去に何度も買い替えを経験し、そのたびに「数字やベンチマークだけじゃ語れないな」と痛感しました。
結局は自分の目と手で感じるしかないんです。
最初に本格的にRTXシリーズを導入したときの衝撃は忘れられません。
レイトレーシングをオンにしてもなお軽快に動く画面を目の当たりにしたとき、思わず「これが本物か!」と声が出ました。
画面の中で光と影が自然に溶け込んでいく様子は、ゲームというより一つの体験そのもの。
まるで新しい世界を見せられたようで、しばらくはただ眺めていました。
DLSS 4を使ったときはさらに驚きました。
高負荷設定でも144fpsを狙える。
その滑らかさは、キャラクターが走り抜けたり、風景が流れるように展開していくときに特に強く実感しました。
探索中、坂を駆け降りて風に乗る瞬間、画面の奥行きと自分の動きが一体化したかのような感覚になり、思わず息を呑んだのを覚えています。
ああ、これを味わいたかったんだ、と。
ところが、そんな私もあるときRadeon RX 9070XTを触る機会に恵まれました。
正直、GeForce派だった私はそこまで期待していなかったのですが、実際に体験してみると印象ががらりと変わりました。
FSR 4によるアップスケーリングとフレーム生成の組み合わせが驚くほど効いていて、遠景の山々が澄んだ輪郭を放ち、木々が風に揺れる様子までしっかりと描かれるのです。
映像の「解像感」の際立ち方は、RTXの滑らかさとは違う方向の美しさ。
これには正直「やられた」と思いましたね。
さらに価格が抑えめであることを考えると、そのバランス感覚は見事としか言いようがなく、「コストを大事にする人にこれは刺さるな」と実感しました。
ここが悩みどころです。
とにかく最新の技術で先を走りたい、そういう気持ちが強いならRTXです。
反対に、コストを抑えつつ鮮明な画をしっかり楽しみたいならRadeon。
こちらは電力効率が高く、発熱や電源周りも安定しているので安心して使えます。
まさに実用性重視の人間にぴったりです。
私は個人的に、RTXの遅延を抑える力に助けられたことがあります。
アクションゲームをやっていると、ほんの一瞬のズレがプレイヤーに与える影響は恐ろしいほど大きい。
攻撃をよけられるかどうか、操作と画面が一致しているかどうかで没入感が決まってしまう。
その点でRTXのレスポンスは実に優れていて、手元での入力がそのまま映像に直結する感じが気持ちいいんです。
逆にRadeonには冷静な強みがあって、電源や熱の扱いやすさ、ドライバの安定性などが使っていくうちにじわじわ評価を高めていく。
最近はRTX 5070TiとRadeon RX 9070XTの比較レビューも多く、ネットで「どっちを買えばいいんだ!」と盛り上がる場面をよく目にします。
実際に触ってみると、それぞれが持つ思想がよくわかるんです。
RTXは高価でも「未来を体験させるよ」と言わんばかりの姿勢。
Radeonは「必要なものを誠実に届ける」という確かなメッセージを感じます。
結局、それをどう受けとめるかは自分次第なんです。
WQHDや144fps以上を目指したいならRTXに頼った方が安心。
流れるような映像の快感はやはり格別で、その差は数値以上に体感として強く響きます。
しかし4Kで60fpsを目標に割り切るならRadeonで十分。
コストをかけすぎず、でも確かな満足感を得られる選択肢としてはとても魅力的です。
選択を迫られたとき、人はつい「どっちが正解か」と答えを求めてしまいます。
でも実際には二者択一ではないんです。
自分が望むプレイ環境と体験、そこに財布の事情を加えて考えれば、必ず自分だけの答えが導き出せる。
自分の基準さえぶれなければ、後悔はそうそうないはずです。
私は声を大にして言いたい。
原神を徹底的に滑らかに動かしたい人にはRTXを!逆に高画質をリーズナブルに楽しめれば満足という人にはRadeonを。
選ぶ基準は自分自身にしか分からないことなんです。
私も過去に何度も迷いました。
そのたびに「自分は何を大切にしたいのか」と問い直し、答えを見つけてきました。
グラフィックカードの選択は単なる性能比較ではなく、自分がどうゲームと向き合いたいかを決める行為そのものなんだと、今なら胸を張って言えます。
大切なのは体験。
忘れてはいけないのは満足感。
結局、最後は「何を優先するか」に尽きるのです。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 48533 | 101751 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32047 | 77933 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30055 | 66640 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 29978 | 73293 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27075 | 68805 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26420 | 60131 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 21879 | 56698 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19855 | 50392 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16507 | 39301 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 15942 | 38131 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15805 | 37909 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14592 | 34857 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13699 | 30804 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13160 | 32303 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10787 | 31685 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10617 | 28534 | 115W | 公式 | 価格 |
メモリは16GBと32GBで体感に差は出るのか
原神を遊ぶだけなら16GBのメモリでも問題ない、そう思っていた時期が私にもありました。
実際、半年間は16GB環境で楽しんでいましたし、特別大きな不満を感じることはありませんでした。
ゲームだけに集中する限り、動きが止まったりカクカクしたりする瞬間はめったにありませんから。
しかし、その後32GBに切り替えて初めて気づいたのです。
数字では見えない「余裕」の大切さに。
たとえばエリア移動の場面。
16GBの時には毎回数秒ほどの停滞があり、そのたびに「まぁ仕方ないか」と言い聞かせていました。
でも32GBに替えてからは、それが嘘のように消えました。
配信中に実況の流れを止めずに移動できる。
正直に言うと、その時は思わず声が出ました。
「なんでもっと早くやらなかったんだ」って。
フレームレート自体にはほとんど差が出ません。
私のPCにはRTX 5070Tiを積んでいますが、ベンチマーク数値で比較してみると16GBと32GBの違いは誤差程度です。
それでもレスポンスの安定感やロードの短縮が積み重なると、プレイ全体の印象がまるで変わるのです。
操作中のストレスがほぼなくなり、気づけば快適さが当たり前になっていました。
やっぱりここが重要だと思います。
そして未来を考えた時、16GBで安心できるのは「今この瞬間」だけだと感じます。
オンラインゲームはアップデートを重ねるたびにデータ量が増え、必要なリソースも膨らんでいきます。
実際に過去の大作ゲームでも数年で推奨スペックが跳ね上がる例はいくらでもありました。
オープンワールド型で進化し続ける原神も例外ではないでしょう。
だからこそ、長期的に安心して遊びたいなら32GBが望ましい。
将来を見据えるほど、この差は決定的になります。
私の仕事面でも、このメモリ差ははっきり現れました。
日々大量のExcelやブラウザを開きっぱなしで作業することが多いのですが、16GBの頃はメモリ不足の警告が何度も出ていました。
正直、そのたびに作業の流れが途切れるのがストレスでした。
しかし32GBに替えてからは、そうしたエラーを一度も見ていません。
まるでPCが「まだまだ余裕あるぞ」と語ってくれているようで、妙な安心感があるのです。
安心感。
DDR5メモリは昔に比べて手頃になったとはいえ、16GBと32GBでは1万円近い差がつくこともあります。
私自身も購入前にかなり悩みました。
財布と相談して「まぁ16GBで妥協してもいいかな」と考えていた時期もあったのです。
でも使ってみて思いました。
安心には値段以上の価値がある、と。
原神をプレイするだけで考えるなら16GBでも十分です。
それは確かに事実です。
32GB。
それがより長く使える最良の選択肢なのです。
「どうせなら余裕を持たせたい」という方には強く勧めたいです。
なぜなら私がその違いを一度体感してしまったからです。
体感してしまったらもう後戻りできません。
16GB環境にいた頃は気づかなかったストレスが、32GBを知ってしまうと明確に思い出されます。
だからこそ強く言いたい。
もし本気でPCを楽しみたいなら、16GBにとどまらない方がいいと。
最後に一言でまとめます。
純粋に遊ぶ分には16GBで十分。
未来に備えたい人にとっては、それが最良の選択になるはずです。
私自身がそう感じているから断言できます。
それが、これからのPCとの付き合い方を変える一歩だと信じています。
ゲーム用なら1TBクラスNVMe SSDを推す理由
実際に使ってみるとわかるのですが、ゲームによっては予想以上にデータ容量が膨れ上がっていきます。
例えば原神のようなタイトルだと、アップデートのたびに追加データが積み重なり、気がつけば最初に見ていた必要容量なんてまるで当てにならなくなります。
以前、私は500GBのSSDを使っていたことがありましたが、アップデートを重ねるたびに残り容量がどんどん削られ、やむなく別のゲームを削除したときの悔しさは今でも思い出すたびに苦い気分になるほどです。
せっかく盛り上がってプレイしている最中に「空き容量が足りません」という無情な警告が表示された瞬間、気持ちが一気に冷めてしまったんです。
あの白けた感じ、正直もう二度と味わいたくありません。
だからこそ今は1TBのSSDを基準に考えています。
容量に余裕があると「このゲームは残しておいて次はこれを入れてみよう」と前向きに楽しめますし、インストールするたびにあれかこれかと消すゲームを決める必要がなくなるのは精神的に本当にラクです。
容量不足のたびに保存データを整理するなんて、正直ゲームより面倒な作業でしたからね。
余裕があるというのは大切なことだと、年齢を重ねてますます実感しています。
速度面での強みもNVMe SSDを選ぶ大きな理由です。
PCIe Gen4対応のSSDなら、数千MB/sクラスのシーケンシャルリード速度を叩き出してくれます。
その違いは、実際にプレイするとすぐに気づくほど鮮明です。
かつてはゲームのマップ切り替え時に長いロードを見せられて、その間ついスマホをいじって待つことも多かったのですが、今では切り替えが一瞬で済み、プレイに集中できます。
読み込みが早いと没入感がまるで違う。
もう昔のHDDには絶対戻れません。
SATAのSSDですら、今となっては物足りないと感じてしまうほどです。
もちろん、理想を言えば2TBのSSDを買えばさらに余裕が広がります。
特に配信や動画キャプチャを並行する方であれば、大容量が正義だと断言できます。
しかし、私自身を含め、すべての人がそこまで必要としているわけではありません。
費用と性能のバランスを考えれば、1TBが最も現実的かつ安心できる選択肢です。
実際、1TBあれば原神のデータ膨張にも長期的に耐えられますし、大作ゲームを複数並行してインストールしても圧迫感は少ないんです。
その上で仕事や趣味のデータも置ける。
要するにちょうど良いんですよね。
ただし容量や速度ばかりに注目するのは危険です。
ゲーム用途だからなんでもいいと割り切るのは、正直かなりリスキーです。
パフォーマンスが突然落ち込んだり、最悪の場合はフリーズしてプレイ中のデータを吹き飛ばす。
長く安心して使うためには、信頼できるメーカーのSSDを選ぶことが絶対条件だと私は考えています。
多少高くとも、安心を買うことには十分な意味があります。
機械が裏切る不安を抱えながら遊ぶなんてストレスでしかありませんからね。
ゲーム中に「空き容量がありません」と出た瞬間のガッカリ感。
だから私は胸を張って言います。
1TBクラスのNVMe SSDこそがベストな選択だと。
導入直後は「ちょっとオーバースペックかな」と思うかもしれませんが、数か月から1年も遊び続ければその余裕に心底感謝するはずです。
とくにアップデートが年月をかけて膨らんでいくタイトルほど、そのありがたみが後からじわじわと効いてきます。
私は、快適なゲーム体験を第一に考える人ほど、ストレージの重要性を軽視すべきではないと思っています。
ロード時間の速さ、十分な容量、削除作業の手間から解放されること。
そのどれもが「遊び」に集中できる環境を支えてくれます。
好きなゲームの世界に思いっきり没頭できる安心感は、買った金額の大小よりはるかに価値がある。
ゲームに限らず、仕事や趣味だって同じです。
環境が整って初めて、存分に楽しめる。
安心して楽しめる。
私にとって、それがすべてです。
だからこそ1TBのNVMe SSDを選ぶことは、遊びに対する真っ当な自己投資だと信じています。
ゲームは楽しむためのものです。
わざわざストレージ不足に悩まされるなんてナンセンス。
大切なのは心から夢中になれる環境を整えること。
そのための土台となるのが適切なストレージの確保なのです。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
解像度別に考える 原神に向いたPC構成

フルHDで安定して動かすならこのレベルが目安
どんなに高性能なパーツを揃えても、それが使い方に噛み合わなければ持て余してしまいますし、逆に少し工夫することで長く安心して使える環境が整うのです。
私も仕事と家庭の合間にゲームを楽しむ身なので、余計なイライラを感じず「よし今日は楽しもう」と思える環境を作ることを最優先に考えてきました。
GPUについては、表面的には軽めのゲームと言われる原神ですが、実際に草や木が茂っているエリアやエフェクトが重なる戦闘シーンでは途端に処理負荷が跳ね上がります。
数年前に古いGPUで試したとき、急にカクついて操作感が乱れるあのストレスといったらもう…正直二度と味わいたくありませんでした。
だから私は余裕のあるGPUを強く推します。
今で言えばRTX5060やRadeon RX9060XTあたりなら、60fpsの安定は当然として、設定を工夫すれば120fpsにも届く余地があるので、安心して没入できるのです。
映像が滑らかであるほど、気持ちまで引き込まれる感覚が得られるのだと実感しました。
実際にRTX5060で試したとき、予想以上の安定感に驚かされました。
マルチプレイで仲間と走り回っても、描画が途切れるような感覚が全くなく、思わず「これは頼れるな」と小さく声を出してしまったほどです。
配信ソフトを同時に立ち上げても絵の崩れがなく、限られた夜の時間だからこそ、この安心感が本当にありがたかった。
一方でCPUはそこまで神経質になる必要はないと考えています。
Core Ultra 5 235やRyzen 5 9600を選べば十分で、私の経験上ボトルネックになることはまずありません。
正直に言えば、上位機種に無理して手を伸ばしたときほど「こんなに差があるのか」と感じることは少なかったです。
その分の予算をGPUやSSDに回した方が、使っていて後悔はずっと少ないのです。
分かりやすい優先順位。
次にメモリですが、16GBあれば最低限は問題なく動きます。
でも現実には複数のアプリを同時に使う場面が多いのです。
ブラウザを開きながらDiscordで通話し、配信ソフトを動かす。
そんな状況では16GBだとやはり少し不安が残りました。
32GBに変えたときの気持ちの余裕は想像以上で、不意のフリーズに振り回されない快適さを手に入れることができました。
心の中で「もうこれで十分だな」と思える、その感覚。
ストレージに関しては、私は声を大にして1TB以上のNVMe SSDをおすすめします。
昔500GBでやり繰りしていたとき、毎回のアップデートで残り容量がごっそり削られ、ゲームやソフトを泣く泣く削除するあの面倒くささは正直こりごりでした。
さらにGen.5対応のSSDに置き換えたときは、マップ移動の早さに心底感動しました。
読み込みが早いというのは地味な違いかもしれませんが、毎日の中で積み重なると大きな差になるのです。
だから私はここにもしっかり投資をしたいと考えています。
冷却対策も見過ごせません。
私も以前は安価な空冷で済ませていましたが、ファンが急に唸りだしたときに「これは嫌だな」と感じ、思い切って信頼できるクーラーに切り替えました。
結果、音も静かになりようやく落ち着いてプレイできるようになったのです。
後から悔やむのは本当に損です。
結局私のおすすめ構成は、フルHDを前提とするならRTX5060クラスのGPU、Core Ultra 5かRyzen 5のCPU、32GBメモリ、そして1TB以上のNVMe SSD。
この組み合わせなら配信や並行作業も余裕があり、消費電力や発熱も過剰にならず、総合的に長く付き合える理想的な構成になると思います。
さらに冷却性能の高いパーツを選べばより完璧に近づきます。
原神というゲームは単に遊ぶだけではなく、美しい世界に浸ることが価値のひとつです。
言い換えれば没入感が損なわれると、その魅力が半減してしまうのです。
だから私は、少し余裕のある環境を整えることが正解だと信じています。
今日は疲れたなと思った日でも、快適に動くPCがあるから「よし遊ぼう」と気持ちを切り替えられる。
その積み重ねこそが、私にとって最高の安心感になっています。
WQHD+高リフレッシュを狙うならやっぱりGPUが要
CPUやメモリも大切ですが、それらに資金を多く投じても決定的な快適さは得られません。
解像度がWQHDクラスになると描画の負荷が一気に高まり、実際の体感はGPU性能次第で大きく変わってきます。
私はこれまで何度も自作PCを組んできましたが、シーンが重くなる場面でGPUの余裕があるかどうかが、安定感を左右する決定的な要素だと痛感してきました。
フルHD環境ではCPUやメモリのバランスを取ることで快適に遊べます。
ところがWQHDになると話は一変し、GPUにかかる負担が跳ね上がるのです。
その瞬間に、せっかくの臨場感が損なわれてしまいます。
私自身も「描画力が支配している」という表現がしっくりくる経験を何度もしました。
過去にRTX 5070TiとRadeon RX 9070XTを試したことがあります。
144Hz対応モニターを使っていると、どうしてもGPUの力が足りない環境はストレスそのものでした。
こればかりは数字ではなく、体感してみないと分からない苛立ちですね。
「あぁ、これは妥協できない」と強く感じた瞬間でした。
原神というゲームは一見「軽そうに見えるタイトルだから、大したGPUはいらないのでは」と思われがちです。
しかし、戦闘中の派手なエフェクトや街中で人が密集したシーンになると一気に重くなります。
そういう場面ほどゲームの醍醐味が現れるのに、GPU性能が足りないとすぐに落ち込むフレームレートに白けてしまう。
私は40代になってから特に目の疲れを感じやすくなったので、小さなカクつきが大きなストレスになります。
そのたびに、「安く抑えたのが間違いだった」と後悔するのです。
私の知り合いにもRTX 5060で構成して失敗した人がいます。
WQHD+144Hzで挑んだ結果、設定を落とさなければまともに動かず、結局5070クラスに買い替える羽目になりました。
彼は苦笑しながら「最初から背伸びしていれば余計な出費はしなかったのに」と話していました。
人間って後にならないと学べないことが本当に多い。
笑うしかない話ですが、実際に財布へのダメージは重くのしかかります。
CPUやメモリに関してはある程度確保しておけば十分です。
Core Ultra 7やRyzen 7クラスならゲーム中で足を引っ張る場面はまずありませんし、Gen.4 SSDを選んでおけばロード時間も短く快適です。
だからこそ強調したいのは、足りないと本当に困るのはGPUだけ、という現実です。
余裕を持って選んだGPUのおかげで「買ってよかった」と心から感じられる瞬間は、他のパーツでは得にくいものです。
私はBTOショップで見積もりを取るとき、まずGPUの選択を軸にします。
例えば5070Tiクラスを中心に構築し、32GBのDDR5メモリ、750Wクラスの電源。
細部を多少調整するよりも、GPUに資金を集中させる方が所有感も満足感も高い。
これは単なる理屈ではなく、何年も自分で組んで使った経験から出た答えです。
ここで特に強く伝えたいのは、「ちょっとオーバースペックかな」と思えるくらいの余裕を持たせることです。
配信や録画、業務との並行といったシーンでは、不意に要求が高まります。
この余裕があるとないとでは、体験が別物です。
要するに、WQHD以上の解像度で快適に長時間プレイしたいならGPUを最優先すべきです。
CPUやメモリに必要以上に投資しても、ボトルネックがGPUにあると何も報われません。
だから私は相談を受けたときには決まって「まずGPUから選びなさい」と言う。
これは私が実際にしくじりと成功を繰り返して辿りついた確信です。
結局のところ、最適な答えはシンプルです。
RTX 5070シリーズ、もしくはRadeon RX 9070シリーズを中心に構築すること。
それこそが、後悔を避けて長期的に安心できる選択です。
私は自分が何度も同じ壁にぶつかった経験を持つからこそ、この言葉を強く伝えたい。
安心して楽しみたい。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60CL

| 【ZEFT R60CL スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal Design Pop XL Air RGB TG |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60FS

| 【ZEFT R60FS スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9060XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54Y

| 【ZEFT Z54Y スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265K 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5050 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55ED

| 【ZEFT Z55ED スペック】 | |
| CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II White |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
4K高画質で遊びたい人におすすめしたいパーツ構成
正直なところ、CPUも確かに重要ですが、実際に遊んでみると多くの負荷がGPUに集中するのを体感します。
同じCPUをそのまま使い続けてグラボだけ新しい世代に切り替えたとき、映像の変化があまりに分かりやすくて驚いたことがありました。
木々のざわめきや水面への反射、稲妻エリアの夜空の光の演出など、4Kで描かれるディテールが一気に鮮やかになり、GPU性能の差がこれほどまでに影響するのかと実感した瞬間でした。
逆に性能が不足していると、映像がカクついて一気に没入感が崩れてしまいます。
だから、最新世代のミドルハイ以上を選ぶのは必須条件。
これは遠回しにせず言い切ります。
譲れない部分です。
CPUに関しては「一番高価なモデルでなければ安心できない」というわけではありません。
ただ、あまりにローエンドなものを選んでしまうと、複雑なエフェクトや多人数のシーンでフレームレートが一気に落ち込んでしまう危険がつきまといます。
私自身、Core Ultra 7クラスやクロックの高いRyzen 7を試してきましたが、やはりこの辺りを選んでおけば移動から戦闘、マルチプレイまで快適に動いてくれます。
CPUは目に見える派手さはないものの、裏方で全体の動きを支えている存在であり、ある程度の余裕がないと必ずプレイの質が下がります。
メモリも思いのほか侮れません。
私は最低でも32GBを積むべきだと考えています。
16GBでもゲーム自体は動きますが、配信をしながらDiscordを開き、さらにブラウザで何か調べながら遊ぶと容量的に不安になります。
32GBにしておけば、4K描画と配信を同時に行っても余裕があり、安心感につながります。
今後さらに重たいゲームやアプリケーションが登場することを考えると、先行投資だと思って32GBにする価値は大きいです。
64GBまでは多くの人にとっては不要かもしれませんが、32GBを選んでおけば「よかったな」と確実に思える余裕が生まれます。
メモリ不足は小さな不満をじわじわ積み重ねる原因。
これが一番厄介です。
ストレージは軽視されがちですが、私は最低1TBのNVMe SSDを用意すべきだと断言します。
原神はアップデートが頻繁で、データ容量もどんどん膨れ上がっていきます。
私も以前500GBで組んでいたとき、気がつけば残りスペースがすぐなくなり、泣く泣く別のゲームを削除したことがありました。
このときのストレスと不便さは強烈に覚えています。
ストレージ不足は心の余裕を奪い、せっかくの体験を台無しにします。
最初から余裕を持っておくこと。
本当に大事です。
GPUにしっかり投資したなら、それを支える電源こそ良質なものを使わないと安定しません。
私の経験では850Wクラスの80Plus Goldあたりが安心できる基準です。
これを下回ると電力が足りなくなったり、負荷がかかる場面で不安定になったり、最悪の場合システムが落ちる可能性すらあります。
プレイ中に突然電源が落ちる。
冷却についても同様に重要です。
空冷の大型クーラーで十分な場合もありますが、静音性を重視するなら簡易水冷にする選択もありです。
冷却ファンの大きな音にいら立つのは本当にストレス。
静けさは快適環境の一部ですよね。
ケースは見落とされがちなポイントですが、これも大切です。
私も以前サイドパネルが密閉気味のケースを使っていたところ、夏場にGPUが高温で苦しくなりフレームの落ち込みが発生しました。
そこでエアフローを優先したケースに替えたら、内部温度が見違えるほど落ち着いて、GPUの動作も安定するようになったのです。
デザイン性にばかり目がいきがちですが、内部の空気の流れは性能と直結しています。
侮れません。
要するに、私が本当に伝えたいのはこれです。
4Kで原神を心地よく遊びたいなら、GPUは最新のミドルハイ以上、CPUは余裕を持ったクラス、メモリは32GB、SSDは1TB以上。
さらに電源と冷却、そしてケースの選択に妥協しないこと。
この組み合わせが安定した体験につながります。
せっかく4Kという贅沢な環境でプレイするのですから、細かい不満に足を引っ張られるのはつまらないです。
それこそが最大の損失です。
映像の美しさは余裕のあるハード構成があってこそ成り立ちます。
複数作業をしても崩れない快適性。
私自身、しっかり構成を整えた後に感じた安心感と満足感は今でも忘れられません。
迷う必要はありません。
この組み合わせこそが、私が提示する理想の4K原神環境です。
納得の一台。
快適な時間。
コスパ重視で選ぶ 原神向けゲーミングPC

価格を抑えつつ快適に遊べるミドルクラス構成
高価なハイエンド機に憧れる気持ちは当然ありますし、私自身も一時はその方向に傾きました。
しかし家庭や仕事があり、趣味に注ぎ込める予算に限りがある40代の私にとっては、背伸びをしすぎても後から後悔するのが目に見えています。
だからこそ、長く続けられて安心できる構成こそベストだと強く感じたのです。
プレイを支える中心になるのはやはりグラフィックカードです。
CPUがどんなに立派でも、GPUの力が不足していれば映像はカクつく。
その苛立ちは本当に大きい。
私が実際に試したRTX 5060Tiは、動作が非常に安定していて気持ちよかった。
フィールドを駆け抜ける時に処理落ちの心配をせずに済む解放感。
滑らかな映像が集中力を支え、しばし現実を忘れさせてくれるのです。
この違いはやった人にしか分からない実感です。
CPU選びはつい欲が出るものです。
けれど冷静になってみれば、Core Ultra 5やRyzen 5で十分満足できる働きを見せてくれました。
特に原神程度の負荷であれば、わざわざ最新のハイエンド品を投入するほどの価値はない。
むしろ中堅クラスのCPUなら消費電力や発熱を抑えられ、ファンの音が気にならないのは助かります。
夜中に一人でじっくり冒険に浸る時、この静けさのありがたみを痛感しましたね。
メモリは最低16GBは必須ですが、私は迷わず32GBを選びました。
理由は単純です。
遊びながら動画を流し、さらにブラウザをいくつも開く生活をしているからです。
気づかぬうちに裏でアプリが山ほど動いていて、16GBでは心許ない。
以前は切り替えのたびに一瞬止まるのが気になっていましたが、32GBにしてからは動きが途切れることなく、本当に快適。
数字の差ではなく、気持ちの余裕が生まれる選択だったと確信しています。
ストレージも重要です。
原神はアップデートのたびに容量を食い、気がつけば100GBを超えていました。
小さめのSSDでは他のゲームや仕事用ファイルとぶつかり合い、常に削除や整理を迫られる羽目になる。
これは正直ストレスです。
そこで1TBのNVMe SSDにしたところ、余裕がありロードも速く、ワープでの切り替えが一瞬で終わるたびに「よし!」と声が出てしまうくらい嬉しくなるんですよ。
冷却方式は水冷か空冷かでよく迷います。
私も一時期は水冷の見た目に心を惹かれました。
でも結果的に空冷を選び、これで正解だったと思っています。
理由は単純で、メンテナンスが楽で壊れにくいからです。
年齢を重ねるにつれて、派手さよりも長期間の安心稼働を優先したくなる。
その価値観にぴったりでした。
置いてしまえば派手なイルミネーションは意外と見なくなるもの。
シンプルで頑丈というだけで日常の安心感が増します。
ケースも軽視できません。
私が最近導入したケースは、エアフローが良く、ケーブル整理がしやすい作りでした。
配線の煩わしさが減り、掃除をする時に妙に気分が楽なんです。
「この作りは助かるなあ」と思わず口に出してしまいました。
使い勝手が良いと自然に長く大切に使える。
見た目よりも日々の扱いやすさが本当の満足度を決めると実感させられました。
予算の話になりますが、現実的なラインは20万円前後です。
この範囲であれば十分余裕を持って楽しめます。
結局は、どこまで先を見越して財布を開けるか。
そこに人それぞれの価値観が現れるのでしょうね。
APEXやVALORANTのような競技性の高いゲームも遊べますし、MMORPGといった大型タイトルでも相当余裕がある。
手にしたPCが長い時間寄り添う相棒になる、この安心感は何より大きいです。
結局のところ私が信じる構成は明快です。
メモリは32GB、ストレージは1TB SSD。
この組み合わせさえ押さえておけば、原神を高設定で楽しめるだけではなく今後の新作ゲームも安心して挑める。
大切なのは見栄を張らず、自分に合った現実的な選択をすることでした。
快適さの土台。
これが、私がたどり着いた答えです。
バランス重視ならCPUとGPUをこう組み合わせる
PCを組むときに一番大切なのは、結局のところCPUとGPUのバランスです。
これは私自身が何度も痛感してきたことなのですが、片方ばかりに予算を振ると必ず後悔する瞬間がやってきます。
昔、私はGPUにばかりお金をかけて「映像は綺麗なのに、肝心の動作がもっさりしていて不満だ」と悩みましたし、逆にCPUばかり強化したときには「処理は速くなったのに、なぜかゲームが迫力不足に感じる」と頭を抱えました。
私は過去にGPUを重視して買い替えたことがあります。
画面の美しさには満足したものの、配信ではフレーム落ちがひどくてまともに楽しめませんでした。
「ああ、自分の選択は失敗だった」と悔しくてたまらなかったのを今でも覚えています。
だからこそ、GPUさえ強ければいいという考え方にはもうこりごり。
人に聞かれても、それだけは断固として勧めません。
フルHDを基準に考えるなら、Core Ultra 5クラスのCPUとRTX 5060。
この組み合わせが一番安心できると私は思います。
理由はシンプルで、コストと性能の両方でちょうどいい塩梅だからです。
初めてゲーミングPCを買う人にも勧めやすい。
「迷ったらとりあえずこのセットで」と背中を押せる安定感があります。
背伸びして高額モデルを買わなくても十分に快適に遊べますし、一番大事なのは安心して使えること。
でも配信や高リフレッシュレートを求めるなら、話は変わります。
CPUをCore Ultra 7に、GPUもRTX 5060Tiや5070に上げた方が絶対に満足できます。
正直、値段は跳ね上がります。
しかし、一度味わうと戻れなくなる。
映像表現がまるで別物で、余裕を持って長く使える環境を手にできる。
AMDを選ぶなら、Ryzen 7 9700XとRadeon RX 9060XT。
この組み合わせは実際に使ったことがあり、意外とコスト面で納得がいきました。
スペック表だけ見ると「Intelと大差ない」と思っていましたが、実際にゲームをすると映像の深みや安定感に驚かされました。
長く腰を据えて遊ぶタイプの人なら気づくであろう差なのです。
PC構成で意識すべき割合は、GPUに6割、CPUに4割くらい。
私は昔、予算をGPUに傾けすぎて動画編集に苦戦し、イライラしていました。
そのとき痛感したのは、短期的な満足感よりも長期の使いやすさを優先すべきだということです。
そして見落としがちなポイントとして、メモリとストレージの存在があります。
メモリは32GB欲しいですし、ストレージは最低でも1TBのNVMe SSDにした方がいい。
今のゲームはアップデートだけで数十GBも平気で増えるので、容量不足は本当にストレスです。
私は以前、ケチって小さいSSDを入れ「いらないアプリを消しては整理」を繰り返し、最終的には増設する羽目になった経験があります。
あの頃の面倒くささは二度と味わいたくないですね。
配信や編集も考えているなら、なおさらCPU・GPU・メモリ・ストレージをトータルで整えることが欠かせません。
どれか一つだけ妥協すると、後になって「もっとしっかり考えておけば」と後悔するのは目に見えています。
これは私の実体験からも言えることです。
私なりに整理すると、フルHD中心ならCore Ultra 5とRTX 5060。
配信や高リフレッシュを求めるならCore Ultra 7とRTX 5070。
AMDならRyzen 7とRadeon RX 9060XT。
十数年PCに触れてきた自分の経験を踏まえても、この組み合わせなら大きく外れることはまずありません。
結局のところ、CPUとGPUの釣り合いこそがPC構成で絶対に外せない要素です。
安心して長く使える1台を選ぶために、このバランスは何より重視すべきです。
長く快適に使うために押さえておきたい拡張性
安さや見た目に惹かれて衝動的に決めてしまうと、数年後に「もう使い物にならない」と感じて全体を買い替えるしかなくなる。
その遠回りは財布にも心にも重い負担になります。
私は過去にそうした失敗を経験しました。
だからこそ今は、初期投資の段階で余裕のある構成を意識するようになりました。
まずはメモリです。
私も当初は「これだけあれば大丈夫だろう」と思っていました。
しかし、実際に配信ソフトを同時に立ち上げてみると途端に動作がカクつき、あのちょっとしたストレスが心に深く残りました。
その時の後悔は今でも忘れられません。
32GBを導入して初めて、余計な不安が消えて本来のゲーム体験を心から楽しめるようになったのです。
だから私は、最初からメモリスロットの拡張性があるマザーボードを選ぶことにしています。
「少し余裕がある」その安心感は、日常で大きな違いを生むのです。
ストレージも同じです。
1本のゲームはそこまで容量を食わないように見えても、アップデートの積み重ねで着実に肥大化していきます。
ある日気がつくと、一つのタイトルが予想以上の容量を占領してしまっていた。
私はその現実に何度も直面しました。
最初に1TBのSSDを入れておいた時は心から救われたと思いました。
追加のM.2スロットに空きがあったので後から増設でき、その柔軟さに驚くほど助けられました。
データ容量に余裕があると、バックアップひとつ取る作業にも妙な落ち着きが生まれるんですよ。
心がざわつかない。
次にグラフィックカードです。
今の主流のモデルなら一見十分に動作すると思えます。
ただ、ゲームは進化し続ける。
3年前は快適だったものが、今や満足に動かないことも珍しくありません。
私はかつて新作を試そうとした瞬間、フレームレートが極端に落ち込み「もうダメだ」と頭を抱えたことがあります。
PCIe規格の対応を軽く見ていた自分を激しく後悔しました。
せっかくのGPUが全力を出せない無念さ。
あの時間は本当に惜しかったです。
忘れてはいけないのが電源ユニットです。
正直、私は最初にここでケチりました。
必要最低限で済むだろうと計算して、安い電源を選んだのです。
しかしのちにGPUを入れ替えようとしたら電力が不足し、結果的に電源ごと交換する事態になりました。
痛い思いをしましたね…。
それ以来、私は電源に関しては最初から余裕を持って選ぶようにしています。
確かに初期費用は上がりますが、最終的には長く安心して使える。
結果的にコストも下がる。
冷却やケース選びも甘く見ないでほしい点です。
性能の高いパーツを詰めても、熱がこもれば力を発揮できません。
私はかつて通気性の悪いケースを選んだばかりに、GPU温度が常に高止まりし、真夏は怖くて長時間遊べませんでした。
その頃は毎日がストレスで、せっかくの趣味なのに心から楽しめないことが辛かったのです。
それ以降は大きめのケースを選び、クーラーにも迷わず投資しています。
しかもケースのデザインを気に入ると、ふと目に入るたびに気持ちが良いのです。
見た目から生まれる満足感。
ゲームだけでなく、仕事や趣味で使うデバイスも年々増えていくものです。
最初は要らないと思っていたのに、あとから必ず増える。
それが現実です。
だから私は拡張性が豊富なマザーボードを優先するようになりました。
「少し余分かな」と思えるぐらいが、最終的には一番ちょうどいい。
こうした経験を踏まえると、当座の予算で最小構成を選ぶのも一つの考えではありますが、私のように痛みを味わいたくないなら最初から拡張性に投資した方がいいと断言できます。
余計に払ったお金は数年後に確実に価値を生みます。
私は「長く快適に遊び続けたい」というシンプルな願いを大切にしています。
そのためには、最初の選択が全てを左右するのです。
最後にもう一度強調します。
私はかつて目の前の節約を優先して、その後に苦い後悔をしました。
数年先に後悔を噛み締めたとき、思いました。
「最初から少し余裕を残しておけばよかった」と。
未来の自分を楽にするには、今の自分がしっかり準備しておくこと。
その答えはただ一つ。
拡張性を選ぶこと。
これに尽きます。
安定性と冷却性能を重視したPC構成の考え方


空冷と水冷 実際に使い勝手が良いのはどっち?
最近よく相談されるのが、ゲーム用PCの冷却方式は空冷と水冷のどちらを選ぶのが安心なのかという話です。
私の経験から言えば、長く安定してPCを使いたいのであれば空冷を選んだほうが無難です。
水冷には水冷の魅力があるのは確かですが、実際に何台も組んできた中で、最後まで落ち着いて信頼を置けたのは空冷でした。
ゲームを長時間やるときにも「やはり頼れるのはこっちだな」と心のどこかで思うのです。
空冷クーラーの大きな魅力は、やはり取り回しのしやすさにあります。
しっかりしたヒートシンクとファンを備えたモデルなら、Core Ultra 7やRyzen 7といったクラスのCPUでも問題なく冷やせます。
しかも最近のCPUは昔のように極端に熱を出さないよう設計されているので、空冷で十分性能を引き出せるのです。
私はWQHDや4Kで原神を長く遊ぶことがありますが、それでも冷却で不安を感じることはほとんどありません。
メンテナンスも掃除の際にホコリを払う程度で済むので、正直ありがたいですよ。
気軽に扱えるというのは思っている以上に大きな安心材料です。
一方で、水冷には確かに強みがあります。
例えば240mmや360mmの簡易水冷を導入すると、ケース内のエアフローを保ったまま効率的に放熱してくれます。
それに静音性。
これは本当にすごいと感じました。
以前NZXTの簡易水冷を試したとき、夜の静かな部屋でPCを回していても、まるでそこにPCがないように錯覚するほどの静かさで、思わず「おお…」と声が出るほどでした。
その体験は今でも印象に残っています。
特に高負荷の配信や動画編集を同時に行う場面では、やはり水冷の優位性を実感します。
静かにパワフルに動くあの感じは心地よいものです。
ただし、水冷にはどうしても不安がつきまといます。
ポンプという可動部分があるので、そこが壊れたらシステム全体に影響が出かねません。
頭では最近の製品は信頼性も高くなっていると理解していますが、それでも「もし止まったらどうしよう」という緊張感は拭いきれないのです。
さらに、ケースのサイズやレイアウトにも制約が出てきます。
水漏れの可能性もゼロではありませんから、慎重になってしまいます。
これは長くPCを付き合い続ける上で、やっぱり避けられない心理的な壁ですね。
直近で私が組んだPCでは大型空冷クーラーを導入し、ケースはLian Liのピラーレス構造を採用しました。
サイドから吸気を意識した設計にして、グラフィックカードにはRTX5070Tiを載せたのですが、実際に運用してみると驚くほど静かで、原神を高画質で2時間以上プレイしても温度は70度程度で安定していました。
電源ユニット含めて全体的にバランスよく放熱してくれており、「ああ、やっぱり空冷で十分じゃないか」と改めて思った瞬間でした。
やはり自分で手を動かした経験は大きい。
見た目の華やかさに関しては、水冷のほうが明らかに優秀です。
RGBで光るクーラーや美しく配管されたチューブのレイアウトは、まるで一つのインテリアを完成させるかのような存在感があります。
配信者の環境でよく見かける大型の360mm簡易水冷のセットアップには実際憧れましたし、「これはひとつのステータスだな」と感じたものです。
仕事終わりにそうした配信を眺めていると、自作好きとしては「自分もやってみたい」と胸がざわつきました。
正直に言います、気持ちが揺れ動きました。
それでも普段の使い勝手や、日常的に安心感を持ってPCに向かえることを考えれば、私は空冷を推します。
水冷は静かでスタイリッシュ、見た目でも所有欲を満たしてくれる優雅さがありますが、それは「演出」や「特別感」を求める人に向いている選択肢です。
一方で私は、長期的な安定性能を大事にしたい。
使えば使うほどそのありがたみを実感できるのは、結局空冷なんです。
余計な不安にさいなまれたくないからこそ、自分の結論は揺るぎません。
そのシンプルな線引きが一番わかりやすい。
私自身の答えは迷いがありません。
空冷が一番。
そういうことです。
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R65V


| 【ZEFT R65V スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7800X3D 8コア/16スレッド 5.00GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R66A


| 【ZEFT R66A スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 8500G 6コア/12スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
| ケース | DeepCool CH170 PLUS Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60XV


| 【ZEFT R60XV スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850I Lightning WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60GU


| 【ZEFT R60GU スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R44CG


高速な実行力で極限のゲーム体験を支えるゲーミングモデル
直感的プレイが可能、16GBメモリと1TB SSDでゲームも作業もスムーズに
コンパクトなキューブケースで場所を取らず、スタイリッシュなホワイトが魅力
Ryzen 9 7900X搭載で、臨場感あふれるゲームプレイを実現
| 【ZEFT R44CG スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 7900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット MSI製 PRO B650M-A WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
PCケース選びで大事なエアフローとメンテのしやすさ
PCケースを選ぶときに私が一番大事だと思っているのは、やはりエアフローとメンテナンス性です。
パーツの性能だけが高くても、この二つがないと本来の力を発揮できないのは身をもって実感しています。
冷却が甘ければ動作中の熱がたまり、パフォーマンスの低下や不快な騒音につながり、最悪の場合はパーツの寿命まで縮めてしまう。
だから多少高くても、風の通りがよくて掃除のしやすいケースを選ぶべきだと、私は経験から確信しています。
その結果、GPUの周りに熱がこもってしまって、プレイ中は顔に熱風が押し寄せてきて、まるで真夏にエアコンの室外機の隣で座っているような地獄でした。
正直、後悔しましたよ。
でもその後、エアフローを重視したケースに買い替えたら驚きました。
本当に温度が下がって、しかもファンの音まで静かになったんです。
強烈な学びでした。
フロントパネルとトップパネルの作り込みは、軽視できない部分です。
ところが最近はガラスやウッドパネルなどデザイン先行のものも増えてきました。
デザインは確かに楽しい。
でも、吸気が塞がれているようでは本末転倒です。
冷却性能を犠牲にしたら、せっかくの美しい外観も意味が薄れる。
見た目と機能のバランス、結局そこに尽きると私は考えます。
どちらかに寄りすぎると後悔しますからね。
そして忘れてはいけないのが、メンテナンス性です。
ストレージの追加や交換は思った以上に頻繁に発生します。
ケーブルがぐちゃぐちゃで、作業のたびに「もううんざりだ」とつぶやきたくなるようなケースでは精神的に参ってしまいます。
反対に、工具不要でSSDスロットにすぐアクセスできたり、裏配線をきれいに収められるケースだと、本当に作業が楽になります。
扱いやすさがそのまま満足感に変わるんです。
正直なところ、ここを軽んじると後で絶対に後悔します。
掃除のしやすさはもっとシビアです。
埃がたまるのは避けられません。
だからこそダストフィルターをさっと外して洗えるケースかどうかで、長期の快適さが大きく変わります。
実際、私も一度メンテを怠ったせいでゲーム中にGPUが過熱し、フレームレートがガタ落ちしたことがありました。
ケースを開けてみたら内部にびっしりと埃が積もっていたんです。
ぞっとしました。
その後すぐ掃除をしてみると動作が安定に戻り、胸をなでおろしたのを今でも覚えています。
あの安心感。
実に大きなものでした。
最近人気のピラーレスケースも、たしかにガラス張りの迫力はかっこいい。
でも冷却が甘ければ、結局は「見せかけだけ」なんです。
ここをしっかり確認しないと、結局長く快適には使えません。
私自身、「見た目だけでは続かない」とつぶやきながら、性能面の重要性を思い知らされたひとりです。
最後は中身勝負。
サイズ感も悩みどころです。
特に最近のGPUは巨大化が激しい。
長さはもちろん、厚みまで増してきている。
本当に大きいんです。
実際私は過去に「スペック上は入る」と思っていたGPUをケースに合わせようとしたら、数ミリの差で入らず冷や汗をかいた経験があります。
その瞬間の焦りは、笑い事ではありません。
だからこそ今は余裕を持った内部設計のケースを選ぶことを強く意識しています。
ここを妥協すると、後から必ずストレスになります。
痛いほど分かりますよ。
つまり私が全体を通して伝えたいことは明快です。
ゲーミングPCを快適に動かすには、ケースは絶対に軽んじてはいけない存在です。
風の通りがよく、埃を簡単に清掃できる。
そしてパーツの増設や配線がしやすい。
こうした条件を満たしたケースを選んでこそ、初めて「安定して長く楽しめるマシン」になります。
最後にもう一度強調します。
エアフローとメンテ性は妥協してはいけません。
見た目に飛びつく前に、未来の自分が快適に作業できるかどうかを想像して選ぶべきです。
これが結果的に一番の近道です。
ケースは軽視されがちですが、私は声を大にして言いたい。
「ここをケチらず、しっかり選べ」と。
必ず未来の自分を助けてくれる投資になります。
電源ユニットの容量不足が招く不安定動作とは
私はこれまで何度もパーツ選びで悩み、選択を誤って痛い経験もしてきましたが、そのなかでも特に電源を安く済ませようとして後悔したことが何度もあります。
細かい部分で性能や静音性を語るのも楽しいのですが、結局電源が足を引っ張ればすべてが台無しになるんですよね。
仕事でPCを使うようになってからはなおさらその重要性を感じています。
結局のところ「安定して動くこと」こそ最大の価値なのだと痛感しました。
私が電源の大切さをはっきりと理解したのは、社会人になって間もないころに遊んでいたオンラインゲームがきっかけでした。
一見軽いゲームは問題なく動いていたのですが、重い場面や別のアプリを同時に開くと突然画面が消え、強制的に再起動がかかることが何度もありました。
当時はOSのせいだと思い込み、何度も再インストールを繰り返したのですが、一向に直らない。
最終的に気づいたのは電源不足が原因だったという事実でした。
その時の落胆は今でも思い出せます。
やられたな、という気持ちでしたね。
ただ、その失敗を経て今では人に助言できる立場になった、とも言えるのです。
ピーク時の一瞬の負荷。
これが本当に厄介です。
最近の重量級タイトルを高解像度で動かしながら、裏で配信や録画を同時に動かすと、CPUもGPUも暴れ馬のように電力を食い尽くします。
その時に余裕のない電源だと一瞬で落ちて、システムごと巻き込んでクラッシュしてしまう。
楽しんでいた時間を奪われるあの瞬間の悔しさ、忘れられません。
だからこそ今の私は余裕をもって電源を選ぶようにしています。
妥協する理由はありません。
特に最近のRTX 50シリーズやRyzen 9000シリーズといった最新パーツは、一瞬のうちに大きな電力を要求します。
カタログの数値を見て「600Wで大丈夫だろう」と思うのは本当に危険です。
実際には見えない突発的な消費エネルギーに驚かされることになります。
私はそれを体で味わったので、電源選びでは決して妥協しないようになりました。
昔、友人が600Wの電源で最新ゲームを配信しようとしたのですが、全く起動できませんでした。
結局その場で750Wの電源に換えたのですが、その瞬間から驚くほど快適に動き出したのを横で見ていました。
その時の感覚は今でも覚えています。
電源容量とは見えない部分で支えてくれる保険のようなもの。
保険だからこそ余裕が必要なんですよね。
問題は、電源が原因と気づくまでに時間がかかるという点です。
最初はドライバを疑い、次はOSを入れ直し、それでも直らず迷走する。
私も初心者のころにまさに同じ道をたどりました。
無駄に時間を潰してしまう。
財布のためにも、心のためにも。
ここは強調しておきたい部分です。
私の現在の環境ではフルHDで60fps程度のプレイなら600Wでも何とかこなせますが、WQHDや4K画質で144fpsを追い求めるなら、750W以上は間違いなく必要になります。
その上で80PLUSのゴールド以上を選んでおくと効果的です。
効率の悪い電源は必要以上に熱を生み、そのせいでファンが常に回って騒音が増す。
夜中、静かに遊びたいのにファン音ばかり気になるのは嫌ですよね。
静音性。
これが地味に大切です。
私はこの「安心感」にこそ意味があると思っています。
仕事で使うPCにしても、大事な会議や資料作成の最中に落ちるようでは信頼が失われます。
たった数千円の差でそうした不安を減らせるなら、投資するに越したことはありません。
ゲームの世界は今後さらに表現力を増し、高解像度化も確実に進みます。
その未来を考えると、750Wや850Wといった容量に余裕を持ち、効率も高いゴールドやプラチナ規格を選んでおくことが合理的です。
余裕のある電源はただ安定させるだけでなく、結局長期的に寿命を延ばすことにもつながります。
その意味で、私は電源選びを「快適さの基盤づくり」と呼んでいます。
最終的には、すべてのパーツを支える土台となるのが電源です。
見えない存在ですが、そこに安心を置くことで初めて、グラフィックボードやCPUといった「魅せるパーツ」が本来の力を発揮できる。
私はその経験から優先順位を大きく変えました。
快適さを求めるなら、まずは土台に投資すること。
これが一番の正解だと思います。
電源は裏方ではありません。
長くPCを楽しむための縁の下の力持ちです。
信頼できる電源を選べば、あとは心置きなくゲームや仕事に集中できる。
原神用ゲーミングPCを買う前によくある疑問


Q. スマホ版やPS版と比べてPC版の利点は?
私はいろいろなデバイスで「原神」を触ってきましたが、長く腰を据えて楽しむならPC版が頭ひとつ抜けていると感じています。
理由はシンプルで、映像の迫力や操作の自由度、さらにパフォーマンスや配信との相性まで含めると、他の選択肢では物足りなさが残るからです。
もちろんスマホやPSでも遊びやすさは十分あるのですが、思わず「やっぱりこれだ」と口に出る瞬間が訪れるのは、いつだってPC版だったのです。
画面の美しさは特に語らずにいられません。
WQHDや4K対応のモニターで立ち上げた時、町並みの光と影が一気に広がり、建物の壁の質感から木々が揺れる様子まで細かく表情を持ち始めます。
PSやスマホでも確かに綺麗ですが、一度PC版で描かれる画を体験してしまうと、どうしても後戻りはできなくなるのです。
気づくと私は画面に吸い込まれ、ただキャラクターを動かすだけで散歩をしている心地になっていました。
操作性の部分でも明らかな差があります。
私はPS用のコントローラー操作にも慣れていたので、最初は特に不満を感じませんでした。
しかしキーボードとマウスで試してみたら、弓キャラで矢を放つ時に敵の細かい動きに確実に合わせられる瞬間があり、「あっ、これだ」と感じたのです。
カーソルを動かす指先の感覚とキャラクターの反応がぴたりと合致する、その小気味よさは何度繰り返しても飽きず、長い1日の仕事を終えてリフレッシュするのにうってつけでした。
狙った通りに動かせる爽快感。
アップデートの速さでもPCに軍配が上がります。
ある時、NVMe Gen.4のSSDを導入してすぐに大規模パッチが来たのですが、以前はコーヒーを飲みながら「まだか」と待っていたものが、あっという間に終わってしまった。
思わず「もう終わったのか?」と笑ってしまいました。
こうなるともう元の環境には戻れません。
SSDの力を体で実感した瞬間で、これがあるから日々のワクワクが削がれないと実感しました。
安定性も大きな要素です。
スマホで長く遊んだことがある人なら、発熱で手が温かくなり、動作が徐々にぎこちなくなる経験をしているのではないでしょうか。
私は何度もそれに悩まされてきました。
PCの場合は冷却を工夫できるのが大きいです。
空冷ファンを選ぶのも良いですし、水冷を導入すれば静かで冷え方も違う。
初めて水冷の環境で遊んだ時、余計な雑音が消え、熱の不安もなく、ただ作品の世界に没頭できることがこんなに快適なのかと驚きました。
静寂の中で集中できる感覚は格別でしたよ。
私は録画や配信のしやすさも重視しています。
仕事の後に遊ぶ時、その体験を記録したくなることがあるんです。
PSやスマホでは「できなくはない」けど、何か制約が多い。
けれどPCなら配信ソフトを立ち上げながらでもゲームは滑らかに動きますし、余力のあるCPUやGPUなら裏で録画までできる。
私は実際にCore i7からRyzenに切り替えた時、エンコード処理の速さに感動し、道具次第で楽しみ方がこんなに広がるのかと実感しました。
新しい武器を得た感覚。
ただし、PSやスマホだけが持つ魅力もあります。
PSの電源を入れればすぐ遊べる気軽さは確かに強みですし、旅先や移動中にスマホ一台で遊べる便利さも大きいです。
私も出張先で少し進めてから帰宅後に続きをPCで楽しむ、そんな組み合わせをしたことがあります。
でも、自分の生活の中で落ち着いた時間と場所を確保して遊ぶなら、結局はPCに戻ってしまうのです。
性能やカスタマイズの自由さが安心感をくれるからです。
例えば144fps設定で動かした時の感動は忘れられません。
その瞬間、「もう60fpsには戻れない」と呟いていました。
同じ世界なのに別物のように感じられ、PCで遊ぶ醍醐味を実感した瞬間でした。
もちろんすべての人にPCを薦めたいわけではありません。
遊ぶ環境や時間、コストを考えれば、それぞれに合った選択があるはずです。
ただ私自身の経験を踏まえて言うなら、もしも本気で「原神」という作品を深く、長く、妥協なく味わいたいのならPCを選ぶことを強く勧めたいです。
映像の美しさや操作の自由度に限らず、配信や録画、マシンの自由なカスタマイズによって遊び方までも拡張できるのはPCという土台があってこそだと感じます。
私はゲームに「ただ遊ぶ」以上の価値を見出したいと思っています。
作品の映像美を眺め、思い通りに操作し、ときにそれを共有したり記録したりする。
そうした一連の流れをすべて支えてくれるのはPC版です。
だからこそ私は迷わず言いたいのです。
腰を据えてこの作品を愛していくつもりなら、間違いなくPCでプレイした方がいい。
長年遊び続けるための選択として、これが私の揺るぎない結論なのです。
これは体験を通して得た心からの実感です。
Q. 将来のアップデートにも対応できる構成はある?
将来を考えてPCの構成を選ぶときに一番大切なのは、やはり少し余裕を持っておくことだと私は思っています。
今の推奨スペックを満たしていれば確かに快適に遊べます。
しかしそれだけでは近い未来に対応できなくなるのが現実です。
オンラインゲームは数年のうちに進化し、アップデートを重ねるたびに必要とされる性能のハードルが高くなっていきます。
だからこそ「今が快適だから大丈夫」と安易に考えず、「数年先も問題なく遊べる環境」を作っておく方が結局は自分を助けることになるのです。
安心したいからです。
そのときの落胆は本当にこたえました。
更新されるたびにデータ容量は膨らみ、画質も強化され、演出も増えていく。
その流れを肌で感じたからこそ、最初に余裕を持ったパーツを選ぶ方がコストも手間も減ると今は確信しています。
そう思えば妙に腑に落ちるんです。
グラフィックボードにしても、エントリークラスではなくミドルレンジ以上を検討すべきだと痛感しています。
例えばRTX5070TiやRadeon RX9070XTクラスであれば現状どころか将来的な4K対応にも期待できます。
私は最新のフレーム生成技術を初めて体験したとき、その変化に本気で驚きましたね。
映像がここまでなめらかに変わるのかと。
やっぱり技術は進歩しているわけです。
CPUの選び方もまた重要です。
単に「今のゲームが動くから十分」では先が持ちません。
Core Ultra 7 265KやRyzen 7 9800X3Dのようなミドルハイ以上を選ぶことで、重いゲームを遊びつつ配信や別作業を同時に行っても問題なくこなせる安心感があります。
それに新世代のCPUは処理能力の向上だけでなく、AI処理の対応やI/Oの改良など、後々に効いてくる要素が詰まっているんですよ。
この広がりはやっぱり侮れません。
メモリに関しては、私は以前16GBで運用していました。
その頃はしばしばブラウザを開きながら遊んでいたのですが、気づくと動作が重くなり、しょっちゅうイライラしていました。
だから今は迷わず32GBを推しています。
原神単体なら16GBでも動きますが、配信や録画をすれば結局はすぐに足りなくなるんです。
最初から余裕を持っておけば増設の手間もなく、心の余裕にもつながるんです。
精神的にもね。
公式の必要容量が30GBと書いてあっても、数回のアップデートで100GB近くになるのは珍しくない。
まして他のゲームと並行すると一瞬で埋まります。
私は1TBのSSDでやり繰りしていた頃、大型アップデートのたびにどれかを削除しなければならず、正直嫌になりました。
だから今なら迷わず2TBを選びますね。
容量に余裕があると本当に気が楽ですよ。
遊びに集中できます。
冷却性能についても油断できません。
最新世代のCPUは以前のような爆熱ではないものの、高負荷をかければやはり熱は溜まります。
私は空冷派ですが、良いクーラーを選べば静音性も十分で、それがプレイに集中する助けになります。
もちろん水冷も魅力的で、特に配信をする方にはファン音が小さいことがありがたいはずです。
静音性は快適さの裏側。
仕事終わりに遊ぶときこそ、余計なノイズは減らしたいものです。
ケースの選び方も軽視できません。
パーツ交換や増設に準備を残しておけるかどうかは、実際に数年使う中で差になります。
最近よく見かけるピラーレス構造のケースは作業のしやすさが抜群で、GPUを載せ替える時に本当に助かります。
自由度の広さは実際に触って使うとありがたみを強く感じます。
未来に残しておく余地。
これが思いのほか大きいわけです。
率直に言えば、私がおすすめする組み合わせはミドルレンジより少し上です。
私自身が過去に妥協して安く済ませたことで、後から無駄な買い替えや追加出費に追われた苦い経験をしたからこそ、今は強く言いたいのです。
「余裕は贅沢ではなく、必要な安心の備えだ」と。
だからこそ最終的な選び方は、ミドルハイクラスで一歩先を見越すこと。
それが少なくとも数年間、余計な後悔なく快適に過ごすための唯一の方法だと私は考えています。
未来の自分を助ける投資。
それこそが社会人として何度も痛い思いをした末にたどり着いた私なりの答えなのです。
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60YM


| 【ZEFT R60YM スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 8500G 6コア/12スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9060XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R67I


| 【ZEFT R67I スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | DeepCool CH160 PLUS Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60GY


| 【ZEFT R60GY スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9070XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| キャプチャカード | キャプチャボード AVERMEDIA Live Gamer 4K GC575 |
| ケース | NZXT H9 FLOW RGB ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II White |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60AW


| 【ZEFT R60AW スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | LianLi O11D EVO RGB Black 特別仕様 |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
Q. BTOと自作、買うならどっちがコスパ良い?
原神を遊ぶためにパソコンを用意する際、私が多くの人に勧めたいのはBTOパソコンです。
自作にも確かに楽しさや自由さがありますが、安定して快適にゲームを楽しみたいと考えるなら、BTOの安心感とコストバランスの方が現実的だと思います。
自分で組む過程はワクワクしますが、その一方でトラブルに直面した時の消耗感もよく知っています。
電源が立ち上がらない。
ケーブルを全部抜いて差し直しても反応がない。
あの途方もない時間の喪失感、正直言ってもう味わいたくありません。
最近のBTOは正直、かなり出来がいいと感じています。
最新のDDR5メモリやGen.4 NVMe SSDが標準で選べたり、空冷と水冷の両方を用意していたりと、細部で抜かりがないんです。
特に冷却性能に関しては昔と比べ物にならないほど進歩しています。
以前はケース内に熱がこもらないか、常にソワソワしていました。
最初の一台を買う人でも不安が少ないラインナップになっていると強く感じます。
「あぁ、こういう完成度の高さを待っていたんだ」と思う瞬間すらありますね。
むしろ年齢を重ねた今の私にとっては、部品をひとつずつ吟味する過程にある手触り感こそが面白い。
昨年も私は仕事と趣味を兼ねて一台を組みました。
完成して電源を入れた時の静かで誇らしい達成感は、やっぱり特別なものです。
あの時は「この満足感こそが自作の醍醐味だ」と改めて思いました。
正直に言えば、BTOではその胸の高鳴りは得られません。
それでも費用面で比較すればやはりBTOの方に分があります。
これが自作だったら、原因究明だけで何日も潰れることもありますよね。
「マザーボードか、メモリか、それとも電源か…」と疑わしい部品を一つずつ替えて試す作業を繰り返す、あの骨が折れる検証地獄。
そう心から思うようになりました。
特にグラフィック負荷の大きい原神では、描画品質と安定性が何より大切です。
BTOならGPUとCPUの組み合わせに合わせて十分な電源容量や冷却設計をメーカーが検証してくれるので、ユーザーは安心して遊べるんです。
つまり「動かないかもしれない」という不安を考える必要がない。
これはゲームを楽しむ上で大きなメリットです。
実際のところ、ほとんどの人にとって重視するのは「ちゃんと動いて、きれいに映るかどうか」。
自作の場合、OSを入れるところからドライバーの更新まで全部自力。
これ、平日の夜にやると非常に骨が折れます。
会社帰りに疲れた体で何時間も作業する気力なんて、正直残っていません。
でもBTOなら初期設定を済ませた状態で届くモデルもあるので、箱を開けて配線を済ませればすぐに使える。
初めてその便利さを体験した時、「あぁ、これは戻れないな」と心底思いました。
とはいえものづくりの充実感を求める人にはやはり自作が魅力です。
私も自作をした時のあの瞬間を鮮明に覚えています。
深夜、BIOSを設定し終えて再起動。
趣味としての喜びはそこにある。
だからこそ、興味のある人にはぜひ試してほしいとも思います。
それでも最初の一台を買う人、そして「ゲームを快適に楽しむこと」が何より大切な人にはこう言います。
「BTOを選んだほうがいい」と。
理由はシンプルで、無駄なストレスが少ないからです。
コストで損をしにくい。
さらに、トラブルがあればメーカー対応に任せられる。
要するに、時間と気持ちに余裕をくれるんです。
安心のサポート。
楽な導入。
40代になった今、この二つの価値が以前より大きく感じられるようになりました。
若い頃は挑戦や苦労自体を楽しめました。
しかし今は、限られた時間の中で安心と快適さを優先したい。
パソコンを手間なく使って、その時間を遊びに充てたい。
だから私は、原神を存分に楽しむためにはBTOが最適だと確信しています。
最終的に言えるのはこれだけです。
効率や快適さを大切にするならBTO。
手触り感や体験を優先したいなら自作。
そのどちらを選ぶかは本人次第。
ただ、原神のように安定した高品質のプレイ環境を重視するなら、やっぱりBTOが一番。
Q. ゲーム配信や動画編集もする場合の注意点は?
ゲームだけを遊ぶだけなら、そこそこの性能でも何とかなるものです。
しかし、配信や動画編集を同時に行おうとすると、一気に現実を突きつけられます。
最初は「まあ大丈夫だろう」と軽視していた私ですが、やってみて CPU とメモリが一瞬で悲鳴を上げるのを見たとき、背筋が冷たくなりました。
だからこそ、最初から配信や編集を前提にした構成でPCを用意することが、余計な遠回りを避ける一番の近道だと痛感しています。
私自身、その代償を何度も払ってきたからです。
中でもまず注目すべきはCPUです。
原神程度のゲーム単体ならば大きな不満は出ませんが、配信ソフトや編集ソフトを立ち上げた途端に、その余裕はあっけなく奪われます。
実際、私がCore Ultra 5を使っていたときには、ソロプレイは快適でも、配信開始と同時にブラウザを開いただけで映像がガクガクになった経験がありました。
あの瞬間、「これは先が短い」と悟ったんです。
結局、Core Ultra 7に切り替えたのですが、そのときの安心感は想像以上でした。
ワンランク上を選ぶだけで、心の余裕まで変わるものなんだと思い知らされましたね。
メモリも同じぐらい重要です。
16GBでゲーム本体だけを動かすなら大きな支障はありません。
しかし同時にブラウザを立ち上げ、さらに編集ソフトまで開くと、すぐに不足を感じる場面が出てきます。
私も16GB環境で動画編集をしたとき、カット作業の最中にスワップが走り、カーソルが一瞬固まる。
その数秒間が締め切り前だと本当に苛立たしい。
あの焦りは二度と味わいたくありません。
だから今は迷わず32GBを選びます。
多少コストは増えますが、その快適さと安心感は何倍も価値があると思っています。
ストレージも実に厄介です。
配信で録画を残していると、数本の動画で簡単に数百GBが消えてなくなります。
私が最初に使ったのは1TBのSSDでしたが、半年経たないうちに「もういっぱい?」と呆れました。
仕方なく2TB SSDへ乗り換えた時、録画を削除する煩わしさから解放されたのは大きな救いでした。
空き容量を気にせずに作業に集中できるというのは、想像以上に精神的なストレスを減らしてくれるんですよね。
これは本当に侮れない要素です。
最初は「RTX 5060 クラスで十分だろう」と考えていました。
実際、プレイ自体は問題なく楽しめましたが、高画質での動画レンダリングを続けると、どうしても余力不足を感じる場面が出てきます。
作品を仕上げていくときに時間を無駄にしないためには、やはり一段上のGPUが頼もしい。
性能に余裕を持たせておくだけで作業効率も完成度も確実に変わりますし、これは長期的にみれば投資以上の見返りだと今では信じています。
冷却と静音性についても、かつての私は甘く考えていました。
水冷なら静かだろうと軽い気持ちで導入しましたが、実際にはポンプ音や取り付け条件で想像以上に気を使うことになり、「あれ、こんなにうるさいのか」と悩まされました。
その後、思い切って大きめの空冷クーラーに変えたのですが、この選択が正解。
配信時にマイクへ入り込むノイズが減り、リスナーから「音がクリアになった」と言われた時は思わず嬉しくなりました。
通信環境についても身をもって学びました。
最初はWi-Fiで気軽に配信していたのですが、ある日数秒間だけパケットロスが発生しただけでチャット欄が荒れたんです。
その雰囲気の冷め具合といったら言葉になりません。
あの経験以降、有線LAN以外の選択肢は考えなくなりました。
地味だけれど、安定性が一番の安心材料だと思います。
私が今たどり着いた理想構成は、CPUはCore Ultra 7かRyzen 7以上、メモリは32GB、ストレージは2TB SSD以上、GPUはミドルハイクラス、冷却は静音性重視の空冷、そして有線LAN。
こう揃えてからというもの、配信も編集も余裕を持って取り組めるようになりました。
特に、配信後の編集がスムーズに終わるようになったのは大きな改善で、リスナーからも「最近安定してるね」なんて言われると、本当に報われた気持ちになります。
やっぱり準備が全てです。
後悔は避けたい。
余裕を見据えた構成は、単なる数値のスペックを超えた安心感を与えてくれます。
それは効率や安定性だけではなく、自分の気持ちの軽さにも直結するのです。
焦りや不安が減り、作品づくりそのものに前向きになれる。
それが一番大きな効果なのではないでしょうか。
今から配信や編集を始める方には、ぜひ私のように遠回りせず、最初からしっかりした構成を選んでほしいと思います。
そのほうが結局、時間もお金も無駄にしませんから。
この数年間の試行錯誤を通じて私が最終的に理解したのは、快適な環境は自己投資以上の価値をもたらすということでした。
見えない部分での安定こそが、最大の成果に直結する。
その事実は、どのカタログスペックよりも強力な説得力を持っていると思います。
だから今の私は胸を張って言えるんです。
「最初から余裕を持った選択をしてください」と。
人気PCゲームタイトル一覧
| ゲームタイトル | 発売日 | 推奨スペック | 公式 URL |
Steam URL |
|---|---|---|---|---|
| Street Fighter 6 / ストリートファイター6 | 2023/06/02 | プロセッサー: Core i7 8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: RTX2070 / Radeon RX 5700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter Wilds
/ モンスターハンターワイルズ |
2025/02/28 | プロセッサー:Core i5-11600K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce RTX 2070/ RTX 4060 / Radeon RX 6700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Apex Legends
/ エーペックスレジェンズ |
2020/11/05 | プロセッサー: Ryzen 5 / Core i5
グラフィック: Radeon R9 290/ GeForce GTX 970 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| ロマンシング サガ2
リベンジオブザセブン |
2024/10/25 | プロセッサー: Core i5-6400 / Ryzen 5 1400
グラフィック:GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| 黒神話:悟空 | 2024/08/20 | プロセッサー: Core i7-9700 / Ryzen 5 5500
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700 XT / Arc A750 |
公式 | steam |
| メタファー:リファンタジオ | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i5-7600 / Ryzen 5 2600
グラフィック:GeForce GTX 970 / Radeon RX 480 / Arc A380 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Call of Duty: Black Ops 6 | 2024/10/25 | プロセッサー:Core i7-6700K / Ryzen 5 1600X
グラフィック: GeForce RTX 3060 / GTX 1080Ti / Radeon RX 6600XT メモリー: 12 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンボール Sparking! ZERO | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i7-9700K / Ryzen 5 3600
グラフィック:GeForce RTX 2060 / Radeon RX Vega 64 メモリ: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE | 2024/06/21 | プロセッサー: Core i7-8700K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce GTX 1070 / RADEON RX VEGA 56 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ファイナルファンタジーXIV
黄金のレガシー |
2024/07/02 | プロセッサー: Core i7-9700
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Cities: Skylines II | 2023/10/25 | プロセッサー:Core i5-12600K / Ryzen 7 5800X
グラフィック: GeForce RTX 3080 | RadeonRX 6800 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンズドグマ 2 | 2024/03/21 | プロセッサー: Core i7-10700 / Ryzen 5 3600X
グラフィック GeForce RTX 2080 / Radeon RX 6700 メモリー: 16 GB |
公式 | steam |
| サイバーパンク2077:仮初めの自由 | 2023/09/26 | プロセッサー: Core i7-12700 / Ryzen 7 7800X3D
グラフィック: GeForce RTX 2060 SUPER / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ホグワーツ・レガシー | 2023/02/11 | プロセッサー: Core i7-8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: GeForce 1080 Ti / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| TEKKEN 8 / 鉄拳8 | 2024/01/26 | プロセッサー: Core i7-7700K / Ryzen 5 2600
グラフィック: GeForce RTX 2070/ Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Palworld / パルワールド | 2024/01/19 | プロセッサー: Core i9-9900K
グラフィック: GeForce RTX 2070 メモリー: 32 GB RAM |
公式 | steam |
| オーバーウォッチ 2 | 2023/08/11 | プロセッサー:Core i7 / Ryzen 5
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 6400 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter RISE: Sunbreak
/ モンスターハンターライズ:サンブレイク |
2022/01/13 | プロセッサー:Core i5-4460 / AMD FX-8300
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| BIOHAZARD RE:4 | 2023/03/24 | プロセッサー: Ryzen 5 3600 / Core i7 8700
グラフィック: Radeon RX 5700 / GeForce GTX 1070 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| デッドバイデイライト | 2016/06/15 | プロセッサー: Core i3 / AMD FX-8300
グラフィック: 4GB VRAM以上 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Forza Horizon 5 | 2021/11/09 | プロセッサー: Core i5-8400 / Ryzen 5 1500X
グラフィック: GTX 1070 / Radeon RX 590 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |