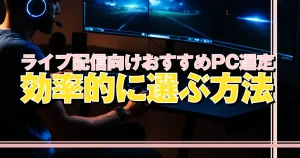原神を快適に遊ぶためのゲーミングPC必要スペックを徹底解説

CPUはCoreとRyzenどっちを選ぶ?実体験からのポイント
原神をゲーミングPCで快適に楽しむなら、やはりCPU選びは避けて通れないテーマです。
実際のところ、どちらを選んでも今の時代であれば大きな失敗にはならず、十分な満足感を得られる水準に達しています。
つまり答えは自分のスタイル次第なんです。
Coreシリーズを選んだとき、まず感じたのはレスポンスの速さです。
ただ、Discordで通話をしつつ配信も同時に行い、さらに裏で複数のブラウザを開きっぱなしにしているような状況では差が如実に表れました。
特にCore Ultra 7 265Kを搭載したPCを使ったとき、予想以上にフレームが安定していて、重たい処理にもかかわらず落ち着いた動作を見せたのです。
あの瞬間、「ああ、やっぱりこれで良かった」と心から実感しました。
頼れる相棒に出会った感覚ですね。
一方のRyzenシリーズも無視はできません。
数年前までは「安価だけど性能はまあまあ」という評価も聞きましたが、今やその印象は完全に覆っています。
特にRyzen 7 9800X3Dを導入したときには、本当に感心しました。
複数のアプリを動かしても滑らかさを失わず、映像の切り替えや細かい影の表現もスムーズ。
これが3D V-Cacheの効果なのかと、なるほどと頷きました。
長時間プレイしていても不思議なくらいストレスを感じない。
その積み重ねが「安心感」に繋がり、自然とこのCPUを信頼するようになりました。
静かな満足感があった。
しかしCPU選びは単純なフレームレートや処理速度の話ではなく、自分がPCをどんな使い方で運用するかが根本的に重要なのです。
私なりに整理すれば、ライブ配信や複数タスクを並行しても性能の余裕を求めるならCore。
コストを抑えつつ持久力やバランスを重視するならRyzen。
選択のベクトルはこのように分かれます。
ここが判断の分岐点だと思います。
実際、私が二台のマシンを同時に使い比べてみたときにも、その違いは明確でした。
配信とプレイをセットにして挑むならCore Ultraに軍配が上がります。
しかし複数の作業を横断的に進めたいとき、同じ価格帯ではRyzenが心地よい余裕を見せてくれるのです。
つまり、どちらを選んでも「失敗」にはならず、むしろ自分自身の利用スタイルを突き詰めて考えることが何より大切なんだと強く実感しました。
ここ数年で大きく進化したのは、CPUだけでなく発熱や消費電力の面もです。
昔のように「高性能なら水冷必須」といった時代は過ぎ去りました。
ただし問題は周辺環境です。
良いCPUを選べば他のパーツにも負担がかかる。
電源ユニットやケースの容量、冷却ファンの必要性など、総コストはあっという間に膨らむものです。
財布への打撃。
実感します。
だからこそ「とにかく性能を上げよう」と突っ走る前に、自分本位でなく実際に必要かを冷静に見極めることが重要だと私は考えます。
本当に必要な部分にだけ投資をする、それが長く使い続ける秘訣だと思うのです。
ただ、私がCPUにお金をかけて良かったと心から納得し、投資の正解を確信したのは、複数作業を絡めて長時間遊ぶときです。
同じ原神でもただ遊ぶだけと、同時に配信や他のアプリを走らせながらプレイするのでは勝手がまるで違う。
頭では理解していましたが、実際試してみてようやく「この快適さにこそ意味がある」と腑に落ちました。
環境が快適だと、気持ちまで安定するんですよ。
最終的に私が導き出した答えは、こう整理できます。
配信や高負荷を伴うプレイを支えたいならCore Ultra 7クラス。
仕事と趣味を横断し、並行処理の効率を求めるならRyzen 7クラス。
それぞれに強みがあるからこそ、自分の生活に寄り添わせて考える必要があるのです。
明確に棲み分けがある。
パーツ選びなんて所詮は自己満足、と言われることもあります。
けれど私は違うと思っています。
PCは仕事道具でもあり、趣味の中心でもあり、日々の生活を彩る相棒です。
だからこそ後悔のない一台を選びたい。
振り返ってみると、私が失敗を避けられたのは「どちらが上か」ではなく「自分に合うのはどっちか」を真剣に考えたからだと思います。
長く使える相棒を選ぶ。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 42923 | 2462 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42678 | 2266 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 41712 | 2257 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41007 | 2355 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38483 | 2075 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38407 | 2046 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37176 | 2353 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37176 | 2353 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35552 | 2194 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35411 | 2232 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33667 | 2205 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32811 | 2235 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32445 | 2099 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32334 | 2190 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29174 | 2037 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28462 | 2153 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28462 | 2153 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25380 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25380 | 2172 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23022 | 2209 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23010 | 2089 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20797 | 1857 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19452 | 1935 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17682 | 1814 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16001 | 1776 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15246 | 1979 | 公式 | 価格 |
ミドルからハイエンドGPUまで、価格差と体感性能の違い
原神を落ち着いて楽しむために環境を整えるなら、まず投資の優先順位はGPUだと私は思っています。
なぜなら、スペック表に並んだ数字よりも、実際にキャラクターを操作した時の滑らかさやレスポンスが最終的に満足度を左右するからです。
フルHDで60fps程度を狙うだけであれば、正直、最新ミドルクラスのGPUで十分です。
しかし144Hzのモニターを最大限に活かしたい時、状況は一気に変わります。
必要となるのはワンランク上の余裕。
そうでないと「あと少し惜しい」と感じる場面が必ず出てきます。
私が特に強調したいのは、数値に出ない「体感」の差です。
カメラを素早く振った時に残像が少なく、キャラクターが生きているようにスムーズに動いた時の一体感。
私は日々の仕事を終え、夜のわずかな時間を楽しむために原神を起動しますが、画面がカクつかず滑らかに流れる映像は、それだけで疲れを和らげてくれる。
数字以上の価値を実感しています。
しかし、やはり価格は大きな壁です。
RTX5070Ti や RX9070XT といったモデルの値段を目の当たりにすると、思わず「高いよな」と声に出してしまう。
実力は確かに申し分ありません。
4KやWQHDを楽しむ予定がある、あるいは映像制作や配信など別の負荷が高い使い方を検討しているなら話は別ですが。
私は過去に仕事用のPCにRTX5070を導入しましたが、原神を起動した瞬間にファンの音すら気にならないほど静かで「ああ、ここまで行くと余裕が違うんだ」と納得しました。
一方で、ミドルクラスGPUの価値も見過ごせません。
RTX5060Ti や RX9060XTなら購入しやすく、消費電力や発熱も扱いやすい。
フルHDで144fpsを目標にするなら十分満足できるレベルです。
実際に私は知人にこのクラスを勧めたことがあります。
その人は導入後に「思った以上に快適で助かった」と本気で喜んでくれました。
忘れてはいけないのは、GPUの寿命や将来性を見通す目を持つことです。
原神は軽量なゲームと思われがちですが、アップデートの積み重ねで少しずつ要求スペックが上がってきています。
今日快適に遊べるPC環境でも、2年後は息切れするかもしれない。
そのため、今の段階で少し余裕のあるモデルを選んでおくほうが結果的には長く安心してプレイできます。
私は大きな買い物だからこそ「未来を読む目が必要だ」と強く感じています。
特に4Kやウルトラワイドモニターを前提にしているなら、RTX5070Ti や RX9070XTクラスが必須だと思います。
逆に、フルHDで配信や編集をほとんどしないなら上位機種は不要です。
つまり、どんな環境でゲームをしたいのか、その問いかけ自体がGPU選びの根本になるということです。
私は実際、GPU市場の不安定さを肌で感じています。
円安や半導体不足の影響で価格が読めず、秋葉原を歩いていると朝より数千円安くなっている場面に出会ったことさえあります。
その瞬間、気づけば衝動買いをしていました。
あの「今だ!」と感じる瞬間を逃さず掴めたことで、金額以上の満足感が得られたのは確かです。
買い物は一期一会。
そう実感しました。
だからこそ多くの人に伝えたいことがあります。
これに対し、将来的にWQHDや4Kを目指すなら5070や9070に投資する価値があります。
このラインが境目で、体感できる快適性が明確に変わります。
自分がどれだけゲーム時間を大切にしたいか。
それを考えることが最終的には答えになるのです。
気楽に楽しむならミドル。
これが私の出した一つの答えです。
私は今、自分が選んだGPUと共に毎晩のプレイ時間を満喫しています。
いや、満喫しているというより、生活の一部になっている感覚ですね。
未来を見据えながら、今の満足感を大事にする。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 48533 | 101751 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32047 | 77933 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30055 | 66640 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 29978 | 73293 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27075 | 68805 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26420 | 60131 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 21879 | 56698 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19855 | 50392 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16507 | 39301 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 15942 | 38131 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15805 | 37909 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14592 | 34857 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13699 | 30804 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13160 | 32303 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10787 | 31685 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10617 | 28534 | 115W | 公式 | 価格 |
DDR5メモリは16GBで大丈夫?それとも32GBが安心?
ただ実際に試してみると、それは本当に「最低限動く」というレベルに過ぎないんです。
プレイ自体は可能ですが、例えば攻略動画を流しながら進めたり、配信やチャットを同時に開いたりすると、一気に重くなる。
こうした不便さは数字だけ見ていると気づきにくいのですが、実際に操作してみるとストレスとしてはっきり現れるものです。
正直に言って、余裕のない環境でゲームをするのは想像以上に疲れます。
私が心から勧めたいのは32GBです。
32GBの環境に切り替えた瞬間、日常の使い勝手がガラッと変わります。
原神を最高画質で動かしつつ、Discordで仲間と話し、その裏でOBSをつけて配信をしながら、必要ならブラウザで動画も再生する。
そういった複数の動作を同時に行っても、ほとんどストレスを感じない。
この状態は思った以上に安心なんです。
まるで仕事中、大きなデータを開いたのにPCが平然と動いてくれる瞬間のような頼もしさがあります。
余裕があるってこういうことなんですよね。
DDR5メモリの特長として帯域の広さがあり、ロードや切り替えなどの細かい操作で違いを体感できます。
ただし、16GBから32GBに変えたからといってフレームレートが劇的に伸びるわけではありません。
それでも私は32GBを強く押すのです。
ゲームは進化を続け、必要とするリソースはじわじわ増えていく。
今は快適だとしても、半年、一年先に窮屈さを感じる場面が必ず出てくる。
そのたびに「やっぱり増設しておけばよかったな」と思い出すなら、最初から余裕を持っておいたほうが圧倒的に気楽です。
未来への投資。
そう考えています。
実際に知人の例があります。
彼は「16GBでも原神は動く」と言って半年ほどそのまま遊んでいました。
ところがアップデートとともにゲーム自体がどんどん重くなり、同時並行でYouTubeを見たり通話をつなぐと、すぐにカクつき始めたんです。
最終的に32GBへ変更した瞬間、「ここまで快適になるのか」と本気で驚いていました。
その話を聞いたとき、私もあらためて確信しました。
原神はUnity製のため、AAA級タイトルと比べれば軽い部類です。
それでも油断すると失敗します。
というのも、多くの人はゲームだけをして終わらないからです。
音楽を流す。
友人と話しながら冒険する。
32GBであれば、その不安を感じなくて済むんです。
安心感。
さらに今はDDR5環境が広まり、32GBはもはや普通になりつつあります。
数年先のことを考えれば、むしろ32GBを選ぶほうが合理的です。
私は以前、コストを抑えたい気持ちから16GBで済ませましたが、あっという間に後悔しました。
増設作業は時間も手間もかかりますし、快適性を後から足すより、最初から整えておくほうが確実に賢明です。
だから今の私なら迷わず32GBを選びます。
未来を見据えたいからです。
実際のところ、原神は16GBで動く。
ただしその環境では余裕がなく、ブラウザを一つ開くだけでも「大丈夫かな」と気を遣う場面が増えます。
その不安は思いのほか大きいんです。
一方で32GBの場合、そうした細かい気がかりがなくなり、心の余裕ができる。
落ち着き。
ゲームは単なる娯楽ではなく、仕事で疲れた私にとって数少ない癒やしの時間でもあります。
その大切な時間に「落ちるかもしれない」「重くなるかもしれない」と心配しながらプレイするのは、正直もったいない。
やはり32GBを選ぶべきだと強く思います。
もし「とりあえず16GBでいいや」と考えている人がいたら、私の過去の失敗を思い出してほしい。
半年後に結局32GBを買い直すより、今すぐ導入してしまったほうが圧倒的に気楽です。
「もっと早くやっておけばよかった」と私は本当に思いました。
だから私ははっきりと言います。
今から快適に遊びたい人、そして数年間安心してPCを使い続けたい人にとって、32GBのDDR5メモリこそ最適解です。
原神向けゲーミングPC選び ― ストレージ性能のチェックポイント

Gen4 SSDとGen5 SSD、実際にどのくらい違うのか
原神のような重たいゲームでSSDの世代差がどれほど快適さに直結するのか、実際に試してみると意外なことに気づかされました。
私は数年前にGen4 SSDからGen5 SSDへと環境を切り替え、その性能差を体感してきました。
数値上は大幅に進化しているのに「ゲームプレイにおいてはそこまでの違いはない」というのが正直な実感です。
だからまず初めに伝えておきたいことは、原神を快適に遊ぶだけならGen4 SSDでも必要十分だということなんです。
Gen5 SSDのカタログ上の性能は確かに圧倒的です。
Gen4でおよそ7,000MB/s程度だった読み込み速度がGen5では14,000MB/s近い製品も存在します。
数字を見れば2倍というインパクト。
思わず「すごいな」と声が漏れてしまう瞬間でしたよ。
正直、拍子抜けでした。
とはいえ、Gen5 SSDの価値を軽んじるのは早計です。
私の場合、ゲームだけでなく仕事や趣味で動画編集や配信録画も行っています。
何十GBもある動画ファイルを扱うとき、あるいは複数の編集作業を並行するときには、Gen5 SSDの恩恵が確実に現れました。
キャッシュ処理の速さが作業効率を押し上げ、編集中に固まるようなストレスから解放される。
これが本当に大きいんです。
毎日のように触れるからこそ、安心感が違います。
ただし、Gen5 SSDには冷却という落とし穴がある。
私がBTOで組んだPCにGen5を組み込んだとき、付属の小さなヒートシンクでは正直不安で、実際に大容量の書き込みを長時間続けたらサーマルスロットリングを体験してしまいました。
その時の「最新の規格でも冷却対策を怠ると意味がなくなる」という実感はかなり強烈でしたね。
静かな環境でファンの音がぶん回るのも地味に気になります。
本当に。
容量も忘れてはいけない要素です。
原神はアップデートのたびに巨大化し、気づくと100GBを軽く超えるようになりました。
実際、以前ストレージ残り容量が20GBを切ったとき、アップデートを入れられず慌てた経験があります。
その時の後悔は「速度じゃなく容量を優先しておけばよかった」です。
今では最低でも2TB構成にしています。
そうするだけで気持ちの余裕が桁違いです。
容量の安心。
では、Gen4とGen5はどちらを選ぶべきかという話に戻ります。
結論としては「使い方次第」です。
ゲームだけを楽しみたいのであればGen4 SSDで十分。
むしろ冷却や安定性の面ではこっちの方が安心できるかもしれません。
ところが、仕事や趣味で動画編集や大量のデータ処理を行う人ならGen5に投資する意味があります。
効率化につながり、結果的に精神的なゆとりまで生まれるのです。
会議用に動画資料を作る、同僚との共有フォルダに巨大なファイル群をアップする、そんな場面が増えてきました。
一方Gen5 SSDだと処理が滑らかに進み、次のタスクにすぐ移れる。
その差は仕事のリズムに直結し、1日の充実感を左右するほどなんです。
これは数字では語れないリアルな実感です。
今後の数年を考えれば、PCゲームや重量級アプリケーションがGen5を前提に設計されていく流れは避けられないでしょう。
今は不要に見える余裕性能も、いざ求められたときに「あの時Gen5を選んでおいてよかった」と思えるかどうかが分かれ目になります。
新しいものを追いかけるだけが正解ではありません。
本当に必要な性能と、心地よく長く使える安心のバランスを見極めることが大事です。
最終的に私が重視しているのは二つです。
容量の余裕。
そして冷却の安心。
この二つを満たしていれば、スペックの数字に惑わされず自分のスタイルに合った環境をつくることができます。
どちらを選ぶにしても大切なのは「自分の安心がどこにあるか」を見極めることなんだと思います。
数値より安心。
私はそう実感しています。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
1TBか2TBか、プレイデータや環境に合わせた現実的な選び方
私は長年パソコンを使ってきましたが、その中でも特に迷ったのがストレージ容量の選び方です。
最初の頃は「1TBあれば十分だろう」と思っていましたが、実際はそう単純な話じゃないとすぐに痛感しました。
そして気がつけば「また削除しなきゃいけないのか」とため息をつく羽目になる。
それを繰り返すのは正直しんどいですよね。
だから私は今でははっきりと2TBを選んだほうが快適だと伝えたいです。
原神は決して最初から巨大な容量を要求するゲームではありません。
ですがアップデートがあるたびに追加データが入ってきて、気づけば数字がぽんぽん積み上がっていく。
そこに自分で撮ったスクリーンショットやプレイ動画まで保存していくと、1TBのSSDではすぐに心許なくなってしまいます。
整理を意識しながら遊ぶのは、まるで楽しむためではなく我慢するためにゲームをしているような感覚で、気持ちが冷めてしまうことさえあります。
少なくとも私はそうでした。
以前、私は1TBのSSDを使っていました。
ゲームを立ち上げるたびに残り容量を確認し、録画した動画を削除するか外付けに逃がす作業が習慣になっていました。
最初は「これも仕方ない」と思っていましたが、数か月も同じことを続けると嫌気がさしてくるんです。
アップデートが来るたびに「ああ、また容量を空けなきゃいけないのか」と憂鬱になる。
気が滅入るばかりでした。
そんな自分にうんざりして、思い切って2TBへ変えた瞬間、本当に肩の力が抜けた感覚を覚えました。
安心感がまるで違いました。
しかも、今の世代のSSDは性能が進化しています。
私はこれを「見えない安心料」だと考えています。
思い返せば、買ったそのときの満足よりも、1年後や2年後にストレスを感じないことこそが、本当の価値だったと心から感じています。
私は動画編集や配信も趣味でやっていますから、SSDの容量がただの数字ではなく「作業の自由度」そのものです。
素材や録画データを保存するとき、1TBだと毎回判断を迫られる。
2TBならそんな無駄な迷いがほとんど消えるんです。
削除の手間から解放された瞬間に気づいたのは、私は作業そのものよりも、容量によって生まれる心理的負担に疲れていたのだということでした。
この差は本当に大きい。
もちろん容量さえ多ければ万能ということではありません。
2TBを持っていても整理を怠れば結局は散らかる。
ですが、1TBでは整理を頑張っていてもすぐに上限が迫ってくる。
だから私は容量を「余らせる贅沢」ではなく「快適さを担保する前提条件」と考えるようになりました。
これは単なる数字の話ではなく、心の余裕をどう持つかの話なんです。
最近ではクラウドゲーミングの話題も耳にしますが、現状ではローカルの保存環境に勝る快適さはまだないと思っています。
回線状況や画質を気にせずに遊びたいなら、現実的にはやはり十分なストレージを持つことが不可欠です。
1TBでは今は大丈夫でも、数年後には必ず窮屈になるのは目に見えている。
これは経験に裏打ちされた実感です。
実際に私は友人とBTOパソコンを選んだとき、「1TBで十分だよね」と言われました。
その瞬間に自分の過去を思い出し、強く「いや、2TBにしたほうがいい」と伝えました。
最初は渋っていた彼も最終的に納得し、数か月後に「容量を気にせず録画できるから助かってる」と感謝されたときには嬉しかったですね。
まるで自分の判断が正しかったと証明されたような気持ちになりました。
こういう生の声を聞くと改めて、自分の言葉に責任を持ってよかったと思えます。
CPUやGPUの性能ばかりに目が行きがちですが、本当に快適さを左右するのはストレージなんです。
軽視して「とりあえず1TBにしておこう」と決めてしまう人ほど、後で面倒な整理や外付けへの移動に追われているのを私は何度も見てきました。
私は確信しています。
原神を長く快適に楽しみたいなら、間違いなく2TBを選ぶべきです。
アップデートのたびにビクビクしなくていい。
やりたいことをやりたいまま実現できる。
それが2TBを導入する本当の価値であり、単なる数字では測れない安心感だと強く思います。
最後にどうしても伝えたいのは、ストレージ選びはただのスペック比較ではなく、これからの数年間をどう気持ちよく過ごすかという選択だということです。
迷っているなら迷わず大きい方を選んでください。
その決断が、数年先の自分を救います。
まさに経験者の言葉です。
後悔しない選択。
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z57A

| 【ZEFT Z57A スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H6 Flow White |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55IM

| 【ZEFT Z55IM スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5050 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55WI

| 【ZEFT Z55WI スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ブラック |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55DX

| 【ZEFT Z55DX スペック】 | |
| CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
よく使われるストレージメーカーの特徴と安心度
ストレージはPCの体験を左右する部品だと、年々強く感じるようになりました。
ゲームでも仕事でも、選び方を誤れば息苦しさのような不便さがつきまとい、逆に良い選択ができれば安心して長く使える。
私自身が数年にわたっていくつかのメーカーを試し、そして日常的に使ってきた経験から言えば、信頼に足るメーカーはWD、Crucial、キオクシアの3社に絞られると断言できます。
華やかな宣伝文句よりも、長く触れてわかる確かな安心に重きを置いてきた結果、そう結論づけるようになりました。
WDに関しては、私の思い出と密接につながっています。
かつて仕事用の資料や企画書、さらに趣味で撮りためた動画や写真を一つのドライブに詰め込み、容量不足にうんざりしていた時期がありました。
思い切ってWDのNVMe SSDに切り替えてからというもの、不思議なくらいストレスが消えたのです。
カタログに載った数字よりも、その実際の安定感が心を軽くしてくれる。
大切なデータがある以上、速度より先に「ちゃんと守ってくれるか」を見極めたい気持ちがありますよね。
WDはその点で裏切らない。
飾り気がなく実直で、まさに相棒と呼びたい存在です。
これは中国出張中、トラブルで急いで大量のデータを処理せざるを得なかったときに、まったく問題なくこなせてくれたことで、私は完全に信頼を置くようになったのです。
Crucialについては「助かった」と何度も心の中でつぶやいた経験があるほどです。
動画編集を休日に行うのが私の小さな楽しみですが、素材となる動画ファイルは容赦なく巨大化します。
ゲームを一つインストールするだけで数十GBを超えるのも当たり前、原神の更新ファイルなど見た日には笑うしかないサイズ感です。
そんなとき、安価で2TBや4TBといった大容量モデルを手に入れられるCrucialの存在が私を救いました。
消耗品として割り切れる値段でありながら、日常使いでは「十分以上」に動いてくれる。
何より「安いから不安」ではなく「安いのに安心できる」と思わせてくれるのがこのメーカーの魅力だと感じています。
財布を守りつつ、快適さもちゃんと確保してくれる。
ありがたい存在ですね。
日本メーカーであるキオクシアは、安心の種類が少し違います。
これは感覚的に近所の頼れる電気屋に例えられる感覚です。
派手さはありません。
ベンチマークの数値遊びをしたい方からすれば物足りないでしょう。
しかし、数年後に「ああ、まだ安定しているな」と気づいたときの安心感が本物なのです。
私の場合、長く同じデータを保持し続ける業務があり、その安心を買う意味が非常に大きかった。
国内サポートがあることも、40代という年齢に差しかかると地味に心強いんです。
多少のトラブルでも日本語で対応してくれるという安心感が、仕事の合間にふっと肩の力を抜かせてくれました。
結局、華やかではないけれど「選んで良かった」としみじみ思えるのがキオクシアなのです。
では、そうしたストレージを扱うBTOショップの姿勢も大切になります。
ドスパラは柔軟さが光りますね。
この対応力が実にありがたいのです。
その時に選び直せる余裕があるお店は、ただの販売店ではなくユーザーの伴走者に近い存在だと痛感しました。
マウスコンピューターは違った意味で安心感をくれます。
初期構成の段階から、長期利用を前提とした作りがされているように感じるのです。
よく見かけるのはキオクシアを組み込んだモデルで、これは「派手さより日常の実用度」を狙った配置だと思います。
そのうえでサポートがしっかりしているのも強みですね。
実際、知人がトラブルを抱えたときにサポートに相談していて、「人と話せる」というだけで心が落ち着いていました。
こんな小さな安心が積もり積もって、長く付き合える相手を決めるんだと改めて思いました。
パソコンショップSEVENは正直、少しマニアックな位置づけかもしれません。
ただ、私はここで購入したPCを今も快適に使い続けています。
知名度は大手に及ばなくても、そのぶん個性や情熱がある。
カスタマイズ性が抜群に高く、プロゲーマーや配信者とコラボしたモデルには「ユーザーのこだわりを尊重しますよ」という熱が伝わってくるのです。
大げさに言えば、隠れた名店。
利用したことのある人には、その価値がきっと伝わるでしょう。
つまり、日常で悩む人にとってはWDとCrucialで容量を安心して確保し、長期安定性を望むならキオクシア。
そして各ショップの特徴を理解し、自分のスタイルに合わせてドスパラ、マウス、SEVENを選べば、結果的に「失敗したな」と思うことはないと私は思います。
PCは安くない買い物ですから、後悔が大きく残れば毎日の作業すら重たく感じてしまいます。
逆に納得して選べば、買った瞬間から心に余裕が生まれる。
これは私自身が感じた実体験です。
安心こそ最大の価値。
私はこの3社を基盤に、自分の直感で信頼できるショップから選ぶ。
そのことで仕事も趣味も中途半端にせず、充実したPCライフを送れていると胸を張れます。
強い組み合わせは今のところ他に見当たりません。
それだけの当たり前が、実は最高の幸せなんだと感じるのです。
使い方別に見る原神向けおすすめゲーミングPC

フルHDでコスパ重視、初めてのゲーミングPCにおすすめの構成
むしろ中堅どころのGPUを選んで、全体のバランスを意識した方が実際の満足度は高いというのが自分の経験からの実感です。
以前は最新のハイエンドに惹かれて無理をして購入したこともありましたが、結局数年たてば性能差が縮まり、価格に見合う満足感は長続きしませんでした。
やたらと背伸びするより、堅実に選ぶほうが結局は快適です。
CPUに関しても似たような考えを持っています。
配信しながら遊ぶ場合や、ブラウザで複数タブを開いて仕事を並行する場面では、妥協がすぐに足を引っ張ってきます。
Core Ultra 5 235やRyzen 5 9600といった中堅クラスを選ぶのがちょうど良いと思います。
少し値は張っても、余裕のあるCPUを選んだときの安心感は大きいですし、長期的に見てもコストを回収できる選び方だと強く感じるのです。
メモリは16GBあれば不満はほとんどなく、将来の拡張を見据えるなら32GBを載せてもいいでしょう。
しかし経験上、8GBでは明らかに不足です。
ゲームが突然もっさりしてしまったり、ロードでテンポを損なったりする瞬間が何度もありました。
苛立ち。
だからこそ、私は最低でも16GBを勧めています。
ここをケチると日常的な使い勝手が一気に悪くなります。
ストレージは1TBのNVMe SSDを外したくありません。
遊ぶ気持ちのままに起動したかったのに、ゲームを消す作業を優先させられる。
あの小さなストレスの積み重ねは後悔しか残りませんでした。
1TBあることで心の余裕が生まれるのは間違いないです。
これはパソコンを長く気分よく使う上でとても重要だと私は思います。
電源は650WクラスのGold認証で安心です。
上の世代のGPUでもある程度余裕を持たせられる容量なので、ここを基盤として選ぶと長く持ちます。
そして冷却に関しては私は空冷ファンを信頼しています。
水冷システムも魅力的ですが、メンテナンスやコストの面を考えると面倒になりがちです。
夜、静かな部屋でファンの低い風切り音が響いているとむしろ落ち着きます。
集中して作業をする時間の雰囲気を邪魔せずに支えてくれるのです。
こればかりは実際に過ごした時間が物語っています。
ケースは強化ガラス付きのベーシックなものを選ぶのが無難です。
最初から派手に光る必要はありませんし、自分の好みに合わせて徐々にカスタマイズしていく楽しさもまた醍醐味です。
今振り返ると、育てていくように自分のPCに手を加える感覚が愛着に変わる瞬間があります。
やっぱり道具というより相棒に近い存在なのです。
こうした構成にすれば、コストを抑えつつ快適に動くPCが手に入れられます。
ちょうど良い選択、これに尽きます。
実際にBTOショップで試したとき、ロードの早さには声をあげそうになりました。
映像がスムーズに動くことはもちろんですが、無駄な待ち時間がなくなることがこんなに心を軽くするのかと実感しました。
必要十分とはまさにこのこと。
私はその瞬間、自分が本当に求めてきたのは派手さではなく安心して使える基盤だったのだと確信しました。
ただし、この構成で快適にできるのはフルHD環境です。
WQHDや4Kを最初から見据えるなら必然的にGPUをさらに上位にしなくてはいけません。
それでも私は、はじめてゲーミングPCを買うのならフルHDで十分だと思います。
性能だけを追うのではなく、生活に合った現実的な選択をするほうが結果的に心から楽しめますから。
私は背伸びをやめたことで肩の力を抜いて遊ぶ時間が増えました。
これは実際に過ごして得た実感です。
最終的にまとめるならば、Core Ultra 5かRyzen 5、グラフィックはRTX5060、メモリ16GB、ストレージに1TB SSD。
初めてのゲーミングPCならまず間違いはないと胸を張って言えます。
そして、それを人に勧めるときも自分の経験を添えることで、自信を持って紹介できます。
数字だけの比較では伝わらない安心感や、過去の失敗を踏まえた納得感。
その両方を踏まえた構成こそが本当に人に寄り添った選び方だと思っています。
大切なのは無理がないこと。
そして続けられること。
この積み重ねが、最終的には一番大きな価値へと変わっていくのです。
WQHD+144fpsを狙える、性能と価格のバランス型
WQHDで144fpsを安定して楽しむには、どのパーツをどの程度のレベルで選ぶかが大きな決め手になると、私は強く思っています。
なぜなら、ゲームをただ動かすだけならそれほど難しくはありませんが、映像に迫力と滑らかさの双方を求め始めると、とたんに妥協の余地が少なくなるからです。
結果的に一番大切になるのはやはりグラフィックボードであり、そこに力を入れないとどんなに他を整えても「惜しいな」と感じる場面が必ず出てきます。
私もあれこれ構成を組み替えてきましたが、今ではRTX5060TiやRTX5070クラスが最も満足度と現実性のバランスを取ってくれる答えだと確信しています。
グラフィックボードに全力投資しすぎると財布が悲鳴を上げますが、逆に安く済ませると「こんなはずじゃなかった」という後悔が残る。
不思議なもので、人はゲームをしていると快適さにすぐ慣れてしまうのに、不快さはずっと引きずるものです。
つまり、心地よい映像を長く味わいたいなら、ちょうど良い中庸を選ぶことが非常に大事なのです。
CPUについては、Core Ultra 7 265KやRyzen 7 9700Xあたりを合わせるのが安心です。
かつて私はCPUで妥協して構築したことがありましたが、GPUの性能を引き出せず「ここまでやったのに」と歯がゆい思いをした経験があります。
逆にこのクラスを選んでしまえば、ゲームだけでなく重めの画像処理や仕事上のタスクも難なくこなすことができ、それが精神的な余裕につながるのです。
節約は大切ですが、ここを削って後悔するよりしっかり押さえたほうが結局お得です。
今の私の環境はCore Ultra 7 265KとRTX5070Tiの組み合わせですが、WQHDの最高画質でも120fps前後をしっかり維持しています。
派手なエフェクトや人の多いマルチの場面でもカクつきが少なく、体験が途切れないことに心底満足しているところです。
もちろん、上を目指せばさらに快適さを得ることは可能ですが、投資額との釣り合いを考えると、このあたりが一番現実的で納得できる構成だと思っています。
コストと体験のバランス、この感覚が何より大切ですね。
私は32GBを推しています。
私も以前は16GBで運用していましたが、その時には「なんとなく重いな」という違和感が常にありました。
それが32GBに変えた途端、気分的にも実際の操作感も大きく変わった。
余裕がある安心感に包まれることで、ゲームしかしていない時でもパソコン自体を信用できるようになるんです。
ストレージに関しても、軽視すると後悔します。
最低でも1TBのNVMe SSDをおすすめしますが、私の場合、最初に1TBを選んだら早々にいっぱいになりました。
そこに他のゲームや仕事用データが加われば空き容量が一気に減っていく。
結局、私は2TBに買い替えましたが、そのとき初めて「最初から投資しておくべきだった」と感じました。
容量不足のストレスは小さなひび割れのようにじわじわ効いて、気づいたころには日常を壊します。
冷却について言えば、大口径の空冷ファンでも十分戦えます。
実際、私も静音重視で大きめのファンを使っていますが、夏場のプレイでも特に不安を感じない。
静かで涼しい。
シンプルですが、それが何よりの安心です。
もちろん、熱をとにかく抑えたいなら簡易水冷にする価値もあるでしょう。
しかし人によって考え方が違うので、自分の生活環境に合わせた選び方がベストです。
ケースの選択肢もここ数年でずいぶん変わりました。
ピラーレスの強化ガラスを使ったものや木を取り入れたケースなど、おしゃれな製品が増えています。
しかも性能面で妥協も感じず、なんだか得をした気分になったものです。
インテリア性と実用性を両立できるのは今の時代ならではでしょう。
整理をしておきます。
これらをしっかり揃えることで、安定感と快適さを手にすることができます。
映像が鮮やかに動き、それが途切れない体験。
この充実感を支えるのは、その土台にある構成なのです。
言いすぎかもしれませんが、高額な最上位環境を組む必要はありません。
必要以上の投資をしても、伸び代は思ったより小さい。
一方で、一定ラインを割り込むと一気に質が落ちていく。
その境界がちょうどRTX5060TiやRTX5070、そしてCore Ultra 7 265KやRyzen 7 9700Xあたりです。
これ以上でもこれ以下でもない。
そういう実感があります。
私はこの組み合わせこそが最適解だと感じています。
グラフィックにお金をかけつつ、CPU、メモリ、SSDをバランス良く揃える。
この構成が、今の段階で「心地よさとコストの両立」を果たす中心になると断言できます。
心地よさ。
使いやすさ。
この二つを両立させたい方に、私はこの構成を自信を持っておすすめします。
4Kでも快適に遊びたい人向けのハイエンド構成
以前は「WQHDで十分きれいだ」と思っていたのですが、実際に4K環境を導入して画面を見た瞬間、その考えが一気に吹き飛びました。
木々の揺れや水面のきらめき、街並みに流れる光の陰影。
その一つひとつがまるで別世界の出来事のように私を包み込み、仕事での疲れさえ忘れてしまう感覚がありました。
没入感が段違いなんですよ。
戻れない世界だと感じました。
やはり支えているのはGPUの力です。
ハイエンドクラスのGPUを搭載すると、高品質設定にしても描画が乱れることはなく、フレームレートも安定します。
4K60fpsは当たり前、設定によっては100fpsを超えていくシーンさえ出てくる。
その数値がどうというより、プレイしていてカクつきによるストレスを感じないことこそが嬉しい。
気持ちに余裕が生まれますし、安心感が違います。
私は5070TiやRX 9070XTクラスを試しましたが、正直「ここまで違うのか」と声に出してしまったほどです。
夜空を見上げた時の星の鮮やかさや、風に揺れる草原の描写は心を揺さぶるものがありました。
ああ、ゲームなのにこんなに胸が熱くなる体験ができるのかと驚きました。
その一方で、CPUに関しては少し慎重になりました。
過去に私は高性能なCPUを優先したことがあります。
しかしその時はGPUがやや控えめになってしまい、結果的に全体の仕上がりは期待を下回りました。
正直、悔しかったですね。
パーツの選び方を間違えたと痛感しました。
だからこそ今は、CPUは最新世代の中上位程度を選んでバランスを取るのが一番だと思っています。
GPUに優先投資する。
この方針は揺るぎません。
16GBでもゲームを起動はできますが、数時間プレイしてアップデートを重ねるうちに段々と動作に余裕がなくなります。
私はある時、プレイ中にロードの長さや細かな引っ掛かりにイライラを覚えたことがありました。
その不快感を解消するために32GBを投入したのですが、体感での爽快感がまるで違いました。
ロードが短くなるだけでなく、プレイに集中できる。
余裕は心にもつながりますね。
ストレージも同じです。
ゲームの容量はどんどん大きくなっています。
1TBではあっという間にいっぱいになります。
原神だけでも100GB超え、他の大作を入れると窮屈になります。
そこで私は2TBのGen4 SSDを選びました。
日常使用でそのわずかな速度差を肌で感じることも少ないので、冷静に判断すればGen4が最も現実的です。
私にとっては安定感を優先した選択でした。
電源と冷却は後回しにすると後悔します。
私は850Wゴールド認証を選びました。
少し余裕を持たせるのが安心です。
そして冷却は本当に油断できません。
夏場に一気に温度が上がって、せっかくの高性能パーツが力を発揮できなかった時は、悔しさが募りました。
エアフローを意識してケースを選び、空冷でも十分冷える設計を選んだら、やっと不安から解放されることができました。
熱対策は命綱。
ケースのデザインも気にしました。
光るファンやガラスパネルに惹かれる気持ちはありましたが、私は実用性を重視しました。
シンプルで空気の流れを優先したケースを採用した結果、夏場でも安定して稼働し、ゲームへの集中を妨げられることはありませんでした。
やっぱり落ち着いた選択が一番です。
4Kでのプレイにおける最適解は、私の経験でいえば5070TiやRX 9070XTを核に据え、CPUはCore Ultra 7 265KかRyzen 7 9800X3Dクラス、メモリ32GB、ストレージはGen4の2TB SSD、そして850Wの電源。
この構成に冷却をしっかり組み合わせれば、安心して美しい映像を心ゆくまで楽しめます。
性能と安定の両方を満たすのは、このバランスだと思います。
長年いろいろな構成を組んできましたが、最終的にたどり着いたのはとてもシンプルな答えでした。
この三つを守るだけで、私は4K環境でも安心して没頭できるようになりました。
予算の中で最善のバランスを探し、納得のいく環境を整える。
そうして築いた毎日のゲーム時間は、ただの娯楽ではなく、自分にとっての癒やしと活力源になりました。
後悔しないための原神ゲーミングPC購入時チェックリスト


冷却は空冷と簡易水冷どちらが扱いやすい?
扱いやすさという点を重視すれば、私はやはり空冷に軍配を上げたいと思います。
パソコンの冷却は単なる温度管理にとどまらず、安定動作や安心感に直結するものです。
特にゲームを数時間どころか深夜まで続ける生活をしている私にとって、その差は確実に体感できるほどです。
今まで何度も冷却の不具合で嫌な思いをしたからこそ、私は最終的に空冷を信頼するようになりました。
空冷が持つ魅力は、そのシンプルさに尽きます。
仕組みが単純だから壊れにくいし、交換作業も本当に簡単です。
以前、引っ越しをした時にPCを慎重に梱包して運んだのですが、空冷なら水漏れの心配をせずに済むので安心して作業できました。
小さなことだと笑う人もいるかもしれませんが、毎日使う機械だからこそ、そうした安心がじわじわと効いてくるのです。
とはいえ、水冷が劣っているわけではありません。
その静音性と冷却能力は確かに魅力的です。
大きな負荷をかけた瞬間に空冷のファンが急に回転数を上げて「ブワッ」と音を立てるあの感じ。
そんな経緯で、一度は思い切って簡易水冷を導入したことがあるんです。
たしか半年ほど前にBTOパソコンを購入したときだったと思います。
「おお、これは快適だ」と心の底から思ったのを今でも覚えています。
でも、調子が良いときばかりではないのです。
水冷の弱点を思い知らされたのは、その数か月後でした。
ある日突然、ポンプから小さな異音がし始め、最初は気にしないようにしていたのですが、やがて耳障りなほどの雑音になりました。
私は仕方なく交換パーツを探し、取り付け直しに悪戦苦闘しました。
その作業に時間と気力を奪われ、正直ウンザリしましたね。
空冷であればファンを数分で付け替えれば済んだはずで、その時は心底後悔しました。
「余計な面倒を増やすくらいなら、やっぱり空冷が一番だな」と痛感した瞬間でした。
ここで勘違いしてほしくないのは、水冷だからといって必ずしも上手くいくとは限らないということです。
ラジエーターの位置ひとつ、ケースの設計ひとつで排熱効率は大きく変わります。
ここ数年流行している強化ガラス製のケースは見た目が格好良いのですが、エアフローを犠牲にして結果的に性能を発揮できないことも普通にあります。
その記憶があるからこそ、私は水冷を盲目的に選ばないようにと心掛けています。
一方で、空冷も進化してきました。
最近のCPUは発熱そのものが抑えられているので、昔のように「水冷でなければダメ」という状況は減ってきているのです。
ただし、空冷が全ての人に合うとは言いません。
リビングに置くPCで音を極限まで抑えたい人や、カラフルなライティングを楽しみたい人、インテリアとして見せたい人などには水冷の方がフィットすると思います。
「かっこよさ」や「静けさ」を優先するなら、きっと満足できるでしょう。
しかし、私のようにゲームを長時間楽しみ、余計なトラブルに悩まされたくないと考える人には、空冷の堅実さが絶対に向いているはずです。
正直、気楽なんです。
毎日当たり前のように電源を入れて、ゲームに没頭する。
多少埃が付き始めても、掃除してファンを交換すればまだまだ動いてくれる。
その「信頼できる道具」という感覚は、長く使うほど強くなるのです。
トラブルを恐れず気楽に構えられること、これこそが空冷の最大の魅力だと思います。
もちろん「性能を極めたい」という明確な目標がある人であれば、水冷の方が合うかもしれません。
けれども実際には、ほとんどの人にとって必要十分なのは空冷です。
もし将来もっと高性能を求めたくなったときにだけ、水冷に挑戦すれば良いのです。
最初から構えすぎて高価で手間のかかる方式を選ぶ必要はありません。
私はこれからも空冷を使い続けます。
効率と安心感の両方を得られる手段として、私のスタイルには最も合っているからです。
多少の泥臭さが残っていたって構わない、安心して遊べる環境を維持する方が大事なんです。
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R63R


| 【ZEFT R63R スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P10 FLUX |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R63O


| 【ZEFT R63O スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9070XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R62P


| 【ZEFT R62P スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R55AE


研ぎ澄まされたパフォーマンスが際立つ、アドバンストスタンダードのゲーミングPC
コスパ抜群!64GBのメモリと最新RTXが織り成す驚異のスペックバランス
Pop XLのケースに、RGBの輝きが宿る。大迫力のデザインながら、洗練されたサイズ感
新時代を切り拓くRyzen 5 7600、スムーズなマルチタスクをコミット
| 【ZEFT R55AE スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 7600 6コア/12スレッド 5.10GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal Design Pop XL Air RGB TG |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASUS製 TUF GAMING B650-PLUS WIFI |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
PCケースは見た目重視か風通し重視か悩んだときの考え方
ゲーミングPCを選ぶとき、一番最後まで私が迷うのはやはりケースです。
見た目にこだわりたい気持ちは大いにありますが、実際に組んで遊んでみると、最終的には冷却性能こそが快適さを左右するのだと何度も思い知らされました。
だから私は今では「まず冷却を優先すること」。
その上で自分好みのデザインを選ぶのが一番正しいと考えています。
昔の自分を振り返ると、正直少し恥ずかしいです。
当時、フルガラスパネルのケースに惹かれ、リビングに置いたときの映える姿にうっとりしました。
自己満足の極みです。
けれども、真夏の夜にゲームをするとGPUが熱を帯び続け、ファンが全力で回転し、部屋全体が機械音に支配される感覚に冷や汗が止まらなかったのを覚えています。
嫌な圧迫感。
あの体験以来、私はデザインよりもまず風通しを意識せざるを得なくなりました。
いくら見た目が良くても、中で熱がこもってパーツが苦しんでいるようでは冷静に楽しめないものです。
ただ、最近は事情が変わってきています。
以前のように「冷却か、デザインか」の二択を迫られる状況は減りました。
例えば透明パネルを採用しつつ、きちんと冷却経路を考慮した製品がずいぶん増えました。
美しく光るRGBライティングを楽しみながらも、高負荷時に温度が上がりすぎないよう工夫されているのを見つけたときには「ようやく時代が追いついてきたな」と思わず声が出たくらいです。
性能とデザインが共存する。
これはPCを長く趣味にしている身として、とてもありがたい変化だと実感しています。
もちろん、冷却性能を確かめるときにメーカーの宣伝をうのみにするのは危ういです。
大切なのは、吸気と排気の素直な流れと、ファンをどこに何基搭載できるかという構造の部分です。
前面から入った空気が背面や天井にすっと抜けていく。
その単純な流れが確保されているかどうかで、ケースの本当の実力は見えてきます。
逆に凝った外装のせいで空気が渋滞したら本末転倒です。
特に高フレームレートで遊ぶタイトルを狙うなら、冷却設計のシンプルさが快適さに直結します。
さらに近年はCPUやGPUだけではなく、ストレージの温度も無視できなくなってきました。
私自身、最新のPCIe Gen.5 SSDを導入したとき、意外な弱点に直面しました。
専用のヒートシンクを付けてもエアフローが悪いと簡単に70度を超えてしまうのです。
その瞬間の焦りは大きい。
高価なパーツですから冷や冷やしました。
ケースを新しいものに入れ替え、温度がすっと安定したときに「やっぱり要はこれか」と心底納得しました。
だからストレージのためにもケースは重要。
軽視できません。
それでも、どうしても惹かれてしまうのは見た目です。
展示会で初めてピラーレスのケースを見かけたとき、人目を忘れて立ち止まっていました。
毎日長時間そばに置いて使うものだから、やはり気に入った見た目であってほしい。
けれど、見た目だけで決めてしまう危うさも何度か経験しました。
結局は、「冷却の安心感があってこそ気分良く美しさを楽しめる」というのが、私の本音です。
その経験を繰り返した私は、ケース選びで迷ったときには、まず風通しを軸にして判断するようになりました。
どんなに美しい外観でも、パーツが実力を発揮できなければ意味がない。
これは自己投資の意味を失うことでもあります。
安定した性能を確保できて初めて、それが住空間を彩るインテリアとしての存在感にもつながる。
逆に「お気に入りの見た目なのに、なんだか温度が不安」と感じるなら、それこそ買い替えを検討するサインなのでしょう。
私が到達した答えは、妥協しないことです。
見て誇れる美しさ、そして安心できる冷却。
どちらか片方を失えば、どちらも魅力を失う。
だから私は両方を天秤にかけ、納得のいく選択ができたときにようやく購入するようにしています。
その考えに至ったのは、数々の失敗と学びの結果でした。
この二つを確保できるかどうかが、日々のゲーム体験を豊かにしてくれます。
確かにデザインに心が揺さぶられることはあるでしょう。
けれど、そこで妥協して後悔する気持ちはもう味わいたくないのです。
BTO購入で必ず確認したい保証とサポート内容
高性能なスペックばかりに目を奪われがちですが、そこにばかり意識を向けていると、いざというときに後悔する羽目になるのです。
私はこの点を軽視して失敗した人を何人も見てきましたし、自分自身も似た経験をしたことがあるので、強い実感を持って伝えています。
性能よりも大事なものがあるんですよ。
例えば、どれだけ高性能で最新のグラフィックカードを積んでいるパソコンを買ったとしても、万が一のトラブルに備える保証が不十分なら、まるで家に鍵をかけないで外出しているような不安が常につきまといます。
事実、私の職場の同僚が購入したBTOマシンは、買って数か月で電源ユニットが故障しました。
保証は最低限しかなく、修理受付から戻ってくるまでに数週間かかってしまったのです。
その間、せっかくの趣味の時間がすべて失われた。
仕事後のリフレッシュが消えたあの顔を見たとき、私は痛感しました。
保証の厚みが心の余裕に直結するのだ、と。
悔やんでも悔やみきれない出来事だったでしょうね。
保証は単なる飾りでもお守りでもなく、実際のリスクを現実的に減らす仕組みです。
私は最低でも3年の基本保証をつけたいと思っていますし、延長保証を選べるなら必ず付けるべきだと考えています。
一見すると余計な出費に思えるかもしれませんが、それで守られるのは「お金」ではなく「時間」です。
だからこそ、もしトラブルでパソコンが使えない日々が続くと、金額に換算できない大きな損失になると強く感じています。
正直、時間のほうがはるかに貴重なんです。
もう一つ見落とされやすいのが、修理対応のスピードです。
「保証がついているからひと安心」と思い込むのは危険です。
現実には、修理完了まで3週間以上かかるメーカーも存在する一方で、2日以内に修理して返送してくれるメーカーもあります。
小さいようですが、この差は日常に大きな影響を与えます。
楽しみにしていた大型アップデート直後の週末にトラブルでも起きてみてください。
パソコンが戻ってくるのに3週間もかかると知った瞬間の絶望感、もうため息しか出ません。
期待していた休日が一瞬で台無しになるわけですから。
私自身、かつて深夜にトラブルに遭遇したことがありました。
電源が突然落ちて復旧しなくなり、頭を抱えたときに救ってくれたのが24時間対応のチャットサポートです。
午前1時に送った問い合わせにすぐ反応してくれ、的確なアドバイスで解決まで導いてくれた。
そのとき私は心の底から思いました。
「このメーカーなら、次も安心して買える」と。
スペックではなくサポート体制こそが本当の選定基準になるのだと実感させられました。
さらなる落とし穴としては交換パーツの在庫状況があります。
自社に部品を常備せず外注頼みのメーカーは、修理期間が長引く傾向にあります。
私も以前経験しましたが、パーツが手に入るまで2週間以上待たされ、心底うんざりしました。
パソコンを目の前にしながら電源を入れられない日々は、本当に時間を奪われている感覚に近い。
だから部品在庫まで確認しているメーカーかどうかも、選ぶべき目安だと痛烈に思いました。
安定動作こそ正義。
毎日ログインするのが前提のオンラインゲームを例に挙げれば、一日触れないだけでも痛手になります。
金額に換算できない損失。
それを避けるために私は保証を「余計な経費」なんて考えません。
「自分への将来の投資」だと心から思っています。
最近のBTOメーカーでは驚くほど手厚い仕組みが整ってきました。
30日以内無償交換や、往復送料負担なしの保証、そして有料保守に入れば修理だけでなくパーツをアップグレードしてもらえるサービスまで出てきています。
これには正直、感心しました。
もはやサポート競争の時代に突入している。
その流れはユーザーにとって大きなメリットです。
もちろん、価格が最優先という人を否定するつもりはありません。
けれども、長期的に見れば保証とサポートがあることの意味が理解できるはずです。
私はかつて保証を軽んじて選び、結局大規模修理の費用を全額負担せざるを得なかった経験があります。
「保証は単なる保険料ではなく、未来の自分を守る盾なんだ」と、強く思った瞬間です。
だから行動すべき選択肢は明快です。
BTOパソコンを買うときは必ず延長保証を選び、迅速で信頼できるサポートを提供するメーカーを選ぶこと。
それだけで後の後悔を大幅に防げます。
スペック表の数字に目を奪われるだけでなく、裏側にある保証制度をしっかり確認する。
それが、私の結論です。
原神ゲーミングPCに関するよくある質問と答え


Q 低スペックPCでも原神はある程度遊べる?
しかし、その「動く」と「快適に楽しめる」とはまるで別物なんです。
画面の美しさと操作の滑らかさ、この二つを同時に満たそうとすると、どうしても低スペック環境では壁にぶつかる。
けれど、それではこのゲームの醍醐味である美しい世界観や繊細な演出を半分も味わえない、そう感じるはずです。
私も過去に安価なミニPCで試したことがあります。
最初は「まぁ、これでも遊べるか」と自分に言い聞かせたものですが、街並みの中で人や建物が増える場面になるとすぐにカクカクし出し、戦闘中には思うようにキャラを動かせず何度も苛立ちました。
あれは本当に辛かった。
あのストレスを思い出すと「安定性こそゲームの核心だ」と改めて実感します。
しかし日常的に遊ぶのなら、楽しさより疲れが先に来る。
だから私の答えは一つです。
長く楽しみたいなら、ゲーミングPCを用意すべきだと。
厄介なのは、低スペックでも最初のうちは「案外動くじゃないか」と勘違いしてしまうことです。
ただ原神はアップデートのたびに世界が広がり、オブジェクトやグラフィックがどんどん豪華になります。
その結果、じわじわとPCへの負荷は高まり、必ず動作が窮屈になっていきます。
結局のところ最初から余裕あるPCを選んでおくことが、一番冷静な判断になるんですよね。
先日、Core Ultra 5とRTX 5060を組み合わせたBTOマシンを使う機会がありました。
フルHD最高画質でもしっかり60fpsを維持してくれて、演出の派手な戦闘シーンでも一切のフレーム落ちなし。
「ああ、これだよ」と声に出してしまうほどでした。
多少値段は張っても最新のGPUに投資する意味を、身体で理解した瞬間でした。
一方、最初から「安いPCで始めて、不満が出たら考えればいい」という考えの人もいます。
それも一つのやり方でしょう。
ですが、後で必ず後悔しますよ。
なぜなら低基準に慣れてしまうと、本来のクオリティを知らないまま終わってしまうからです。
映画のブルーレイをスマホ動画並みの画質で見て「これで十分」と思い込むようなもの。
そう考えたとき、心底もったいないと感じるわけです。
私も過去に、低価格PCで半年ほどプレイしていた時期がありました。
ロードの遅さにため息をつき、冒険のテンポがいちいち削がれる。
暑い夏には冷却不足でPCケースが熱を持ち、触れると驚くほど熱かった。
「これ、全然快適じゃないな」と独り言を漏らしたあの瞬間を、今でも覚えています。
少し話は変わりますが、この数年でPCハードの進歩は明らかです。
Core UltraやRyzenの上位モデルは、静音性と性能の両立を当たり前のように実現しています。
空冷のシンプルな仕組みでも快適に使えるし、ケースもエアフローを重視した設計が普及している。
昔のように「熱がこもって苦しい」という環境からはもう解放されているのです。
だからこそ私は、いまだに低スペックで我慢する理由が見当たらなくなったとつくづく思います。
快適さが、すべて。
どんなによくできたゲームも、フレームレートが不安定だととたんに疲れる。
心地よさや没入感がどこかへ逃げてしまう。
遊びがストレスになるのは本末転倒でしょう。
だから私ははっきり言います。
本気で遊ぶなら妥協するな、と。
もちろん現実的には予算もありますし、無理に最上級の構成を選ぶ必要はありません。
ただし、進化を続ける原神にふさわしい環境を整えたいなら、CPUやGPUはできるだけ最新世代を、メモリは16GB以上、ストレージは1TBクラスのSSDを選んで損はありません。
私は遠回りしてこの答えにたどり着きましたが、最初からそうしておけばよかったと今でも思うんです。
結局のところ、「低スペックでも遊べるか」という問い自体がズレているのだと思います。
大切なのは、原神の世界を存分に楽しみ抜ける環境を整えること。
そうやって初めて、このゲームが本来持っている美しさと心地よさに、きちんと出会えるのだと私は信じています。
Q SSDは1TBあれば十分?それとも2TB積んだほうが安心?
SSDの容量について迷っているなら、私の答えははっきりしています。
1TBでも数本程度のゲームなら十分動きますし、例えば『原神』のようなタイトルなら当面問題なく使えると思います。
しかし実際にはゲームの容量は毎年のように大きくなっており、気づけば200GBを超える作品も珍しくない状況です。
そうなると1TBはあっという間に埋まっていくのです。
私自身、痛い経験をしました。
数年前、BTOパソコンを買ったときに「まあ1TBあれば余裕でしょ」と軽く考えていたのです。
しかし、ゲームを3本インストールし、さらに録画データや業務資料を入れた途端に、残り容量が200GBを切ってしまった。
容量不足のたびに古いデータを削除したり、外付けドライブにコピーしたりと、余計な作業が発生します。
本来は遊びや仕事に集中したいのに、煩雑な管理に時間を取られる。
正直なところ、これは本当にバカらしかったです。
余裕こそが大事。
これは仕事でも遊びでも共通の真理だと私は思います。
ゲームは本来、気分転換や没頭のためにするものなのに、いちいち空き容量を気にしながら楽しむのはストレスでしかありません。
気持ちよさ。
価格の面でも、今はとても手が届きやすくなっています。
数年前までは高嶺の花だったNVMe SSDも、今ではGen.4のモデルなら7000MB/s近いスピードを備えながらリーズナブルに買えるようになってきました。
確かに最新のGen.5も出てはいますが、発熱や価格の観点では正直まだ現実的ではない。
私が勧めたいのは「2TBのGen.4 SSD」です。
値段のバランス、性能の安定性、そして長く安心して使える安心感。
この3つを満たしてくれるのです。
もちろん、プレイするゲームが少なくて「常時2、3本で十分」という人なら、1TBでも問題ないでしょう。
その場合は追加で外付けSSDを使うのも選択肢の一つです。
最近はUSB4対応で転送速度も十分に速く、取り回しも便利になっています。
ただし、私はそれでもおすすめはしません。
理由は簡単で、毎回容量のやりくりに神経を割くのが嫌だからです。
ほんの数分の節約だと思うかもしれませんが、その積み重ねが心の余裕につながるのです。
Steamのライブラリ管理をしていると、このことはさらに実感します。
昔はゲーム一本のインストールに数十GBが当たり前でしたが、今ではインディーズ作品でも50GB近く要求してくることがあります。
気になるタイトルを試したい、セールのときにまとめ買いしたい、そんな気持ちを抑えてしまうのは本当にもったいない。
1TBではすぐに限界が見えてきます。
遊びたいタイトルを自由に積み上げる喜びを味わうなら、最初から2TBを選ぶのが一番です。
ここで強調したいのは、容量の余裕は単に贅沢ではなく「必要経費」であるという点です。
増設は決してスマートではなく、コストも手間も発生します。
その結果、「最初から余裕を選んでおけばよかった」と後悔することになるのです。
後悔は無駄。
振り返ってみると、これはビジネスの道具選びとも同じだと気づきました。
その繰り返しは効率を悪くするだけで、精神的にも疲弊します。
だから今の私ならはっきりと伝えたい。
「最初から余裕を見込んで選んでおけ」と。
SSDにおける2TBの選択は、その教訓を体現するものです。
最終的に私が間違いなく選ぶのは「2TBのGen.4 SSD」です。
パフォーマンスも容量も十分で、余裕を持って中長期的に使える。
結果として「快適にゲームを楽しめる環境」が手に入る。
仕様表だけではわからない価値がそこにあるのです。
そして最後に伝えたいのは、数字や性能指標だけでは語れない安心感の重要性です。
仕事を終えた夜に遊びたい時、容量不足でまずアンインストール作業を始めるのか、それともすぐに起動して遊べるのか。
この差はとても大きいのです。
だから私は胸を張って言います。
ゲーミングPCを選ぶなら2TBを選びなさい、と。
容量の余裕。
心の余裕。
どちらも持ちあわせてこそ、ゲームは心から楽しめるのです。
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R64N


| 【ZEFT R64N スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal North ホワイト |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60FS


| 【ZEFT R60FS スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9060XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z59M


| 【ZEFT Z59M スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285K 24コア/24スレッド 5.70GHz(ブースト)/3.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Corsair FRAME 4000D RS ARGB Black |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47CC


最新のパワーでプロレベルの体験を実現する、エフォートレスクラスのゲーミングマシン
高速DDR5メモリ搭載で、均整の取れたパフォーマンスを実現するPC
コンパクトでクリーンな外観のキューブケース、スタイリッシュなホワイトデザインのマシン
クリエイティブワークからゲームまで、Core i9の圧倒的スピードを体感
| 【ZEFT Z47CC スペック】 | |
| CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 ROG Strix B760-I GAMING WIFI |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
Q 拡張性を考えるならRTXとRadeonどちらを選ぶべき?
拡張性を考えると、私はRTXを選んだほうが安心できると思っています。
正直に言うと、性能や価格だけで判断できるものではなく、数年後の自分がどんなふうにPCを使いたいかを見据える必要があると強く感じているのです。
RTXは配信や録画といった用途を同時にこなす場面でも安定して動き、余裕を失わずに対応できる印象があり、やはり頼もしさを覚えます。
結果的に、拡張性を重視するならRTXという結論に落ち着くのが自然でした。
RTXシリーズに惹かれるのは、何よりもソフトや周辺技術との相性の良さに安心できるからです。
私は普段から仕事も遊びもPCで済ませることが多く、急に新しい技術を試してみたくなるときがあります。
そんな時に、RTXならすでに環境が整っていることが多いのです。
例えばDLSSやReflexといった機能は、単に描画をきれいにするとか反応を早めるといった利点にとどまらず、「新しい体験を自分に許してくれる余白」があると感じます。
だからこそ、毎日の使用感がなんとなく楽しくなるんだろうなと自分では思っています。
価格を重視するなら強い選択肢になるし、とくに最近の世代ではFSRという技術のおかげで、高解像度設定でも滑らかさを維持できています。
その差額が決して小さくないのも事実で、少ない予算で満足感を得たい場合には十分に魅力的です。
私は数年前までRadeon派で、原神を1440p環境でしっかり楽しめていたので、ゲーミング用途に絞れば十分だという実感があります。
仕事終わりにさっと遊んで心の切り替えをする瞬間に「Radeonで問題ないな」と思えたのはリアルな経験です。
ただ、将来を見越したときに考えが変わっていくのです。
RTXのほうがドライバー更新や対応アプリの多さの面で先行している傾向が強く、その安心感は自分には非常に大きな支えになります。
私がRTXに強く気持ちを寄せるきっかけになったのは、去年PCを組み替えたときの出来事でした。
それまでRadeonを使っていたのですが、配信中に音ズレやカクつきが頻発して、解決策を探すのに散々頭を抱えたのです。
ところがRTX 5070に切り替えてみたら、嘘のようにすべて消えました。
その瞬間、「こんなに違うのか」と思わず声に出てしまったぐらいです。
心が楽になる瞬間というのは本当にあるんだなと実感しました。
過去に振り回された不安から解放された体験が、自分の中でRTXへの信頼の土台をつくったのだと思います。
もちろん、割り切ればRadeonも魅力的です。
ゲーム専用としてコストを抑えても性能は十分にあるし、FSR4が生む滑らかな画面は驚かされる場面が多いです。
さらにPCIeの新しい規格に対応しているという点も高く評価できます。
だから、用途をはっきり区切れる人にとっては「Radeonで十分」と言い切れる場面も確かにあるでしょう。
ただ私の場合、仕事も趣味もPCに頼る生活である以上、数年単位での変化を見込んでおいたほうが安心だと考えます。
新しいデバイスの導入、ソフトの進化、あるいは趣味が少しずつ広がっていくことなど、未来が完全に固定されているわけではありません。
細かい変化の積み重ねで生まれる新しいスタイルに寄り添える環境こそが拡張性の価値だと思っています。
その柔軟性を感じられるのがRTXというわけで、だから私はRTXを選びました。
未来を見据えた選択。
一方で短いスパンだけを考えるなら、Radeonの高いコストパフォーマンスは強みとして輝きます。
すぐに最新技術をフル活用したいわけではなく、欲しいのは「今を十分楽しめるスペック」だけだというなら、むしろそちらのほうが選びやすい。
実際多くのゲーマーがそういう理由でRadeonを選択していると聞きますし、その価値は確かです。
ただ私は、後悔のない数年先を見据えたいと思うのです。
そのときの環境や価値観によってベストは違ってくるものです。
ただ、私はこれからも変化する環境を「育てていく」感覚を大事にしたいと思っています。
だから同じように未来を見越した安心感を求める方にはRTXを心からおすすめしたいのです。
安心と拡張、この二つを同時に抱えておける状態が、きっとPCライフを長く楽しくしてくれる。
それが私の実感であり、結論です。
信頼性。
Q メモリは16GBで済む?32GBにしておいた方がいい?
私の考えでは、原神を快適に遊ぶだけなら16GBでも問題なく動きます。
ただしその上で、少しでも余裕を持ちたいなら最初から32GBを選んだ方が気持ちよく遊べる。
なぜなら、余計な心配を抱えたまま遊ぶのは正直つまらないからです。
経験上、その差は「動くかどうか」以上に精神的な安心感につながり、長く遊び続けるうえで意外と大きなポイントになるのです。
私は数年前、BTOで組んだマシンにコストを優先して16GBを選んだことがあります。
その時は「まあ十分だろう」と軽く考えていたのですが、実際に遊んでみると後悔の連続でした。
原神そのものは何とか遊べるのに、配信ソフトやチャットツールを並行して使い始めると一気にメモリが苦しそうな顔を見せる。
使用率が90%超えなんてザラで、気がつけばロードが長くなったり、描画が妙に遅れてカクカクし出すんです。
イライラしましたよ、本当に。
「動くけど不安定」。
この状態は想像以上に神経を削ります。
遊んでいる最中なのに頭の端では常にメモリの残量が気になってしまう。
楽しみたいのに集中できないんです。
仕事を終えてようやくリラックスできる時間くらい、余計な心配などせず没頭したい。
それが正直な気持ちでした。
そんな状況に我慢できず思い切って32GBに増設した瞬間、世界が変わりました。
OBSを立ち上げながらブラウザを開いても、余裕がある。
ロードも描画もスムーズで、まるで別のPCに乗り換えたような感覚です。
切り替えのストレスから解放されたことで、遊ぶ楽しさが圧倒的に増しました。
こんなに違うなら、最初から投資しておけば良かったと心底思いましたね。
もちろん16GBでも動くこと自体は確かです。
ただし原神は頻繁に大型アップデートが入り、そのたびに必要なメモリ量がじわじわ増えていきます。
グラフィックは美しい方向へ磨かれ、背景や演出は一段と豪華になる。
それは歓迎すべき進化ですが、裏を返せばシステムへの負担も同時に膨らんでいくことを意味します。
数年先を見据えるなら、いずれ16GBでは足りなくなる未来は避けられないのではないかと感じています。
近ごろはブラウザやチャットアプリを開きっぱなしにしながら遊ぶのが当たり前の環境になっています。
リモートワークが増えた影響もあり、SlackやTeamsを閉じ忘れていることなんて頻繁にある。
いや、閉じるのが面倒なだけなのかもしれませんが、そんな日常においては16GBはどうしても綱渡りのような心許なさがあります。
加えて、DDR5メモリの価格が以前に比べてずいぶん落ち着いたことも大きいです。
昔は32GBを選ぶと一気に金額が跳ね上がり、正直「手が出ない」と感じるほどだった。
それが今ではBTOモデルで32GB標準構成も珍しくないのです。
コスト面で16GBを選ばざるを得なかった時代は、すでに過ぎ去ったと言っていいでしょう。
後から増やすより最初から32GBを選ぶ方が、結局は合理的です。
後付けで増設しようとすると、同じメーカーで同じ規格のものを探さなければならず、うまくいかなければ全部差し替えになることもある。
自分でケースを開けることが好きな人ならまだしも、面倒だと感じるなら最初から揃えておいた方が確実に楽なんですよ。
私が特に伝えたいのは、「環境に余裕があると気持ちまで軽くなる」という体験です。
メモリ容量が安定していると、ちょっとブラウザを開いたくらいならまったく気にならないし、「まあ大丈夫」と思える。
それが積み重なって、毎日の満足感に直結します。
精神的に余裕があるかないかで、同じ体験も大きく変わるんですよ。
40代に入った私は、自分の自由時間をどう過ごすかに敏感になってきました。
限られた時間だからこそ、余計な我慢を強いられる余地はないと痛感しています。
集中できる環境に身を置くことは、とても大きな贅沢だと感じるようになったのです。
そのために必要な選択が32GBのメモリだった。
ただ、それだけです。
繰り返しますが、16GBでも動きはします。
しかし「安定した快適さ」を求めるのであれば、32GBを最初から選ぶのが一番です。
アップデートによる負荷増を考えても、早めの投資は後悔を生まない選択だと私は断言します。
遠回りした経験があるからこそ、人には最初からその道を勧めたい。
だから改めて言います。
選ぶべきは32GBです。
安心できる環境。
原神を心から楽しむために大事なのは、華やかなグラフィックや最新CPUだけではありません。
最終的にゲーム体験を支えるのは、余裕あるメモリなのです。
その余裕があることでストレスのない切り替えができ、配信や録画を同時にしていても気持ちよく遊べる。
結果として「ああ、まだ遊べるな」と感じられる。
まさにそれが長い目で見たときの価値になるのです。
だから私は声を大にして言いたいんです。
どうせ長く遊ぶなら、最初から余裕のある32GBを選んでください。
Q ストレージ強化を考えるならBTOと自作PC、どちらが得?
ストレージを強化するときに私が勧めたい選択肢は、正直なところBTOパソコンです。
もちろん自分でパーツを選んで組み立てる楽しさはよくわかりますし、それを否定する気はありません。
昔はBTOの自由度なんてそれほど高くありませんでしたが、今はメーカーごとに特徴もあり、SSDも定番ブランドを選べるなど柔軟さがあります。
容量の自由度も高く、後々の拡張を考えると満足度は高いんですよね。
私にとってBTOが頼もしいのは、やはり仕事用にもゲーム用にも「動作の安定」が最優先だからです。
趣味で組むPCならその時間も充実感に変わりますが、平日の昼間はそうはいきません。
たった数分でも業務が止まると冷や汗ものです。
BTOパソコンは冷却設計や電源容量まで全体として調整されているため、使う側がいちいち神経をすり減らす必要がありません。
実際、私は以前サブで使っていた自作マシンにNVMe SSDを追加したことがあったのですが、放熱を軽く見てしまった結果、いつの間にか温度が上がって読み込みが不安定になりました。
そのとき本気で思ったんです。
「冷却済みのBTOにしておけば、こんな心配はなかったのに」と。
小さな違いのように見えても、毎日の安心につながる差は大きいですね。
もっとも、自作の魅力を私が忘れているわけではありません。
セカンドマシンを自分で組みましたが、その工程はやはり楽しいものです。
ケースを選んだり、SSDのメーカーをこだわったりする時間は格別です。
特に、先日導入したCrucialの2TB Gen.4 SSDは取り付けてすぐに動作の速さを実感しました。
思わず「いや、速いなこれは」と声が漏れたほどでした。
値段も少し前に比べると手の届きやすさが増していますから、好きな人には大きな喜びになります。
ただ、ストレージ強化目的だけを考えるとやはりBTOが合理的です。
最新のGen.5 SSDは理論上では驚くべき速度を持っていますが、正直そこまでの違いを体感する場面はほとんどありません。
本当に重要なのは容量と信頼性です。
容量不足で毎回データ整理に追われるのは無駄なストレスですし、大切なときにデータが安全に守られるほうがよほど安心です。
BTOで必要な容量を初めから載せてしまえば、余計な不安を抱かずに済むんです。
保証面の安心も大切です。
自作のときは、パーツの調子が悪ければ「さて、どの部品のせいだろう」と考えるところから始まり、メーカーやショップへの問い合わせもばらばらになるため、とにかく時間を食います。
BTOならショップ保証とメーカー保証がセットになっていることが多く、対応もまとまっているので実にスムーズ。
「悩む時間を減らすために払うお金」と考えれば納得できます。
経験してみれば、このありがたみはすぐにわかりますよ。
一方で、やっぱり自作の特権も気になってしまいます。
特にデザイン面ですね。
最近はフロントガラスがすっきりしたケースや、木目調で部屋に溶け込むようなものも増えました。
そうしたものを自分の手で仕上げると、ものすごく達成感があります。
BTOではどうしてもそこまでの自由度は難しいので、ここだけは自作が勝ると感じます。
正直なところ私も、次のメインマシンが欲しくなったらまた自作してしまいそうだと思うくらいです。
所有欲というのは理屈ではなく心を動かしますね。
整理するとこうです。
あれこれ悩む時間をカットでき、安定して長く安心して使えるからです。
逆に「自分の理想の一台」を作りたい人、工程そのものを趣味として楽しめる人なら自作を選ぶ価値があります。
例えば「原神」のように容量負担の大きなゲームを中心に遊ぶなら、BTOで最初から2TBを選んでおくのが賢明です。
結果的に余裕のある快適な環境で日常を支えてくれるからです。
私が最終的に大切にしているのは、自分がどこに価値を置くかという一点です。
効率と安心を優先したいならBTO。
自由と所有欲を楽しみたいなら自作。
結局のところその選び方に正解はなく、自分のスタンスに素直でいることが一番なんだろうと思います。
私にとっては、仕事の道具でもあり遊びの相棒でもあるPCだからこそ、安定と保証を優先しています。
気楽さ。
安心感。
働き盛りの世代だからこそ、私はBTOを強く推すのです。
少なくとも今の私にとって、それが間違いなく最適解だと胸を張って言えます。
人気PCゲームタイトル一覧
| ゲームタイトル | 発売日 | 推奨スペック | 公式 URL |
Steam URL |
|---|---|---|---|---|
| Street Fighter 6 / ストリートファイター6 | 2023/06/02 | プロセッサー: Core i7 8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: RTX2070 / Radeon RX 5700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter Wilds
/ モンスターハンターワイルズ |
2025/02/28 | プロセッサー:Core i5-11600K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce RTX 2070/ RTX 4060 / Radeon RX 6700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Apex Legends
/ エーペックスレジェンズ |
2020/11/05 | プロセッサー: Ryzen 5 / Core i5
グラフィック: Radeon R9 290/ GeForce GTX 970 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| ロマンシング サガ2
リベンジオブザセブン |
2024/10/25 | プロセッサー: Core i5-6400 / Ryzen 5 1400
グラフィック:GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| 黒神話:悟空 | 2024/08/20 | プロセッサー: Core i7-9700 / Ryzen 5 5500
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700 XT / Arc A750 |
公式 | steam |
| メタファー:リファンタジオ | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i5-7600 / Ryzen 5 2600
グラフィック:GeForce GTX 970 / Radeon RX 480 / Arc A380 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Call of Duty: Black Ops 6 | 2024/10/25 | プロセッサー:Core i7-6700K / Ryzen 5 1600X
グラフィック: GeForce RTX 3060 / GTX 1080Ti / Radeon RX 6600XT メモリー: 12 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンボール Sparking! ZERO | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i7-9700K / Ryzen 5 3600
グラフィック:GeForce RTX 2060 / Radeon RX Vega 64 メモリ: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE | 2024/06/21 | プロセッサー: Core i7-8700K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce GTX 1070 / RADEON RX VEGA 56 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ファイナルファンタジーXIV
黄金のレガシー |
2024/07/02 | プロセッサー: Core i7-9700
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Cities: Skylines II | 2023/10/25 | プロセッサー:Core i5-12600K / Ryzen 7 5800X
グラフィック: GeForce RTX 3080 | RadeonRX 6800 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンズドグマ 2 | 2024/03/21 | プロセッサー: Core i7-10700 / Ryzen 5 3600X
グラフィック GeForce RTX 2080 / Radeon RX 6700 メモリー: 16 GB |
公式 | steam |
| サイバーパンク2077:仮初めの自由 | 2023/09/26 | プロセッサー: Core i7-12700 / Ryzen 7 7800X3D
グラフィック: GeForce RTX 2060 SUPER / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ホグワーツ・レガシー | 2023/02/11 | プロセッサー: Core i7-8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: GeForce 1080 Ti / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| TEKKEN 8 / 鉄拳8 | 2024/01/26 | プロセッサー: Core i7-7700K / Ryzen 5 2600
グラフィック: GeForce RTX 2070/ Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Palworld / パルワールド | 2024/01/19 | プロセッサー: Core i9-9900K
グラフィック: GeForce RTX 2070 メモリー: 32 GB RAM |
公式 | steam |
| オーバーウォッチ 2 | 2023/08/11 | プロセッサー:Core i7 / Ryzen 5
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 6400 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter RISE: Sunbreak
/ モンスターハンターライズ:サンブレイク |
2022/01/13 | プロセッサー:Core i5-4460 / AMD FX-8300
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| BIOHAZARD RE:4 | 2023/03/24 | プロセッサー: Ryzen 5 3600 / Core i7 8700
グラフィック: Radeon RX 5700 / GeForce GTX 1070 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| デッドバイデイライト | 2016/06/15 | プロセッサー: Core i3 / AMD FX-8300
グラフィック: 4GB VRAM以上 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Forza Horizon 5 | 2021/11/09 | プロセッサー: Core i5-8400 / Ryzen 5 1500X
グラフィック: GTX 1070 / Radeon RX 590 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |