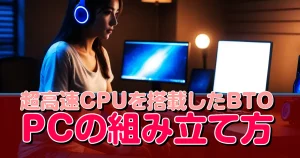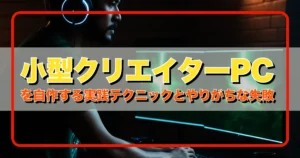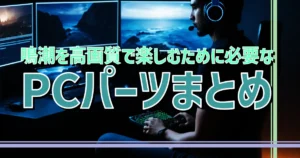鳴潮を快適に遊ぶために意識しておきたいゲーミングPCの性能目安

CPUは最新CoreかRyzenか―自分に合った選び方
CPUの選び方ひとつで、ゲーム体験の心地よさは驚くほど変わるものだと私は思います。
何となく「映像を処理するのはGPUだから、そこさえ強ければ安心だろう」と考えがちですが、実際にはCPUが全体のバランスを引っ張っています。
せっかく高性能GPUを載せても、CPUが力不足だとその性能を引き出せない。
だからこそ、私は真っ先にCPUにしっかり投資するべきだと感じています。
今の主流となるのは、IntelのCore UltraシリーズとAMDのRyzen 9000シリーズ。
この二つを比較してみると、スペック表だけでは読み取れない癖の違いがはっきりしています。
Intelはタスク切り替えやレスポンスが軽快で、複数のアプリを同時に立ち上げても不思議なほどテンポが落ちません。
一方でRyzenは負荷が高くかかる状況でもじっくり粘って処理を続けるような頼もしさがある。
まるで性格の違う二人の優秀な社員を見比べている感覚です。
結局は、自分が「仕事も遊びも同時進行派」なのか、「目の前のゲームに腰を据えて集中派」なのかによって選び方が分かれてくる。
シンプルですが、そこが最大の判断軸だと思います。
私はCore Ultra 7 265KとRyzen 7 9800X3Dを実際に使い比べてみました。
前者は市街地のように細かいオブジェクトが大量に表示され、NPCが多数動くシーンでも切り替えの反応が俊敏で快適でした。
逆に後者は広いフィールドで長時間探索を続けるときや高解像度での戦闘になると強みを発揮し、処理が安定していて「まだまだ余力があるな」と思わせる安心感がありました。
プレイするジャンルや遊び方によって、どちらがより合うかがくっきり見えてきましたね。
CPUを選ぶ際に最も伝えたいのは「後から簡単には変えられない」という点です。
しかしCPUはマザーボードやメモリの規格に直結しているため、換装するとなると一式の大幅な再構築につながってしまう。
だからこそ、最初にしっかり余力を持ったものを選ぶことが賢明です。
今後はゲームエンジンがAI処理を組み込んでいくことも想定されますから、最新世代のCPUであればそうした未来にも適応していける。
その長期間の安心感に投資する意味は大きいと私は感じます。
昔の私は「動けば十分」と思っていました。
しかしある日、配信や録画を同時に試みた瞬間に状況は一変しました。
CPU負荷が跳ね上がり、ゲームはカクつく。
没入どころではなくなったんです。
その時、職場の会議で古いPCを使って資料を映そうとしたら画面共有が頻繁に止まって議論の流れが乱れた光景と重なりました。
CPUは司会進行役。
力が弱いと全体を止めてしまうんだと強烈に実感しました。
特に私が魅力を感じたのはRyzenのX3Dモデルです。
大容量のキャッシュを搭載しているので、大量のテクスチャ読み込みが伴うゲームでは読み込みがスムーズです。
わずかな改善に見えても、積み重なるとストレスのなさが違ってきます。
加えて、Core Ultraの優位性も光ります。
EコアとPコアの住み分けが秀逸で、配信や録画、バックグラウンドタスクを並行して走らせながらもメインゲームがスムーズに動き続ける。
こうした効率性は、まさに企業向けの発想が反映されていると感じます。
WQHDあたりで快適に楽しむ方にとっては非常に心強いパートナーになります。
これも見逃せない強みです。
最終的な整理としては、鳴潮を快適に楽しむならCore Ultra 7以上かRyzen 7 X3Dクラス。
この二つがもっとも現実的な結論になります。
負担を減らしつつバランスを重視するならCore Ultra 7 265K。
だからこそ「勝敗がつかない」んです。
どちらを選んでも、自分の遊び方と性格に合えば満足度は非常に高い。
ただ一つ言い切れるのは、CPU選びに妥協は禁物という点です。
ここで手を抜くと、せっかくの時間や楽しみを不意にしてしまいます。
私は40代になり、ゲームも仕事も人生の一部として大切にしています。
その中で痛感しているのは、CPUが快適さを決定づける大黒柱だということ。
だから、これだけは繰り返し強く伝えたい。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 42923 | 2462 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42678 | 2266 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 41712 | 2257 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41007 | 2355 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38483 | 2075 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38407 | 2046 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37176 | 2353 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37176 | 2353 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35552 | 2194 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35411 | 2232 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33667 | 2205 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32811 | 2235 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32445 | 2099 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32334 | 2190 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29174 | 2037 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28462 | 2153 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28462 | 2153 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25380 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25380 | 2172 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23022 | 2209 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23010 | 2089 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20797 | 1857 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19452 | 1935 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17682 | 1814 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16001 | 1776 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15246 | 1979 | 公式 | 価格 |
グラフィック性能、現実的な選び方の着地点
グラフィック性能を踏まえて私がまず言いたいのは、「性能は目的に合ってこそ真価を発揮する」ということです。
高性能なグラボは確かに魅力的ですが、全員に必要かといえばそうではありません。
仕事でも趣味でもちょうどいい投資が一番強い。
つまり、いい意味で身の丈にあった選び方が、使っていて一番しっくり来るんです。
私は昔、高価な機材を衝動的に買って後悔したことがあるので、なおさらそう感じます。
安心感って実際のスペック数字では測れませんからね。
以前、検証用にRTX 5070を導入した時のことを今でもよく覚えています。
フルHD環境で120fpsを余裕で出す安定感に舌を巻きました。
正直なところ、「これで十分だな」とホッとした気持ちがありました。
さらにWQHDに切り替えても、映像の細部がくっきりしていて、プレイ中の引っかかりをほとんど感じなかったんです。
その美しさには思わず満足感が込み上げました。
ただ同じ時期に最新のRTX 5090を体験する機会もあり、その圧倒的な力強さには興奮したものの「ここまで使いこなせるのか?」という疑問が正直な気持ちでした。
宝の持ち腐れ、という言葉が頭に浮かんだんです。
Radeonを試した時の驚きも忘れられません。
RX 9070XTでFSR 4を有効化した瞬間、画面の描写がグッと引き締まって、「これでこの価格帯か!」と素直に感心しました。
余計な小細工ではなく、本当に実用的な強さを見せてくれたんです。
オープンワールドゲームの「鳴潮」を遊んでいるとき、広大な景色を見渡す瞬間に違いがはっきり分かりました。
その時に改めて強く感じたのは、機材がもたらす体験の価値こそが選択の基準になってくる、ということです。
解像度という分岐点はとても大きな意味を持つと思います。
フルHDならRTX 5060TiやRX 9060XTで十分以上に快適に遊べます。
これ以上求める理由が見つからないぐらいです。
WQHDならRTX 5070やRX 9070がちょうどよい落としどころ、無理がありません。
そしてもし4K環境を本気で整えるなら、RTX 5080やRX 9070XTといったカードが適任になります。
ただしこのクラスは電力消費もコストもどっと重くのしかかります。
私ははっきり言いますが、4Kは贅沢であり覚悟でもある。
どちらにせよ財布と気持ちに余裕がいる世界です。
fpsの安定性に目が行かない人は意外と多いと感じます。
ですが私はここを一番に重視します。
60fpsを下回るだけで、プレイ体験の充実感は一瞬で崩壊するんです。
特にアクションゲームではパリィや回避の一瞬の遅れが致命的になり、「なんで今ミスしたのか」と自分を責める羽目になります。
実際、それが原因でゲームを楽しめなくなることもありました。
だからこそ私は最低でも安定した60fpsを基準として譲りません。
基礎体力と同じ。
ここを外した環境では楽しめないんです。
確かに技術的にはすごいんですよ。
でも「鳴潮」を遊んでみて感じた面白さは、光の反射の緻密さではありませんでした。
実際に動かしてみると、マップをストレスなく探索できる快適さのほうがずっと重要でした。
正直に言うと、レイトレーシングは余裕がある人が楽しめれば十分。
無理にこだわるものじゃない。
私はそう感じています。
自分にとって最も大事なのは「最初にどの解像度で遊ぶのかを決めること」だと断言できます。
選択肢が多くて迷いがちなGPU選びでも、解像度を基準にすると一気に絞り込める。
不安な人は少し上位モデルにして心の余裕を持つ、逆に安定性とコスパを大事にするなら一段階下げても大丈夫です。
最上位モデルに飛びついた結果、手に余って後悔する人も少なくないと私は見てきました。
私が最終的に行き着いた結論を率直に言うとこうです。
フルHDはRTX 5060TiやRX 9060XTで快適に遊べます。
WQHDは5070やRX 9070で不足なし。
必要十分。
それがすべて。
ただ、この話は単なる効率比較ではありません。
それが後悔しない選択につながるんです。
それだけのことです。
最高スペックを誇る一枚を持つことよりも、大事なのは長く自然に寄り添える一枚を選ぶこと。
私はそう断言します。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 48533 | 101751 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32047 | 77933 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30055 | 66640 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 29978 | 73293 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27075 | 68805 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26420 | 60131 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 21879 | 56698 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19855 | 50392 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16507 | 39301 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 15942 | 38131 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15805 | 37909 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14592 | 34857 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13699 | 30804 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13160 | 32303 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10787 | 31685 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10617 | 28534 | 115W | 公式 | 価格 |
快適プレイに必要なメモリ容量の考え方
CPUやGPUももちろん必要不可欠ですが、最終的に快適さを左右するのは余裕のあるメモリだと強く実感しています。
どれだけ高価なパーツを使ってもメモリが足りなければ処理が詰まり、動作がカクついたりロードにやたら時間がかかったりします。
そのストレスが大きいんですよ。
だからこそ私は32GBを基準に考えるべきだと思っています。
場面の切り替えごとに膨大なデータを読み込むタイプなので、設定を高くするほどメモリにしわ寄せが来るのは当然です。
特にWQHDや4Kで挑戦するのなら16GBで遊べないことはありませんが、余裕がなくすぐに不安定になります。
動くには動くけれど、すぐ頭打ち。
そういう遊び方って結局は楽しさを損ねるんですよね。
何年か前、私は実際に16GB環境で最新ゲームに挑んだことがありました。
最初の1、2時間は問題なく動いていたのですが、途中でブラウザや配信ソフトを諦めて閉じざるを得なくなりました。
表面上は快適そうに見えても、裏で負荷が積み重なっていたんです。
結局、ゲーム自体よりも周辺の制約にイライラしてしまい、「なんでこんなことに」とつぶやいたことを今でも覚えています。
そして32GBへ増設した瞬間、すべて変わりました。
後ろにまとわりついていた重荷がスッと取れたような感覚でした。
あのときの解放感は何とも言えません。
実際「推奨スペックに16GBと書かれているから十分ではないのか」という意見をよく耳にします。
私の肌感覚としては、32GBがあればDiscordで仲間と通話をしながら情報を調べたり、録画や配信を同時に行っても余裕がありました。
現代のPC利用環境を考えれば、マルチタスクが標準であることは誰もが理解しているはずです。
それを踏まえると、32GBの安心感は万全の保険のようなものです。
64GBという選択肢も一応存在します。
私自身、最近BTOパソコンを購入した際にタイミングが合って64GBモデルを選んでしまったのですが、これはゲーム専用で考えれば少しやりすぎです。
ただし、動画編集や3Dモデル作成といった重たい作業を頻繁に行う方にとっては確かに意味があります。
私の場合、Excelで巨大ファイルを扱うときに「おお、早いな」と体感しました。
だからと言って全員に勧めるべきものではないと考えます。
結局のところ標準解は32GB。
ここに落ち着きますね。
メモリ事情を取り巻く技術も変わってきています。
いまやDDR5が主流で、DDR4は過去の存在になりつつあります。
DDR5-5600程度であれば価格も以前より下がっていますから、「高いから容量を削る」という判断はもう合理的ではありません。
実際問題として速度の違いよりも、容量の違いのほうが体感的に大きく効いてきます。
ですから最優先すべきはやはり容量確保。
これは明らかです。
そして忘れてはいけないのが、アップデートによるデータ肥大化です。
発売直後はよくても、1年後には追加要素が積み重なり、メモリも圧迫されるケースが珍しくありません。
そのときに余白を最初から確保しておけば、慌てる必要がなくなります。
余白が人に安心を与えるんです。
仕事と同じですね。
スケジュールに余裕がないと焦る一方ですが、時間を多めに取っておけば冷静でいられる。
それと同じです。
私が64GBを体験して思ったのは、「余裕は贅沢ではなく武器になる」ということでした。
タスクを切り替えてももたつかず、PCの存在を意識する時間がなくなりました。
ゲームはもちろん快適。
さらに業務効率も上がり、単純に仕事のストレスが減ったのです。
余裕が結果として生活の質を底上げしてくれる。
これは実際に体感してこそ理解できる点だと感じています。
ただし繰り返しますが、64GBを誰にでも推奨するつもりはありません。
多くの人にとって最適解は32GB。
これが鳴潮を心から楽しみたいすべての人への答えです。
迷うとすれば16GBでいいか、32GBにすべきか。
答えはもう出ているでしょう。
つまり、鳴潮を本気で楽しむための鍵は32GBのDDR5メモリです。
これを搭載すれば長時間プレイでも集中を切らさず、ストレスのない時間を過ごせます。
余裕を求める方だけが64GBを検討すれば十分であり、16GBはすでに過去の選択肢です。
私はその事実を何度でも伝えたいと思っています。
答えはシンプルなんです。
鳴潮を長く遊ぶために確認したいゲーミングPCの拡張性

SSDは1TBで足りる?将来を考えた容量選び
これは最初に決めておかないと、あとで必ず後悔するテーマだと私は感じています。
経験上、1TBで済ませようとすると、半年から1年で容量不足に悩まされる未来がほぼ確定的にやってきます。
だからこそ、余計なストレスを抱えずにゲームや動画を心から楽しみたいなら、2TBを選んでおくのが一番安心なのです。
言ってしまえば、その違いはゲームを「趣味として楽しむ空間を確保できるかどうか」という、思った以上に大きな意味を持ちますね。
私が昔オンラインゲームに夢中になっていた頃、500GBのHDDで「このぐらいなら足りるだろう」と軽く考えてスタートしました。
しかし、その半年後には録画データが雪だるま式に膨れ上がり、気づけばHDDは常に赤ランプ状態。
動作は重くなり、ゲームの起動やロードが遅すぎて、せっかくの楽しい時間がストレスに変わってしまったのです。
その苛立ちを思い返すと「ストレージだけは妥協すべきじゃない」と今でも痛感しています。
後から拡張できるのは事実ですが、結局は余計な作業や手間を強いられるだけ。
ならば最初からしっかり積んでおいた方が、精神的にも時間的にも圧倒的にラクなのです。
実際、OSとソフトをインストールするだけで容量はあっという間に減っていきます。
Windowsでほぼ100GB近く使い、そこに鳴潮のような大型タイトルを入れ、さらに他のゲームも入れると、残りは思った以上に少なくなる。
そこで動画キャプチャを保存し始めれば、一瞬で容量不足です。
そのたびに要らないデータを探して削除する羽目になり、遊ぶ時間を整理に取られる。
正直、これほどつまらないことはありません。
遊びたい時間に限って「どれを消すか」なんて考えている自分に気づくと、なんともむなしい。
これ、ほんとに無駄ですよね。
もちろん「1TBで浮いた分をGPUにまわしたい」という考え方も理解できます。
私自身、GPUを少しでも良いものにしたくてSSDを小さめに設定したこともあります。
ただ、結局そこで得られた快適さは一時のもので、最終的には容量不足の息苦しさがやってきました。
空き容量を常に気にしながら遊ぶゲームって、どうしても解放感がないんですよね。
だから私は今、誰に聞かれても「SSDは絶対に余裕を持たせた方がいい」と伝えています。
最近はSSDも昔に比べてずっと安くなりました。
特にGen.4対応の2TBモデルは、もう高嶺の花ではありません。
私は先日BTOショップで1TBから2TBにカスタマイズしたのですが、予想以上に価格差が小さくて驚きました。
その場で思わず「なんだ、最初から迷わず2TBにしておけば良かった」とつぶやいたくらいです。
価格と容量のちょっとした差で、安心感が大きく変わる。
この実感は実際に体験してみないと分からないかもしれません。
だって、ゲームを立ち上げるたびに「容量は大丈夫かな」なんて思い続けるか、それとも気にせず好き放題録画やインストールができるか。
そこで受けるストレスの差は、想像以上なのですよ。
ロード速度についても少し触れます。
確かにGen.5のSSDは数値だけ見れば圧倒的です。
ロード時間が数秒縮まるのは間違いなく気持ちいい。
でも、それがゲーム体験を根本的に変えるかといえばそうではありません。
むしろ容量が足りなくなった時の不自由さの方がインパクトとして大きいです。
私自身、鳴潮のアップデートで数十GBが追加されるたびに「やっぱり容量に余裕があるのは正解だな」と強く思います。
ロードが数秒早いよりも、安心して容量を気にせずプレイできるほうが、はるかに大きなメリットだと断言できます。
先日、知人がSSDを増設する場面に立ち会いましたが、予想以上にケースの開閉や配線で手間取っていました。
もちろん追加すれば済む話です。
しかし、仕事や家庭の合間にわざわざそんな作業をする時間と気力があるかと考えれば、現実的ではありません。
限られた自由時間を有効に使いたいからこそ、最初に容量で余裕を持っておくべきだと心から思います。
安心感がある。
私は結果として「鳴潮を本気で楽しみたいなら2TB SSDを選ぶべき」という持論になりました。
でも、途中で必ず困る。
外付けやクラウドで誤魔化すより、最初から広くしておいた方が確実に後悔しません。
これは単なる理屈ではなく、何度も失敗してきた私の実体験として出てきた結論なのです。
だから、誰かに相談されたら私は迷うことなくこう答えます。
経験からくるストレートな本音です。
時間は有限です。
遊べる時間は限られている。
だからこそ余計な心配をせず、シンプルに「遊ぶこと」に集中できる環境を整える。
それが長くゲームを心から楽しむために必要なことだと、私は強く信じています。
容量にゆとり。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
空冷と水冷、実際の使いやすさで比較する冷却方式
実際にいろいろ試してきましたが、やはり安定性と手間の少なさを重視するなら空冷、静音性や冷却効率まで徹底して求めたいなら水冷に軍配が上がる、そういう結論に落ち着きました。
特に夜遅く、長時間ゲームをするときにはその差がはっきりと感じられました。
平日は仕事で余裕がなく、帰宅して細かい手入れをする気力などほとんど残っていません。
それでも休日に軽く埃を払うくらいで安定して稼働しているのですから、本当に頼もしい存在です。
ただし、大型の空冷クーラーはやはり存在感がありすぎる。
過去に背の高いDDR5メモリと干渉してしまい、手を差し込もうとして汗だくになったあのときの焦りは、今も忘れられません。
まるでパズルを無理やり解こうとするような苦戦でした。
その一方で、水冷にはやはり空冷にはない魅力があります。
PCケースのガラス越しに覗き込んだ時のあの整然とした印象には、思わず「いいな」と声が漏れるほどでした。
さらに最近のオールインワン型は信頼性が大幅に高まっており、以前よく耳にした水漏れのトラブルを気にする必要がぐっと減ったのは大きな進歩です。
ただ、その安心が永遠に続くわけではありません。
数年するとポンプの寿命や冷却液の劣化が避けられず、交換対応が必ず発生します。
要するに、水冷を選ぶということは将来的に一定の追加作業を自分に課すという覚悟ができているかどうか、そこに分かれ道があるのです。
もちろん、空冷の弱点も無視できません。
発熱の激しいCore Ultra 9やRyzen 9を積むと、冷却ファンが全力で回転します。
その音が深夜の静けさを打ち消してしまい、せっかくの没入感を壊してしまうことが何度もありました。
静まり返った書斎でファンの回転音が耳に刺さる瞬間は「ああ、もうこれは水冷しかないか」と正直観念した記憶があります。
ただ、だからといって水冷が完璧というわけではありません。
万一ポンプが壊れたり冷却液が漏れたりするリスクは完全に消えません。
頻度こそ低くなりましたが、頭の片隅に残る不安がゼロになることはないのです。
その点、空冷は潔さを感じます。
ファンが故障しても簡単に替えがきき、大ごとになる可能性が極めて低い。
私のようにPCを長時間稼働させっぱなしにする人間にとって、これは大きな安心材料でした。
ホッとするんです。
PCケースの選び方で冷却の印象が変わるのも面白いところです。
例えば前面メッシュの吸気重視設計であれば、空冷は驚くほど快適に力を発揮してくれます。
逆に広いトップパネルを備えたケースなら、水冷用ラジエーターを搭載したときの見栄えと冷却性能が際立ちます。
このケースとの相性を見落としたことが、私が過去にした大きな失敗のひとつでした。
買った後でサイズが合わず、泣く泣く部品を買い直した悔しさは今でも鮮明に覚えています。
あのときは本当に落胆しました。
盲点として忘れてはいけないのがSSDです。
空冷であればCPUクーラーの風がマザーボード付近に流れ込み、副次的にM.2周りも冷やしてくれます。
私自身、組み上げた水冷構成でヒートシンクが想定外に高温になり、慌てて追加ファンを導入する羽目になりました。
あのときモニター画面を見つめながら「ここまで熱くなるか」と思わずつぶやいたのを今も覚えています。
最終的に、どちらを選ぶかは利用スタイルに強く左右されます。
拡張性やメンテナンスの手軽さを優先するなら空冷が穏当で安心。
一方で、映像美と没入感を最大限重視し、少しくらい余分な手間が増えても静けさと冷却性能を求めたいのであれば、水冷が最適です。
私は高負荷のゲームを本気で楽しみたいときは水冷で構築し、それ以外の場面では空冷で安定を重視するという棲み分けをするようになりました。
状況に応じた使い分けが一番しっくりくるのです。
そして、最後に残るのは意外にも単純な問いです。
「自分はどう遊びたいのか」「どこまで手をかけられるのか」。
この二つの軸です。
派手な見栄えや冷却性能の数字に引きずられるのではなく、長く付き合える形を冷静に選ぶこと。
それが私にとっての大切な視点です。
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R66D

| 【ZEFT R66D スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 8500G 6コア/12スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | DeepCool CH170 PLUS Black |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55EG

| 【ZEFT Z55EG スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II White |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60RY

| 【ZEFT R60RY スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5080 (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55WX

| 【ZEFT Z55WX スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285 24コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60AY

| 【ZEFT R60AY スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9900X 12コア/24スレッド 5.60GHz(ブースト)/4.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | LianLi O11D EVO RGB Black 特別仕様 |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
ケース選びで失敗しないために押さえておきたい点
私も20年以上パソコンに触れてきて、CPUやGPUの派手な性能に目がいきがちな人間でしたが、ケースを軽視したせいで後悔した経験を何度もしてきました。
今ならはっきり断言できます。
ケースは見た目以上に中身の設計こそが大事なんです。
この三つを外すと結局長く満足できませんし、後悔が必ずやってきます。
冷却については、私自身が一番苦しんで学んだ部分です。
真夏の日、せっかく大枚をはたいて組み込んだ高性能GPUが熱にやられて、ゲーム画面がカクつき、苛立ちの中でプレイしたことがあります。
そのときの気持ち、もう二度と味わいたくないと心底思いました。
あの「ブオオオ」というファンのうなり。
ゲームの世界に集中したいのに、背後から現実を突きつけられるようで、悔しさばかりでした。
だから私は冷却性能を軽く見ません。
エアフローを意識したメッシュ構造や、複数ファンを自然に組み込める設計のケースは、値段が多少上がったとしても投資する価値があります。
ゲーム中に温度を気にせず安定したフレームレートを保てる安心感。
その快適さは想像以上で、出費以上の体験をもたらすのです。
拡張性についても、以前は「今の時点で充分」と考えて選んでしまいました。
だけど社会人になって時間も収入もそれなりに増えると、自然にやりたいことや保存するデータが膨れ上がっていくんです。
私も2TBのSSDがあれば十分だと本気で思っていました。
しかしゲームを複数インストールしながら映像編集の素材を保存していくと、あっという間に容量は限界を迎えました。
しかも増設しようとしたらスロットが足りず、スペースも狭い。
その瞬間、以前の自分の浅はかさを思い知りました。
ケーブル配線も地獄でした。
狭いケースに手を突っ込んで血がにじんだことさえあります。
あの痛みは今も鮮明です。
これだけは声を大にして言いたい。
静音性も軽視できません。
特に夜中に仕事を終えて、ようやく自分の時間でゲームや動画編集を楽しみたいというとき、背後でファンが叫ぶように鳴り響くのは本当に疲れます。
集中力を削るノイズというのは意外に精神的にも負担です。
だからこそ私は、防振設計や静音ファン向けの構造を備えたケースに切り替えました。
すると深夜の時間が驚くほど穏やかになり、まるで生活が一段階レベルアップしたような心地よさを覚えました。
静かで落ち着いた夜。
心に余裕が戻る瞬間でした。
見た目もやっぱり重要です。
昔は黒い金属むき出しのケースをリビングに置いていたのですが、ある日家族から「これ、部屋で浮いてるね」と正直に言われました。
部屋に溶け込まず、存在感ばかり悪目立ち。
日々目に入るものだからこそ、デザイン面の調和が心に及ぼす影響は侮れません。
気分が違います。
ただしデザインばかり求めて性能を犠牲にすると、それもまた後悔の火種になります。
そのバランスをどう取るかこそ、成熟した選び方なんだと思います。
つまり、見た目と実用性の両立。
これが本質なのです。
私も過去に安さを優先して、いわゆる安物ケースを買ったことがあります。
当時は「このくらいで十分」と思い込んでいたのですが、ハイエンドのGPUを積んだ途端、真夏は熱暴走でサイドパネルを強制的に外して使う毎日に。
そこから舞い込むホコリ、乱れた見た目。
結果として日々ストレスにまみれる羽目になりました。
楽しく使うはずのPCが、まるで足かせのように感じる瞬間さえあったんです。
その経験があったからこそ今は、冷却性も静音性も揃ったケースを大切に使っています。
夜に気兼ねなく長時間ゲームを続けていられるというだけで、何よりの満足です。
最終的に学んだのは、ケース選びを軽んじると見栄えも性能も、そして気持ちすら損なってしまうという当たり前の事実でした。
冷却効率、拡張性、静音性。
この三本柱を丁寧に満たしつつ、自分や家族の暮らしにしっかり溶け込むデザインを選ぶこと。
性能やスペックに踊らされやすい私たちですが、ケースはPCの土台にして未来への投資だと捉えるべきです。
だから私は、見えない部分ほど手を抜かずに選ぶことを自分への教訓にしています。
単なる自己満足ではなく、心から快適な時間を長く続けるための必然の判断。
その積み重ねが、私にとって理想のPCライフを支えているのです。
解像度ごとに見た鳴潮向けゲーミングPCの構成例

フルHD高画質で安定動作させるためのポイント
映像がカクついたり、せっかくの美しいグラフィックが乱れてしまうと、一気に気持ちが冷めてしまうんですよね。
特に仕事終わりや休日に時間を取って楽しむゲームでそれが起きると、ただのストレスに変わってしまう。
なので、少なくとも1920×1080の解像度で安定して動かせる環境は絶対に整えておきたいと思っています。
安心して時間を投資できる環境。
一番大きな役割を担っているのはやはりグラフィックカードです。
戦闘シーンのように激しい描画負荷がかかる場面でも映像が崩れないので、集中力を削がれることがありません。
正直なところ、以前の私はGPUを軽視して安めのものを選んでいた時期があります。
ですが、アクションゲームの爽快感がカクつき一つで台無しになった時に「ああ、もうこんな失敗は繰り返せないな」と心底思いました。
お金の使いどころはここなんだと実感しましたね。
CPUも忘れてはいけない要素です。
Core Ultra 5やRyzen 5シリーズの最新世代は、フルHD環境で余裕を持った処理が可能ですし、発熱や消費電力も以前と比べて格段に改善されています。
昔は「自作でゲームをやるなら水冷一択」と思っていたのですが、最新のCPUなら空冷でも十分に静かで、長時間のプレイを快適に支えてくれる。
私にとって、自室の静けさを保ちながら長く没頭できる時間というのは、何よりも価値のあるものなんです。
静寂の中でゆっくり遊べる贅沢。
メモリは16GBでも動作自体は可能ですが、不安が残ります。
私は以前ベータ版を試していたときに、同時にブラウザを開いたら重くなって「ああ、これは足りないな」とすぐに感じました。
結局32GBを導入したのですが、その瞬間から気持ちの余裕が生まれました。
性能の限界を気にしながら遊ぶのは落ち着かないんです。
「もうこれで安心だ」と思えるだけで、なんとも言えない安堵が得られる。
やっぱり心持ちの違いは大きいですよ。
ストレージについては、1TB以上のNVMe SSDを勧めます。
それに高速SSDの恩恵は大きく、エリア移動時の読み込み画面が一瞬で終わる快感を味わうと、もう従来の環境には戻れません。
ロード時間のためにスマホをいじる癖が完全になくなったのですから、その差は明らかです。
ケース選びも、思った以上に重要です。
見た目だけで選んで失敗したことが私にはあります。
冷却を無視したデザインを買ってしまい、内部に熱がこもってしまったんです。
そのせいでパフォーマンスが落ち、GPUの本来の性能を生かせませんでした。
それ以来はエアフローを必ず重視するようになりました。
しっかり空気が循環するケースは、長時間の安定性を支える屋台骨であり、見えにくい部分でゲームの楽しさを大きく変えると学びました。
快適な風の流れは表には出ませんが、確実に違いを生むんです。
私が昔やらかした体験をひとつ。
コストを抑えるために古いGPUを流用しようとしたのですが、あるイベントシーンで画面がカクついて感情移入ができなくなりました。
その時の虚しさは今でも覚えています。
結局すぐに最新世代のGPUを買い直しましたが、最初からケチらずに選んでおけばよかったと心底後悔しました。
やはりゲームは「快適さ」が命なんだと痛感しましたね。
冷却に関しても、軽視はできません。
とくに夏場の午後は部屋の温度も上がり、PC内部はさらに高温になります。
そんな状況で頼れるのが質の良いクーラーで、DEEPCOOLなどの空冷やCorsair製の水冷は安心して任せられます。
ファンがうるさいとどうしても気になってしまうので、静かで強力な冷却は長時間プレイの満足度をぐっと上げてくれます。
これは実に難しく、そして奥深いテーマだと私は思っています。
振り返れば、GPU、CPU、メモリ、ストレージ、ケース、冷却、それぞれが欠けてはならないピースです。
RTX5060TiやRX9060XTクラスのGPU、Core Ultra 5やRyzen 5の最新世代CPU、32GBの余裕あるメモリ、1TB以上の高速SSD、そしてエアフローに優れたケースと信頼できる冷却。
それらを整えれば、不満のない環境が実現できます。
安心できる遊び場の完成です。
結局のところ、鳴潮をフルHDで快適に楽しむためには、GPUとCPUで最新世代を選び、メモリとSSDには余裕を持たせ、ケースと冷却性能を決して軽視しないこと。
この条件が満たされてこそ、本当の意味で「ストレスなく長時間楽しめる」環境が出来上がります。
妥協した分だけ、結局楽しみは削られてしまうのだと私は実体験で学びました。
だからこそ、これだけは譲れない。
それが私の正直な気持ちです。
快適な体験は準備から生まれる。
そして最後に伝えたいことは、ゲーム体験を支えるのは単なるグラフィック描画ではなく、裏で黙々と働く環境全体だということです。
WQHDで144fpsを目指すなら気をつけたいパーツ構成
これを怠ると、後で悔やむ瞬間が必ずやってきます。
敵が一気に出現して派手なエフェクトが重なった時、処理落ちが発生して一瞬でも戦意を削がれる経験は、本当に痛い。
だからこそ、CPUよりもまずGPUに優先度を置くのは間違いない、と断言できるのです。
Core Ultra 7やRyzen 7あたりであれば、描画処理の安定と計算能力の両立が取れる。
もちろんCore Ultra 9を選べば余裕を感じられるのはたしかですが、その分、消費電力と発熱に悩まされます。
夏の蒸し暑い夜に、エアコン全開でも汗をぬぐいながらPCの排熱に耐えてゲームをしたときには、「もう少し冷却も考慮すべきだった」と心底思いました。
社会人はゲームに割ける時間が限られています。
だからこそ、安定して快適に遊べる環境こそが最優先になってくるんです。
メモリは32GBが妥当です、と胸を張って言いたいです。
しかし、同時にブラウザを開き、チャットや資料を複数立ち上げると、容量不足が顔を出す。
本当に地味なストレスなんですよ。
16GB環境で遊んでいた頃、ロードのたびに「ちょっと止まった?」と感じることが多く、これが積み重なると不思議と疲労感に変わるのです。
今は32GB環境で余裕を持って作業もゲームも回せています。
安心感があります。
ストレージは経験上、大きめがお勧めです。
私は1TBで充分だと思っていましたが、日を追うごとにゲームのアップデートや追加コンテンツで容量が膨らみ、あっという間に圧迫されました。
更新中に容量不足で中断され、せっかくの休日にプレイできなかったあの日は本当に苦い思い出です。
忙しい社会人にとって、限られた自由時間が潰れるのは何より辛い。
その後2TBのNVMe SSDに切り替えたことで、容量を気にせず快適に遊べるようになり、心の余裕まで手に入れました。
空き容量を気にして整理するストレスから解放されただけで、ゲーム時間がより楽しいものに変わるのです。
冷却も軽視できません。
深夜にリビングでプレイしていると、ファンの音が急に轟音に変わり「さすがにこれは家族を起こすな」と冷や汗をかいたことがありました。
結局、簡易水冷から大型空冷に替えたのですが、その変化は想像以上で、動作音が一気に静かになったのです。
以来、深夜でも安心して没頭できるようになり、冷却と静音性を両立することがどれほど重要かを思い知りました。
静音性。
これは快適さを保つ根幹です。
さらに意外に大事なのがケースです。
ハイエンドGPUは本当に大きい。
サイズを確認せず購入してしまった私は、ケースに無理やり押し込み、結果的にエアフローが悪化するという失敗をしました。
性能をフルに引き出すには、広さと冷却効率が確保できるケース選びが欠かせません。
最近は透明パネルや組みやすい設計のピラーレスケースが主流で、見栄えと機能性を両立できます。
正直、もっと早く買い替えていたら良かったと後悔しましたよ。
結局、WQHDで144fpsの快適さを得たいなら、GPUに投資し、CPUはミドルハイクラス、メモリは32GB、ストレージは2TB NVMe SSD、冷却性能と静音性を兼ねたクーラーを用意し、そして余裕のあるケースを選ぶことが必須です。
これが私が行き着いた答えです。
そしてここにこそ、無駄な出費や後悔を避ける最適解があるのだと思います。
これは間違いなく没入感を支える柱。
静かな動作。
この二つを揃えてこそ、WQHD環境は完成形に近づきます。
働き盛りの40代である私にとって、ゲームはただの娯楽以上の意味を持ち始めています。
それは一日の疲れを癒やす時間であり、限られた自由を充実させる瞬間です。
環境にこだわり、失敗しつつも少しずつ整えていく過程そのものが、自分にとっては充足感となりました。
小さな工夫や投資が、生活の質に直結するのだと実感しています。
だから私は、これからも自分に最適なゲーミング環境を追い求めていくでしょう。
4Kプレイに必要なGPU性能と冷却面での準備
私自身、痛い経験を繰り返してきたので断言できます。
どちらかが欠けると、せっかく高額な投資をしても後悔しか残らないのです。
まさに高価な趣味だからこそ、中途半端ではいけないと身をもって知りました。
最初にPCを組んだとき、私は「少し妥協しても大丈夫だろう」と自分に言い聞かせて、コストを重視してしまいました。
結果は惨敗。
悔しくなって電源をオフにし、ため息しか出なかった夜を今でも覚えています。
散財を避けたはずが、かえって時間とお金を無駄にしただけ。
結局はハイエンドのGPUに入れ替えるしかなく、それでようやく心から満足できる環境を得られました。
あの一件以来、私は「安定した動作は最優先」という考えを手放さなくなったのです。
ただ、意外と見落としがちなのが冷却です。
GPUばかりに目を向けがちですが、4K環境下ではCPUにも相応の負荷がかかり、ケース内部のエアフローが不十分だと一気に熱がこもります。
その結果、パーツが熱保護のために自動的に性能を落とし、知らないうちにグラフィック設定を下げざるを得なくなってしまう。
何度も「どうして急に処理が落ち込むのか」と悩みましたが、調べていくと原因のほとんどは冷却不足でした。
冷却軽視は本当に厄介。
忘れてはいけない要素だと痛感しました。
ところが2時間ほど遊ぶと温度が90度に迫り、映像はカクカク。
それから思い切って360mmサイズの簡易水冷を導入したのですが、これが大正解。
温度は70度前後で安定し、途切れるようなストレスが完全になくなったのです。
以前の私は「大型の冷却装置は動作音がひどいだろう」と思い込んでいました。
ところが最新の水冷ユニットや大型ファンは低回転でもしっかり冷却でき、むしろ静音性が増しました。
最初に電源を入れたとき、あまりに静かで「本当にちゃんと動いてるのか?」と耳を澄ましたほどです。
これには感心しました。
静けさがあるおかげで、逆に没頭度が高まりました。
ケース選びの重要性も忘れられません。
私は最初、デザインを優先して強化ガラス製のサイドパネル付きケースを使っていました。
その後、思い切って前面や側面にメッシュ加工を施したケースに変えてみたら、内部温度が一気に7度下がりました。
また、意外な盲点はストレージです。
私は最初ヒートシンクを付けずに使ってしまい、アップデート中に温度急上昇で動作が詰まることに何度も苛立ちました。
ヒートシンクを後付けしたら、嘘のように安定して、ラグは大幅に減少。
ゲームが途中で止まる不安から解放されたときの安心感は大きかったです。
小さな部品ひとつでこうも違うのか、と感慨深くなりました。
休日に3時間以上ぶっ通しでゲームをしても、GPU温度は70度前後に収まり、以前より平均で15度も低下。
数字よりも体感のスムーズさが圧倒的に変わり、プレイに没頭できるありがたさを強く実感しました。
単にスペック表の数字を追うだけでは測れない価値があります。
だから私は言い切ります。
4Kで本気でゲームを遊ぶなら、ハイエンドGPUと徹底した冷却、これが揃わなければ成立しません。
それさえあれば、他の構成が多少標準的であっても十分満足できます。
妥協せずに準備すること。
それが唯一の正解だと考えています。
大人の趣味だからこそ、納得感が大事なんです。
安定と楽しさ。
この二つを支えるのは、結局は冷却とGPUなんですよ。
これこそが全て。
忙しい社会人が選びやすい鳴潮用ゲーミングPCの買い方


BTOと自作、コストと手間のバランスをどう考えるか
鳴潮のような重量感のあるゲームを楽しむために、限られた時間と労力でどう環境を整えるか。
私は社会人として迷った末、BTOパソコンを選びました。
理由はとても現実的で、すぐに安定した環境を準備できるからです。
仕事が終われば疲れて帰宅し、家庭の用事に追われる日々。
その中で自作に挑戦する余裕をひねり出すのは正直難しい。
だからこそ、最小の手間で最大の効果が得られるBTOが、今の私にとっては一番しっくりきたのです。
BTOの魅力は「買ってすぐ使える」ことに尽きると思います。
動作確認済みで届く安心感は大きく、余分なストレスを抱える必要がありません。
以前、私はBTOで購入したPCが届いたその日の晩、急いで鳴潮をインストールしました。
最初の起動で画面が滑らかに動き出した瞬間、本当にホッとしましたね。
社会人にとって、その「時間を買う」感覚は何よりも価値のある投資なんです。
一方で、自作の魅力を理解していないわけではありません。
むしろ昔は夢中でパーツを調べ、ケース選びや冷却ファンの効率にまでこだわり抜きました。
電源ボタンを押し、初めてモニターに映し出される画面を見た時の高揚感は今でも忘れられません。
とはいえ、休日を丸ごとつぶして組み立てや不具合調査に追われた経験も同じくらい刻まれています。
正直なところ、その疲労感に勝る満足感が得られなかったこともありました。
あのむなしさ、今も鮮明に覚えています。
これがすべてです。
社会人の私がパソコンに求めるのは、とにかく安定してゲームを快適に動かせる環境。
それ以上でも以下でもありません。
鳴潮を心置きなく楽しみたいと考えた時、フレームレートが一定であることや描画が美しいことが大前提で、余計なトラブルに時間を奪われる余裕などないのです。
ただし、BTOにも工夫は欠かせません。
SSDが標準構成で1TBしかないモデルでは、アップデートやキャッシュによってすぐに容量不足になるのは目に見えています。
実際に使ってみて、私は2TBは必要だと心から感じました。
また、メモリも16GBでは不安になる場面があるため、32GBを選んでおく方が結局安心です。
こうしたカスタマイズを容易に反映できる点は、BTOの強みでもあります。
ですが、自作の醍醐味であるはずの自由度が裏目に出て、パーツの相性問題に直面することも珍しくありません。
私自身、動かない原因を夜通し調べ続け、気づけば休日が丸ごと消えてしまったことがありました。
そのときの疲労感と虚無感は今も苦い記憶として残っています。
だからこそ私は思うのです。
保証やサポートがついているBTOの価格差は決して割高ではなく、自分の時間を守る投資だと。
私は以前、Core Ultra 7と最新GPUを搭載したBTOを購入しました。
わずかな設定ですぐに理想の環境を得られたあの時の安堵感は、自作ではなかなか得られないものでした。
それでも不思議なことに、私は自作の楽しさも捨てきれません。
趣味としてのパソコン組み立ては別物の魅力があり、休日にゆっくりパーツを並べて「次はどうしようか」と考える時間は確かに楽しい。
夢中で格闘したあの感覚は、また味わいたいと正直に思います。
ただしそれはあくまで趣味。
普段の日常で快適にゲームを遊ぶためのツールとしては、やはりBTOを選ぶべきだと頭では理解しています。
気楽さ。
人生の中で仕事や家庭に追われる日々を送る以上、パソコンにまで神経をすり減らす余裕はありません。
だからまずはBTOで安定した環境を手に入れて、余暇の中で遊びとして自作に挑戦する。
その順序が、今の私にとって最も現実的で、そして心にも体にも優しいと思っています。
社会人としての私の結論はこうです。
メインはBTOで確保し、自作はあくまで趣味として楽しむ。
その切り分けをすることが、限られた時間の中で最大限の楽しみを得る最良の方法だと考えます。
大げさではなく、この方針が私の生活のバランスを保ち、余裕を取り戻してくれるのです。
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R64N


| 【ZEFT R64N スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal North ホワイト |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60FS


| 【ZEFT R60FS スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9060XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z59M


| 【ZEFT Z59M スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285K 24コア/24スレッド 5.70GHz(ブースト)/3.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Corsair FRAME 4000D RS ARGB Black |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47CC


最新のパワーでプロレベルの体験を実現する、エフォートレスクラスのゲーミングマシン
高速DDR5メモリ搭載で、均整の取れたパフォーマンスを実現するPC
コンパクトでクリーンな外観のキューブケース、スタイリッシュなホワイトデザインのマシン
クリエイティブワークからゲームまで、Core i9の圧倒的スピードを体感
| 【ZEFT Z47CC スペック】 | |
| CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 ROG Strix B760-I GAMING WIFI |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
仕事使用との両立を見据えたPC構成の工夫
在宅勤務が当たり前になってしまった今、私は長年付き合ってきたPCをどう見直すか、真剣に考えざるを得ませんでした。
結局のところ、私が行き着いた答えは「派手さを求めず、業務に安心して使え、かつゲームもそつなくこなせるPC」でした。
仕事をこなしながらも、自分の趣味であるゲームを楽しみたい。
その二つを両立させるためには、見かけや数字よりも安定した使い心地こそが何より重要だと悟ったからです。
邪魔になりますし、正直に言えばメンテナンスも二倍になります。
だから一台に集約するしかない。
最初はどうしてもゲーミング寄りの煌びやかなモデルに目が行きました。
光るケースに水冷の大仰な仕組み、なんだか少年に戻ったような高揚感も確かにありました。
だけど、冷静に考えたら昼間は会議、夜は資料作り、そして休憩にゲームという毎日の流れを支えるには、派手さよりも静かで安定した作動が優先だろうと気づいたんです。
派手さはもう要らない。
心からそう思いました。
メモリの話は今でも忘れられない経験です。
最初は16GBで十分と思い込んでいました。
けれど、会議ソフトを開き、資料を広げ、その裏で鳴潮を動かそうとしたら、もうカクカクでイライラの連続。
イラつきすぎて途中で全部閉じてしまったことだってあります。
思い切って32GBに増設したら、あれほどのストレスが嘘のようになくなりました。
あの瞬間「ケチらなくて本当に良かった」と心から思いました。
これ以上なく実用的な投資でしたね。
ストレージでも失敗しています。
1TBだけの頃は、資料もゲームも同じ場所にどんどん溜まっていき、気づくと残り容量が真っ赤。
キャッシュやアップデートのファイルでパンパンになり、不要ファイルを探して削除に追われる日々。
時間の無駄でした。
結局2TBに切り替えて、業務データとゲームデータを完全に切り分けたら、一気に気が楽になったんです。
不思議ですが大事なことだと思います。
グラフィックボードについても冷静に判断しました。
あれもこれも欲張れば天井なしですが、必要十分な性能を選ぶことが肝心です。
私はRTX 5070を導入しましたが、これが驚くほど快適でした。
鳴潮がWQHDでスムーズに動き、さらに二つのモニターに資料を並べてもカクつきひとつない。
あの時「これで十分だ、いや十分すぎる」と心底思えたのです。
無理にハイエンドを買っても使いこなせない。
大切なのは、必要なシーンできっちり応えてくれる安心感でした。
余裕感。
CPUも同じです。
オーバークロックなんて不要。
数字の強さよりも安定と低発熱がありがたい。
最近のCPUはAIによるノイズ除去や効率化機能も備えているので、会議をしながらバックで更新も進められる。
これには正直、技術の進化に驚かされました。
「ゲームと仕事両立できるCPUって、スペック以上の価値があるんだな」としみじみ思ったんです。
冷却には一度水冷を夢見ました。
光るチューブに透き通った液体。
見た目は格好良い。
でも実際に欲しいのは、静かで気にならない環境でした。
在宅の会議中、背後でブーンとポンプ音が響くなんて困ります。
だから空冷の静音性を最優先しました。
結果、大正解。
耳にノイズが届かないだけでこんなにも仕事に集中できるのか、と実感しました。
静けさこそ正義です。
ケースに関しても意外と拘りました。
ゲーミングPCだからといって光らせるのはもう卒業。
私が選んだのは木目調の落ち着いたケース。
部屋に溶け込み、本棚や資料棚の横に置いても全く違和感がない。
その自然さが思っていた以上に心を満たしてくれました。
業務空間に馴染むからこそ、気持ちも落ち着くんです。
「この部屋に置いて違和感のないPC」に価値を感じる日が来るとは、昔の私なら想像もしなかったでしょう。
最終的に辿り着いたのは、私が欲しかったのは単なるゲーミングPCでもなく、業務専用マシンでもなく、その両方を支える実用的な一台だったという事実です。
社会人である以上、日常業務の妨げになるような使い勝手の悪いマシンは要らない。
必要なのは静音性や扱いやすさ、そして信じられる安定感。
それらを兼ね備えた上で夜には存分に遊べる。
その両立こそが本当の価値でした。
性能競争に踊らされるより大事なことは、毎日の生活を気持ちよく支えてくれるかどうか。
その答えを私はやっと手に入れたのです。
今では、昼の会議も夜のゲームも、同じ机で同じPCが担ってくれている。
生活の質が、一段上がった実感です。
引越しや出張が多い人に向けたモデル選びのポイント
引っ越しや出張ばかりの生活をしていると、パソコン選びは単なる数字の比較や最新機能の確認だけでは済まないと痛感させられます。
私自身、仕事と趣味のゲームを両立する中で何度も失敗し、そのたびに「なぜもっと自分の行動パターンを考えなかったのか」と後悔した経験があります。
最終的に私が行き着いたのは、携帯性を重視するならゲーミングノートが一つの現実的な答えになるということです。
デスクトップと比べれば冷却性能や拡張性では劣りますが、毎日の移動という現実の前では、性能差よりも安心して持ち歩けることのほうが圧倒的に価値を持つのだと気づきました。
新幹線に乗るとき、大きなデスクトップ本体を無理にバッグに詰めて持ち運んだことがあります。
そのときの疲労感といったら、一日が始まる前にすでにエネルギーを半分失ったような気分でした。
だからこそ、少し性能を抑えてでもノートで良かったと実感する瞬間が多いのです。
昔はゲーミングノートといえば「熱で性能が落ちる」「結局遊びきれない」というイメージしかありませんでしたが、いまのモデルは違います。
CPUやGPUの効率化、熱を逃がすための冷却設計の進化、本当にこの10年で大きく変わったと感じています。
以前なら机に据え置いたまま諦めていたようなパワーを、バッグに入れて持ち出せる。
これは生活が変わる体験でしたね。
例えば、出張先のホテル。
昼間は打ち合わせや移動で疲れ果てても、夜に鳴潮を立ち上げると、自宅と何ら変わらない景色が広がる。
あのときの「隔たりがない安心感」は、言葉以上に強いインパクトがありました。
正直、一度味わえば離れられません。
知らない土地で過ごす不安な夜に、普段通りの世界がそこにあること。
それがどれほど心を落ち着けてくれるか、経験ある方なら分かるでしょう。
もちろん良いことばかりではないです。
冷却面では限界があります。
同じGPUを積んでいても、数%から十数%は性能に差が出ると言われています。
その現実は受け止めざるを得ません。
ただ、その差を背負ってでも「すぐ持ち出せる」という価値は揺るぎませんでした。
特に出張や転勤が続くビジネスパーソンにとっては、会社の資料も趣味も1台に詰め込んで軽々とリュックに収まるノートこそ、伴走してくれる存在だと思うのです。
画面サイズの選択も慎重になるべきです。
私はかつて14インチの軽量モデルを選び、最初は「これで十分」と思っていました。
ところが出張先で2時間ほどゲームを続けると、熱でクロックが落ちて動作が重くなり、キャラクター操作にイライラすることに。
あのときの後悔は忘れられません。
その後16インチのモデルに切り替えましたが、重さの分得られる安定感は圧倒的でした。
肩に負担はかかります。
ただ、不安定な挙動に振り回されることと比べれば、私は後者を選ぶ。
もう一つ外せない問題がストレージです。
500GB程度では数か月で一杯になり、1TBでも気づけば警告が表示される。
そのたびに不要なデータを整理するのは、本当に神経をすり減らします。
私は2TB以上を基本とし、必要に応じて外付けSSDも併用しています。
これが意外なほど生産性や気分に影響しますよ。
最近のモデルの冷却機構も頼もしいものがあります。
二基のファンと専用のヒートパイプを搭載し、高負荷がかかっても安定して稼働できる構造。
鳴潮のように長時間腰を据えて遊ぶタイトルでは、ボタン一つで冷却をブーストできる機能はありがたい。
これはもう性格の問題でしょうね。
もちろんゲーミングノートが唯一の正解というわけではありません。
小型デスクトップ、いわゆるSFFケースを使い、人によっては専用バッグで持ち歩いている人もいます。
拡張性を確保しつつ、どうしても必要なときだけ移動できるという発想は面白いもので、出張の多い友人が実際に実践していました。
彼の言葉には説得力がありました。
「これしかなかった」と。
確かに、自宅に腰を据えられる時間が多い人にとっては、この選択肢も一理あります。
ただし忘れてはならない。
電源の問題です。
ノートですらACアダプタが大きく重いのに、小型デスクトップならなおのこと滞在先に環境が揃っていなければ役立ちません。
私は過去に電源周りを甘く見たせいで仕事すら滞ったことがあります。
小さなことのようでいて核心に迫る課題でした。
そうした「想定と現実のギャップ」こそが最大の落とし穴なのです。
だから、生活リズムを正確に思い描き、自分にとって優先すべきものは何かを整理しなければいけません。
移動の多さにゲーム体験が邪魔されないよう、ほんの少し慎重に選んでほしいのです。
最終的にどんな選択をしても、自分に合ったモデルを見つけられさえすれば、鳴潮をどこででも楽しめる環境は整います。
安心して持ち運べて、信頼の置ける相棒を選ぶこと。
それこそが40代の私が経験を踏まえて伝えたい答えです。
安心感。
信頼性。
鳴潮用ゲーミングPCに関するよくある疑問


ノート型ゲーミングPCでも鳴潮を快適に動かせる?
ただし、それは単純に「はい、大丈夫です」と言い切れるほど甘い話ではありません。
なぜなら、高性能を誇る一方で、熱の問題やファン騒音といった現実的な要素がいまだ立ちふさがるからです。
私自身、いくつかのノート型ゲーミングPCでゲームをプレイしてきましたが、素直な気持ちを話せば「動くことは動く、けれども本当に落ち着いて遊べるかとなるとやや心もとない」という感想が多いのです。
最近のノート型は驚くほど高性能です。
CPUやGPUは一昔前ならデスクトップでしか味わえなかったレベルにまで来ており、カタログを眺めていると「もうこれで文句ないだろう」と錯覚しそうになる。
しかし実際に数時間プレイすると、手元から伝わる熱がどうしても気になり始めるんです。
「うわ、これはちょっと熱いな」と思わず口にしたこともありました。
集中すべき場面で余計な心配が頭をよぎる。
これがノート型の現実なのだと痛感します。
半年前、私は鳴潮ではなく別のオープンワールドゲームをノート型で遊んでみました。
性能面では確かに快適だったものの、気付けば一番気になったのはファンの騒音でした。
ゴォーッという大きな音がずっと響き続け、まるで横で掃除機が回っているような状態。
ゲーム音よりファンの音に意識を奪われるのは本当に辛かったです。
結局は冷却台を買い足しましたが、その出費は正直余計だったなと感じています。
静音性の改善は確実に進歩してきたとはいえ、まだ課題が残っています。
それでも、持ち運べる自由さは大きな魅力です。
自宅のデスクに縛られず、出張先のホテルや移動の合間、新幹線の中でも「少しだけ遊ぼう」と思えるのは、慌ただしい社会人にとって本当にありがたいこと。
仕事に追われる毎日の中、数十分でもお気に入りのゲームを触れる時間は心の余裕を与えてくれました。
デスクトップによる安心感は比類ないけれど、ノートの機動力には救われる場面が意外と多いんです。
鳴潮は特に美しいビジュアルが売りのゲームですから、それに見合ったGPU性能が必要です。
RTX 50シリーズやRadeon RX 90シリーズを積んだモデルなら、フルHD環境であれば80fpsから120fpsを維持することも珍しくありません。
確かに快適です。
ただし、WQHDや4K画質で挑むと発熱が一気に高まり、ファンが再び本気を出して唸り始めることもよくある。
購入する際は冷却設計をしっかりチェックしておきたいところ。
風を大胆に下から噴き上げるような機種に出会うと、「おお、進化したな」と素直に驚きます。
頼もしい瞬間ですね。
一方で、冷静に考えればノート型の弱点は明らかです。
メモリやSSDの交換はある程度可能ですが、CPUやGPUはまず不可能です。
数年後にゲームの要求スペックが跳ね上がれば、まるごと買い替えせざるを得ない。
この事実はどうしても無視できません。
高額を支払ったのに、いざ時が来れば資産価値がほとんど残らない。
それを考えると胸が苦しくなります。
それでも私の生活スタイルを基準にすると、ノート型の存在は軽く見られません。
仕事帰りにカフェで少しだけ冒険を進める。
休日に出先で気分転換にプレイする。
その積み重ねが、日々の疲れを和らげ、また次の日を頑張ろうという活力につながる。
ここには確かに意味があると感じます。
さて、本当に腰を据えて鳴潮をメインで遊び尽くしたいのなら、答えはデスクトップです。
冷却性能の圧倒的な優位、拡張性の豊かさ、長期にわたって安定した静音性。
これらは残念ながらノートには真似ができません。
ただし、どうしても持ち運びが大事なら、それに応えられる高性能ノート型も十分選択肢になります。
Core Ultra 7 265KやRyzen 7 9700Xといった最新CPUに加え、RTX 5070クラス以上のGPUを搭載したモデルであれば、最高画質でも大きなストレスなくプレイできるでしょう。
とはいえ、まだ技術的に求めたい部分もあります。
特に冷却技術。
もしもノートにデスクトップ並みの静音冷却が搭載されれば、妥協を飲み込む必要はぐっと減るはずです。
いつかそんなモデルが出てくることを願わずにはいられません。
鳴潮は動きます。
ノート型でも十分に。
けれども本当に心からゲームの世界に入り込みたいなら、やはり私はデスクトップを選ぶ。
これは揺るがない本音です。
生活のどこに価値を置くか、その人自身のライフスタイルが最後の答えを決めてくれるのだと思います。
これに尽きます。
今日の結論はシンプルです。
ノート型の便利さとデスクトップの安定性。
それが最良の選択につながります。
鳴潮を遊ぶ前提なら予算はどのくらいを見ておくべき?
鳴潮を快適に楽しむために必要なのは、15万円というミニマムな予算ではなく、20万円から30万円という枠を覚悟することだと私は思っています。
もちろん、最低限動けばいいという割り切りもありますし、15万円程度なら一応形にはなるのです。
だからこそ、先行投資と割り切って余裕のある環境を最初から整えるべきだと強く思うのです。
予算を15万円に抑えた場合、現実的な構成はミドルクラスのグラフィックボードとCore Ultra 5やRyzen 5、そしてメモリ16GBあたりが限界です。
遊べないわけではありませんが、アップデートが続くゲームの性質を考えると数か月後には物足りなくなります。
私もかつて同じ構成で半年ほど遊びましたが、すぐに画質設定を落とさざるを得なくなり、「あのとき数万円を惜しまなければ」と愚痴りたくなるほど後悔しました。
せっかくの娯楽で、後から自分に不満をぶつけるのはつらいものです。
一方、20万円から30万円を用意できれば話はまったく変わります。
最新の50番台のグラフィックボードやRX 90シリーズ、CPUはCore Ultra 7やRyzen 7を積み、メモリも32GBにしておく。
そこに1TB以上のNVMe SSDを加えれば、鳴潮を最高設定で遊びながら裏で配信や動画を同時に処理することも余裕です。
この段階になると「遊びやすい」ではなく「遊んでいて心強い」と思える環境が手に入る。
以前、私はケースや電源を妥協したのですが、結局見た目や騒音が気になり、後で買い替えました。
最初から潔く揃えておくべきだったと痛感しました。
妥協のツケは案外大きいのです。
ストレージの話も外せません。
ゲームのサイズは想像以上に膨れ上がります。
最初は大したことがなくても、数年後には2倍近い容量になっていたこともあります。
私は以前500GBのSSDで足りると考え、結果的に外付けHDDを増設してしのぎました。
しかし保存場所を毎回工夫する手間が積み重なり、正直ストレスでした。
やっぱり最初から1TB以上が無難です。
自分の経験で痛感しました。
冷却も重要です。
私は昔、冷却をケチったPCを使っていましたが、真夏の夜に突然フリーズを連発し、休日を泣く泣く修理に費やしました。
原因はたった数千円の冷却性能不足。
たったそれだけで、大切な時間を奪われるのです。
あれから私は常に「冷却に妥協なし」と決めています。
社会人にとって、ゲームの時間はとても限られています。
その数時間で画面がカクつけば、一気に疲労感が重くのしかかってきます。
私は過去に「まあこれで十分だろう」と思って構成を抑えた結果、遊んでいるのに気持ちが休まらない夜を何度も過ごしました。
だから今は妥協せずに投資することが、むしろ自分の気持ちを守る最短の道だと確信しています。
本当に違います。
高めの予算で組んだPCは、鳴潮を満足に動かすだけではありません。
この安心感は、ただの数字以上の価値を持つのです。
私にとっては、平日の夜に画面の前へ座り「待ち時間ゼロで遊べる」ことこそが、かけがえのない幸福です。
安心して没入できる環境が、日常の疲れを消してくれる大切な時間に直結します。
私は敢えて言います。
20万円から30万円は高く感じるかもしれませんが、それが鳴潮を心から楽しむためのベストラインです。
安さを優先すれば遊べる環境は作れますが、それは「ただ動く」に過ぎません。
40代になり、時間の価値を強く意識するようになると、後悔しない選択肢は自然と見えてきます。
数万円を惜しんで不満と付き合うくらいなら、最初からしっかり投資した方がいい。
快適さを買うための投資。
私が数々の失敗を経て学んだのはそこです。
最終的に、しっかりしたスペックを用意することが、仕事の合間に得られるかけがえのない没入体験を守ってくれるのです。
私は今、自信を持ってそう言えますし、実際にその選択が私の生活を豊かにしていると心から感じています。
だから私は20万円から30万円を、自分の喜びと安心を買う値段だと捉えているのです。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R63R


| 【ZEFT R63R スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P10 FLUX |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R63O


| 【ZEFT R63O スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9070XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal Pop XL Silent Black Solid |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R62P


| 【ZEFT R62P スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R55AE


研ぎ澄まされたパフォーマンスが際立つ、アドバンストスタンダードのゲーミングPC
コスパ抜群!64GBのメモリと最新RTXが織り成す驚異のスペックバランス
Pop XLのケースに、RGBの輝きが宿る。大迫力のデザインながら、洗練されたサイズ感
新時代を切り拓くRyzen 5 7600、スムーズなマルチタスクをコミット
| 【ZEFT R55AE スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 7600 6コア/12スレッド 5.10GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal Design Pop XL Air RGB TG |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASUS製 TUF GAMING B650-PLUS WIFI |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
今買うならIntelとAMD、どちらを選ぶのが無難?
今の時点で私の考えを率直に言えば、限られた時間を快適に遊びたい社会人にとっては、やはりIntelのほうが落ち着いて使える安心感が強いと思います。
たとえばIntelのCore Ultraシリーズは最新のアーキテクチャを採用していて、AI処理を支援する仕組みまで組み込まれているので、ゲームと配信ソフトを同時に動かしても、あるいはブラウザで複数のタブを開きっぱなしにしても、挙動がバタつかず安定しているのです。
社会人にとって一番困るのは「今日は一時間だけと決めたゲームの時間に限ってフリーズする」というような事態です。
だからこそ、毎回安心して電源を入れられるという単純な事実が大きな価値を持ちます。
安心感。
とりわけCore Ultra 7 265Kは発熱のコントロールが見事で、空冷で問題なく運用できるのがありがたいところです。
出張から戻った夜に、疲れた体を癒すようにPCを立ち上げて遊ぶことがありますが、そのとき本体が大きく唸ることもなく落ち着いて動いてくれると、なんだか「今日もよく頑張ったな」と自分を肯定してくれているような気持ちにさえなります。
小さな違いですが、こういう静かな安心が、日々の暮らしに効いてくるんですよね。
もっとも、AMD Ryzen 9000シリーズにも魅力はあります。
Ryzen 7 9800X3Dは膨大なキャッシュを積んでいて、オープンワールド系の重めのタイトルを遊んだときでも描画が揺るがず、安定したフレームを維持してくれる。
あの一瞬の驚きは、たぶん体験した人にしかわからない特別な感覚で、AMDならではの味わいだと思います。
ただしRyzenを本気で選ぼうとすると、マザーボードやメモリとの相性でちょっと迷う場面があるのも事実です。
最初のセットアップで躓くと、限られた時間のなかで「あの数時間でゲーム一本遊べたな」なんて思ってしまうんです。
仕事に追われてやっと取れる自由時間を、設定の時間に割くのは正直惜しい。
Intelはその点で相性面のリスクが少なく、箱を開けてすぐ安心して動かせるのは社会人にとって心強いです。
でもRyzenも侮れない。
特にマルチスレッド性能は圧倒的で、裏で動画のエンコードを走らせながらゲームを動かしても重くならない。
これは遊びだけでなく、仕事で映像編集や解析作業を行う人にも確かなメリットです。
私も深夜にデータ処理を流しつつ、その横で息抜きに軽く遊ぶ姿を想像すると、なんだか惹かれるんですよね。
この余剰パワーの持つ頼もしさは、確かに魅力です。
実際の体験を話すと、Intel Core Ultra 7を積んだPCで同僚と鳴潮のマルチプレイをやった際、Teamsで画面共有を同時にしても動きが乱れることは一切ありませんでした。
これは素直に「安定しているな」と感じました。
一方で別の日にRyzen 9800X3Dで同様のことを試したとき、やはり快適に動いたのですが、面白いことにリソースの使用率にはまだ余裕があり、「あ、力を持て余してるな」と感じるくらいでした。
Intelは硬派で安定、AMDは力強く余裕たっぷり。
そんな印象です。
CPU選びというのは単にスペックを追う話ではなくて、自分がどんなふうに時間を過ごしたいかという「暮らし方」と直接重なってくるものです。
数字上の性能はどちらも十分で、ゲーム自体は快適にできます。
でも私の体感としては、仕事から帰ってすぐにパッとゲームを起動して気持ちを切り替えたい人にはIntel、何かを並行しながら効率的に時間を使いたい人にはAMDがしっくりはまります。
迷う時間さえ楽しめるのが趣味の世界ですが、最後はやはり自分がどんなスタイルを選びたいかに尽きます。
私自身は今の生活ではIntelを選ぶのが後悔の少ない選択だと感じていますが、もしこれから動画編集や並行作業が増えるようになれば、AMDの力強さを活かした選択に魅力を感じるようになるかもしれません。
どちらも十分に遊べる性能を備えていることは確かです。
その上で、自分の生活に寄り添ってくれるかどうか。
そこが判断の軸になります。
でも未来の自分がAMDを手に取り、その余剰のパワーを嬉々として使っている場面も想像できるのです。
最終的に重要なのは、CPUのスペック表の数字ではなく、自分が手にしたときに、その日常がどれだけ豊かになるのか。
選択の核心は、そこです。
将来のアップグレードを考えたPC構成のヒント
将来のことを見据えてPCを組むとき、もっとも大切なのは余裕を持たせることだと私は考えています。
一見すると、推奨スペックに合わせるだけで済むように思えるのですが、その場しのぎで組んだマシンは数年後に必ず不自由さをもたらします。
たとえば、別の重めのタイトルを遊びたくなったときや、高解像度モニターに買い替えたときなど、拡張に余地がない構成だとそこで限界が露呈してしまうのです。
そして残念ながら、そのタイミングは唐突に訪れます。
あっという間に、です。
私にとって忘れがたい失敗があります。
数年前、「今はこれで十分だ」と安さを優先した構成を組んだのですが、後にグラフィックボードをアップグレードしようとしたら、電源容量が足りず電源ユニットまで丸ごと交換するはめになりました。
安物買いの銭失いとはよく言ったものだと、そのとき本気で思いました。
あの苦い記憶から学んだことは、最初から少し余裕を見込んで投資しておいた方が、結局は出費もストレスも少なく済むということです。
特にメモリとストレージは、欲張りすぎるぐらいの備えがのちの安心につながります。
今の鳴潮だけなら16GBでギリギリ足りますが、録画や配信を同時に行うなら32GBはあった方がいい。
動作が安定することで、わずかなカクつきに意識を奪われることもなくなり、結果としてゲームの楽しさそのものを存分に味わえるのです。
私は20代のころ、メモリ不足から来る小さな引っかかりに気を散らされて、ゲームの魅力をまともに楽しめなかった時期がありました。
わずかな違いに見えて、実際は大きな違いになる。
これは確かな体験です。
ストレージも甘く見ると痛い目に遭います。
最新のGen.5 SSDは速さが魅力ですが、発熱や価格とのバランスを考えると現実的にまだ難点が多い。
現状ではGen.4 NVMeの2TB程度が最も手堅い選択肢だと思います。
動画のキャプチャデータや重量級のDLCを保存するとき、都度ファイルを削除してやり繰りするのは本当に面倒ですし、ゲームを始めるたびにどこを空けようかと悩むのは余計なストレスになります。
最初から余裕を確保しておけば、そうした煩わしさから解放され、気持ちからしてずっと落ち着きます。
安心感というのは性能表やベンチマークだけでは測れないものですから。
GPUについて言うと、確かに鳴潮を遊ぶだけならハイエンドは必要ありません。
ただ、どうせならケースや電源といった見えづらい部分こそ、妥協しないでおくべきです。
750W以上のゴールド認証電源を積めば、将来的にRTX 5070やRadeonの新モデルへ差し替えるときも慌てずに済みますし、冷却性能の高いケースを同時に選んでおけば夏場も安心です。
私は以前、外観のスタイリッシュさに惹かれてコンパクトケースを選んだのですが、結果としてGPUの熱がこもり、夏はゲームどころではなくなりました。
あのときの部屋はまさにサウナ状態。
苦い教訓です。
デザインより冷却。
結局そこに尽きます。
CPUについてはCore Ultra 7やRyzen 7あたりが扱いやすい中心軸です。
発熱も抑えられ、空冷クーラーで十分に静音性と快適さを両立できます。
ただ、将来的にさらに上位CPUを載せ替える可能性を踏まえるなら、マザーボードで手を抜くべきではありません。
実際に私の知人も、この落とし穴で泣きを見ました。
マザーボードは地味ですが、基盤であり縁の下の力持ちです。
軽視してはいけない。
この数年でゲーミングPC市場を見渡すと、GPUやCPU性能ばかりが話題の中心になりがちです。
でも何度も組み直しを経験してきた私からすると、後から長く効いてくるのは電源や冷却能力、それとストレージスロットの数です。
特にM.2スロットは、最初から2つ以上あることで後の拡張が格段に楽になります。
一見些細に思えるかもしれませんが、マザーボードを買い替えるコストと手間を考えると我慢できる差ではありません。
もちろん、今すべての最高級パーツをそろえる必要はありません。
来年にはさらに性能の良いパーツが必ず出ます。
それを意識して選ぶだけで、無理ない予算の中で長く快適に使えるマシンを手に入れることができ、アップグレードのたびに「やっぱりこれでよかった」と再確認できるのです。
PCを組むのは鳴潮という一本のゲームのためだけじゃない。
これから先、自分の余暇や楽しみを何年も支えてくれる存在だからこそ、少し余裕を前提にした選び方が正解だと信じています。
その選び方が後悔の少ない選択につながり、長く支えになるベースとなるのです。