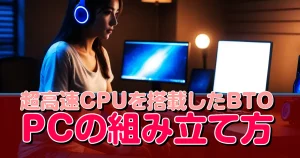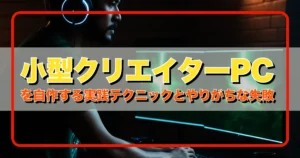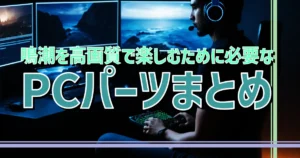RTX5090で30万円台ゲーミングPCを組むときに考えたこと

価格と性能のバランスをどこで取るか
正直に言えば、最新かつ最強クラスのGPUが搭載されたマシンを持つこと自体は憧れです。
しかし同時に、私は40代になり、家計や他の出費とのバランスを重視せざるを得ません。
冷静に価格を調べた瞬間は思わずため息がもれ、笑ってしまうような複雑な気持ちでしたよ。
ただ、落ち着いて整理していくと、30万円台に収めることは工夫しだいで決して夢ではないと気づきました。
結局のところ、最重要なのはお金をどこに集中させるか。
言い換えれば、抜くところと締めるところの見極めです。
私はまず心配したのが、GPUひとつだけで予算を食いつぶしてしまうのではないかという点でしたが、意外にもカギを握ったのはCPU選びでした。
最上位のモデルにこだわらなくても、性能のバランスを壊さずにRTX5090を支える中上位クラスのCPUが十分に存在する。
見栄を張らずとも安定した性能が得られると分かったとき、肩の荷が下りましたね。
メモリやストレージを考えるときも、最初は「せっかくなので上限いっぱい積みたい」と考えていました。
しかし落ち着いて振り返れば、ゲーミング用途なら32GBから64GBもあれば十分ですし、それ以上を載せても過剰投資になりがちです。
SSDについても、最新のGen.5規格に惹かれて心が揺れましたが、コストや発熱を含めたトータルで判断するならGen.4で必要十分でした。
華々しい性能が欲しくなる気持ちは誰しも同じですが、大切なのは長く使える安定感。
私自身「高性能に飛びつくのではなく、必要な範囲で堅実に」という選択に至ったとき、不思議と安心感が広がったのを覚えています。
そう、安定感は何よりの強みなのだと。
冷却も悩みどころでした。
水冷は確かに見た目も美しく、ハイエンドらしい華やかさがあります。
しかし現実的に考えれば、空冷の上位モデルは音も静かで取り扱いが容易。
メンテナンスコストや故障リスクを踏まえると、私がたどり着いた答えは「実用性重視」でした。
実際に空冷を選んでみて、静音性や冷却性能への不満はなく、結果的に正解だったと思っています。
これが40代の私には何よりもしっくりきました。
ケース選びもまた同じです。
派手なライティングや特殊なデザインに惹かれる一方、私が求めたのは冷却性能と堅牢さでした。
風通しが良く、無駄な装飾のないケースは一見地味ですが、日常的に扱う道具としての価値を感じやすいのです。
結果として予算を大幅に削減できましたし、派手さがない分、長く愛着をもって使える存在になりました。
派手さより誠実さ。
ここに自分の性格が出たのでしょうね。
実際に構築を終えて気づいたのは、CPUとGPUの適切な配分が極めて重要だということです。
ここを間違えると全体のバランスが一気に崩れ、宝の持ち腐れになります。
イメージするなら、高級料理店でワインばかりに予算を割いて料理がお粗末になるようなもの。
RTX5090を搭載する以上、それを活かす舞台を整えなければならない。
私はその点で妥協しなかったし、むしろそこに一番のこだわりを込めました。
最終的に私が導いた方針は明確です。
CPUでは無理をしない。
メモリやストレージは必要十分を意識して堅実に。
そして投資すべきはGPU、つまり5090に絞り込む。
攻める部分と守る部分をしっかり分けて考えたときに、予算内で現実的な構成が見えてきました。
冷静に考えればシンプルなことですが、自分の欲望と折り合いをつけるのは簡単ではありません。
でもその葛藤を越えたとき、ようやく「30万円台は可能」という実感にたどり着けたのです。
やはり全体のバランス感覚こそ最も大切です。
高く積み上げすぎれば予算を超えてしまい、削りすぎればGPUが活きない。
決して無謀に40万円台に突入する必要はないし、GPUを足枷にするようなアンバランスも避ける。
それこそが最適解だと今も信じています。
最後にひとつ。
PCは単なる機械ではなく、自分の価値観や性格を反映するものだと思います。
私は見栄ではなく、実直さと堅実さを重んじた選択をしました。
その結果として手に入れたマシンは、華やかではないけれど自分にとって最高の相棒になったのです。
GPUとCPUの組み合わせで実際に迷ったポイント
GPUが圧倒的であるとわかっていたからこそ、CPUの選択を誤れば宝の持ち腐れになるのではと不安が消えず、しばらくは落ち着かない気持ちが続いたのです。
単純にスペック表の数字やベンチマークのスコアでは答えが出ない。
悩みの中心は「Core Ultra 7」と「Ryzen 7 X3D」でした。
スペックと価格のバランスでは拮抗しており、紙の上ではどちらも選ぶに足る性能を備えています。
ただIntelの方は長年の歴史と幅広い最適化による安心感があり、実際の動作も滑らかに感じられるであろう予感がある。
どちらにも引き付けられる要素があり、まるで二人の優秀な部下をどちらのポジションに配置するのが正解かを思い詰めているような感覚でした。
私自身、普段からAAAタイトルやオープンワールドを遊ぶことが多いので、その要求水準が頭にこびりついて離れません。
特に広大なフィールドを移動するときはCPUがワールドを処理し、その後の美しい描画ではGPUが全力で走る。
このリズムを想像しながら「どの瞬間でつまずくだろうか」と考える時間は正直、楽しいよりも疲れるものになっていました。
数字やレビューは参考になっても、自分の場面にそのまま当てはまるわけではない。
このジレンマを痛感しました。
さらに悩みを深くしたのは、私はこのPCを純粋にゲーム専用として使うわけではなかったという事情です。
仕事では動画編集や生成AIの処理を並行して回すことがあり、マルチタスク性能や安定したエンコードの速さも求められます。
ゲーム性能に限ればRyzenに心が傾く。
気持ちが行ったり来たりして、夜中にスペック表を見返すのが習慣になっていました。
見積もりや構成を何度も書き直す中で現実的に見えてきたのは、CPUに投資すれば確かにパワーは増すが、その分メモリやストレージが手薄になるということです。
RTX5090という強大なGPUに頼る以上、環境を制限してしまう要素はメモリ不足やストレージ速度の遅さかもしれない。
気付いたときに「CPUにお金をかけすぎても意味が薄れるのでは」という感覚が強まりました。
そうなんです、組み立てというのは部品同士の比較競争ではなく、システム全体をどう活かすかの思想が問われる行為だったのです。
最終的に私は、突出したハイエンドCPUではなく安定と拡張性を両立する無難なモデルを選び、余った予算をメモリとストレージに配分しました。
これが功を奏して、仕事でもゲームでもストレスのない環境をつくることができた。
RTX5090が持つパワーが桁外れである以上、CPUにすべてを託さなくても十分に余裕を実感できる。
決して簡単に割り切れたのではなく、腹をくくるまでに随分と時間を費やしましたが、答えにたどり着いたときは妙な充足感さえ覚えました。
振り返れば、選ぶ過程での心の揺れはかなり激しいものでした。
深夜、ネットショップのカートを何度も更新しながら「いや、もう一段階上にした方がいいのか」と独り言を繰り返す。
40代になった私がこんなふうにPCのパーツ一つで真剣に悩んで胸を高鳴らせるとは思いませんでした。
若いころの情熱とは違い、今は生活や仕事とも密接につながっているからこそ真剣になれるのでしょう。
安心感の大切さをあらためて知りました。
最強だけを追い求めても、実際の使い方と噛み合わなければストレスになる。
長く安定して、ゲームも仕事も快適にこなす相棒。
その姿を思い描いたときに、肩ひじを張りすぎる構成は不必要だと理解しました。
むしろ心地よい余白を残す選択こそが、大人としての賢さのように思えたのです。
GPUは圧倒的。
CPUは静かな支え役。
その関係はまるで、表舞台で全力疾走するランナーと、それを後ろから律する伴走者のようです。
どちらかが突出するだけでは意味がなく、二人三脚で進むからこそゴールに近づける。
私が選んだPC構成を眺めると、自然にそんな比喩が頭に浮かびます。
最終的に思うのは、PCの部品選びにおいて「性能をできる限り上げたい」という欲望が必ず顔を出すものの、その欲望が正解を保証するわけではないということです。
数値で優劣を決められる分野だからこそ、ランキングやグラフに目を奪われがちになる。
しかし私の場合は、ゲームとクリエイティブの二本立てを心地よく支えてくれる構成こそが勝ち筋でした。
だからこそCPUに過剰な期待を寄せず、全体のバランスを重視した判断が今の満足感につながっています。
納得できる一台が完成しました。
今ではそのPCで日々の仕事を支え、夜には趣味の時間を全力で楽しんでいます。
あのとき無理をして最上位に飛びつかなかったことを思い出すたびに、「これで良かった」としみじみ感じます。
最適な答えは数値の上にはなく、自分の暮らしの中にある。
そのことを、RTX5090と一緒に教えてもらった気がするのです。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 42923 | 2462 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42678 | 2266 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 41712 | 2257 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41007 | 2355 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38483 | 2075 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38407 | 2046 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37176 | 2353 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37176 | 2353 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35552 | 2194 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35411 | 2232 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33667 | 2205 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32811 | 2235 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32445 | 2099 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32334 | 2190 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29174 | 2037 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28462 | 2153 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28462 | 2153 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25380 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25380 | 2172 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23022 | 2209 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23010 | 2089 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20797 | 1857 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19452 | 1935 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17682 | 1814 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16001 | 1776 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15246 | 1979 | 公式 | 価格 |
RTX5090を選ぶときに気になった市場状況と初心者のつまずきやすい罠
RTX5090を導入して痛感したのは、単純に「性能が最高だから買えば良い」という話ではなく、価格と周辺環境のバランスを見誤ると、そのパワーを発揮できないどころか、不満ばかりが積み重なるという現実でした。
しかし同時に、周辺の部品や電源、冷却、そして導入のタイミングを誤れば、とても高い授業料を支払うことになります。
性能だけを追いかけるのではなく、それを支える土台を冷静に作る覚悟が必要なのだと強く学びました。
導入を考え始めた当初、私は価格の変動に翻弄されました。
発売直後の市場は独特の緊張感に包まれ、ほんの数日の違いで数万円も値が跳ね上がることがあるのです。
私が最初にチェックをしたときも、まるでジェットコースターのように価格が上がっていき、気がつけば5万円近く高騰しており、胸の奥がズンと重たくなる感覚を覚えました。
その瞬間、「このままでは30万円台に収まらないかもしれない」と不安で眠れず、夜中に何度もPCの前で価格サイトを更新していた自分がいました。
馬鹿みたいだと笑われるかもしれませんが、必死だったんです。
GPUの実力を十分に生かすにはCPUをどうするかという問題も、思っていた以上に頭を悩ませました。
最初は予算を抑えようとミドルクラスのCPUを組み合わせました。
しかしゲームを実際に走らせると、フレームレートが予想以上に伸びない。
数値は悪くないのに、プレイ中にわずかなもたつきを感じ、胸の中がざわつく。
結局のところ耐えきれずに上位CPUに買い直しました。
GPUに30万円近く払って、CPUをケチるのは本末転倒です。
そう気づいた瞬間、ため息しか出ませんでした。
電源にしても軽く考えてはいけない。
RTX5090の消費電力は強烈で、容量の余裕がない電源を選ぼうものなら、いざというときに不安定動作を起こしかねません。
最初は定格ぎりぎりで足りるだろうと考えたのですが、長時間稼働したあとに突然再起動する悪夢を想像しただけで背筋が冷たくなりました。
それで結局、大容量かつ信頼できるメーカーの製品に切り替えました。
お金を払って安心感を買う。
大げさに思えるかもしれませんが、大人の投資ってそういうものだと今は思います。
パーツの話で見落としがちなものにケースがあります。
私は、正直に言って最初は見た目のデザイン重視で選びました。
それが自慢だったのに、実際に使い続けるとGPUの温度が常に高く、長時間ゲームをすると処理落ちが増えていったのです。
あの時の苛立ちと落胆は忘れられません。
現実です。
ストレージに関しても同じような落とし穴を経験しました。
最新規格のGen5 SSDを見たときは、ベンチマークの数値に心が踊りました。
ですが、実際の利用シーンではゲームのロードが少し短くなる程度で、それ以上の大きな体感差はほとんどない。
必要な場面を見極めることこそが、本当の選択だと悟りました。
振り返れば、RTX5090という存在は単なる一つの製品を超えて、市場全体に心理的な影響をもたらしていると感じます。
圧倒的に高額なフラッグシップを掲げることで、その下に位置する製品が相対的にお得に見えてしまう。
まさに人間の心理を突いたメーカーの戦略です。
気づけば私も同じ罠の中にいました。
冷静に考えればこれは立派な消費者心理の操作だと苦笑せざるを得ません。
こうして経験を重ねてわかったのは、RTX5090を巡る判断で一番大事なのは、周囲の熱気や広告に流されず、自分の基準を持って取捨選択をすることです。
価格の上下に振り回されず、必要な場面に本当に必要な投資をする。
そしてGPUだけを突出させるのではなく、CPUや電源、ケースやストレージといった支えを同じ熱量で整える。
この姿勢を持てるかどうかで、後悔するか満足できるかが分かれると確信しています。
だから私は自分の結論をこう言葉にできます。
RTX5090を選ぶ覚悟とは、単に高性能なGPUを手にすることではなく、それを支える環境全体を誠実に組み上げることへの覚悟です。
高額な投資だからこそ決断には迷いが生じますが、それでもブレない基準を持つことが必要なのです。
相応しい準備なくして最高の性能は活かせない。
その当たり前のことを、ようやく実感できるようになりました。
今、私は胸を張って言えます。
このカードを真に生かす道は、基盤を整え、一つひとつの選択を誠実に積み上げていくこと。
それ以外に答えはありません。
RTX5090ゲーミングPCに合わせるCPU・メモリ構成を決めた過程

Core UltraとRyzenで迷ったときの判断プロセス
RTX5090を中心に据えたゲーミングPCを組むとき、私が強く感じたのは「CPU選びは利用シーンで決まる」ということです。
これは机上の比較だけではなく、実際に使ってみて痛感した現実で、どれだけの時間をゲームに割くのか、それとも動画編集やAI処理といった作業を日常的に行うのかで、選ぶべきCPUは大きく変わってきます。
私は最初、スペック表とにらめっこをしていたのですが、結局のところ数字だけを見ても本質的な答えにはたどり着けませんでした。
使い方を具体的に思い描いた途端に霧が晴れたように整理できたのです。
Core Ultraの一番の魅力は、その万能さだと私は思います。
NPUが搭載されているおかげで、これから数年間でAI関連のツールやサービスが生活の一部になっていく未来を想像したとき、確かに「入れておいて損はない」と安心感が生まれます。
それに加え、放熱の面で扱いやすく、手の届きやすい価格帯の空冷クーラーで安定運用できる点は非常にありがたいです。
実際、Core Ultra 7のKモデルを試しに組んで長時間負荷をかけたことがあるのですが、温度管理に悩むことなく落ち着いて動いてくれました。
頼れる相棒のような存在感でしたね。
安心感。
そう表現するのがしっくりきます。
一方でRyzenは尖っています。
特にX3Dモデルはキャッシュ量の多さが効いて、ゲーム中のフレームレートがしっかりと安定するのです。
その晩、私はRyzen 7 9800X3Dを搭載したマシンでシューターを試したのですが、驚くほど画面の動きがスムーズで、気づいたら声が出ていました。
「これか」と。
思わず笑ってしまうほどの体験で、まさにゲームに没頭する喜びを強烈に感じさせてくれました。
それまでの小さな引っかかりが消えて、まるで肩の力が抜けたような感覚を得られたのです。
ただ、Ryzenを選ぶなら冷却や電源に気を使わなければいけません。
性能が高い分、発熱と消費電力も無視できませんから、電源ユニットや冷却パーツのレベルを下げると痛い目を見ることになります。
その点、Core Ultraは扱いやすく、あまり工夫をしなくても安定的に動いてくれるので、手を煩わせたくない人に向いていると感じました。
40代ともなれば、こういった「手間を減らせる安心感」は積極的に選びたくなるんですよね。
気楽さ。
これが効いてきます。
価格の面でも違いが見えました。
Ryzen 7 9700Xは性能と価格のバランスが優秀で、RTX5090と組み合わせると「まさにこれだ」と思わせる安定感がありました。
コスパ良し。
シンプルですが、この言葉に尽きます。
反対にCore Ultra 9は確かに余裕ある性能でしたが、価格が跳ね上がるため、周辺パーツのグレードを落とさざるを得なくなり、本来主役であるべきRTX5090の力を引き出せなくなるという逆転現象が起こるのです。
選んだのはRyzen 7でした。
理由はシンプルで、私が本当にしたかったのはゲームを快適に楽しむことだったからです。
もちろん動画編集やAIの処理も興味はありますが、そのためにバランスを崩すわけにはいきません。
ゲームに没頭できる環境こそ、私に必要だったのです。
それと、決断してからの気持ちの軽さ。
これが大きかった。
出来上がったPCでプレイしたときの満足感は格別でした。
長時間遊んでも安定したフレームレートが続き、余計なストレスを感じることなくのびのびとゲームの世界に入り込めるのです。
あの快適さは、単に数値で語れる性能だけでなく、バランスよく設計したことによって生まれる「心の余裕」でもあると感じます。
若い頃はCPUの性能を限界まで追求することに夢中になりましたが、今は余裕を残した全体の調和が何より大切だと思えるようになりました。
これは40代になった今だからこそ得られる実感です。
結局のところ、RTX5090という圧倒的なGPUを中心に据える以上、CPUの選び方は「自分が何を求めるか」に尽きます。
徹底してゲームを楽しみたいのか、あるいはゲームに加えて多彩なクリエイティブ分野で活用したいのか。
その答えが「Ryzen」か「Core Ultra」かを決めるのです。
どちらを選んでも大きな失敗にはなりません。
しかし、曖昧なまま選ぶと、後々の不満が積み重なりやすいのは事実です。
だからこそ、自分が何に時間を割くのかを最初に考える必要があります。
私は最終的にRyzenを選びましたが、これはあくまでも私の事情に合っていただけの選択です。
大事なのは、あなた自身がどう過ごしたいのか。
その一点です。
理想のPCを組むための唯一の正解は、自分自身の生活スタイルを基準にCPUを決めること。
そうすれば、RTX5090という主役を余すところなく使いこなし、長く愛せるPC環境を手に入れられると信じています。
DDR5を32GBにするか64GBにするかで悩んだ話
パソコンを組むときに悩ましいのが、やはりメモリの容量です。
RTX5090を中心に構成を考えながら、最後の最後まで32GBにするか64GBにするかで頭を抱えていました。
結果から言えば、私は64GBを選びました。
それが今の自分の仕事と趣味の使い方に最もしっくりきたからです。
ただ、その結論に至るまでの過程は決してすんなりとはいきませんでした。
「32GBでも十分じゃないか」と自分に言い聞かせようとしながらも、心の中で消えない不安が何度もよぎっていたのです。
普段の私はゲームを楽しむだけではなく、同じ時間に動画編集や複数の仕事用アプリを立ち上げることが少なくありません。
32GBでも通常の作業で困ることはまずないと分かっていましたが、もし大きな案件の動画を抱えた状態で余力がなくなったら、そのたびに「あのとき積んでおけばよかった」と後悔するに違いない。
そう考えた瞬間、帰宅後ですら心が落ち着かなくなる自分を想像してしまい、どうしても割り切れなかったのです。
実際に64GBにしてみると、その不安が一気に吹き飛びました。
タイムラインに複数の4K映像を並べてもカクつかない。
Chromeで無数のタブを立ち上げ、その裏でレンダリングが走っていても安定している。
まるで作業机が以前より二倍広くなったような開放感に包まれ、「ああ、もっと早く決断していれば」と思わず声に出してしまうほどでした。
この瞬間ほど、迷いの時間が無駄に思えたことはありません。
最新ゲームを遊ぶ程度なら32GBで全く問題ない。
しかし私の場合はそう単純ではなく、趣味と仕事が入り混じった使い方をしています。
映像編集、資料作成、オンライン会議、同時進行の処理。
それらが絡み合う現実を考えると、最初から余裕を持って構成する方が安心だと強く思ったのです。
私はこの選択を二つの観点から正当化しました。
未来の自分を安心させる投資であること。
そして並行作業をサポートできるだけの土台作りであることです。
パソコンは一度作れば最低でも数年は使い続けます。
その間に後悔したくない。
仕事に置き換えると、優秀な営業社員を雇ったのにサポート体制を整えなかった、といった失敗と同じです。
誰かの力を引き出すには、きちんと支える仕組みが必要なのです。
RTX5090というハードを最大限に活かすには64GBで支えるのが自然だと納得しました。
とはいえ購入直前は指が止まりました。
金額が決して小さくないからです。
「これでいいのか、本当に必要なのか」。
カード決済画面に映る数字が重くのしかかり、何度も躊躇しました。
しかし、どこに投資し、どこを抑えるかを冷静に考え直したとき、性能の要となるグラフィックボードに高額をかけておきながらメモリで手を抜けば、全体のバランスを崩しかねないと気づいたのです。
妥協が全体を中途半端にする。
そう思うと決心が固まりました。
ここが分かれ道でした。
64GBにしたことを深く安心しています。
Chromeのタブを数十枚並べ、動画編集も同時に回し、AI処理も裏で動いていても不安定にならない。
快適さよりも「作業が乱されない安心感」が胸に染みてきます。
余計なストレスに振り回されない日常がこんなにも心強いものかと実感しました。
正直に言うと、自分がここまで迷いを振り切って決断できるとは思っていませんでした。
これまでの自分はどこかで妥協して選択してきたことが多かった。
しかし40代になってようやく、「後悔しない選び方」を優先できるようになった気がしています。
今回の投資は、まさにその姿勢を象徴するものでした。
それは確かです。
でも5年先を考えると、64GBは必須だった。
シンプルだけど強い意味を持つ投資。
そういう選択をした自分を少し誇らしく感じています。
だからこそ断言できます。
RTX5090を本気で活かし切りたいなら、メモリは迷わず64GB。
今の用途に見合わなくても、将来必ず必要になる時が来る。
そのとき慌てて乗り換えるくらいなら、最初から備えたほうが絶対にいい。
安心できる投資です。
もうメモリ不足を恐れて手を止めることはない。
仕事も趣味も、楽しく、のびのびと。
自分の毎日に感じるこの解放感こそが、投資の正しい結果なのだと思います。
答えは明確です。
64GB。
これが私のベストな答えでした。
GeForce RTX5090 搭載ハイエンドPC おすすめ5選
パソコンショップSEVEN ZEFT RTH61U

| 【ZEFT RTH61U スペック】 | |
| CPU | AMD AMD Threadripper Pro 9995WX 96コア/192スレッド 2.50GHz(ブースト)/5.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 512GB DDR5 (64GB x8枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:14900Gbps/14000Gbps WD製) |
| ケース | Silverstone SST-RM52 |
| マザーボード | WRX90 チップセット ASRock製 WRX90 WS EVO |
| 電源ユニット | 1300W 80Plus PLATINUM認証 電源ユニット (ASRock製) |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN EFFA G08F

| 【EFFA G08F スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H9 FLOW RGB ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 360 Core II White |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 1300W 80Plus PLATINUM認証 電源ユニット (ASRock製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT R64E

| 【ZEFT R64E スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X3D 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster MasterFrame 600 Black |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 360 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 1300W 80Plus PLATINUM認証 電源ユニット (ASRock製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60O

| 【ZEFT R60O スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | LianLi O11D EVO RGB Black 特別仕様 |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 1300W 80Plus PLATINUM認証 電源ユニット (ASRock製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60W

| 【ZEFT R60W スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 7950X3D 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | クーラーマスター MasterBox CM694 |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 360 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASUS製 TUF GAMING B650-PLUS WIFI |
| 電源ユニット | 1200W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (LianLi製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | ブルーレイスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
配信やマルチタスク前提で考えたメモリ容量の目安
正直、最初は私もグラフィック性能ばかりに目を奪われていましたが、実際に配信や動画編集を同時に走らせると、CPUだけでなくメモリが足を引っ張る場面が多いのです。
32GBあれば「とりあえず大丈夫だろう」と思いがちですが、実際はそう甘くはありません。
配信を始めた途端に動画がカクつき、画面が止まり、せっかくの性能が無駄になることもある。
そうなると、せっかくのハイスペックPCをわざわざ買った自分自身が嫌になるんです。
私は一度、32GBで構成した環境を使っていました。
動きはする。
けれど「息切れしそうだな」と感じるような頼りなさがあったのです。
わずか数万円の出費で、精神的にも作業的にも劇的に楽になる。
それを体験したときには、思わず「何で最初からやらなかったんだ」と頭を抱えました。
64GBにしてからは、録画しながらのエンコードも安心して実行でき、ゲームのフレームレートもまったく乱れない。
CPUもGPUものびのびと力を発揮して、こちらは余分な心配をせずに過ごせる。
控え選手がしっかり揃ったチームのようで、本当に心強い。
安心感が全く違うんです。
もちろん、128GBという選択肢があることも知っています。
ただ正直に言えば、そこまで必要な環境を持つ人は稀です。
しかし多くの人にとって64GBあれば十分だと私は断言できます。
これは経験からそう言えます。
とはいえ、BTOショップで構成を選ぶとき、どうしても32GBが「標準」として目に入ります。
私自身も「まあ十分かな」と見誤った一人です。
しかしそのときは、配信しながら録画を始めた瞬間に処理が明らかに重くなり、結局後から増設する羽目になった。
増設自体はできますが、無駄な労力を払った感覚が強くて、正直げんなりしました。
最初から64GBを選んでいればそんな後悔はしなくて済んだのに、と今でも思い出します。
配信というのは誰かに見てもらうものです。
だからカクつきやラグは、自分一人の問題ではなく視聴者の満足度をも下げてしまう。
限られた時間での配信がトラブル続きになると「今日はやめておこうか」と気持ちがしぼんでしまうこともあるでしょう。
それこそが一番もったいないのです。
大切なのは楽しい時間をきちんと確保すること。
快適さを犠牲にしてまで妥協する必要はありません。
私の経験から間違いなく言えるのは、RTX5090を搭載した本気のゲーミングPCにするなら、32GBは「最低条件」、そして64GBが「真の選択肢」だということです。
コスパや効率を考えても、このラインがもっとも合理的で後悔しにくい落としどころだと感じています。
余裕が生む優位性。
普段の仕事でも同じですが、リソースに少し余裕を持たせることこそが、安定した結果につながります。
土壇場でバタバタ動いても消耗するばかり。
最初からゆとりを持った準備をするからこそ、余裕を感じながら成果を出せるのです。
ゲーミングPCのメモリ選びもまさに同じで、自己投資を惜しまない姿勢が結局は快適な環境を保証してくれます。
だから、私としては声を大きくして言いたいのです。
RTX5090を本気で活かそうと思うなら、迷わず64GBにしてくださいと。
それがこれまでの私の経験上、失敗しないたったひとつの方法でした。
以上が実際に私が感じ取ったリアルな体験です。
きっと同じように悩んでいる方が多いと思いますが、少なくとも私の場合は64GBを選んだことでゲーム配信や作業環境が格段に進化しました。
RTX5090搭載PCでストレージと冷却に気を配った点

Gen5 SSDを選ぶべきかどうかを自分の用途で考えた結論
私は今回の体験を通じて、RTX5090クラスのゲーミングPCを構築する際には、Gen5 SSDよりもGen4 SSDを中心に選ぶのが現時点では最も賢い選択だと感じました。
カタログに載っている数値は確かにGen5の方がずば抜けていますし、その転送速度を目にすると「これが未来なんだ」と心が動くのも自然です。
ただ、いざ日常的なゲーム体験に落とし込んでみると、その凄さを肌で感じられるシーンは意外と限られている。
この点が現実なんですよね。
実際に自分の環境でGen5 SSDを試してみました。
正直に言います。
最初は胸が高鳴りました。
ベンチマークの数字が画面に並ぶだけで、まるで高性能車を手に入れたような高揚感があった。
でもその喜びは長くは続かなかったのです。
まさに冷水を浴びせられたような逆転劇でした。
いくら性能があっても、熱に弱ければ安定しない。
それはゲーム中に突然パフォーマンスが落ちることを意味し、まるで高速道路でアクセルを踏んでも急に車が加速しなくなるようで、正直がっかりしました。
その点で、Gen4 SSDには大人な落ち着きがあります。
私はWD製の2TBモデルを使いましたが、これが実に安定している。
おかげで「今日も安心して遊べる」と肩の力を抜ける。
この安心感は、使ってみて初めて理解できる大きな価値です。
平日の仕事終わりに数時間続けて遊ぶこともあれば、週末に一気にやり込むこともありますが、そのどちらにおいても温度や速度の不安を感じないのは本当にありがたい。
こればかりは数字以上の実感として響いてきました。
もちろん、未来を考えればGen5 SSDを完全に切り捨てるのは現実的ではありません。
動画や写真を本格的に扱うユーザーにとっては大きな助けになる。
例えば数百GBのRAWデータを扱う場合、Gen5の持つ速度は実務に直結し、効率の差は「わずか数秒」どころではない。
この場合は、投資にしっかりとした見返りがあるわけで、プロやクリエイターには意味ある存在でしょう。
私は現状ゲーム中心の利用ですが、将来的に映像編集に手を伸ばすなら、作業用ディスクやキャッシュとしてGen5を導入する意義は大きいと感じます。
ただし、実際に導入すると課題が明らかになります。
市販マザーボード付属の一般的なヒートシンクでは冷却力がまったく足りません。
負荷をかけると、途端に性能が落ちていくのがモニター越しに見える。
その瞬間、ふと考え込んでしまいました。
「このために追加のヒートシンクや小型ファンを買うべきなのか?投資したコストは本当に快適さにつながるのか?」と。
目の前にあるコストと時間、それが生活全体の満足度に直結するのだと痛感する場面でした。
だから私の結論はこうです。
ゲーミング用途であればGen4 SSDを中心に据え、必要になった段階でGen5を補助的に導入する。
これがコスト、安定、将来性のバランスを最も取りやすい形でした。
そして、ゲームを本気で快適にしたいなら、SSDよりも先にGPUや電源、冷却強化といった根幹部分に投資すべきです。
むしろ余った予算で静音性の高いファンや、信頼できる電源ユニットを選んだ方が断然心強いです。
私はそう実感しました。
実際に導入して数値を見ながら興奮する瞬間以上に、日々の趣味の時間を支えてくれる安定性のありがたみは大きい。
この落ち着いた選択が、40代になった今だからこそ自然にできる判断なのかもしれません。
若い頃なら「速いのが正義!」と即断したでしょう。
数値と現実を冷静に切り分ける力がついた。
これは年齢を重ねたからこその経験値です。
自分の欲望を一歩引いた視点で眺め、最終的に「長く付き合えるもの」を選ぶ。
そういう決断が増えた気がします。
要は、RTX5090を活かす土台にGen4 SSDを据え、余裕ができたらGen5を追加。
この二段構えが今の私の最適解なのです。
試行錯誤を経たからこそ、はっきりこう言い切れます。
安心と安定。
それが心地よく健全な選択だと、胸を張って言えるからです。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
静音性と冷却を両立させるために選んだクーラー
RTX5090クラスのGPUを導入して一番大きな気づきとなったのは、単に性能や冷却性能を追い求めるだけではダメだということでした。
私にとって本当に大切だったのは、毎日使ううえで「ストレスなく扱えるかどうか」でした。
性能がいくら優れていても、動作音が気になって集中力が削がれてしまえば意味がありません。
静かに落ち着いて作業に没頭できる環境こそが、私にとっては最大の価値だったのです。
だからこそ私は空冷を選びました。
正直、今振り返ってもあの選択は間違ってなかったと思っています。
確かに冷却能力は高く、数値だけを見れば「優秀」の一言でした。
しかし、夜の静かな時間に小さなポンプ音が「ジー」と響くたびに、そこでの快適さは大きく削がれてしまいました。
数字上の冷却性能に惑わされたあの経験は、私にとって大きな教訓です。
やはり、性能だけでは語れない世界があるのだと。
静かさがもたらす安心感、それこそが毎日触れるPCに求めるものだと学びました。
心の安定。
まさにそれです。
導入した大型空冷クーラーは、その点で期待以上でした。
静かに見守ってくれるようにファンがゆっくりと回る姿は頼もしくすらありました。
そして高負荷のゲームや3Dレンダリング時でも温度の上昇はしっかり抑制され、耳障りなノイズに悩まされることがありません。
音ではなく進捗に意識を向けられる。
これは私にとって非常に大きな違いでした。
まるで快適さが背中を押してくれるような感覚すらあったのです。
もちろん、冷却はCPUクーラーだけで完結する話ではありません。
ファンの位置、吸気と排気の流れ、ケーブルの取り回し。
そうした一つひとつが連携して機能する時、真価を発揮します。
あの瞬間は思わず「冷却もチームプレーだな」とつぶやいていました。
水冷か空冷か。
この話題はよく聞かれます。
私の答えははっきりしています。
私は空冷派です。
なぜならシンプルで壊れにくいからです。
水冷は確かに冷却力が魅力的ですが、ポンプの寿命や水漏れなど、常に意識せざるを得ない不安がつきまといます。
その点、空冷はトラブルを気にすることが少なく、ファンの交換だけで延命できる安心感があります。
それが空冷クーラーなのです。
頼もしさを感じます。
面白いことに、この「静かさと冷却の両立」というテーマは、仕事の進め方にも似ているなと最近つくづく思います。
効率ばかりを追求していると、ある日必ず無理が出る。
無理をしていると長く続かない。
人間にとっても「心地よさ」や「安心感」が大切で、それを軽く見るとあとでツケを払うことになるのです。
静音と冷却の両立は、仕事と生活のバランスそのものに通じていました。
冷却設計を考える時に意識すべきは、CPUやGPUだけに限りません。
VRMやストレージ、メモリも確実に影響を受けます。
特に高負荷運用を続けていると、数度の違いが致命的な安定性の差となって現れるのです。
私は実際にそれを体感しました。
たった数度低く温度を抑えただけで、安定した稼働時間が大きく伸びた。
そういう積み重ねこそが大事なのだと理解しました。
空冷にして得られるものは派手さではありません。
しかし、日常的な安心こそが本当の価値なのだと気づきました。
実際、静かに動作しているクーラーに日々支えられていると、それ自体が「環境を育ててくれている」ように感じられます。
派手さがなくてもいい。
安心できる存在に勝るものはないのです。
RTX5090や次世代CPUが発する熱は確かに大きいです。
ですが私は迷わず空冷を選び続けます。
「最高性能を求めたい。
でも、疲れない環境で楽しみたい」。
その願いをかなえてくれる道具が空冷クーラーだからです。
そこで得られた静けさが、集中力を最大化してくれると確信しています。
これが私の答えです。
やっと見つけた安定。
静かで冷たい。
冷却不足で実際に起きたパフォーマンス低下の体感談
その瞬間、自分の手で掴んだはずの最先端の力が、熱という見えない敵にじわじわと奪われていくような無力感を覚えました。
正直、悔しい思いでいっぱいでした。
長く楽しめると信じて投資しただけに、心のどこかで自分の判断ミスを責めていました。
ゲームをしていてもその影響は如実に現れました。
FPSの世界では、その一瞬の遅れこそ致命傷。
自分の技術が落ちたのではなく、マシンに振り回されるような感覚は、本当にやりきれませんでした。
「ああ、これじゃ勝てないな」と呟いてはため息をついたものです。
さらに私の記憶に強く残っているのは映像の乱れでした。
激しい戦闘シーンになった途端、画面がカクつき、まるでネット回線が不調になったかのような挙動が起きるのです。
しかし原因は明確でした。
通信ではなく熱の蓄積。
あの時気づいたのは、熱問題を放置すればパフォーマンスの低下に留まらず、高価なパーツの寿命までも確実に縮めてしまうという厳しい事実でした。
数十万円の投資を自分の甘さで無駄にするわけにはいかない、と背筋が寒くなったのを覚えています。
その背景には、自分がケース選びで失敗した事実がありました。
けれど、エアフローが極端に悪く、内部の熱気がこもる一方だったのです。
しかも静音性を優先して吸気を大幅に減らしていたので、結果は想像以上に惨憺たるものでした。
見た目のカッコよさに気を取られ、実用性を軽んじた。
その代償は自分に返ってきたのです。
改善のためには覚悟が要りました。
大型の空冷クーラーを導入し、さらに横から風を送り込む補助ファンを増設しました。
「ファンを数個増やした程度で本当に違うのか?」と半信半疑だったのですが、実際に稼働させたときの変化は衝撃的でした。
GPUとCPUの温度が驚くほど安定し、フレームレートも滑らかに。
以前のように映像が止まることもなくなり、初めてRTX5090が本来持つ力を心ゆくまで体験できたのです。
思わず「よし、これだ!」と口走ったのを覚えています。
その経験を通して理解したのは、冷却を軽く見てはいけないという当たり前の事実でした。
けれどその「当たり前」を本気で体感しないと、人は軽く扱ってしまうのだと痛感したのです。
CPUやGPUはもちろん、SSDなどストレージですら高温にさらされやすい今の環境では、ケースの中で起こるわずかな熱の滞留がシステム全体に影響を与えます。
冷却設計を怠れば、パフォーマンス低下だけでなく予期せぬトラブルにつながりかねないのです。
冷却こそが信頼性の基盤。
私は最近でもSNSで多くの自作PC写真を目にします。
木目調パネルや三面ガラスなど、非常に美しい外観のケースが人気ですが、その中には明らかに排熱経路が不十分な構造のものも見受けられます。
確かにデザイン性の高いケースは所有欲を満たしてくれますし、人に自慢したくなる気持ちも理解できます。
しかし、もしそれが肝心の性能を削ぐのであれば、それは本末転倒。
人の選択でありながら、「惜しいな」とため息まじりに心でつぶやく自分がいます。
ハードウェアの完成度の高さを自分の環境で活かせない、その不完全燃焼感は本当にストレスでした。
しかし対策を講じて負荷時でも安定動作するようになった瞬間、私の胸に広がったのは解放感でした。
「ようやく本来の姿を見せてくれた」、その言葉が自然に漏れました。
冷却を整えることは、ただの技術的配慮ではありません。
長期的に安定して安心して使うための、一番の投資です。
静音性やデザイン性も無視はできないのですが、優先順位を取り違えると結果的に自分の期待を裏切ることになります。
RTX5090のように高額で高性能な製品を導入するなら、まず迷うことなく冷却を最優先に据える。
これこそ、私が身をもって学んだ最も実践的な知恵です。
忘れてはいけないのは、熱対策を先送りすれば努力も資金も一瞬で台無しになるということです。
私は冷却を整えることで安定感を得ましたが、その背景には苦い失敗がありました。
同じ失敗を繰り返す人が少しでも減ってほしい、そんな願いを込めて経験を語っています。
安定感は安心につながるのです。
私がこの体験から伝えたいのはシンプルです。
RTX5090という最高クラスの性能を引き出したいなら、必ず冷却を中心に環境を考えること。
冷却の土台さえ固めれば、どんな場面でも安定してその力を発揮してくれると実感しました。
見かけの良さや静音性も確かに大事ですが、それ以上に冷却こそがすべての前提なのです。
RTX5090用のケースと電源をどう選んだか


ガラス多めのケースとエアフロー重視ケースを比べてみた結果
実際に自作PCを体験してみて一番痛感したのは、最初のケース選びで冷却性能を軽く見ると、後から余計な出費や調整が避けられない、という現実でした。
見た目重視でガラス多めのケースを選んだ時は、正直「おお、やっぱり格好いいな」とテンションが上がったのです。
部屋に置いた瞬間、その華やかさに満足感もありました。
しかし、いざ何時間もゲームを続けると、数字は冷酷に真実を教えてくれます。
GPUの温度はジワジワと上昇し、同じ構成でもエアフロー重視のケースとの差ははっきり出る。
後になって「これは油断してたな」と苦笑せざるを得ませんでした。
ガラス多めのケースの美しさは分かりやすい魅力です。
LEDの光が反射する様子は確かに気分を高めてくれますし、部屋の雰囲気も一気に華やぎます。
ところが、数時間にわたり高負荷で遊んでいると熱がこもり、GPUの温度が平均で5度から7度も上がってしまいました。
でも夜中、静まり返った部屋で「ブーン」と響くファンの音に気づいた時の、あの現実感。
心の中で「これが積もり積もった代償か」と思ってしまいました。
一方で、しっかりしたエアフロー設計のケースを使った時の安定感は驚くほどでした。
その単純な流れが結果的に冷却性能を底上げします。
GPUもCPUも数度下がった数値だけでも安心できましたが、何よりファンが静かに回っている時間が増えたことに感動しました。
深夜に聞こえるのは静けさだけ。
静寂の贅沢。
もちろん、見た目を軽んじたくはありません。
私は家具やインテリアには昔からこだわっていて、デスクは木材調、椅子の張地にも気を配ってきました。
そんな環境にガラスパネルのケースを置くと最初は「浮くかな」と不安でしたが、意外にもLEDが家具に馴染んで映り込み、良い雰囲気になったのです。
この調和を見た瞬間、「なるほど、これはこれで違う価値だな」と感じました。
やはりインテリアとの融合も無視できません。
ただ、いざ冷静にコストを計算してみると話は変わってきます。
ガラスケースの冷却不足を補うためにファンを追加したのですが、温度は確かに下がったものの、出費は増え、ファンの音も増しました。
時間もお金も、後から修正するほどに重くのしかかる。
だからこそ失敗も実感に変わりました。
特にRTX5090のようなハイエンドGPUになると、発熱はまさに暴力的と言っていいほど強烈です。
最新ゲームを全力で動かせば、まるで自分の膝の上にストーブを抱えているような感覚に陥ります。
その熱をケースが処理できるかどうかで、ゲーム体験自体が大きく左右されてしまいます。
没入感を保てるかどうか。
その境界線が冷却性能だと、体で理解しました。
だから私としては結論が明確になりました。
ケースを選ぶ時に一番大事にすべきは冷却性能、その次に見た目。
この優先順位を崩さなければ、大きく後悔することはありません。
コストを抑えながら安定した環境を作りたいなら、エアフロー設計がしっかりしたケースを最初から選ぶべきです。
派手さか実用性か。
この二択で私は実用性を選びました。
今振り返っても、この選択は間違っていなかったと思っています。
とはいえ、人それぞれ大切にしたい価値観は違います。
光り輝くPCを見て「これが欲しかったんだ」と胸が高鳴る瞬間、それ自体が大きな喜びですし、余裕があるならそれも良い選択です。
個人的には、今後デザインと冷却の両方を兼ね備えたケースが当たり前になってくれることを期待しています。
いつか理想のケースが登場すると思うと、正直ワクワクしてしまいますね。
これから自作に挑戦する人に言いたいのは、雑誌やネットで「おすすめ」と紹介されているものをそのまま信じて選んではダメだということです。
自分の部屋の温度や使用時間、騒音への敏感さなど、生活に直結する要素を真剣に考えてほしいのです。
数字の比較やレビュー以上に、リアルな日常との相性が重要になります。
生活習慣との折り合い。
答えはそこにあります。
長年ビジネスの世界で効率を求める毎日を送ってきた私にとっても、今回の経験は新鮮でした。
仕事でも趣味でも結局はそこに戻ってくるんだなと、改めて強く感じました。
GeForce RTX5090 搭載ハイエンドPC おすすめ5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55GY


| 【ZEFT Z55GY スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285K 24コア/24スレッド 5.70GHz(ブースト)/3.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | intel Z890 チップセット ASRock製 Z890 Steel Legend WiFi |
| 電源ユニット | 1300W 80Plus PLATINUM認証 電源ユニット (ASRock製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60V


| 【ZEFT R60V スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 128GB DDR5 (32GB x4枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | be quiet! SILENT BASE 802 Black |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 360 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 1300W 80Plus PLATINUM認証 電源ユニット (ASRock製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT RTH61U


| 【ZEFT RTH61U スペック】 | |
| CPU | AMD AMD Threadripper Pro 9995WX 96コア/192スレッド 2.50GHz(ブースト)/5.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 512GB DDR5 (64GB x8枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:14900Gbps/14000Gbps WD製) |
| ケース | Silverstone SST-RM52 |
| マザーボード | WRX90 チップセット ASRock製 WRX90 WS EVO |
| 電源ユニット | 1300W 80Plus PLATINUM認証 電源ユニット (ASRock製) |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60GJ


| 【ZEFT R60GJ スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 1300W 80Plus PLATINUM認証 電源ユニット (ASRock製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60RC


| 【ZEFT R60RC スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 360 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 1300W 80Plus PLATINUM認証 電源ユニット (ASRock製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
850Wと1000Wの電源で迷ったときの決め手
RTX5090を搭載したゲーミングPCを組むとき、私は1000W電源を選びました。
理由は単純で、850Wでは「不安」がぬぐえなかったからです。
動くのは分かっています。
ただ長年PCを仕事にも趣味にも使っている身からすると、万が一にも電源が足りず作業が中断される状況は、精神的に相当こたえるんです。
だから、1000Wという選択に迷いはなくなりました。
RTX5090はGPU単体だけで見ても消費電力が大きく、そこに最新世代のCPUや複数の高速SSDを足せば、消費電力が一気に跳ね上がるのは想像できます。
本気で動画編集やAI生成に取り組もうと思うと、余裕のなさはすぐに不安材料に変わる。
その場面を思い浮かべてしまうと、「これ本当に850Wで大丈夫か…?」とどうしても疑念が残るんですよね。
たかが電源。
いや、されど電源。
まさにその実感でした。
もちろん、850Wが間違っているわけではありません。
ただ、5080と5090では要求される電力のレベルが違います。
私は自分の用途を考えると、850Wに賭けるのはリスクが高すぎると判断しました。
でも、駄目かもしれない。
その「駄目」の瞬間、失うものは時間や集中力だけではなく、自分の気力まで削られる。
だから妥協しなかったんです。
1000W電源を導入した最初の感想は、「気持ちに余裕ができる」というものでした。
実際に稼働させたときの静かさには驚かされましたね。
ファンの音ひとつとっても、電源に無理をさせないとこうも落ち着くのかと感心しました。
夜中、部屋に一人で作業しているとき、低く一定に回るファン音だけが耳に届く。
雑音がない空間で集中できる幸せ。
静かな安心感というのは、こんなにも大きいものなのかと初めて知りました。
特にハードな作業をしているとき、大きな差を実感しました。
生成AIをローカル環境で試すと、瞬間的に消費電力が跳ね上がります。
私は1000Wに助けられ、これまで作業中に一度も強制終了や再起動に悩まされませんでした。
もし仮に途中で落ちていたら、大事な案件が止まり、数時間の作業が無駄になっていたはずです。
数万円の電源差どころではない損失。
そう思うと、選択の正しさに心から納得できます。
電源は容量が大きければいいという単純な話ではありません。
グレードも重要です。
最低でも80PLUS Gold。
できればPlatinum。
静けさが違う。
これまでGoldを使っていて十分満足していたはずなのに、一度Platinumの世界を知ってしまうと戻れない。
とくに季節の変わり目、ファンの稼働が増えるタイミングでの安心感は格別でした。
「ああ、これが上位認証の力か」としみじみ思いました。
また、長期的に見ても1000Wという選択は合理的でした。
休日の夜、無心でパーツを取り付ける時間こそ私にとっての癒し。
その時間に余計な心配をしないで済むことこそ、最高の価値なんですよ。
余裕の力。
40代に入ると、仕事も家庭も予定外の出来事が次から次にやってきます。
だからこそ、自分で選べる範囲では安心を優先したいんです。
せめてPCくらい、安定して動いてほしい。
心からそう思います。
RTX5090を組むなら1000Wを推します。
ギリギリのPCを回すのは、まるで自分の体を無理に酷使しているようで、いずれどこかで破綻する。
そのイメージと重なりました。
結果、自然と答えは一つに絞られたわけです。
私が本当に伝えたいのは、余力がないことは常に不安と背中合わせだ、ということです。
RTX5090を中心に据えるなら、最初から1000Wを用意しておけばいい。
そうすれば心置きなくゲームも仕事も創作も楽しめる。
それは決して贅沢ではなく、自分の時間を守る合理的な投資です。
心底そう感じています。
見た目と作業性を両立させるために工夫したところ
最初は単純にサイズさえ入れば問題ないと思い込んでいましたが、現実はまったくそう甘くありませんでした。
入るかどうかの話だけではなく、冷却効率やケーブルの取り回し、さらに日々の掃除のしやすさまで考慮しないと、高価なパーツが本来持つ力を発揮できないのです。
私は最初に買ったケースで組み込もうとしたとき、GPUの先端がフロントファンに干渉してしまい、すぐに不安を覚えました。
無理に押し込むような作業はストレスそのもので、これは長く使うには無理があると悟った瞬間でした。
そして、ため息をついて最初からケースを選び直す決断をしたのです。
最終的に行き着いたのが、ピラーレス型の強化ガラスケースでした。
これが思いのほか快適で、配線を裏に回すときの余裕には感動しました。
狭いスペースでケーブルを曲げる必要がなく、自然と手がすっと入り込む。
そんな小さな工夫のおかげで、組み立て作業そのものが穏やかな時間に変わるのです。
私は派手なRGBライティングにはあまり興味がないのですが、このケースは内部設計がすっきりとしていて風の通り道がきちんと確保されている。
結果として見た目も落ち着き、全体がシンプルで整った印象に仕上がりました。
ケーブルマネジメントには特に気を遣いました。
補助電源ケーブルが正面に突き出ていると、せっかくのガラスケース越しの眺めが一気に雑に見えてしまいます。
そこで私はL字コネクタを導入し、ケーブルを横に逃がして背面に回しました。
本当にちょっとした工夫ですが、その効果は大きい。
配線の美しさは単なる自己満足に見えるかもしれませんが、結果として冷却効率まで支えてくれるのです。
見た目も気持ちも軽やかになる。
そう実感しました。
息苦しさをなくす。
これこそが冷却性能を底上げする最優先の要素です。
その熱を滞留させずに流してあげることで、ファンはようやく最大限の力を発揮できます。
私はストレージの搭載位置にも注意を払い、熱を持ちやすいNVMe SSDは最初から大型ヒートシンク付きモデルを選び、なおかつ増設がしやすい位置に設置しました。
この工夫が将来の作業負担を軽くし、長期的な安心につながるのだと心から感じています。
掃除のしやすさも妥協できない部分でした。
以前のケースはフロントパネルを外すのにサイドのネジをいちいち取り外す必要があり、掃除のたびに苦痛を覚えていました。
しかし今回のケースは軽く引くだけでパネルが外れ、驚くほどストレスがありません。
手軽に掃除ができるからこそ、内部を清潔に保ち、結果としてパフォーマンスも落ちにくい。
小さな構造の違いがここまで生活感に直結するのかと実感しました。
私は昔からLian Liを選ぶことが多いのですが、その理由は金属パネルの質感と剛性のバランスにあります。
安っぽさがなく、仕事机の横に置いても違和感がない。
特に私はリビングにPCを置くことがあり、家具に馴染むデザイン性は大切です。
生活に自然に溶け込むからこそ、毎日目に入っても嫌にならない。
やっぱりデザインも大事ですよね。
冷却ファンの制御にも時間をかけました。
私は静音性と冷却の両立を目指し、マザーボードのファンカーブを細かく設定しました。
アイドル時にはほとんど無音に近く、負荷が増すにつれて回転数をじわじわ上げていく。
この効率の良さは、まさに気持ちよさの源泉といえます。
ここを放置している人を見かけますが、正直にもったいないとつい思ってしまいます。
作業性と美観の両立を実現できたのは、強化ガラスによる内部の見せ方を選んだことと、エアフローを阻害しない設計に決断したこと、この二つが大きかったと私は考えています。
ケーブルの処理、ストレージの配置、冷却ファンの設定、掃除の手間。
このすべてを「今の自分に本当に満足できるか?」と問い続けながら作業しました。
その積み重ねが一つひとつ納得を呼び、完成後には深い充実感となって心に残ったのです。
RTX5090のような大消費電力GPUを支えるには、内部の冷却設計と電源の安定が最低条件です。
その上で意識できる余裕をどこに振り分けるかと考えると、やはり見た目にまで気を配ることだという結論に私は至りました。
これこそが完成形だと信じています。
本当にそう思います。
では何が正解なのか。
私の出した答えは明快でした。
RTX5090を長期的に快適に使いこなしたいなら、広い作業空間を持つピラーレス型のケースを選び、ケーブルをきちんと整理し、冷却経路を塞がない設計を徹底すること。
この三つが揃って初めて性能と美しさを両立したPCが生まれるのです。
私は胸を張ってそう言えます。
安心感。
確かな手応え。
RTX5090ゲーミングPCを買う前に自分が整理した疑問


30万円台でRTX5090搭載PCは本当に組めるのか
率直にお伝えすると、30万円台でRTX5090を搭載したゲーミングPCを自作するのは、理屈の上では可能ですが、現実には相当な割り切りが必要になります。
パーツの値段を見比べながら組み上げる作業をしていると、楽しい反面、財布に突き付けられる現実に胃が痛くなる瞬間の方が多いのも事実です。
一番頭を抱えたのはGPUの価格でした。
RTX5090を選んでしまった時点で、予算の大部分がその一枚に吸い込まれていく。
残りのお金でCPUやメモリ、ストレージを整えなければならないので、最初から消耗戦の様相でした。
CPUについては本音を言えばRyzen 9を検討したかったのですが、計算しただけで残りの予算が吹き飛びました。
結果的にはRyzen 7あたりで落ち着かざるを得ない。
正直、「どうしてもこれしか選べなかった」という感覚です。
メモリも同じで、本当は64GBを積んで余裕を持たせたかったのですが、32GBが限界でした。
財布と相談する自分が情けないようで、それでいて現実的な判断だと自分を納得させるしかありません。
ストレージについても、最新のGen.5 SSDに挑戦したい気持ちは強かったのですが、発熱対策や追加費用を考えると手を出す勇気がなく、結局はGen.4の2TBに落ち着きました。
理想と妥協の間で揺れる気持ちは、苦笑いするしかないほど鮮烈でした。
完成に近づくにつれて見えてきたのは、電源という落とし穴でした。
当初は1000Wで十分だろうと高をくくっていました。
ところが消費電力の見直しを進めていくと、その数字では全く安心できず、急いで1200Wクラスに変更。
電源を甘く見ていた自分に「まだ経験不足だな」と苦い思いをしました。
この瞬間、再度全体の設計を練り直す必要が出てきたのは正直堪えましたね。
ケース選びでも同じように悩みました。
最近流行のスタイリッシュなデザインには強く惹かれました。
木製パネルなんて、眺めているだけで所有欲を刺激される。
しかし、支払いの現実と向き合えば選べるわけがない。
泣く泣く、通気性重視でシンプルなケースに決めました。
デザイン性を犠牲にせざるを得ない現実に、「ああ、もっと予算さえあれば」と未練が残るのはどうしようもありません。
それでもPCを起動した瞬間、8Kの映像がレイトレーシングを有効にした状態で滑らかに表示された時には、鳥肌が立ちました。
「うわ、ここまで動くのか」と声が漏れたほどです。
一方で、同時に動画編集や配信を並行するとCPUやメモリの不足が一気に顔を出すので、得意不得意がはっきり分かれる構成になったと感じました。
用途を割り切らずにいろいろやろうとすれば、やはり追加投資は必須だと痛感しました。
印象に残ったのは冷却性能でした。
大型空冷を選びましたが、その静かさには驚きました。
てっきり「やっぱり簡易水冷にするしかない」と思っていましたが、夜中に稼働させても気にならないほど静かなファンが回っていて、その安定感には感動すら覚えました。
偶然とはいえ、これは嬉しい誤算でしたね。
BTOと自作の違いについても、今回あらためて実感しました。
BTOは完成品をすぐに受け取れる安心感がありますが、不必要なパーツや割高な組み合わせに引っ張られることも多い。
仕事帰りにパーツを触りながら、まるで子どものようにニヤついている自分に驚きました。
手間と楽しさ、その両方を味わえるのが自作の醍醐味なのかもしれません。
ゲームだけに特化すると考えれば、30万円台で十分夢のある構成は可能です。
ただし、仕事や複数用途まで期待すると、必ず限界に直面します。
動画編集を生業にする人や長い時間の配信を考える人なら、やはり追加の10万円を投じてCPUやメモリを強化するべきです。
むしろ、その投資を惜しむと後で強烈な後悔がやってくる。
それを肌で感じました。
RTX5090という選択は、最初から「贅沢」か「割り切り」の二択を強要されます。
だからこそ、このGPUの圧倒的な存在感を実感せざるを得ません。
興奮と葛藤。
まさに両方を突き付けてくる存在です。
最終的に私がたどり着いた答えはシンプルです。
しかし万能マシンを求めるなら、そこに固執してはいけない。
自分が何を一番大事にしたいのかを突き詰めること。
そこだけは避けて通れない、と思います。
嬉しさと悔しさ。
それが今回の自作体験のすべてでした。
自作とBTOではコスパがどう変わるのか
RTX5090を前提にゲーミングPCを考えると、やっぱりBTOの方がコスト面で現実的に優位なケースが多いと感じます。
大手ショップが部品を大量に仕入れることで、個人がCPUやGPUを一つずつ選んで買うよりずっと安くなる。
冷静に数字だけ見れば、同じ30万円台を投じるならBTOの方が賢い選択に映ります。
私の経験上、それは間違いなく事実です。
自分が手を動かして一台を作り上げる、その過程にある達成感やこだわりの反映は、単なるスペック以上の価値があると思うんです。
以前、私はケースを選ぶのに異常なくらい時間をかけました。
最終的に木目調のパネルを配したケースを選び、仕事から帰って机に向かうと、その落ち着いたデザインがふっと目に入る。
それだけで心が和らぐ瞬間がありました。
性能には直接関係ありませんが、「これを選んで正解だ」と誇らしく思えた。
正直、あの気持ちはお金に換算できないのです。
冷却やストレージについても触れておきます。
BTOの標準構成は最近かなり優秀で、空冷クーラーで普通の用途には十分冷えますし、すぐに水冷にしなきゃならないわけではありません。
むしろ水冷はコストもリスクも増えます。
SSDについても今のBTOでは大容量のGen.4が標準搭載されていて、体感的にはすでに十分速い。
確かにGen.5は存在感がありますが、価格差や発熱を考えると、決して必須ではありません。
だからBTOの標準構成が結果的に非常にバランスよく落ち着いていると感じる場面が多々あるのです。
とはいえ、自作の魅力を無視するわけにはいきません。
自分の理想に寄せたパーツ選びは、楽しさと同時に独特の充実感を生みます。
例えば最初からメモリを64GB積みたいとか、オーバークロック耐性の高い部品を探したいとか、USBポートの数にまで細かく注文をつけたいとか、その自由度の高さはやはり自作の醍醐味です。
ただしそこには予算超過の罠もあります。
RTX5090自体が20万円超という高額なパーツですから、気を抜くとあっという間に40万円台に到達してしまう。
しかし「これは全部自分で選んだ」という事実。
それは替えがたい誇りになります。
最近では、配信者やストリーマーにBTOを選ぶ人が増えているのも印象的です。
余った資金をマイクやカメラに振り向けて、音質や映像品質を高めていく。
その発想に私はすごく納得しました。
RTX5090搭載のマシンならゲーム配信や動画編集にも困らないわけですし、むしろコンテンツの見え方や聞こえ方が視聴者の満足度を直撃する。
冷静な判断だなと素直に思います。
ただ、BTOも万能ではありません。
私は過去に、BTOで購入したPCの電源ファンが半年で異音を出した経験があります。
保証で直せたので致命的ではありませんでしたが、そのとき学んだのは「コスパを重視しても細部の品質チェックは欠かせない」という当たり前の教訓でした。
RTX5090搭載機が30万円台で手に入るようになったのは実際に凄いことです。
でも重要なのは「安ければいい」ではなく、どこに妥協できるか、どこは絶対に譲れないかを見極める冷静さ。
GPUの性能さえ確保できれば満足なら、BTOで十分満たされます。
けれどデザインに落ち着きを求めたり、静音にこだわったりするなら、自作という選択が自然に浮かんでくる。
私はこの二択をシンプルに捉えるのが最も健全だと考えています。
効率性を突き詰めるなら迷わずBTO。
でも「この手で理想を形にしたい」という思いが強ければ自作に軍配が上がる。
RTX5090という特別な存在を扱うからこそ、自分自身のこだわりを試すべきなんです。
自由と効率のはざま。
心と財布の綱引き。
GeForce RTX5090 搭載ハイエンドPC おすすめ5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60RU


| 【ZEFT R60RU スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 128GB DDR5 (32GB x4枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 360 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 1300W 80Plus PLATINUM認証 電源ユニット (ASRock製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61XD


| 【ZEFT R61XD スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X3D 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H9 FLOW RGB ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ NZXT製 水冷CPUクーラー Kraken Plus 360 RGB White |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 1300W 80Plus PLATINUM認証 電源ユニット (ASRock製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55GW


| 【ZEFT Z55GW スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285K 24コア/24スレッド 5.70GHz(ブースト)/3.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 128GB DDR5 (32GB x4枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | LianLi O11D EVO RGB Black 特別仕様 |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ ASUS製 水冷CPUクーラー ROG LC III 360 ARGB LCD |
| マザーボード | intel Z890 チップセット ASRock製 Z890 Steel Legend WiFi |
| 電源ユニット | 1300W 80Plus PLATINUM認証 電源ユニット (ASRock製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61AHC


| 【ZEFT R61AHC スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X3D 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster HAF 700 EVO 特別仕様 |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 360 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 1300W 80Plus PLATINUM認証 電源ユニット (ASRock製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55GY


| 【ZEFT Z55GY スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285K 24コア/24スレッド 5.70GHz(ブースト)/3.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5090 (VRAM:32GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | intel Z890 チップセット ASRock製 Z890 Steel Legend WiFi |
| 電源ユニット | 1300W 80Plus PLATINUM認証 電源ユニット (ASRock製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
4Kや8Kゲーム以外でRTX5090が必要になる場面はあるのか
確かにその一面は否定しませんが、実際に触れてみると、むしろ仕事の現場で役立つことの方がずっと多いのではないか、と今では感じています。
私自身、40代を迎えてからはゲームより仕事用にPCを酷使する時間の方が格段に多くなりました。
最も強く体感したのはAI関連の作業です。
以前まではクラウドに処理を投げて、結果が届くまでただ待つしかなかったのですが、5090を導入すると考えが変わりました。
ローカルで走らせたモデルの応答が、気持ちの準備をする間もなく返ってくるのです。
大量の処理を短時間で片付けられると、思考と手の動きが途切れず、気持ちが乗ったまま次の作業に進めます。
仕事のリズムを崩さない、これはとても大きな意味を持ちます。
映像編集の面でも、実は私の心をつかみました。
過去に8K映像を同時に複数扱ったとき、旧世代GPUでは読み込み中に何度もため息をついたのを覚えています。
5090に切り替えてからは、目の前で映像がすっと動き、プレビューでのストレスが消えました。
32GBの大容量メモリのおかげで余裕があり、さらに書き出し速度もアップ。
以前の環境と比べて3割ほど早く仕上がることもあり、納期に迫られる制作現場では「これは助かる」と自然に口からこぼれました。
短縮された時間は単なる数字ではなく、集中力と心の余裕を取り戻す時間そのものです。
VRやメタバースの検証も欠かせない仕事の一つですが、この分野でも明確な違いを感じます。
首を動かした瞬間に映像が自然に追従する感覚。
それによって没入感が一切途切れない。
ある日、試しにヘッドセットを装着しながら作業していると、あまりに自然に体が映像に入り込むので「これぞ本物だ」と思わず呟いてしまいました。
わずかな遅延で酔ってしまったり冷めてしまったりするVRだからこそ、この改善は計り知れない意味を持ちます。
そして建築や製造の現場での活躍も見逃せません。
数百万ポリゴン規模のCADデータを扱うとき、従来はレンダリングの合間にコーヒーを入れて一息つくのが習慣となっていました。
ところが5090では読み込み待ちがほとんど消え、その隙間時間すらなくなってしまいました。
正直、「いつ休憩すればいいんだ?」と苦笑したほどです。
しかし、それだけ作業に集中しやすくなったということでもあり、効率の高さは一言では片付けられません。
もちろん「そんなに高性能でも使い切れないのでは?」という声もあるでしょう。
しかし、いざ現場で使ってみると、余裕があることの価値がはっきりとわかります。
余裕があるから何も詰まらず、精神的にも安心できる。
システム全体の構成についても言及しておきたいのですが、GPUがここまで高性能だとCPUやメモリの不足が露呈します。
私の場合はDDR5?5600の64GBメモリとGen.4 NVMe SSDを組み合わせました。
それでようやく本領を発揮する感覚です。
GPUだけに投資しても周辺が足を引っ張るようでは意味がない、これは実務で投資を判断する立場の人間として、声を大にして伝えたい部分です。
パーツの選択は自己満足ではなく、結果に直結する重要な投資判断ですから。
一方で、弱点もあります。
発熱と消費電力はやっぱり気になる。
水冷であれば静かですが、空冷で長時間高負荷をかけると、どうしても耳に残る音が目立ちます。
40代になり、静かな環境で仕事をしたいという自分の性格からすると、あと少し改良してほしいなと思う部分です。
ただし、それを超えるパフォーマンスがあるため、受け入れることもできる。
悩ましい問題ですが、高みに登れば登るほど贅沢な悩みになるものです。
こうして振り返れば、5090はゲーマーの夢を叶えるカードであると同時に、私のようにビジネスで実務に取り組む人間にとっても大きな力になっています。
AI処理、映像制作、VRの検証、CADの現場。
どの領域でも頼れる存在です。
確かに30万円を超える出費は重い。
しかしそれを無駄遣いと見るか、未来の時間を買う投資と見るかで価値は大きく変わります。
私は後者だと考えていますし、仕事を進める上での安心感と余裕を得られたことを実感しています。
数年先まで戦える装備を手に入れたという満足感もある。
安心感があると、人は落ち着いて判断できます。
不思議なほどに信頼できる相棒になるのです。
RTX5090を導入してから、私はそのことを何度も確信するようになりました。
将来のアップグレードを意識して余裕をもたせた部分
将来を考えるうえでゲーミングPCの構成に余裕を残すことは、とても大きな意味を持つと私は思っています。
RTX5090を軸にした組み合わせは、現時点で見れば圧倒的すぎるほど強力です。
しかし、だからこそ他のパーツを最低限で固めてしまうのは危険です。
数年後に「どうしてあのとき余裕を持たなかったんだろう」と後悔して財布を開く羽目になる。
そういう苦い経験を、40代の私はすでに何度か味わってきました。
だから言えるんです。
GPUの豪華さにばかり目を奪われず、それを支える土台こそが数年後の快適さを左右する。
冷静にそう考えています。
私がまず配慮したのはメモリでした。
購入時は32GBを積みましたが、スロットをあえて半分空けたままにしました。
将来的に64GBへと一気に伸ばせるようにしたのです。
この余地を残した設計が、実際の安心感になっている。
動画編集やAI処理といった重たい作業を同時に扱わざるを得ない日が来ても、慌てなくて済む。
40代の私にとって、この「余裕を残してある」という事実が精神的な落ち着きにつながっています。
安心感って、年齢を重ねるほどに大事になってくるものですね。
もちろんGen5の速さには心を惹かれましたが、価格が高く、発熱のリスクもある。
無理して導入しても、今の私が体感できる快適さはそこまで変わらないはずです。
それよりも、将来値段がこなれた瞬間に空いたスロットへ差し込む。
その方が実利的です。
昔なら「とにかく最新を」と飛びついたかもしれません。
でも今は違います。
経験の積み重ねが「身の丈に合った選択」の価値を教えてくれました。
ケースについても悩みました。
RGBが華やかに輝くモデルを前に、心が揺れました。
結果的にこの判断は良かったと思っています。
大型GPUを入れて水冷クーラーを組んでも、内部に余裕があれば空気の流れを妨げないし、配線の取り回しもずっとスムーズに済む。
実際に組み上げた瞬間、「これは正解だったな」と心の底から思いました。
ワクワクしました。
電源についても妥協はしませんでした。
RTX5090を搭載するなら大電力が必要になるのは明らかでしたから、1000Wの容量を選びました。
余裕がありすぎるかな、と思った瞬間もありますが、結果としては正解です。
ピーク時に消費電力が跳ね上がる場面でも不安を感じない。
精神的なゆとりがあるんです。
実のところ、昔は安い電源で済ませて突然電源落ちに怯えることもありました。
もう、ああいう細かい心配とは距離を置きたい。
余裕の電源は生活リズムにも静けさをもたらす。
年齢を重ねるほどに、そういう小さな安心の価値がよくわかるのです。
CPUも、一度は最上位にしようと考えたのは事実です。
でもRTX5090とのバランスを考え、私はCore Ultra 7を選びました。
性能とコスト、両方に納得感があったからです。
なにより、もしも将来さらなるCPU性能が必要になった時に、アップグレードできる選択肢を残せる。
「選択肢を残す」ことは、実はかなり贅沢な安心につながるんです。
いずれにしても今の私の用途には十二分に応えてくれる。
だから充分なんです。
充分すぎるんです。
最上位機種を買って持て余すより、中間モデルを選んで不足なく使い、その次の更新時にステップアップする。
その柔軟さの方が現実的で、結果的に出費を抑えつつ楽しみを継続できます。
今の時代は「全部最高」より「必要なだけ、でも余地は残す」。
この発想が本当に合理的だと思います。
私は今回のPC構成を決めて、自分の中で一つ腑に落ちた感覚がありました。
それは、PCの購入は未来の自分への投資だということです。
余裕を残すことは、実際の拡張性以上に心のゆとりを生む。
豪華さより持続性。
まさにそのバランスが価値を生むのだと強く感じました。
だから言い切ります。
今の時点で最上位を積み上げる必要はないんです。
大切なのは、電源に余裕を持たせること、ケースに広がりを持たせること、メモリやストレージを後から伸ばせるようにすること。
この三つを押さえれば、私は大規模な改造をせずとも5年先まで快適に使えると自信を持って言えます。
でも40代になった今は違う。
未来を意識して余地を残すことの大切さを身をもって理解しました。
しみじみそう感じています。
未来への備え。
これに尽きます。