長時間の動画編集を快適に進めるためのPC構成の考え方

CPUはIntelとAMD、編集作業で有利なのはどっち?
私はこれまで長く動画編集に携わってきましたが、カタログに並ぶ性能表をにらんでも、本当に意味のある答えは出なかったんです。
プレビューが軽いだけでは不十分で、レンダリングが速いだけでも物足りない。
仕事をしている最中に「ああ、今日は楽だった」と感じられる、その空気感こそが一番重要だと身をもって学びました。
AMDのRyzen 9を初めて導入した時の驚きはいまでもはっきり覚えています。
4Kを超える映像を複数重ねて、さらに複雑なエフェクトを試しても止まらない。
プレビューがなめらかに進んでいく。
すると気持ちが途切れず、夜遅くまで編集に没頭できる。
思わず「おお、これは違うな」と声が出たくらいです。
映像編集にとって時間は命ですから、一日の終盤でも集中を維持できることは何よりもありがたい。
これは机上の数値では測れない強さなんです。
とはいえIntelにも確かな魅力があります。
理由はPremiere ProでBRAW素材を扱ったときの安定感。
レンダリングの速さそのものではAMDに優位性もありました。
それでもタイムラインをスクラブする際の「引っかかり」が明らかに減ったんです。
数字上は些細な違いに映るかもしれませんが、その心地よさで全体の効率がむしろIntelの方に傾いたように感じました。
そのとき初めて、効率というのは単に処理速度だけで決まるものではないと腑に落ちましたね。
最近はDaVinci Resolveに関する検証動画が増え、AMD優位という声をよく見かけます。
実際にマルチコア性能とGPU性能をあわせて使える場面ではRyzenのパフォーマンスが本当に頼もしい。
8K編集まで現実的に運用できることがある。
この勢いは編集者に勇気を与えてくれるんです。
深夜に一人で仕上げ作業をするときに「これなら走り切れる」と背中を押してくれる心強さ。
安心して突き進める環境でした。
一方で、IntelのQuick Syncは侮れません。
思い返すと、納期直前に十数本の動画を一気にエクスポートしなければならなかった案件がありました。
胃が締め付けられるような緊張感のなかで、Quick Syncのエンコード性能に心底救われたんです。
書き出しが想定以上に早く進み、間に合わないのではという焦燥から一気に解放された瞬間は忘れられません。
こういう実体験があるからこそ、現場での安心感につながっているのだと思います。
今でも「あのとき助けられたな」とつぶやいてしまうことがあります。
では最適解はどちらなのか。
長編映像や高負荷のレンダリングを日常的に行う人にとってはAMD Ryzenが抜けています。
しかしPremiere Proなどで短尺案件を多数処理する人や、Quick Syncを活かして大量の動画を短時間でエクスポートするニーズが強い環境ではIntelに軍配が上がる。
大切なのは、「安定して結果を出すことができる」という一点に尽きるんだと思います。
どちらのCPUもその条件を満たしているからこそ、必要に応じて選び分けることが意味を持つのです。
私の場合、現在はAMDをメインに使っています。
長編の案件が増えたこと、複数のソフトを同時に動かす状況が当たり前になったことが大きな理由です。
ただ実際には、案件ごとにIntelを引っ張り出して併用する場面もまだあります。
それが精神的な余裕にもつながっている。
選べる選択肢があるから、自分自身の作業に集中できるんです。
40代になってから特に、この「切り替えの自由」がありがたいと感じるようになりました。
道具に助けられている安心感ですね。
最終的には、どんな働き方をしたいかに答えは集約されると思います。
数字の比較やレビューの評価はあくまで参考程度にとどめ、自分の仕事の流れを丁寧に振り返ったうえで選ぶことが大切です。
私はこう捉えています。
Ryzenは力強く背中を押してくれる存在、Intelは緊張する現場で最後に支えてくれる相棒。
結局のところ、どちらも頼れるCPUです。
CPU選びで迷うときは、一度深呼吸して、自分がどういう毎日を送りたいのかを考えてみる。
その瞬間に、自分が求めてきた答えが見えてくるんだと思います。
私はそう信じています。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 42923 | 2462 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42678 | 2266 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 41712 | 2257 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41007 | 2355 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38483 | 2075 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38407 | 2046 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37176 | 2353 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37176 | 2353 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35552 | 2194 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35411 | 2232 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33667 | 2205 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32811 | 2235 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32445 | 2099 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32334 | 2190 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29174 | 2037 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28462 | 2153 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28462 | 2153 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25380 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25380 | 2172 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23022 | 2209 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23010 | 2089 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20797 | 1857 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19452 | 1935 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17682 | 1814 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16001 | 1776 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15246 | 1979 | 公式 | 価格 |
グラボ選びで書き出し速度はどれだけ変わるのか
私自身、業務で長時間の映像を扱う機会が多く、その待ち時間がどれだけ精神的にも肉体的にも消耗につながるかを痛感してきました。
そしてはっきり言えるのは、グラフィックボードを適切に選ぶことで、そのストレスを大幅に減らせるということです。
特に4K以上の高解像度映像を扱う場合、CPUの力に頼り切るやり方では明らかに限界があり、性能の高いGPUを導入すれば効率が劇的に改善されるのです。
かつて私は「CPUさえ強ければ編集作業は快適に回るはずだ」と信じていました。
けれど、それは大きな勘違いでした。
GPUの性能が低ければ、結局のところ作業全体がCPUに偏ってしまい、せっかく高速なメモリやストレージを揃えても思ったほどの効果は出ませんでした。
まさに焼け石に水という状況です。
その教訓を学んでからは、システム構築において最初に検討するべきはGPUだと強く思うようになりました。
自宅の環境を実例として挙げるなら、私はRTX4060からRTX4070Tiに切り替えました。
正直、その結果には驚かされましたよ。
同じプロジェクトをレンダリングしただけで、30分以上かかっていた作業が10分程度に短縮されたのです。
この短縮は単なる数字の変化ではなく、仕事全体のテンポを支える大きな力になりました。
さらに安定性も格段に向上し、以前はエンコード途中で処理が止まってしまうこともありましたが、それがきれいさっぱりなくなったのです。
信頼できる相棒を得た、そんな感覚でした。
処理速度の向上だけでなく、作業中の気持ちの余裕までも変わりました。
「ああ、やっと仕事のリズムが戻ってきた」と心から思えました。
もちろん、PC全体のパフォーマンスはGPUだけで決まるわけではありません。
メモリ容量やストレージの速度も無視できない要素です。
ただ私の実感として、最初にきちんと投資すべき場所はGPUだと断言できます。
動画編集においてGPUは純粋にエンジンです。
ハードウェアエンコード機能の有無が処理時間を大幅に変えてしまうことを考えれば、このパーツこそが作業効率の要であることは明らかです。
ノイズの自動除去、色味の自動調整、被写体の切り抜きなど、以前は数十分かかった作業がボタンひとつで完了してしまう。
便利です。
ただ、その裏でGPUには膨大な計算が常時走っています。
生成AIが膨大な処理能力を消費するのとまったく同じで、結局はGPUをどれだけ賢く選ぶかで効率の差が大きく広がるのです。
とはいえ不満もあります。
それは熱と騒音です。
フル稼働状態ではGPUは明らかに発熱し、デスク下はまるで足元から温風ヒーターが当たり続けているかのようになります。
その熱気に参ってしまう瞬間が正直あるんです。
冷却ファンの音も深夜の作業中にはなかなかの妨げになる。
快適さを求めるなら、ここは無視できない課題ですね。
次世代GPUが省電力で静かに回るようになれば、もっと理想に近付くと思います。
実際に導入を検討している方に向けて言うなら、どのクラスのGPUを選ぶかは用途によって変わります。
フルHDの映像編集が中心なら、ミドルクラスで十分対応できます。
しかし4Kの長尺編集を日常的に行うなら、RTX4070以上、できればRTX4090あたりまで視野に入れるべきです。
価格を見て思わずため息が出るのは私も同じでした。
ただ、時間という資産を購入していると考えれば、その投資は決して高くはありません。
そう割り切れるかどうかが大きなポイントです。
結局大切なのは予算の割り振りの優先順位です。
CPUやメモリを強化してもGPUがボトルネックなら全体の効率は頭打ちになります。
だから私は最初にGPUに資金を割くべきだと強くお勧めします。
その判断は日々の作業効率を引き上げ、ストレスを明らかに減らしてくれる。
これは私の経験から断言できます。
動画編集は単なる作業ではなく、時間との戦いです。
その限りある時間をどこに使うかによって、成果物の仕上がりも自分自身の精神状態も大きく変わります。
GPUに投資することはその戦いに勝つ確率を高める行為だと、私は実感しました。
だからこそ今から環境を整えようという方には強調したいんです。
「GPUだけは妥協しないでください」と。
数字や性能表では表現しきれない価値が確かに存在します。
高性能なGPUは単なるパーツではなく、日々の作業を支える相棒です。
机の下で地道に全力を発揮してくれる姿を思うと、感謝の気持ちすら湧いてきます。
価格の迷いよりも作業効率にかける思い。
その選択こそが正解だと今では心から思えるのです。
最後に。
書き出し時間で悩んでいるなら、ぜひ良いGPUの導入を検討してください。
未来の自分が「ありがとう」と必ず言ってくれるはずです。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 48533 | 101751 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32047 | 77933 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30055 | 66640 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 29978 | 73293 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27075 | 68805 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26420 | 60131 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 21879 | 56698 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19855 | 50392 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16507 | 39301 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 15942 | 38131 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15805 | 37909 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14592 | 34857 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13699 | 30804 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13160 | 32303 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10787 | 31685 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10617 | 28534 | 115W | 公式 | 価格 |
メモリは32GBと64GB、実際に作業すると体感は違う?
結論を言えば、長編動画やクリエイティブ案件に本気で取り組むなら64GBを選ぶべきだと強く思っています。
表面的には数字の大小に過ぎないのですが、実際に現場で作業する立場からすると、その違いは机上の話では済まされないほど大きいのです。
これは単なるスペックの比較ではなく、仕事のテンポや精神面にまで影響を及ぼす話だと断言します。
フルHD編集や簡単なエフェクト処理くらいなら確かに大きな不満は出ない。
私も以前はそう信じて疑わなかったのですが、60分を超える長編案件に差し掛かったとき、タイムラインを動かすたびに映像がカクつき、プレビューがまともに進まず、焦りを通り越して仕事の流れそのものを壊されました。
正直な話、20年以上社会人を続けてきた私でも、このとき感じた心臓のざわつきはなかなか忘れられません。
あの「待たされる」感覚こそクリエイティブに最も邪魔になるんです。
全く同じプロジェクトを開いても、再生は滞りなく滑らか。
プレビューで止まることもなく、After EffectsやPhotoshopを同時に動かしてもストレスにならない。
たとえ重たいコンポジションを投げてレンダリングさせても、その間に他の作業を進められる──これがどれほど大きな違いか、現場で一度でも味わえば痛いほど分かります。
効率という言葉がただの概念ではなく、はっきりと実感できた瞬間でした。
確かに、64GBをすべて使い切る場面はそれほど多くないかもしれません。
それでも「余裕が残っている」という事実が、私にとっては精神的な後ろ盾になります。
例えるなら、航続距離に余裕がある車を運転している安心感と同じ。
必要になったときに困らない、その心の余白がどれほど仕事に集中させてくれるか。
安心感が背中を押してくれるんです。
ここまで考えてきて、では32GBと64GBのどちらを選ぶべきか。
答えはシンプルです。
日常的なSNS用の短編や数分の軽い案件であれば32GBで十分ですし、無理に投資をする必要もないと思います。
しかし、腰を据えて取り組む長編企画や複数のソフトを並行して使うような案件に挑む人であれば、64GBへの投資は避けて通れない。
本気でやるなら妥協してはいけない領域だと断言します。
これは贅沢ではなく、むしろ必要経費。
仕事を止めないための保険だと私は捉えています。
あの日、締め切り前に32GB環境で作業が止まり、冷や汗をかいた経験が忘れられません。
切羽詰まった場面でパソコンが足を引っ張る。
あれほど無力感に襲われる瞬間はなかなかない。
だからこそ64GBに切り替えて以降、同じ緊張感の中でも「もう環境に振り回されることはない」という自信が胸の奥に宿ったんです。
これは数値や処理速度の問題を超えて、私の心の安定にまで関わってきました。
まさにそういう存在になったわけです。
私はこれまで何度も機材選びに迷い、そのたびに「本当にここまで必要なのか」と自問自答してきました。
けれども、仕事を続けてきて実感するのは、スペックに余裕を持たせることは決して無駄ではないということです。
むしろ余裕こそが仕事を守る。
これは現場に立つ者にしか分からない感覚かもしれません。
机の上で数字を並べただけでは想像できない現実があるんです。
ITの世界は日進月歩で、来年にはさらに高性能な環境が当たり前になっているかもしれません。
しかし、不思議なことに「余裕が仕事に与える影響」は時代が変わっても普遍的です。
たとえ処理能力が飛躍的に進化しても、作業が詰まり動かなくなる瞬間は必ず訪れる。
そのとき私たちを救うのはスペック表の数字ではなく、余裕を持たせた選択をしていたか否かに尽きるんです。
結局のところ、私は未来に投資する意味で64GBを強く推します。
ですが、もしあなたが本気で長編や複数同時処理に挑むのであれば、この選択を後悔することはまずありません。
その差を決めるのは、わずか32GBの違いかもしれませんよ。
そう思うからこそ、私は声を大にして伝えたいのです。
スペックに迷ったら、余裕を買う発想を持ってください。
現場の私が胸を張って言えるのは、この一言に尽きます。
編集作業を支えるストレージ運用のリアルな工夫

Gen4 NVMe SSDとGen5 SSD、用途ごとの使い分け方
新しいもの好きな人ならGen5 SSDのスペック表の数字を目にしただけで心が動くでしょうし、私も最初はそのひとりでした。
しかし冷静に仕事に落とし込んで考えてみると、その性能を実際に必要とするケースは本当に限られているのが現実なのです。
私の業務は映像編集が中心で、4Kはもちろん、時には6Kの素材を扱うこともあります。
こう書くとかなりヘビーな負荷に耐えられる環境が必要に思えますが、正直に言うとGen4 SSDを使っていて速度に不満を感じたことはほとんどありません。
昨年のことですが、納期が詰まっている案件で膨大な4K60p素材をPremiere Proで扱った時、作業ディスクとシステムディスクをGen4で分けて運用しました。
睡眠時間を削って徹夜で進める中、「まあ、このスピードなら心配はいらないな」と心底思ったのをよく覚えています。
重たいプロジェクトでも問題なくこなせたあの安心感は、経験上とても大きいものでした。
一方でGen5 SSDも好奇心から何度か試しました。
理論上は1万MB/sを越える数字を叩き出せると聞けば「これは次世代だ」と期待してしまうのは自然なことです。
ところが、実務で映像を扱うとその期待はすぐに冷めることになりました。
例えば8KのRAW映像を長時間コピーするような極端な場面では確かに光るのですが、普段の編集作業では能力を持て余す結果になるのです。
さらに困ったのは発熱でした。
高性能モデルを導入して大量データをコピーしていたら、あっという間に温度が上昇して速度が急落。
慌ててヒートシンクや小型ファンを追加したのですが、「いやいや、仕事より温度管理に神経を使ってどうするんだ」と思わず独り言が漏れたほどです。
余計なトラブルを招きかねないと改めて痛感しました。
もちろん業界の流れを見ればGen5の本格普及は時間の問題だと感じます。
各社とも冷却技術や新しいマザーボード設計を進めていますし、ソフト側もこれから高性能ストレージを前提にした設計になるでしょう。
その未来はすぐそこまで来ています。
私も十数年前にHDDからSSDに切り替えた頃の衝撃を今でも鮮明に覚えていますが、あの時のように「もう後戻りできない」と感じる日はGen5でも確実に訪れるはずです。
ただし、それが「今なのか」と問われれば、まだ答えはノーだと思っています。
私が今一番強調したいのは、通常の動画編集や納品作業ではGen4で十分事足りるという現実です。
数年前までは「待ち時間=仕方ないもの」だったレンダリングやコピーが、すでにGen4の7,000MB/sクラスでほとんど解決されています。
無理にGen5を導入しても、高い投資に見合う効果を得られる人は少ないでしょう。
そういう時だけGen5を導入するのが合理的です。
これが私の実感としての答えです。
仲間と話す機会も多いのですが、皆だいたい同じ結論に行き着きます。
「数字的にはすごいけど、自分たちにはまだ必要ないな」という感覚です。
一方で高額予算を抱える大手制作会社ではテスト導入が進んでいて、やはり使い方の違いが投資の是非を分けています。
結局は用途に尽きる、そう感じます。
だから私は後輩にも「焦って買い替える必要はない。
まずはGen4を使いこなせ」と伝えるようにしています。
現場で汗をかいている彼らの顔を見れば、余計な不安を与えるより実用性を優先すべきだと心から思うのです。
ただ、人間というのは新しいものに弱いですよね。
私も正直言うと、Gen5やその先の規格が発表されるたびに情報を追いかけては「次はどう進化するんだろう」と楽しんでいます。
触れて試してみることで未来を実感できるのは確かに面白い。
新しいものに触れる高揚感と、日常の業務の現実。
その両方を天秤にかけ続けることこそが、堅実な機材選びに結びつくのです。
要するに今は、Gen4を基軸にして必要に応じてGen5を追加する。
そのバランスが現場に最もフィットします。
確かに長い目で見ればGen5が主役に座る時代がやってくるはずです。
ただ、私たちが本当に重視すべきことは華やかなスペック値ではなく、「仕事に穴を空けないこと」「締め切りを守ること」です。
その信頼に応えてくれるのは、現状では間違いなくGen4 SSDだと断言できます。
納期に間に合う安心感。
だから私は今日もGen4を主役に据え、必要な場面でだけGen5を補助的に使っています。
それだけで安定した作業環境を維持でき、余計な発熱や設定に気を取られることもありません。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
動画編集用ストレージ容量、1TBと2TBならどちらが使いやすい?
もちろん1TBでも作業自体はできますし、最初のうちは「まあ大丈夫だろう」と考える人も多いと思います。
しかし仕事として長時間向き合っていると、やはり容量不足に直面してしまうのです。
素材が増えていけば管理に追われ、外付けドライブを持ち歩くストレスに悩まされる。
私はかつて1TBのSSDで編集を回していました。
導入直後は動作に不満もなく、少し安心感すらありました。
ただ数か月で現実が追い付いてきました。
4K映像を扱うようになると一気に空き容量が足りなくなり、キャッシュや一時ファイルの積み重なりでプレビュー画面すらカクつくようになった。
焦る気持ちを抑えながら外付けドライブを繋ぎ、作業ごとにファイルを退避させる。
正直、その繰り返しの日々には心底うんざりしました。
編集作業の大敵は、集中の途切れです。
作業中にファイルを探し続けたり、中間ファイルの生成を待ったり、保存先を都度確認したり。
作業が中断されるたびに思考が分断され、自分のリズムが一度壊れる。
数分のロスでも、一日積もれば明らかに能率が下がるのです。
だからこそ私は思い切って2TBのSSDに切り替えました。
その瞬間から世界が変わったようでした。
タイムラインを編集しても動作が遅くならず、キャッシュ処理も見事に早い。
保存先を迷わずに済み、作業が途切れなく流れていく。
ここまで快適になるのかと、最初は驚きとともに心から安堵しました。
趣味でやるのであれば1TBでも使い切れるでしょう。
短いYouTube動画を撮って編集し、すぐにプロジェクトを削除するようなスタイルなら大きな不満は出ないと思います。
ただ、長編作品や複数案件を並行する編集者にとっては1TBは余りに狭い。
容量に余白があると不思議と気持ちにも余裕が生まれ、一つひとつの判断に落ち着きが出る。
これが意外に大切なのです。
私が導入したのはWestern DigitalのSN850Xでした。
ベンチマークの数値などより、作業中の動作が滑らかであることの方が何倍も価値がありました。
プレビュー再生の途中で手が止まらず、息をつきながら読み込みを待つ時間もなくなった。
あの小さなストレスから解放されるだけで、作業全体が圧倒的に快適になります。
もう前の環境には戻れません、と心から思いました。
実際にこうした積み重ねが最終的に作品の出来に影響します。
数秒の待ち時間でも繰り返せば数十分にも及ぶ。
そこで集中力が散漫になれば精度も落ちる。
クオリティを少しでも高めたいのなら、まずは環境を整えることが順序として大事なのです。
私はその痛みと効果を経験したからこそ断言できます。
つまり短期的に動画編集を楽しむだけなら1TBでも問題はありません。
しかし長期的に、しかも複数のプロジェクトを同時に抱えるとなると1TBはあっという間に限界を迎えます。
2TBにしておけば納品データやバックアップを安心して保存でき、余計な神経を使わなくて済みます。
その安心感があるからこそ本当の意味で制作に力を注げるのです。
悩んでいた頃を今振り返ると、答えは最初から明快でした。
仕事で使うなら迷わず2TB以上。
動画の面白さや作品づくりの喜びを、容量不足のイライラにかき消されるのは本当に勿体ないことです。
結局、道具に投資することは自分自身の可能性に投資することと同じでした。
安心できる環境。
ストレスのない流れ。
この二つが揃って初めて、プロとして本当に納得できる仕事ができるのだと私は実感しています。
迷わず2TBを選んでほしい、と。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45DBX

鋭敏なゲーミングPC、プロ並みのパフォーマンスを実現
バランスよく配されたスペックで、どんなゲームもスムーズに
クリアパネルが魅せるコンパクトな省スペースケース、美しく収まる
Core i5が織りなす、無限の可能性を秘めた処理能力
| 【ZEFT Z45DBX スペック】 | |
| CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | INWIN A1 PRIME ピンク |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 ROG Strix B760-I GAMING WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60BX

| 【ZEFT R60BX スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7800XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6300Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H9 Elite ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ホワイト |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASUS製 TUF GAMING B650-PLUS WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55DF

| 【ZEFT Z55DF スペック】 | |
| CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster NR200P MAX |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 ROG Strix B760-I GAMING WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R55AE

研ぎ澄まされたパフォーマンスが際立つ、アドバンストスタンダードのゲーミングPC
コスパ抜群!64GBのメモリと最新RTXが織り成す驚異のスペックバランス
Pop XLのケースに、RGBの輝きが宿る。大迫力のデザインながら、洗練されたサイズ感
新時代を切り拓くRyzen 5 7600、スムーズなマルチタスクをコミット
| 【ZEFT R55AE スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen5 7600 6コア/12スレッド 5.10GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7300Gbps/6600Gbps WD製) |
| ケース | Fractal Design Pop XL Air RGB TG |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASUS製 TUF GAMING B650-PLUS WIFI |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
SSDの発熱対策と速度低下を防ぐための小さな工夫
SSDの発熱対策として私が最も効果的だと実感しているのは、やはりヒートシンクの取り付けです。
過去の経験から、これは単なるパーツの付け足しではなく、必須の投資だと確信しています。
取り付けを怠ると、せっかく高額をはたいて手に入れた高速SSDが本来の性能を維持できなくなり、結果として時間も労力も無駄になります。
特に動画編集や大容量データの扱いでは、一瞬で温度が上がり速度が落ち、作業が中断されるような事態も普通に起こってしまいます。
焦りと苛立ちが混じった、あの手に汗握る瞬間は、もう二度と味わいたくないものです。
私もかつて、気合を入れて導入したNVMe SSDで手痛い思いをしました。
初めのうちは「これで生産性が一気に跳ね上がるぞ」と胸を張っていたのですが、4K映像をエンコードした途端に性能が失速し、転送速度が見る見る半減。
まるで暴走したスマホが熱で性能を制御するのと同じ光景で、正直呆然としました。
その安堵感と「ああ、最初から冷やしておけば良かった」という悔しさは今でも鮮明に覚えています。
実際にやって効果を感じたのは二つ。
まずはM.2 SSD専用ヒートシンクをしっかりつけること。
そしてケース内部の空気の流れをきちんと整えることです。
特に後者については、最初の私は軽く見ていました。
正直、ファンを数個つけておけば充分だろうと思っていたのです。
しかし実際には、ファンの位置を数センチずらしたり、回転方向を一つ変えたりするだけで、目に見えて温度が数℃下がる。
しかもその作業は手間も費用もほとんどかかりませんでした。
なんで早く気づかなかったのかと、思わず苦笑しました。
さらに、私が声を大にして伝えたいのは、作業用とシステム用のSSDを分けて使うことです。
最初の頃は一台のSSDに全部を詰め込んで、さあ快適だと思っていたのですが、実際にはOSと同時に素材やアプリを扱うことで温度が不安定になり、かえって効率が落ちることの方が多かったのです。
分けることで負担が軽くなり、熱も分散され、スムーズさが格段に違う。
これはもう「ちょっとした工夫」ではなく「基本」ですよ。
最近では次世代のPCIe Gen5 SSDにも興味を持っています。
確かに数値上の速度はすさまじいですが、同時に発熱も桁違いです。
小さなヒートシンクでは無理があり、中にはSSD本体に小型ファン付きクーラーを標準搭載した製品まで出てきています。
その姿を初めて見たときには「ここまで来たか…」と少し笑ってしまったほどですが、それほど冷却の重要性が切実になってきているのを痛感します。
高速と安定、そして静音性。
その三つを両立するためには新しい解法が必要になると実感しています。
私はここまでの経験を通じて、SSDを冷却なしで全力稼働させるのは危険極まりないと身をもって感じました。
短時間だからと油断したときほど痛い目にあいました。
発熱はそのまま不調の入り口。
だからこそ、快適に長時間の作業を続けるためには冷却環境を最初から備えておくことが、何よりの保険なのです。
SSDは冷却あってこそ実力を発揮します。
ヒートシンク取り付け、ケース内のエアフロー最適化、そして用途別のSSD使い分け。
この三つを組み合わせれば、速度低下やサーマルスロットリングの不安は一気に減り、大きな安心が得られます。
結果的にストレスを抱えず作業に集中でき、生産効率も精神的な余裕も高まるのです。
いわば快適さそのものが変わる。
私は以前、単なる部品交換で十分だろうと考えていました。
しかし実際には「空気の流れ」という目に見えない要素がパソコン全体の安定性を大きく左右し、SSD一つの冷却だけでも作業感覚が見違えるほど改善されるのだと痛感しました。
この事実を知って以来、私は冷却対策を「快適な作業環境のために絶対外せない投資」と位置づけています。
そしてこれは、単に速度を守るだけでは終わりません。
長寿命化にも直結します。
同じSSDをできるだけ長く安定して使い続ける、そのためにも冷却は欠かせないのです。
投資の回収をきちんと果たすという意味でも見逃せない。
結果として、慌てず焦らず落ち着いて成果を出すための基盤になるのです。
安心できる環境。
信頼して任せられる道具。
冷却対策を真剣にやるかどうかで、作業の質は大きく変わります。
SSDを万能の存在として過信せず、あらかじめ冷却を前提に組み立てる。
そうしてこそ、私は穏やかに、そして効率的に仕事を進められるのだと強く信じています。
冷却と静音で変わる作業しやすさとPCの安定性

CPUクーラーは空冷か水冷か、実際どちらが扱いやすい?
CPUクーラーを選ぶときに私が強く思うのは、やっぱり空冷に落ち着いてしまう、という事実です。
派手さや新しさには惹かれる気持ちもあるのですが、日常的に業務で使う立場としては結局「長く安定して動いてくれること」が優先順位の一番上に来てしまいます。
空冷は取り付けもシンプルで、何より使っている間に不安を感じにくいのが大きな強みです。
正直に言ってしまえば、水冷の魅力も十分理解しています。
見た目の格好よさ、ケースに組み込んだときの存在感は抜群です。
しかも冷却効果も高く、CPU温度がぐっと下がるのは事実です。
ただ、実際に使い込んでみると「良さ」だけでは済まされない部分も出てきます。
私が数年前にオールインワンの水冷を導入したとき、最初の数週間は「すごいな」と感激していました。
ところが数か月も経たないうちにポンプの振動音が耳に残るようになり、作業中に思わず気が散るようになってしまったんです。
仕方なく空冷に戻したのですが、そのときの安心感は今でも忘れられません。
ファンの音は確かにあるのですが、それが一定のリズムで響くだけなので不快でもなく、むしろ落ち着くほどです。
静かなオフィスでじっと集中しているときに、安心して任せられる雰囲気を感じさせてくれる。
これなら長期的に付き合える、と心底納得しました。
昔の空冷というと、とにかく巨大で重く、音も大きいという印象がありました。
しかし現在のモデルは全然違いますね。
そのためケース内のエアフローを妨げず、効率よく熱を逃がしてくれる。
こういった強みは、華やかさより堅実さを重視するビジネスユースにおいて大きな価値につながります。
とはいえ、世の中はカスタム水冷が人気を集めています。
透明なチューブを走る冷却液やライティング効果を楽しむ人も多く、それがSNSで目を引くのもよく分かります。
だから、水冷の良さを否定する気は毛頭ありません。
むしろ趣味として自作PCを楽しむ人にとっては最高の選択肢です。
ひとたびどこかの部品がトラブルを起こせば、それがシステム全体に直結して作業が止まる。
背筋が冷えるような危うさがあります。
実際、水冷が故障すれば修理や交換の負荷は決して軽くなく、忙しい業務を抱える身としては想像するだけで頭が痛くなるのです。
静かさと冷却性能。
この二つを両立できることが大事です。
性能数値として優秀でも、運用中に気を揉むようであれば、それは精神的な負担になり、本来の生産性に影響を及ぼしかねません。
私の経験からすれば、空冷はそういった心配が圧倒的に少ない。
だから一度その安定感を味わうと、「やっぱり空冷で十分だ」と自然に思えてしまうのです。
もちろん水冷の魅力を無視するのは不公平でしょう。
美しさや独自の性能を追求したい人には大きな価値があります。
ただ、私にとってパソコンは毎日使わざるを得ない道具であり、そこで一番重要なのは安心して稼働できること。
「仕事用なら空冷にしておけ」。
これは本音です。
日々の業務でストレスを抱えずに使えること。
結局そこに尽きるのだと思います。
華やかさよりも、安定性。
見た目の派手さよりも、信頼性。
確かに水冷は格好いいのですが、パソコンの前に座るたびに心配が頭をよぎるようでは長期運用には向きません。
その点、空冷はほとんど気にせず任せられるので、本当にありがたい存在です。
ケース内エアフロー設計が処理速度に響く理由
パソコンの性能を本当に支えているのは、派手なスペックではなく目に見えにくい空気の流れなんじゃないかと、私はしみじみ感じています。
だからこそケース内部の環境を軽んじると、高額なパーツを積み込んでも期待通りには動いてくれない。
これが現実です。
昔の私はそこを甘く見ていました。
ある時、自作したPCでフロントパネルの吸気口を気にせずデザイン重視で組んでしまったことがありました。
最初はご機嫌に動いているように見えたのですが、レンダリングを始めて少しすると、ファンが轟音を上げて回り始め、画面の動作も妙に引っかかる。
無情にも、処理が終わるのに予定より15分以上余計にかかってしまったんです。
思わず「なんだこれは…」と声が出ましたね。
悔しさと情けなさでいっぱいでした。
結果は驚くほどはっきりしていました。
ケース内部の温度が下がり、処理のスムーズさが一気に変わったのです。
夜中にイライラしながら作業を待つことも減り、静かに回るファンの音が妙に落ち着く存在になったのを覚えています。
なぜだか、心拍が整うような安堵がそこにあったんですよね。
ケース内の空気の流れって、人間の血流みたいなものだなと今では感じています。
新鮮な空気が前から入り、部品を冷やし、後方や上部から押し出される。
その繰り返しが健全さを保っている。
GPUを複数枚載せると部屋全体がサーバールームみたいに暑くなることもあり、ファンの轟音には心が折れます。
「ただファンを増やせばいい」なんて考えは、残念ながら甘いんですよね。
重要なのは風の通り道をどう作るかということなんです。
最近のケースは確かに進化しています。
メッシュ仕様のフロントにして吸気量を稼ぎ、上面から効率的に排気するデザインも見かけるようになりました。
ゲームや動画編集のように長時間使い続ける作業では、耳元の風切り音がじわじわ効いてきて疲労感を増すのです。
もちろん静かな高性能ファンもあるにはありますが、値段が跳ね上がりがちで財布には厳しい。
もっと現実的な落としどころが欲しいな、ついそんな愚痴をこぼしたくなります。
では、どうすればいいのか。
答えは意外とシンプルで、ケース内のエアフローを正しく整えることに尽きるのです。
細部のスペックをあれこれ検討するよりも、まず風の流れをデザインすること。
フロントから十分に冷たい空気を取り込み、内部で発生した熱をリアやトップからちゃんと逃がしてあげる。
この循環がしっかり構築されていれば、負荷がかかってもCPUやGPUはクロックを下げず、一定のパフォーマンスを維持できる。
私は実際、配置に工夫を加えただけでエンコードの時間が10分以上短縮され、精神的な余裕を取り戻した経験があります。
「あの工夫で自分の時間が戻ってきた」と思えたのは小さな感動でした。
大切なのは、特別なスキルではなく基本を愚直に守ること。
熱を逃がす仕組みを理解し、内部で空気が溜まらないように気を配る。
業務が滞らず心に余裕が生まれれば、自然と成果にもつながる。
現実に、少しの工夫が働き方そのものを変える力を持っていることを知ったのです。
冷却バランス。
これこそが肝です。
空気の流れを整えるという地味な工夫が、安定性と信頼を支える最大の秘訣。
数字だけでは測れない安心感がそこにあります。
ファンの音すら心地よく思えるような安定環境を手に入れることは、決して特別ではなく、誰にとっても必要なことなのだと思います。
これから先、もっと洗練されたケースやファンが増えていくことを、私は期待せずにはいられません。
安心感。
信頼性。
音の静けさを守りつつ、必要な時には存分に性能を引き出す――そんな機械との付き合い方を、私たちはまだ模索しているのかもしれません。
少しばかりの工夫と気配りで、働き方も気持ちも変わる。

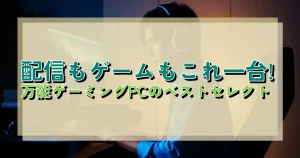
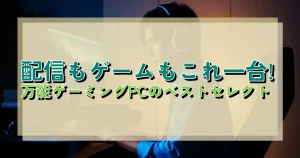
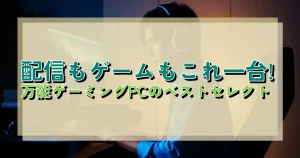



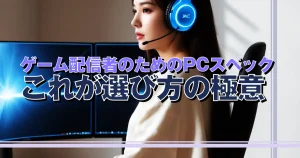
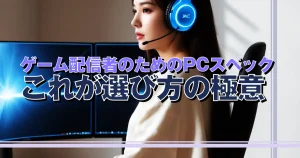
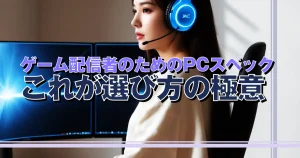
静音性と性能を両立させるための組み方の工夫
性能ばかりを追いかけた結果、冷却が不十分でファンがうなるように回り続け、仕事どころではなかった苦い経験があります。
そのとき痛感したのは、静音と冷却のバランスこそが本当の快適さを決める、ということでした。
性能の数字ではなく、日常で味わう作業の心地よさ。
これがすべてなのだと。
CPUクーラーの選択ひとつで結果が大きく変わるのを私は身を持って学びました。
以前は値段を抑えようと手頃な空冷クーラーを選んだのですが、少し負荷をかけただけでファンが騒がしく、耳が疲れてしまいました。
深夜に作業していると、ただの生活騒音ではなく自分の集中を乱される敵のように感じてしまう。
そんな気持ちになったんです。
半ば諦めながらも簡易水冷のモデルに切り替えてみると、あまりに快適で驚きました。
温度が下がり、ファンが静かになり、作業に没頭できる。
これこそが自分に必要だったんだと気づきましたね。
ケースファンの配置は、想像以上に影響が大きいものでした。
小型ファンを増やせば良いと思っていた頃は、ただにぎやかなだけで空気は滞っていました。
熱がこもらない。
そして音が静か。
配置ひとつでこんなに変わるのか、と膝を打ちました。
大切なのは数ではなく質。
これを理解した瞬間でした。
静かな風。
そして見落としがちな電源ユニット。
私はゼロRPMモードが備わったモデルを選びましたが、これが本当にありがたい。
軽い作業中はファンが止まり無音の環境が保たれ、仕事に没頭できる。
重い処理が走るときは静かにファンが回って冷却を補う。
その切り替えが非常に自然で、あたかも車が必要に応じてスムーズに力を切り替えていくような感覚です。
とはいえ、まだ課題も残ります。
GPUです。
高性能なモデルは圧倒的な発熱を伴い、そのサイズにも驚かされます。
数年でこれほど大型化するとは本当に思っていませんでした。
もちろんハイエンドを求める以上は仕方ない部分もありますが、私はメーカーにもっと工夫を期待してしまいます。
スマートフォンがあの小さな筐体で高い処理能力を引き出しているのですから、PCの世界でも熱処理の新しい発想がもっと出てきてもいいのに、と。
正直な気持ちです。
私なりの結論は単純です。
CPUとGPUは余裕を持った冷却で支え、大口径ファンをゆるやかに回す。
そして電源にはゼロRPM対応を選び、無音の時間を確保する。
これだけで部屋に静かな空気が広がります。
実際、この構成に替えて以降、深夜の作業中にも家族から「うるさい」と言われなくなりました。
これだけで家庭内の小さな摩擦がひとつ減ったわけですから、静音設計の価値は数字以上に大きいと感じています。
性能だけを追わなくなったのも年齢の影響があるのでしょう。
若い頃はオーバークロックに挑戦しては、熱と騒音の渦に後悔することも度々ありました。
けれど、今では安定性を優先する静かな構成を選びたいと思うようになりました。
結果、精神的にもずっと楽だと気づいたのです。
仕事の道具なのだから、安定して淡々と使えることが一番大事。
それは40代になって、やっと腑に落ちた考え方でした。
静音を意識するようになってから、私はパーツ選びの指標がひとつ変わりました。
「どれだけ静かに働いてくれるか」。
数字では測れない要素ですが、これが作業環境を左右する大きな軸です。
カフェでのちょっとした作業も、オフィスでの長時間の資料作成も、自室での動画編集も。
静かな空間では発想や集中力に余裕ができ、結果として生産性そのものが上がることを実感しています。
今日も私は自分の組んだマシンで編集作業をしています。
耳に届くのはタイピングの音だけ。
こうした環境を整えられたのは、40代になって「静けさ」の意味を深く理解できるようになったからかもしれません。
若い頃の私なら「静かなんて贅沢だ」と笑っていたかもしれませんが、今は違います。
この静けさがあるからこそ、一日の終わりまで心を削られることなく、爽やかな気持ちでいられるのです。
静けさの価値。
これを知らなかった頃の自分にはもう戻りたくありません。
最後に伝えたいのは、パーツを選ぶうえで「静音」を意識することは単なる趣味や贅沢ではないということです。
静けさは確かな体験であり、仕事の質を支える土台そのものです。
私にとって静かなPCは、無理なく集中力を引き出せる環境をつくる最高のパートナーです。
これが、働く私たちを支える本当の力だと胸を張って言えます。
クリエイター向けPCでレンダリング時間を短縮する工夫


ハードウェアエンコードを使って効率を高める方法
ハードウェアエンコードを賢く取り入れることが、映像編集の時間を大幅に削減し、結果的に仕事全体の効率を底上げしてくれる方法だと、私は実際の経験から強く感じています。
CPUだけに任せていた処理をGPUや専用エンコーダーに分担させることで、速度が上がるのはもちろんのこと、発熱や消費電力も抑えられる。
これが積み重なると最終的には納期そのものを守れるかどうかという、非常にシビアな分かれ道になるのです。
映像制作をしている人であれば、この数十分の差がどれだけプレッシャーを左右するか、身に覚えがあるのではないでしょうか。
実際に私が体験したケースをお話しします。
手元のPCに搭載されているRTXシリーズ、そこでNVENCを使って長い尺の映像を書き出したとき、CPUのみの処理と比べると体感で本当に半分ほどの時間で終わってしまったのです。
誇張ではなく衝撃。
普段ならコーヒーを淹れて一息ついた後も延々と続いているレンダリングが、あっという間に完了している。
細かく見るとCPUエンコードとの画質の違いは確かにありましたが、YouTubeやSNSといった配信を前提にするなら視聴者が気づくことはまずありません。
むしろ配信者にとっては時間を買えるほうに価値がある。
ただ、ここで気をつけておきたいことがあります。
GPUエンコードがまるで万能のように思えたとしても、実際にはそう単純ではありません。
つまり重要なのは両者のバランスです。
ここを誤ると「最新の機材を導入したのに期待した効果が出ない」という残念な結果に直結する。
さらに見逃せないのは、GPUそのものが世代ごとに進化しているという事実です。
今ではH.265やAV1といった新しいコーデックへの対応が進み、高画質でありながら容量を抑えた書き出しが可能になっています。
これは単に見栄えの問題ではなく、ファイル取り回しのしやすさに直結します。
容量が大きすぎればクラウド納品やネット経由の共有に時間がかかり、最終的にスケジュールが圧迫される。
逆に容量が軽減されれば、その分でトラブルのリスクも減り、納品の安心感、そして余裕が生まれるのです。
成果物の品質を支える裏側の力、とでも言いましょうか。
先日、制作仲間の一人が最新のNVIDIA GPUを搭載したノートPCを購入し、実際その場で書き出しを見せてもらいました。
短いMVのレンダリング速度が、数年前に私がデスクトップで体験したものよりずっと速い。
しかもファンの音も控えめで、発熱も落ち着いている。
私は思わず口にしてしまいました。
「これだったら出先でも全然やれるじゃないか」と。
以前はノートPCでの映像編集なんて制約だらけで、どうしても妥協を強いられると考えていました。
しかし今は違います。
確実に時代が進んでいる。
小型筐体の存在感。
十数年前、CPUだけで一晩かけてエンコードし、朝方にようやく完成品を提出したときの疲労感は今でも忘れられません。
だからこそ今の状況をしみじみありがたいと感じるのです。
便利すぎて甘やかされている気さえする。
もちろん、最新技術を導入しておけばすべて良し、という甘い話ではありません。
どんなに優れたGPUがあっても、設定を誤れば宝の持ち腐れになる。
これは恥ずかしい経験ですが、実際に私も初めてGPUを使ったとき、アクセラレーションを有効化する設定を見落としていました。
その結果、性能が全く発揮されていなかったのです。
自分で気づいたときには思わず苦笑いをしてしまいました。
けれど、そういう小さなつまずきも含めて、使いこなしていくプロセスが技術者としての成長そのものだと感じています。
作業効率化の実感。
最終的にどう取り組むべきかを整理するとシンプルです。
長編の映像編集をきちんとこなしたいなら、まずハードウェアエンコードに対応するGPUを導入する。
そのうえでCPUも十分な性能を備え、編集ソフトの設定を状況に応じて最適化する。
私自身の結論を言います。
映像編集の現場で最も大きな敵は「時間」そのものです。
時間が奪われ続ければ、体力も気力もすり減っていく。
だからこそ技術を味方につけ、効率を高めて余裕を作り、その余白を新しい企画やクリエイティブな思考に振り向けるべきなのです。
時代は変わりました。
私たちの働き方も、それに合わせて変えていかなければいけない。
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52BS


| 【ZEFT Z52BS スペック】 | |
| CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55EN


| 【ZEFT Z55EN スペック】 | |
| CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45CFO


| 【ZEFT Z45CFO スペック】 | |
| CPU | Intel Core i9 14900KF 24コア/32スレッド 6.00GHz(ブースト)/3.20GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7900XTX (VRAM:24GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) |
| ケース | CoolerMaster HAF 700 EVO 特別仕様 |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 360L CORE ARGB |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 1000W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (アスロック製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55A


| 【ZEFT Z55A スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra5 235 14コア/14スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z52AH


| 【ZEFT Z52AH スペック】 | |
| CPU | Intel Core i7 14700F 20コア/28スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.10GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake Versa H26 |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
キャッシュ用ドライブを分けて作業を高速化する仕組み
動画編集で本当に時間を短縮したいなら、キャッシュ専用のドライブを用意するのが一番効果的だと、私は身をもって感じています。
昔は「正直そこまで変わらないんじゃないか」と疑っていましたが、素材用SSDとキャッシュ用SSDを分けてからは、作業の流れがまったく違う。
待たされるイライラが減り、集中力が途切れなくなったのです。
動画編集ソフトは想像以上に一時データを生み出します。
エフェクトを重ねたり色補正を繰り返したりしていると、気が付けばプレビューがまともに動かない状態になってしまう。
もしキャッシュとメイン素材を同じドライブで処理していたら、ソフトは息切れ状態になり、こちらはため息ばかり。
ところがキャッシュを別のSSDに逃がしただけで、あのカクつきや予告なしのフリーズがほとんどなくなりました。
単純な対策なのに恐ろしいぐらい効く。
これは本当に効いた、と胸を張って言えます。
私は思い切ってSamsungのGen4 NVMe SSDをキャッシュ専用に導入しました。
あの日のことを今もよく覚えています。
まるで足かせが外れたように。
感動しましたね、心から。
「やっと来たぞ」と思わず声に出したほどです。
確かに発熱には少し焦りましたが、ヒートシンク付きモデルを選んでからは落ち着いて安心して使えています。
あれは正しい投資でした。
正直、ケチらなくて良かったと今でも思います。
最近はAI生成映像や8K素材など、データサイズも負荷も桁違いです。
以前の環境では深夜まで延々と作業が終わらず、体も気持ちもボロボロになっていました。
しかし今は違います。
メイン512GB SSD、保存用2TB SSD、キャッシュ専用1TB SSDという構成にしてから、納品直前のヒリつく場面でも冷や汗をかく機会がぐっと減りました。
夜中まで作業しても、無駄に待たされる時間がないので気力が持ちます。
大げさかもしれませんが、私にとっては体を壊すリスクを避けて睡眠を確保できることが最大の成果です。
それが一番大きい。
かつてHDDやSATA SSDをキャッシュ用に流用していたこともありましたが、あれはやはり半端な解決策でした。
コストを抑えているつもりでも結局どこかの段階で時間を奪われる。
トータルで考えると高くつくのです。
だから私は今ならはっきり言えます。
これが遠回りしないための近道。
タイムラインが滑らかに動き、レンダリングも思ったより早く終わる。
それだけで作業の疲労感は一気に減ります。
編集中に自分の思い通り操作できると「仕事ってこんなに楽しいんだ」と感じられる瞬間が増えるんです。
「妥協せずに良い環境を整えてよかった」と、自分自身で納得できる。
私はこれまで効率化プラグインや様々なツールを試してきましたが、結局ここまで効果が大きかった改善は他になかった。
それほど強烈な変化でした。
安心感がある。
道具が仕事を支えるという当たり前の事実を、ストレージ環境を整えてから改めて痛感しました。
特にキャッシュ専用ドライブの有無は、日々のリズムに直結します。
これは単なるパーツ選びではなく、仕事の質そのものを左右する選択です。
締め切り前の一時間。
その重さを知っている人ほど、この意味を理解してくれるはずです。
その時間を守るために、私は高速SSDを迷わずキャッシュ専用にしました。
信頼できる環境。
これからはさらに高解像度、高負荷が当たり前になり、「とりあえず何とかなる」と考える余地はどんどん狭まっていきます。
だからこそ今の段階で環境を整えておくことが、自分自身を守る道でもある。
疲れ果てた夜中に「あのとき導入しておけば」と悔やむのはもうごめんです。
だから私は先に動きました。
そして今なら誰にでも伝えられる。
快適な作業は未来を支える、と。
最後に強調しますが、追加でキャッシュ専用NVMe SSDを一台用意するだけで、作業効率は想像以上に変わります。
私は何度も失敗と遅延に苦しんだ末に、ようやく最適解にたどり着きました。
「この選択で良かった」と心から胸を張れる。
効率だけでなく心の余裕まで得られるのです。
プロジェクト設定を見直して時間の無駄を減らす編集の工夫
プロジェクトの準備を省いて作業を始めると、ほぼ例外なく余計な時間を浪費することになります。
私はそれを身をもって経験して、「素材に合わせたプロジェクト設定を最初に正しく行うことこそが、編集作業全体の効率を決定づける要素だ」と強く思うようになりました。
どんなに高性能なPCを導入するよりも、はじめの数分で設定を整える行為の方が、のちの作業ストレスを大幅に減らしてくれることを嫌というほど体感したのです。
だから映像編集の現場で私が最優先しているのは「まず環境を整える」という一点に尽きます。
設定を誤ったまま走り出してしまうと、必ずと言っていいほど取り返しのつかない遠回りが待っています。
4Kで撮影した映像をフルHDのプロジェクトで作ってしまい、途中で慌てて気づく。
軽く修正できるように思えますが、最終的にはレンダリングで大きく響いてくるんです。
私は何度も徹夜してひたすら処理が終わるのを待ち、イライラの中で「なんで最初にちゃんとしなかったんだ」と肩を落としました。
だからこそ今では、作業を始める前にフレームレートや解像度、さらには色深度まで一つずつ確認するのが習慣になっています。
単なるルール化ではなく、もう朝の歯磨きのような生活の一部。
面倒に見えて本当は一番の時短策なんです。
だって、数時間の手戻りを想像したら、最初の2分の確認なんて安い投資ですよね。
小さな工夫が大きく自分を救うのだと痛感しています。
プレビュー設定も軽視してはいけません。
私はRTX4080を積んだPCで嬉々として編集作業を始め、フル解像度プレビューを力任せに使ったことがありました。
しかしタイムラインはカクつき、何度も止まる。
無駄に時間だけ過ぎていく。
さすがに我慢できなくなって設定を半解像度に落とした瞬間、嘘みたいにスムーズに動き始めました。
その時の解放感といったら、思わず笑ってしまったほどです。
「なぜもっと早く気づかなかったんだ」と。
あの体験が今も私の判断基準になっています。
最終的に出力する段階ではフル解像度で問題なく書き出せるわけですから、作業中に多少粗く見えても支障はありません。
それ以上にプレビューの処理が軽くなることで集中力が乱されず、編集に没頭できる。
これは単なる小技ではなく、心身の負担を減らす大切な工夫だと実感しました。
やってみればわかりますが、本当に効果が大きいです。
納品形式がH.265の4:2:0指定だったのに、何の気なしにプロジェクトを4:4:4で進めてしまったのです。
編集中は動いているので気にもせず、しかし最終段階でGPUのVRAMが悲鳴を上げ、レンダリングは異様に遅い。
調べて初めて理由を知ったときの悔しさといったらありませんでした。
しばらく自分を責めるほどでしたよ。
それ以来、私は必ず「最終アウトプットをどうするのか」を先に確認してからプロジェクトを立ち上げるようにしています。
目的に沿った設定をしておけば、同じPCでも驚くほど動作が軽快になる。
安定感ある作業環境。
しかし、それらはコストがかかったり表現の幅を狭めてしまったりするリスクも含んでいます。
実感をもってそう言えます。
私が本気で勧めたいのは三つです。
素材の規格に合わせること、プレビュー設定を賢く軽くすること、そして納品形式に即した設定をあらかじめしておくこと。
たった数分の確認で数時間を取り戻す。
年々効率を重視するようになった今の私には、それがどれほど価値のあることかよくわかります。
私が何より伝えたいのは、作業を始める前の準備を甘く見てはいけないということです。
準備を丁寧にすれば、必ず自分の未来が楽になる。
逆に怠れば、その負債は必ず後で返すことになる。
長編動画編集用PCに関してよくある疑問


編集用PCとゲーミングPCはどんな違いがある?
映像編集に本気で取り組むなら、ゲーミングPCではなくクリエイター向けに設計されたPCを選ぶことが最も合理的です。
私が身をもって経験したのは、見た目やスペック表の数値に惹かれてゲーミングPCを導入したものの、いざ編集に使い続けると数々の制約に直面してしまう現実でした。
表面上は似ているように見えても、両者はまったく別物なんです。
最初に買ったゲーミングPCは高性能GPUを搭載していました。
だから編集ソフトのプレビューもサクサク動き、タイムラインを触るときは「これはいける」と思ったものです。
けれども動画を書き出す段階でCPUが処理落ちし、4Kファイルひとつの出力に一晩以上かかったときは、本当にがっかりしました。
深夜にモニターの前で腕を組みながら、時計の針だけが進むのをやり過ごす。
あの時ほど「時間をお金で買うつもりだったのに」と後悔した瞬間はありません。
映像編集という作業の本質を突き詰めると、GPU一辺倒では成り立ちません。
数字上のFPSやグラフィック性能ばかり目立つゲーミングPCとは、ここで決定的な違いが出ます。
派手さと現実の作業効率のギャップですね。
私はストレージ面でも苦労しました。
ゲーミング用途ならゲームデータを収める程度で事足りますが、編集作業となれば数百GBの動画素材を一度に抱えることが普通です。
作業没頭どころか、環境に振り回される毎日でした。
正直、これは精神的にかなり疲れた。
最近は生成AIを活用する場面も増えてきていますが、AI処理の安定稼働にも冷静な視点が必要です。
GPUだけ強化しても全体がバランスを欠けば頭打ちになり、期待したパフォーマンスは得られません。
さらに見過ごせないのが静音性です。
ゲーミングPCのカタログを見れば、LEDが鮮やかに光り、いかにも性能の象徴という構えですが、現実の現場で必要なのは静かさと安定です。
夜中に長時間のレンダリングを走らせているとき、後ろから轟音のファンが鳴り響くとどうなるか。
集中どころか、ただの騒音のストレスにしかなりません。
「見た目はいらない、静けさをくれ」とつぶやいたのを今でも覚えています。
実際、私はあるMSIのゲーミングPCを編集用に試したことがあります。
購入当初は性能の高さに期待していましたが、数時間かけた書き出しの途中で温度が上がり続け、ファンが永遠にフル回転。
オフィスの空調を全開にしても追いつかず、結果としてPCケースの中から噴き出す熱に手を焼きました。
瞬間の力はあるのに、長期戦になると崩れてしまう。
スポーツ選手で例えるなら短距離ランナーです。
編集はマラソンなんですよ。
それ以降、私は迷わず編集専用に設計されたワークステーションやクリエイターPCを選ぶようになりました。
結果的に効率が改善し、精神的にも余裕が生まれる。
これを経験したとき、安物買いの銭失いとはまさにこういうことかと骨身にしみました。
作業に集中できる環境。
安心して走らせられるマシン。
この二つがそろって初めて、真の仕事道具だと私は感じます。
スペック表をにぎやかに飾る数値は目をひきますが、実際に役立つのは地味で目立たない安定性なのです。
私はそう言い切ります。
結局のところ、成果を出すためのカギは4つにまとめられます。
この柱を意識して環境を整えると、日々の作業そのものが驚くほど快適になるんです。
お金を抑えたつもりが結果的に非効率に悩まされるくらいなら、最初から適切な機材を選ぶ。
その方が何倍も健全です。
だから私は声を大にして言いたい。
本当に求めるべきは、安定して静かに支えてくれる堅実な相棒のようなPCなのです。
レンダリングにGPU性能はどれくらい効いてくる?
フルHD程度の映像編集であればRTX4070以上を選んでおけば不安はありませんし、4Kの長尺動画を扱うのであればRTX4080以上を導入したほうが間違いなく快適です。
そんな風に言い切れるのは、私自身がレンダリング速度の差に何度も驚かされてきたからです。
CPUだけに負担をかけて作業を進めようとしたときには、進まない処理を延々と待つことになり、正直うんざりしましたね。
やはり動画編集においてGPUは欠かせない存在だと身をもって実感しています。
この前、実際にDaVinci Resolveで90分の4K動画を仕上げる案件がありました。
環境はRTX4070TiとCore i7の組み合わせで、結果はわずか30分弱で書き出しが完了したのです。
そのときの感覚は「救われた」と言うのが近いかもしれません。
昔、RTX4060環境で同じ作業をしたときには1時間半以上かかり、ただの待ち時間が精神的にも辛かったことを思い出すと、この差は圧倒的でした。
GPUを軽視することは、いまの私にとって単なる不便を通り越して損失だと断言できます。
もちろん何でもGPU任せで解決できるわけではなく、実際のところソフト側の最適化にも左右されます。
Premiere ProではGPUの恩恵を受けられる部分がある一方で、CPUの助けを必要とする処理も多々あります。
そうした状況を踏まえると、ソフトがどこまでGPUを活かすか、そしてエンコード方式をどう選ぶかが重要になってくるのです。
特にH.265やAV1といったコーデックはGPUの専用エンコード機能があってこそ現実的に使えるもので、CPUだけで無理に処理しようとすると出口の見えないほど長い時間を待たされる羽目になります。
最近ではAI生成の素材を取り込む機会が増えてきました。
その役割分担が数字や進行具合にはっきりと出てくるのです。
AIブームもそうでしたが、ここで問われるのは結局リソースの最適配分。
どこにどんな力を割り振るのか、これは現場の効率を大きく左右する要になります。
それでも時々感じるのは、ソフトウェアの進化の遅さです。
GPUが世代を追って性能を引き上げていく中で、ソフト側の作り込みが伴わないことがあるのです。
例えるなら、せっかく高性能車を手に入れても、道路が荒れていたらスピードを出し切れないのと同じこと。
抑え込まれているポテンシャルを見るたびに「もっと活かしてほしい」と思わずにはいられません。
私は普段の仕事で言えば答えは既に見えています。
長尺動画を仕事として制作する限り、GPU性能を軽視することはできません。
そしてCPUはその力を支える土台として同じくらい大事です。
組み合わせて初めて調和が生まれるのだと痛感します。
40代になった今、時間の意味合いは以前と比べて大きく変わりました。
若い頃なら夜を徹してレンダリングさせておいても気にしませんでしたが、今は違います。
家族との時間も大切にしたいし、翌日の体調にまで悪影響が出るやり方は続けられません。
だからこそ待ち時間を減らす技術に投資する価値があるのです。
実際にGPUの力を体感すると、楽さだけでなく成果にも直結することを思い知らされます。
進行がスムーズになれば余裕が生まれ、その余裕が仕上がりの質へ好影響を与えることさえあるのです。
効率化がそのまま品質向上にもつながるのだと理解してしまった以上、もう引き返すことはできません。
私自身、今後もGPUを軸にした作業環境を求め続けると思います。
技術を追いかけるのは大変ですが、その労力以上の結果が返ってくることをこの数年で実感しています。
むしろ職業上の必須条件であり、成果を安定させるための当たり前の選択なのです。
最終的に言えるのは、動画編集という現場においてGPU性能を軽視する理由は一切ないということです。
時間を削り、無駄を減らし、品質を確保する。
そのすべてを実現する近道がGPU強化なのです。
だから私はこれからも環境構築においてGPUを中心に据えていくでしょう。
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R59CCA


| 【ZEFT R59CCA スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7900XTX (VRAM:24GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) |
| ケース | クーラーマスター MasterBox CM694 |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M Pro-A WiFi |
| 電源ユニット | 1000W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (アスロック製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R52CA


力強いパフォーマンス、ソフィスティケートされたデザイン、究極のゲーミング体験を叶えるゲーミングPC!
グラフィックスが際立つ、次世代プレイを牽引する極上のスペックバランスのマシン!
清潔感あるホワイトケースに、心躍る内部を映し出すクリアパネル、スタイリッシュなPC!
高性能Ryzen 7 7700搭載、高速処理はコミットされた頼れるCPU!
| 【ZEFT R52CA スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (8GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | DeepCool CH510 ホワイト |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASUS製 TUF GAMING B650-PLUS WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60BS


| 【ZEFT R60BS スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 7800XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H9 Elite ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASUS製 TUF GAMING B650-PLUS WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60AW


| 【ZEFT R60AW スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | LianLi O11D EVO RGB Black 特別仕様 |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASUS製 TUF GAMING B650-PLUS WIFI |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
初心者はBTOと自作、どちらから始めるのが現実的?
なぜかといえば、安定稼働や冷却性能の確かさ、そして何かあった時に頼れるサポート体制まで備えているからです。
自作の方が一見すると安く上がるように感じるかもしれません。
しかし実際に相性問題でつまずいたり、電源の不安定さで不意にシャットダウンするようなトラブルが起きた時に、その解決にかかる時間と精神的な疲労を計算に入れると、とても仕事向きだと胸を張れるものではないのです。
数年前、私は意気揚々と自作PCを組み、Adobe Premiere Proで長尺動画の編集に挑みました。
ところが、最初の書き出しでCPUの温度が急上昇し、パフォーマンスが落ち込み、最終的にはフリーズ。
冷却不足の現実を思い知らされ、結局は大型CPUクーラーへの交換、ケースファン増設と、休日をまるごと潰すような大掛かりな調整が必要になりました。
ガジェット好きの私にとって部品を触るのは楽しい作業でもありましたが、納期が迫る案件の最中で同じ事態に直面していたと思うと、本当に冷や汗ものです。
あのときの焦りは、今も鮮明に頭に残っています。
忘れられないほどに。
あの頃の私は、正直に言えば「自作こそ正義」と思い込んでいました。
けれど現実は甘くなく、部品選びや動作検証に想像以上の時間を奪われました。
休日に冷却対策を試行錯誤している最中、ふと「これがもし仕事用だったら完全に詰んでたな…」とつぶやいた自分の声を、今でも覚えています。
あの瞬間こそが、私がBTOの現実性を本気で理解した時でした。
一方で最近のBTOメーカーの進化には、目を見張るばかりです。
たとえば動画編集に特化したモデルでは、最初から大容量の32GBメモリや高速SSDが搭載され、GPU性能とのバランスも緻密に考えられています。
以前は「ゲーミングPCを動画編集に転用して使う」といった雰囲気が強かったものですが、今は動画編集者の声を直接反映させたモデルが増えているのです。
こうした進化を見ると「ここまで用意してくれるのか」と素直に驚き、時代の変化を深く実感します。
ただ、自作の楽しさを否定するつもりは一切ありません。
むしろカスタマイズの自由度こそが自作の魅力であり、電源容量を多めに取り、冷却の仕組みを練り、ストレージを用途ごとに分けて構築する過程は「遊び」と呼べるものです。
徹夜して部品を交換しながらパズルのように動作を確認していくあの体験は、まぎれもなく醍醐味でした。
でも。
安定した稼働や安心できるサポート体制と天秤にかけると、こと仕事で使う場合にはBTOの方がどう考えても妥当だと感じます。
実際、私の周囲でも業務にパソコンを使う人はまずBTOを選びます。
納期や品質の厳守を迫られる現場では、不具合が起きたら窓口にすぐ電話するだけで助けが得られる環境が、どれほどの安心になるか計り知れません。
一方で自作だと、調べて、試して、失敗して、また調べる。
この繰り返しで何日も消耗してしまうことが珍しくありません。
余裕のある時期ならそれも楽しみのひとつですが、納期が目の前にあるときには、そんなプロセスは単なる苦行としか言えないのです。
私がBTOに切り替えてからは、動画の書き出しが途中で止まるのではという不安から解放されました。
電源を入れれば迷うことなくすぐに作業が始められる環境は、効率だけでなく気持ちの余裕にも直結します。
単なる道具ではなく、精神的な支えにまでなる。
これこそが私にとっての最高の投資でした。
もっとも、パーツの知識を深めたい、トラブル解決力そのものを磨きたいという人にとってはやはり自作が向いているのも確かです。
自由を手にするためには手間も惜しまない、その姿勢が報われるのも自作の世界です。
私自身も若い頃には、夜を徹して部品の交換を繰り返し、その過程で一喜一憂していました。
あのときの熱を今思い出すと、人生の一部のような気がします。
だから結局のところ、初心者が効率的に動画編集を始めたいならBTOを選ぶ方が間違いありません。
もし「仕事用にはどちらが正解か」と誰かに真剣に問われたら、私は迷わずBTOを勧めます。
余計な不安に惑わされず編集作業に集中できることで、成果に直結するからです。
動画編集という作業は性能と安定性の積み重ね。
その基盤をどう整えるかこそ、すべてを左右するのです。
安心できる選択。
信頼できる相棒。
それがBTOパソコンです。
実務のパートナーとして考えるなら、最初の候補はやはりこれしかないと私は胸を張って言い切れます。



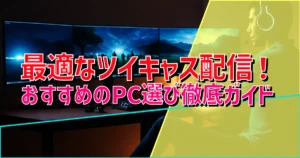
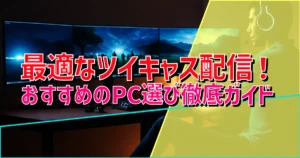
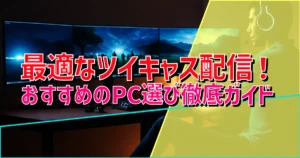



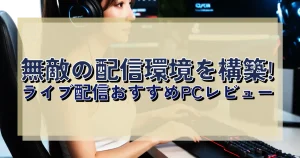
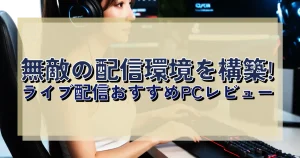
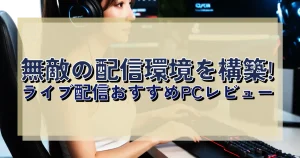
ストレージはSSDだけで十分か、それともHDDも必要か
ストレージを選ぶときに一番大切なのは、速さと容量、そして安心感のバランスだと私は思います。
SSDの快適さを一度でも体験してしまうと、もう昔のHDDだけの環境には戻れません。
それでも、SSDだけに頼るのは現実的ではないのです。
だからこそ、私はSSDとHDDを組み合わせて使う方法こそが最適解だと自信を持って言えます。
SSDを導入して最初に驚いたのは、動画編集中のプレビューの軽さです。
以前はHDDで作業をしていて、再生ボタンを押しても数秒は待たされました。
ところが、NVMeタイプのSSDを入れてからは劇的に変わりました。
プレビュー再生がサクサク進み、エフェクトを重ねても画面が止まらない。
「ああ、これで仕事が楽しくなる」と素直に感じた瞬間でした。
ほんの小さな改善のようでいて、その違いは仕事のリズムそのものを大きく変えます。
1つのプロジェクトで数百GBという容量を扱う場面が何度もあったからです。
結局、外付けHDDに急いでデータを移し替えることになり、その焦りと不安で余計に疲れる。
容量不足に追われながら作業するのは、心の余裕まで奪います。
私にとって「容量のゆとり=精神的なゆとり」だと痛感した出来事でした。
HDDの役割はシンプルです。
撮影済み素材や完成したデータをしっかり守る保管庫。
この感覚は昔から変わりません。
動画素材はとにかく容量を食います。
気付けば数百GBどころか数TBが埋まっている、なんてことも珍しくない。
私はHDDを「書庫」と考えています。
机の上(SSD)には今必要な資料だけを置いて、その他は広い書庫(HDD)にきちんと整頓してしまっておく。
そんなイメージで使い分けています。
これが安定した作業環境の秘訣だと私は信じています。
もっとも、私は一度だけ怖い経験をしました。
大事な案件のデータを外付けHDDにだけ保存していたところ、そのHDDが突然認識されなくなったのです。
その瞬間、血の気が引きました。
頭が真っ白になり、復旧業者に泣きつくしかなかった。
結果的に多額のお金を払ってなんとか救えましたが、胃が痛くなる思いでした。
その失敗以来、私は必ず二重保存を徹底しています。
作業中のデータはSSDに置きつつ、HDDにバックアップ。
そしてさらに別のHDDやクラウドにもコピー。
ここまでやって、やっと安心できるのです。
人は失って初めて、本当の意味で備えの大切さを学ぶのだと思います。
HDDは守りの役割。
私はそう表現しています。
GPUが並列処理でチームワークを発揮するように、ストレージにもきちんとした役割分担があります。
SSDだけでは体力が足りない。
HDDだけではスピードが出ない。
それぞれが強みを持ち寄ってこそ、映像編集の厳しい現場を乗り切れるのです。
特に長尺の映像を扱うとき、SSDの速さがなければ編集効率が落ちるし、HDDの保管力がなければ安全の裏付けがなくなる。
以前、10分以上の映像に複数のレイヤーやエフェクトを重ねる案件を担当しました。
SSDがあったから快適に編集できたのですが、もしあれをHDDで処理しようとしていたらどうなっていたかと想像するだけでもゾッとします。
プレビューごとに長い待機時間が発生して集中力が切れ、効率どころの話ではなかったでしょう。
この差こそがSSDの強みです。
そしてそれを補完してくれるHDDがあるからこそ、最終的に安心して納品ができる。
両者の組み合わせによる安心感は計り知れません。
一方で、HDDがただの古い記録媒体だと思ったら大間違いです。
むしろ今の時代だからこそ、その存在感は増しています。
過去にDVDやBlu-rayに焼いて保存していた時代を思えば、今のHDDの大容量とコストパフォーマンスはとんでもない恩恵です。
こうして世代を越えて技術が進化しつつも、結局「大切なものを守る」役割に人は安心を求め続けるのかもしれません。
最終的に私がたどり着いた答えは、とてもシンプルです。
この組み合わせを外す理由はないと感じます。
ならば両方をバランスよく活かすほうが建設的です。
正直に伝えます。
これしかないんです。
昔のように感覚や勘だけで道具を選ぶのではなく、失敗も経験したうえでの確信として、私はSSDとHDDの併用を強くおすすめします。
これから動画編集を始める人には、遠回りをせず、最初から快適な環境を整えてほしい。
そのために、あの時の私と同じように苦い経験をしないでほしいのです。
SSDとHDD、両方の良さを掛け合わせる。
その選択が、結局一番長く安心して続けられる道なのです。
安心できる環境。
拡張性を考えるならどのパーツに注目すべき?
動画編集を快適に続けていく上で、私が一番大切だと思うのは、後から柔軟に手を加えられる余地を残しておくことです。
性能にばかり目を奪われてしまうと、あとで身動きが取れなくなってしまうものだと痛感しました。
正直な話、私も最初の自作ではCPUやGPU性能を優先し、マザーボードや電源にはコストをかけませんでした。
しかし数年経つとすぐに限界を迎え、「何であの時に土台をしっかり固めなかったんだ」と自分を責めた経験があります。
あの時に少し背伸びをしてでも堅実なパーツを選んでいれば楽だったのにと、今では苦笑いするしかありません。
マザーボードはその典型です。
PCIeスロットやM.2スロットの数が、思った以上に将来の動きを左右します。
以前、安さに釣られて選んだATXマザーボードを使っていたのですが、後からGPUを二枚挿ししようとしたときに配置の制約で泣きを見ました。
本当に「数千円ケチって後々に大きな痛みを背負う羽目になった」と頭を抱えたんです。
動画編集の領域は常に進化しており、フルHDから4K、さらに8KやVRまで広がっていきます。
拡張性のない構成にしてしまうと、その変化に全くついていけない。
だからこそ将来の可能性を考え、最初から余裕あるマザーボードを選んでおくことは、大げさではなく安心の保険だと思います。
ケースも甘く見てはいけません。
以前、フルHD編集向けに組んでいた構成で4K編集へと移行した時期に、冷却不足で痛い目を見ました。
レンダリングが始まるとGPU温度が急上昇してクロックダウン、結果的に処理落ち。
しぶしぶケース丸ごと買い直したのですが、あの予想外の出費は財布に響きました。
だから今では見た目のデザインよりも、内部のスペースと冷却設計を最優先で選んでいます。
正直ちょっとやりすぎじゃないかと当初は思っていたけれど、今では「熱対策を軽く考えたら必ず後悔する」と声を大にして言いたいくらいです。
そしてストレージ。
近年の映像プロジェクトは一案件で数百ギガなんてざらにあります。
以前の私は単純にSSDを一台だけ搭載し、足りなくなれば外付けを買い足すという安易な発想で進めていました。
その結果、机の下がケーブルとドライブでごちゃごちゃに。
そこからようやく気づいたんです。
マザーボードやケースのスロットやベイに余裕を持たせておけば、必要な時にスマートに追加できる。
こうして内部拡張で工夫できることが、毎日の作業を驚くほど快適にするのです。
本当に助かった。
電源ユニットも忘れてはいけない要素です。
昔は「どうせ750Wあれば十分だろう」と軽く考えていました。
しかし新しいGPUを積み増した瞬間、電力不足でPCがまともに起動しなくなり、結局丸ごと電源を交換する羽目に。
あの無駄な出費を思い出すだけで、胸の奥がムズムズします。
今では1000Wクラスを当たり前に検討しますし、余裕を持たせること自体が将来の安心に直結すると確信しています。
最新の環境で私が実際に試した構成では、大型ワークステーション用のケースと高性能なATXマザーボードを組み合わせてみました。
結果としてNVMe SSDを4枚使えるようになり、転送速度も体感できるくらい快適。
長尺の素材を扱うプロジェクトでも、一切ストレスなく編集に没頭できました。
120fps映像素材を重ねても滑らかに動いてくれるので、思わず「ここまで仕事が楽になるのか」とつぶやいたほどです。
これまでは容量不足や転送速度の限界に苛立っていたのが嘘のようで、PC環境がきちんと整うと心まで軽くなる。
安心。
では最終的に、何に投資すべきか。
それはやはりマザーボード、ケース、電源、この三つに尽きます。
CPUやGPUは技術の進化で数年ごとに世代交代しますが、この土台さえしっかりしていれば柔軟にアップデート可能です。
実際に私は、5年以上使い続けても快適に編集を続けられる構成が実現できました。
つまり土台への投資が、長期的に見れば最もコストパフォーマンスに優れた選択なのです。
拡張性は結局、「未来への余裕」に他なりません。
目先の性能や価格に惹かれる気持ちは私にもよくわかります。
でも、そこで安易に飛びついてはいけないのです。
長く安心して向き合える環境を用意しておけば、余分な出費を抑えながら気持ちにも余裕が持てます。
私自身の失敗や後悔を通じて学んだことを率直に伝えますが、土台に投資して損をすることはまずありません。
そうなんです、これが本音です。





