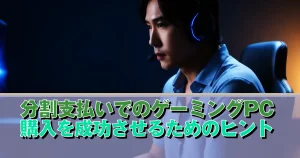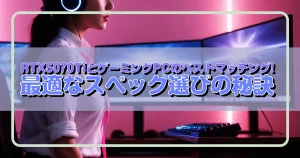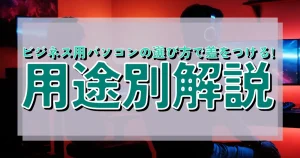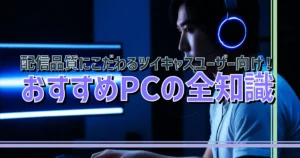10万円前後で組む エーペックスレジェンズ用ゲーミングPCの実力を検証

フルHDプレイで気をつけたいCPUの選び方
フルHD環境でApex Legendsをプレイするとき、軽視されがちなのは実はCPUです。
しかし実際に遊びながら配信までやってみると、あっという間に現実に引き戻されました。
その差が露骨に出るのは、画面の一瞬の遅延や敵のワープのような不可解な挙動です。
理解した瞬間、私はあまりのストレスにため息をつきました。
フルHDという解像度自体はGPUにとって重くないため、「GPUが余裕だから問題なし」と考えがちです。
しかし、実際は逆でCPUの処理能力が目立つのです。
特に144Hzや240Hzといった高リフレッシュレートでプレイする場合、CPUがボトルネックになると一気に映像がカクつき、高価なモニターを買った意味すら薄れてしまいます。
素直に悔しい気持ちになりました。
では、どこまでのCPUを選べば良いのか。
私の経験ではCore Ultra 5やRyzen 5クラスが一つの基準になります。
実際にCore Ultra 5で環境を組んでプレイと配信を同時に試したところ、170fps前後で安定。
性能と価格の折り合いに「ああ、これなら納得できる」と感じられました。
しかし、長時間の配信や複数アプリを並行して動かす使い方では、それでも負荷がかさむのです。
Ryzen 7を導入したときの衝撃は忘れられません。
私が試したRyzen 7 9700Xでは、配信をしながらブラウジングやシーン切り替えをしても、すべてがなめらかに流れる感覚でした。
裏でのエンコード処理も止まらず、動きに不満が出ない。
作業が楽に進む、そんな当たり前のことが心底ありがたく感じられたのです。
ほんの少しの投資が、これほど環境を変えるのかと実感しました。
CPUにおいては、性能だけでなく発熱や電力効率も重要です。
最新世代は改善されているとはいえ、負荷がかかれば一気に熱を帯びます。
冷却を軽視すると「あと数千円惜しまなければ良かった」と必ず後悔する瞬間が来る。
こればかりは私も痛い経験をしました。
さらに忘れてはいけないのは、GPU側の技術をフルに引き出すためにはCPUの処理速度が不可欠だという点です。
いくら高価なGPUを積んでも、CPUがデータを供給できなければGPUは遊んでしまいます。
宝の持ち腐れ。
そうならないためにはGPUとCPUの釣り合いが最重要です。
片方を極端に良くしても実際の使用感は伸びにくい。
コストを抑えたいとき、最初に削りがちなのがCPU。
特に90fps以上を目指すのであれば、CPUに投資しなければ絶対満足できません。
「ここまで変わるのか」と驚くほど性能差が出るのです。
フルHD環境において「軽いから大丈夫」と誤解する人は多いのですが、Apex Legendsのように試合ごとに負荷が変化するゲームではCPU性能が追いつかないと一瞬で処理落ちします。
快適な操作感を得るには、やはり一定以上のCPUが必要。
こうした現実を思い知ったときから、私はCPUを軽視しなくなりました。
フレーム安定こそが快適さを生む条件なのです。
まとめると、CPUは削って良いパーツではありません。
フルHDでApexを楽しみ、配信までしたいのであればCore Ultra 5やRyzen 5が最低ライン。
さらに余裕を求めるならCore Ultra 7やRyzen 7を選ぶことで確実にストレスが減り、満足感が増します。
GPUを活かすのも結局CPUの体力次第。
私はやっと、その意味を心の底から納得しました。
今ではプレイ中に映像がカクつく恐怖はなくなりました。
だから私にとって、CPUは「後回しのパーツ」ではなく「頼れる相棒」。
安心してゲームと配信を楽しむためには、そこにしっかり投資する。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 42923 | 2462 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42678 | 2266 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 41712 | 2257 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41007 | 2355 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38483 | 2075 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38407 | 2046 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37176 | 2353 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37176 | 2353 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35552 | 2194 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35411 | 2232 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33667 | 2205 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32811 | 2235 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32445 | 2099 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32334 | 2190 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29174 | 2037 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28462 | 2153 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28462 | 2153 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25380 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25380 | 2172 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23022 | 2209 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23010 | 2089 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20797 | 1857 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19452 | 1935 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17682 | 1814 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16001 | 1776 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15246 | 1979 | 公式 | 価格 |
GPU選びでつまずきやすいポイントとその対処法
エーペックスレジェンズを本気で楽しもうと思ったら、やっぱり最初に向き合うのはGPUの選択になります。
ここを誤るとせっかくのゲーム体験が一気に台無しになる。
私は何度かその失敗を身をもって味わってきました。
値段だけで選ぶのは本当に危険です。
最初は「これで十分いけるだろう」と思い込んでいたのですが、いざ配信とゲームを一緒に走らせるとVRAMが足りず、無理やり画質を落とさざるを得ませんでした。
プレイ中に映像がもたついたときの苛立ち。
あの感覚は二度と味わいたくありませんね。
もう一つ痛感したのは、最新世代のモデルだから大丈夫と過信してしまうことです。
当時、RTX5070なら何も心配いらないと信じて導入したのですが、配信をしながらの144Hz維持は厳しい場面が多々ありました。
完全に見通しが甘かったのです。
最新という言葉に飛びついた自分を思い出すと、今でも苦笑いしてしまいます。
ではどうすればいいのか。
私なりの答えは、まず自分がどんな環境で遊びたいのかを整理することです。
フルHDで144HzをターゲットにするならRTX5060TiやRX9060XTで十分戦えます。
この時に大事なのは数字の羅列を眺めるのではなく、自分が実際に遊ぶシーンを頭の中に思い描いて照らし合わせることです。
ここを意識すると選び方が変わります。
また発熱や冷却も軽視できません。
GPUはモデルによって発する熱量が違い、ケース内の空気の流れが不十分だと真価を発揮できません。
私も数年前、冷却を甘く見てグラボが熱で力を出せなかった経験があります。
そのときはため息をつきながら「結局、根本を無視していたんだな」と苦く反省しました。
最近の技術で見逃せないのはアップスケーリングです。
DLSS4やFSR4は画質を大幅に犠牲にせずにフレームレートを底上げしてくれます。
これが有効化されているかいないかで快適さがまるで別物になる。
配信ソフトとの相性やエンコード方式の違いもかなり影響するので、事前に少し調べるだけでストレスが大きく減ることを実感しています。
正直、知らないまま損していた時期もありましたよ。
意外と忘れやすいのはドライバです。
「安定して動いているから」と更新を後回しにしていた時期がありましたが、ゲームのアップデートに合わせて最適化が進んだドライバを当てた途端、一気にフレームレートが上がって驚いたことを今でも覚えています。
面倒くさいと思って放置すると、実は大きな差になって返ってくるのです。
自分の遊び方に合わせた投資であり、快適さと安心感に直結します。
値段だけで妥協すると、後から「やっぱり足りなかった」と不満がつのり、結局買い直す羽目になる。
財布にも心にも負担が大きい。
だからこそ、私はここは絶対に抜かりなく考えるようにしています。
私の答えとしては、フルHD前提ならRTX5060TiやRX9060XTが妥当で、WQHD以上を考えるならRTX5070以上が安心。
ただし単純な数字合わせではなく、自分がやりたい遊び方や環境に照らして考えることです。
それを怠らず選んでこそ、心から満足できる一台に出会える。
多少時間がかかっても悩む価値はあるんです。
GPU選びは面倒に感じることも多いですが、同時に楽しい時間でもあります。
部品を眺めながら「これでどんな体験ができるんだろう」と考える瞬間は子供の頃のワクワクに似ています。
そのワクワクを裏切らない一枚を選び抜けたとき、やっと「これで大丈夫だ」と自分を納得させられる。
安心感がある。
40代になった今でも、新しいパーツを吟味する時間がちょっとした楽しみであり、大人の遊びの一部になっています。
それが私にとって、ゲームを通して心から満足できる時間を過ごすための秘訣なのです。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 48533 | 101751 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32047 | 77933 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30055 | 66640 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 29978 | 73293 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27075 | 68805 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26420 | 60131 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 21879 | 56698 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19855 | 50392 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16507 | 39301 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 15942 | 38131 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15805 | 37909 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14592 | 34857 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13699 | 30804 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13160 | 32303 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10787 | 31685 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10617 | 28534 | 115W | 公式 | 価格 |
配信も視野に入れるならどれくらいのメモリが必要?
ただし同時に配信も快適に行いたいのであれば、32GBを用意しておくのが間違いのない判断だと私は思います。
実際の体験から言えば、余裕のある環境を整えることでプレイヤーとしての集中力や気持ちの持ち方まで大きく変わるのです。
私は長い間16GBで格闘していました。
正直「まあ、動くし大丈夫だろう」と思い込んでいたのです。
ところがOBSを立ち上げてコメントを追いかけつつ、演出を少し足そうとすると突然のカクつきや遅延。
あの瞬間、心臓がギュッと掴まれるような焦りに襲われていました。
プレイどころじゃない。
楽しいはずの時間が、ただのストレスへと変わってしまったのです。
特にApexのように反射神経が命のゲームでは、ちょっとしたラグが結果を左右します。
一瞬の遅れで負けを喫する。
負けた自分を悔やむより、「配信環境のせいだ」と嘆いてしまうことの方が多かったのをよく覚えています。
そんな自分に嫌気がさしたこともありました。
だからこそ32GBを搭載したときの解放感は強烈で、ゲームに全集中できるようになった体験は忘れられません。
余裕。
単なる数字の違いではなく、精神的に平穏を取り戻せることこそ大きな価値なのです。
配信中に冷や汗をかかずに済むようになり、フレーム落ちもしなくなる。
視聴者から「今日はすごく安定していて見やすい」と褒めてもらった瞬間には、思わず胸に込み上げるものがありました。
小さな違いのように見えても、それは大きな意味を持ちます。
もちろん64GBという選択肢も頭をよぎりました。
私も動画編集をするので全く無関心ではありません。
ただ、配信とゲームを同時に楽しむ程度であれば正直そこまで必要ないと感じました。
4K動画を複数扱うヘビーな使い方をする人なら話は別ですが、私の生活スタイルには過剰すぎます。
結果として32GBが一番バランスの取れた落としどころだった。
無駄にお金をかけるよりも、ちょうど良さを選ぶ方が健全です。
実際、最近のOBSは進化が早く、便利なプラグインが次々と登場しています。
ノイズ除去や自動の映像補正といった機能は確かに心強いのですが、その分メモリ負荷も高まります。
だからこそ、最初から十分な容量を備えておく。
これが失敗を避けるコツだと実感しています。
思い返すと私が32GBに踏み切れたのは、同僚の一言がきっかけでした。
「お前、毎回ギリギリでやりすぎだぞ」と笑われたのですが、その通りだと妙に納得してしまったのです。
仕事でもプライベートでも、余裕があれば判断や行動は自然とスムーズになります。
機材投資だって同じこと。
16GBで後悔して買い直すより、ずっと賢い選択です。
正直、私も昔は「16GBで十分だろう」と軽く考えていました。
本音を言えば当時は安さを優先したかったのです。
しかし実際に配信中に視聴者から「映像がちょっと止まってるよ」と言われたとき、ひどく落ち込みました。
こちらは必死に楽しい空気を作ろうとしているのに、裏で環境が邪魔をしてしまう。
それを繰り返してきた経験があるからこそ、今は32GBを心から推奨できるのです。
そうすれば数年後にソフトが重くなっても慌てなくて済みますし、新しいエフェクトを導入して配信画面を華やかにしても余裕です。
実際に使ってみると、この余裕がクリエイティブな工夫を後押ししてくれることに気づきます。
結果として配信の楽しさが持続し、視聴者との関係も長続きしていくのです。
だから私は声を大にして伝えたいのです。
Apexを快適に配信するなら32GBを迷わず選んでください。
ぐずぐず考える必要はありません。
その判断が、プレイヤー自身の満足度と視聴者の笑顔を守ります。
結局のところ、32GBはコストを超えた価値を与えてくれる。
競技シーンを意識したエーペックスレジェンズ用PC調整のコツ

144fps以上を狙いやすいグラボの候補
CPUやメモリももちろん大事ですが、最終的にゲームの快適さを左右するのはGPUです。
これは実際に私が何度も買い替えて痛感してきたことですし、「どのGPUを積んでいるか」でプレイの満足度が全く変わるのです。
勝負の一瞬に勝てるかどうかを決めるのは数字だけではなく、その裏にある環境の安定感なんだと、歳を重ねるほどに思うようになりました。
だからこそ、少し高くても安定した環境に投資する意味がある。
そう腹落ちした瞬間がありました。
正直、最初はそこまで期待していなかったのですが、実際にBTOパソコンに組んでみるとフルHD環境で200fps近くまで安定して出てくれる。
その数字を実際に自分の目で見たときには「ここまで行けるのか」と思わず声が出ました。
さらに静音性が高くて、深夜にプレイしていても家族に気を遣わない。
静かなリビングで一人集中できることがこんなにありがたいのかと気づきました。
これは「もうワンランク上だな」とすぐに分かる力強さがあって、フルHD環境で240Hzモニターをフルに生かせる実力があります。
私は大会の配信を観るのが好きなのですが、選手が使っているような環境を少しでも自分の部屋で味わえたとき、何とも言えない高揚感を覚えました。
そして熱の処理も安定していて、そこまでハイスペックな電源を用意しなくても余裕があります。
正直、余裕のある環境というのは気持ちをラクにしてくれるものです。
あ、これなら安心して遊べるな、と実感できる。
一方でAMD派の方ならRadeon RX 9060XTや9070XTに魅力を感じるはずです。
私自身も試してみましたが、FSR 4によるアップスケーリングとフレーム生成の効果は本当に大きく、映像のなめらかさには驚いたほどでした。
特に9060XTは価格とパフォーマンスのバランスが良く、設定を適切に調整すれば180fps前後で安定して動きます。
この価格でここまでいけるのかと思った瞬間、「これで十分じゃないか」とつぶやいていました。
GPUはいつもコストとの戦いですが、AMDはそこに強みを出してくる。
納得しましたね。
ただし物足りなさを感じる部分もあります。
それはVRAM容量です。
まだ8GBどまりのモデルがあるのは正直きつい。
実際に私は一度VRAM不足に陥り、テクスチャ設定を落とさなくてはいけなくなりました。
そのとき配信で視聴者から「画質下がったね」と言われて、胸にずしんと響きました。
あの瞬間から、12GB以上は必須だと考えるようになりました。
嫌な記憶ですが、大事な学びでもありました。
もうひとつ忘れてはいけないのが遅延の問題です。
GeForceのReflex 2やRadeonの最新FSRによる低レイテンシ技術は、数字では表しづらいのですが、操作の「速さを感じる感覚」が確かに変わります。
敵を発見してから射撃までの一瞬がスムーズになるだけで、ゲーム自体の手応えが別物になるんです。
数字としてのフレームレートが多少落ちても撃ち勝てる感覚が残る。
これがあるかどうかは、真剣にプレイする人なら実感できる差になると思います。
それでは実際どれを選ぶのが良いのか。
コストを抑えても144fps以上を安定して出したい人にはRTX 5060Tiがおすすめです。
そしてAMDを選ぶなら、9060XTを基本としてコストを重視しつつ、さらに余裕を求めるなら9070XTを検討すると良い。
私も数え切れないほど環境を変えてきましたが、今のところこの4枚の中から選べば後悔しにくいはずです。
迷ったら素直に予算と用途を照らすこと。
それが結局の正解なのだと思います。
正直、安心できる環境じゃないと長く続けられないんです。
仕事や家庭が優先になる中で、その少ない時間をストレスの残る環境に割きたくない。
だからこそGPUの選択には本気になります。
安さに妥協して結局後悔するより、少し高くても長く快適に遊べる環境に投資する方が幸せです。
過去の失敗から学んだのはまさにそこでした。
やっぱり最後は、自分自身が納得して選んだ一枚が最高の一枚になる。
そして、心から思います。
「あのとき妥協せずに選んでよかった」と。
だから今日も、静かな夜にゲームを立ち上げるとき、私は自分で選んだGPUに感謝しています。
WQHDゲーミングで相性が重要なCPUとGPUの組み合わせ
経験上、どちらか一方だけを良くしても、結局はストレスが残る環境になってしまうのです。
私は以前、GPUを強化すればそれで解決すると信じていた時期がありました。
確かに画質は華やかになりましたが、CPUがついて来られず、フレームレートが頭打ちになった瞬間のあの落胆は、今でもよく思い出します。
要は組み合わせを見極めることが、快適な環境に直結するのです。
今の私はRTX 5070とCore Ultra 7 265Kを合わせて使っていますが、この構成にしてから数か月、実感としてかなり安定しています。
ある日、大型アップデート直後にグラフィック設定を思い切って最高に上げて試してみました。
結果は平均160fpsを維持。
安堵感に包まれましたね。
数値だけでなく、体で感じて安心できるかどうか。
もちろん新しいGPUは強力です。
ただしフラッグシップモデルに手を伸ばすと、消費電力と価格という現実の壁が立ちはだかります。
私のような一般の社会人ゲーマーにとって、電源を買い替えたり、生活費を削ってまで最新最強に走るのは現実的ではありません。
CPUで言えばRyzen 7 9800X3DやCore Ultra 7 265Kあたりが、価格と性能の両立という意味でいちばん納得できるポジションだと思います。
フレームレートが安定しないストレスというのは、本当に理屈を超えて強烈です。
撃ち合いの真っ最中に画面がカクついた瞬間、負けた理由が自分の腕ではなく環境だったと気づくと――正直やっていられません。
GPUを一段上にするという解決策もありますが、それだけではまだ不十分で、私の実感としてはCPUとの兼ね合いが与える影響の方が大きいのです。
昔の1080p環境の感覚でGPUだけを意識すると、むしろ期待外れでがっかりするリスクが高い。
それが怖いところなんですよね。
さらに、配信となると話は別次元です。
8コア以上のCPUならGPUが描いたフレームをしっかりエンコードに回せます。
しかし8コア程度だと、ベンチマーク結果は悪くなくても、本番でカクつきが発生する。
滑らかに動くと思った矢先にわずかなもたつきが生じ、「ああ、まだ足りないのか」と頭を抱えました。
ここで学んだのは、WQHD環境においてCPUを軽視してはいけないという教訓でした。
GPUばかりに目を向けると、相性の悪さが分かりやすい「fpsの谷間」として現れる。
そのフレームがガクッと落ち込む妙な感覚は、もう二度と味わいたくない。
だから私は、人に聞かれれば迷わず「ミドルハイクラスを選ぶのが最適解です」と伝えています。
机上の論理ではなく、私自身の悔しい体験が裏打ちしているのですから。
具体的に言うと、RTX 5070TiとRyzen 7 9800X3DやCore Ultra 7 265Kといった組み合わせであれば、配信を同時進行してもWQHDの高設定で144fpsを安定して維持できます。
以前、RTX 5060TiとRyzen 5 9600を組み合わせた時期がありました。
「十分だろう」と楽観視していましたが、実際にはフレームが不安定で、撃ち負ける理由が自分のプレイではなく環境にあったと気づいたとき、本当に悔しかったです。
その記憶はいまでも鮮明です。
私はそこから「中途半端な妥協は最大の敵」と強く思うようになりました。
結局あとで不満が募り、買い直しで余計にコストがかさむ。
これほど無駄なことはありません。
だからこそ今は慎重に見極め、最初から必要十分なレベルのパーツを用意するようにしています。
正直な安心感がほしい。
それを満たすためには、配信込みでも動かせる余裕のある構成にするしかない。
パーツの数字をただ追いかけるのではなく、使っていて心から「任せられる」と思える感覚。
そこに辿り着くまでが大事なんです。
そしてもう一つ、大切なのは信頼感です。
私が出した結論は明確です。
それ以外の遠回りは避けた方がいい。
その結果、映像の美しさと滑らかなフレームが両立し、「戦えるPC」として頼れる存在になるのです。
そうなると、気持ちに余裕が生まれ、プレイに集中できる。
私は今、その快適な環境を手に入れたことに心から満足しています。
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R67S

| 【ZEFT R67S スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen9 9950X3D 16コア/32スレッド 5.70GHz(ブースト)/4.30GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Corsair FRAME 4000D RS ARGB Black |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 360 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z58C

| 【ZEFT Z58C スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | CoolerMaster Silencio S600 |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z58W

| 【ZEFT Z58W スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265F 20コア/20スレッド 5.30GHz(ブースト)/2.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
| ケース | Okinos Mirage 4 ARGB Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z56AD

| 【ZEFT Z56AD スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265KF 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R52O-Cube

ハイレベルゲームも快適に対応するパワフル・ゲーミングPC
高速32GB DDR5メモリと最新のSSDの極上のハーモニー
省スペースに収まる美しきコンパクト設計のマシン
Ryzen 7 7700の力強いパフォーマンスを体感せよ
| 【ZEFT R52O-Cube スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | INWIN A1 PRIME ピンク |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850I Lightning WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
高リフレッシュレートモニターを活かすためのPC性能
高リフレッシュレートのPC環境を整えることは、単なる趣味や贅沢ではなく、自分自身の集中力や快適さを長い時間維持するための大切な投資だと私は考えています。
以前は「モニターさえ最新なら快適になるだろう」と軽く見ていたのですが、実際にPC全体のバランスを欠いた環境を経験してからは、その甘さを痛感しました。
肝心のフレームレートが安定しない瞬間、あの映像のカクつきが引き起こすストレスは、仕事で集中を途切れさせられるのと同じくらい致命的なんです。
こればかりは机上の理屈ではなく、目の前で負けにつながる経験があるからこそ、今も強く心に残っています。
GPUの選び方ひとつでも「正しい落とし所」があります。
フルHDなら最近のミドルクラスでも十分戦えますが、調子に乗って設定を盛りすぎるとたちまち動作が不安定になり、もろくもバランスが崩れるのです。
その時の悔しさときたら、「欲をかいた自分が負けたんだ」と思わざるを得ませんでした。
派手さに惑わされず、安定した実用性を優先することが本当に大切なんですよ。
CPUの存在感も見過ごせません。
ゲームはGPU依存と言われますが、配信や動画編集といった裏方作業を同時にこなすと、CPU性能の差は一目瞭然です。
ある時、旧世代のCPUで配信をしたことがあります。
映像は何とか動いていたものの、配信がカクついて視聴者から「止まってるよ」と指摘されました。
結局再投資を余儀なくされ、「安物買いの銭失い」とはまさにこのことだな、と深く反省しました。
仕事でも同じですが、二度手間は最も痛い失敗です。
熱問題についても無視できません。
冷却不足によってクロックダウンが起きると、動作は目に見えて鈍くなります。
これは本当に落とし穴のような存在で、原因に気づくまでに時間を取られてしまうんです。
一度「熱暴走か?」と不安になり、夜遅くまでケースを開けて試行錯誤したことがあります。
その経験から強く断言できるのは、冷却はオプションなんかではなく性能を引き出すための絶対条件だということです。
最大の敵は熱だと心から思います。
メモリも同様に油断できません。
16GBで足りる環境もありますが、配信やマルチタスクを考えるなら32GBは必須です。
当時16GBの環境で複数のアプリを起動したまま配信していたら、肝心な試合でカクつきが出て本当に冷や汗をかきました。
画面が固まったその瞬間、視聴者のチャットに「止まってる」と流れたときの気まずさは、今思い出しても胃が痛くなります。
ストレージについても同じで、容量不足のSSDを使っていた頃はアップデートのたびに古いデータを削除する羽目になり、その煩わしさで気持ちが萎えていました。
些細なようで大きなストレス。
操作遅延の問題も強調しておきたいです。
反応の速さ。
直結する判断力。
ReflexやFSRといった最新技術は単なるトリックではなく、根本的にゲーム体験の質を底上げするものであり、それを活用できる環境は決して過剰投資ではありません。
むしろ「これがあるからこそ安心できる」と感じています。
ケース選びについても侮れません。
そのとき見た目に惹かれて買ったケースでは風通しが悪く、熱がこもって焦った経験があります。
以来私はシンプルでも風量重視のケースを好んできました。
少し地味でも安定して使えるほうが結局は長持ちするんですよ。
仕事道具と同じで見た目より使い勝手。
ここを間違えると必ず後悔することになります。
だから私はこう言い切ります。
フルHDかつ240Hzの環境を目指すなら、余裕のあるCPUとミドルレンジ以上のGPU、そして32GBのメモリを備え、なおかつ冷却を強く意識した構成を整えるべきです。
WQHD以上に挑戦するならさらにGPUのグレードアップが必要になりますが、工夫次第で10万円台でも不可能ではありません。
快適さを担保できる構成こそ、長く付き合える安心感を生みます。
信頼できる仕組みを持つこと。
それが時間をかけてでも築く価値のある選択だと私は思います。
未知の投資に見えた環境構築も、実際に体感してみると「これがなかった頃には戻りたくない」と本気で思える自分がいました。
配信込みでも快適に動かせるエーペックスレジェンズ用PC構成例

OBS配信で重視すべきCPUコア数とモデルの選び方
エーペックスレジェンズを配信するうえで私がどうしても強く伝えたいのは、CPUを軽んじると必ず後悔するということです。
グラフィックボードに目が行きがちなのは理解できますし、私自身も最初はそちらに予算を割いていました。
しかしいざ配信を始めてみると、映像が途切れ途切れになったり、操作に遅延を感じたりと、本来楽しみたかったはずのゲーム時間がストレスに塗り替わってしまうのです。
どれだけ高価なGPUを積んでも、CPUが弱ければ配信の快適さは維持できない。
ここが根本なんだと痛感しました。
OBSは単純に録画するだけでなく、リアルタイムに映像を処理して配信へ載せていくものです。
そのため、CPUには想像以上の負荷がかかります。
8コア程度でも動作は可能ですが、実際に試すと余裕が少ないことはすぐにわかります。
明らかに処理落ちしてカクカクになった瞬間は、正直「これはダメだ」と頭を抱えました。
くやしい思いをしたのは一度や二度ではなく、今でもあの焦燥感を思い出すと胸がざわつきます。
数年前、Ryzen 5からRyzen 7へ切り替えたときの体験が私の転機でした。
同じ配信設定なのに、突然ドロップフレームが激減したのです。
正直「嘘だろ?」と画面を二度見したほどです。
わずか数世代の違いでここまで快適になるなんて思いもよりませんでした。
あのとき私はようやく気づいたのです。
CPUへの投資は先送りしてはいけない、と。
あれは今に続く確信をくれた瞬間でした。
これは単に数字上の性能差というより、プレイしていて「余裕がある」と実感できるか否かの違いなのです。
視聴者にとって映像が安定していることは当然のようですが、提供する側からするとその「当たり前」を保証してくれるのがCPUなのだと実感します。
安心感。
もちろん、GPUによるハードウェアエンコード機能もあります。
これは確かにCPU負荷を下げる手段になります。
けれど、特にフルHD以上や高ビットレートで配信を行おうとすると、やはりCPUが弱ければ限界が来てしまうのです。
私は過去に画質を優先するあまり設定を上げすぎ、あっという間に映像がカクついた苦い経験をしました。
「見るに堪えない」というコメントを視聴者からもらい、あのときは本当に落ち込みましたよ。
だから今は少しでも余裕を持ってCPUを選ぶようにしています。
それでようやく心置きなく「見てくれてありがとう」と言えるようになりました。
では、どれくらいのCPUが必要なのか。
私の答えは明快で、8コア以上が現実的なラインです。
最近のプロセッサは1コアあたりの性能が上がってきており、昔のように「コア数がすべて」とは言えませんが、配信を並行して行う環境を考えるなら、最低限この水準は外せません。
Core Ultra 7 265KやRyzen 7 9800X3Dのようなクラスであれば、ゲームをスムーズに動かしながらOBSを走らせてもまだ余裕が残る。
この安心感は実際に触ってこそ分かる領域ですし、私にとっては「信頼できる相棒」と呼べる存在になっています。
一方で「ハイエンドCPUが必須なのでは?」と考える方もいるでしょう。
しかしその問いに対して、私は自信を持って「必要ない」と答えます。
正直、コストに見合わない。
むしろその分の予算をモニターや回線環境に回した方がよほど効果的です。
ベストバランス。
それが7クラスだと私は思っています。
私がeスポーツの大会を見に行ったときも同様の印象がありました。
プレイヤーにとっての一瞬の遅延より、配信自体が崩壊することの方が大会全体にとっては致命傷なのです。
Apex配信の核心。
それが安定性です。
さらに最近はCPUにAI処理用のNPUまで統合され始め、これが今後どのように配信技術に活かされていくのか私は楽しみにしています。
まだまだ試行段階ではありますが、エンコードや背景処理をCPU内部で効率的に賄えるようになれば、配信というカルチャー自体がもっと手軽で身近な存在になるはずです。
それを想像するとワクワクしてきます。
だから私は強く言いたいのです。
エーペックスレジェンズを「快適に遊びながら配信したい」と願うならば、まず8コア以上のミドルハイクラスCPUを検討すべきです。
それが一番の近道ですし、一度手にすれば長い間きっと後悔しないはずです。
CPUこそが配信クオリティの基盤であり、そこを外してしまうと全体が揺らいでしまう。
これは私の実体験から出た答えであり、何度も遠回りをしてやっとたどり着いた結論なのです。
CPU選びは基礎工事。
これを間違えれば、その上に積み上げる機材はすべて不安定になります。
私はその失敗を経験したからこそ、誰よりも「土台を大切にせよ」と言えるのです。
配信や同時作業に余裕をもたらす32GBメモリの利点
最初にPCを組んだとき、私は正直「まあ16GBで十分だろう」と軽く見ていたんです。
でも配信ソフトを起動し、ブラウザを並行して開き、さらに仲間と通話まで挟むとたちまち動作がもたつく。
ゲーム画面自体はなんとか動くものの、肝心の配信映像が途切れたり、シーン切り替えで遅延を感じたりして、やりながら胸がざわつくんですよね。
せっかく視聴してくれている人をイライラさせてはいけないと焦ったことも一度や二度ではありません。
そこで32GBにして初めて「ようやく落ち着いて配信できる」と実感できるようになったのです。
増設したときの違いは、言葉にするより体感のほうが大きかった。
攻略サイトを見ながらOBSのレイアウトを切り替えても、動作が一切引っかからない。
以前は我慢していた小さなストレスが消えたことで、気持ちに余裕まで出てきたんです。
環境が変わるだけで、こんなに配信が楽しくなるのかと驚きました。
配信環境というのは動画キャプチャや録画など細かい作業が積み重なり、思っている以上にリソースを使います。
一見ゲームが普通に動いていても、裏側では負荷が跳ね上がっている。
その怖さを16GBのときに何度も味わいました。
だからこそ今振り返ると、32GBの魅力は「ゲームが動くかどうか」ではなく「他の作業を同時に行っても余裕を保てる」点にあると強く感じています。
私が特に効果を実感したのは、配信後の動画編集作業でした。
録画した大容量データを読み込み、カット編集やエンコードをする際に、以前は何分も待たされるのが当たり前だったんです。
仕方なく珈琲を飲みながら待つ時間も多かった。
でも32GBにしてからはその待ち時間が激減。
操作がスムーズで、やりたいことを思い立ったその流れのまま作業に移れる。
この差は本当に大きい。
社会人にとって、空いた時間をどう有効活用できるかは死活問題ですからね。
時間は有限ですから。
最近はDDR5メモリの価格も落ち着き、BTOパソコンの構成でも32GBを自然に選べるようになってきました。
私自身、DDR5?5600を購入しましたが、帯域や応答の速さに安心感があり、エーペックスのように画面が絶えず変化するシーンでも不安を感じることはありません。
体験して初めて分かる種類の安心感ですね。
これまでCrucialやG.Skillなど複数のメーカーのメモリを使ってきましたが、どれも安定動作してくれました。
その中でも個人的にG.Skillは長期間トラブルなく運用でき、自分に合っていると確信できたブランドです。
40代になり、日々の生活の中で小さなトラブルを最小限に抑えることの大切さを改めて感じるようになりました。
だから私は派手さより安心感を求めます。
「32GBなんてやりすぎじゃないの?」という声もまだ耳にします。
でも配信や動画編集を伴う環境では、過剰どころか必須に近い存在です。
GPUやCPUを最新のものにしても、メモリが不足していれば本来の力を出し切れない。
だから私はCPUやGPUに加えてメモリ容量を同じレベルで重視しています。
バランスが何よりも大切だからです。
「fpsを上げるだけならメモリは不要なのでは」と言う人もいますが、実際に並行作業を交えて配信をしてみれば違うとわかります。
GPUがfpsを左右するのは確かですが、メモリ不足で全体が足を引っ張られれば結局fpsも落ちてしまう。
快適さが損なわれれば視聴者に伝わる映像もカクつき、不満を与えてしまいます。
それは避けたいですよね。
だからこそ私は32GBを「数字」ではなく「心の余裕」として捉えています。
余裕があると気持ちも楽になるんです。
最終的に私が下した結論は明確です。
エーペックスを遊びつつ配信で人とつながるなら、32GBは間違いない選択です。
10万円台のパソコン構成であっても、CPUやGPUとのバランスを崩さずに32GBを確保すれば、安定感がぐっと増します。
結果的に配信に集中でき、視聴者との交流を楽しめる余裕も生まれる。
これは浪費ではなく、自分の時間と気持ちを守る投資だと私は考えています。
16GBで我慢してイライラしながら作業するか、32GBで余裕を手に入れて楽しさに浸るか。
この二択で私は迷うことなく後者を選びました。
そして今、その判断に一片の後悔もありません。
NVMe SSDでロードを短縮するためのポイント
ゲームを配信しながらエーペックスレジェンズを快適に遊びたいなら、結局のところストレージ環境にしっかり投資するのが一番です。
多くの人がグラフィック性能や回線速度ばかりを気にしますが、実際に快適さを左右するのはNVMe SSDの存在です。
特に試合が始まる直前やシステムを再起動した後の立ち上がりは、ここでケチると痛い目を見る。
私は過去に安価なSSDで何度もイライラを味わったので、声を大にして言いたいのです。
最近はPCIe Gen.4対応のNVMe SSDが主流になり、カタログ上では7,000MB/sといった派手な数字が並んでいます。
確かに速さは感じますが、Gen.5と比べても実際のゲームプレイ中に「劇的に変わった」と実感する機会は意外と少ないものです。
価格は跳ね上がり、冷却強化まで必要になるGen.5を選んでしまうと、導入時の出費も運用時の手間も増えるばかり。
私自身、いろいろ試した結果「現状の最適解はGen.4の1TBか2TBモデルだ」と確信するに至りました。
容量の問題は、本当に後から響きます。
エーペックスレジェンズだけで数十GBを消費するうえ、アップデートのたびに着実に膨れ上がっていきます。
私がかつて500GBのSSDを使っていた頃は大変でした。
アップデートが来るたびに別のゲームを削除して、また入れ直して。
時間は奪われるし気持ちは荒れるし、趣味なのにストレスばかりがたまりました。
あの感覚は、もう二度と味わいたくない。
いまは1TB以上に変えて余裕を持てていますが、その安心感の大きさは言葉では語り尽くせません。
手間から解放されるというのは本当に大きい価値です。
余裕のある容量があると、日常の小さなわずらわしさから解放されます。
ストレージで忘れてはいけないのは、メーカーの信頼性です。
配信予定だった日がすべて台無しになったという愚痴を聞いたとき、心底「重量のあるメーカーを選ぶことの意味」を感じました。
WDのGen.4 SSDを導入した際には、長時間の配信でも不安をまったく感じなくなり、正直胸を撫でおろした瞬間を今でも覚えています。
本当にホッとしたんです。
ただし、公式スペックの数値だけを鵜呑みにして決めるのは危険です。
持続書き込み性能やコントローラーの発熱耐性、さらにはヒートシンク搭載の有無といった細かな仕様が、実際に配信をしながらゲームを楽しむ体験に直結します。
私も一度、冷却を軽視して購入したSSDが熱でパフォーマンスを落とし、配信中に映像がカクついた経験があります。
あの瞬間の冷や汗と言ったら、本当に嫌なものでした。
だからこそ私は、最初からヒートシンク付きモデルを選ぶことを強くおすすめします。
最近ではBTOパソコンで標準採用されるケースも増えており、これは確かにユーザーにとって安心できる要素だと感じます。
安心して遊べる環境。
また意外と無視できないのが、取り付け位置です。
M.2スロットがグラフィックカードの真下にあると、そこはまさに高温地帯。
SSDにとっては過酷以外の何物でもありません。
私は一度設置場所を選び間違えて、せっかくの高性能SSDが熱で力を発揮できず、速度が落ちてしまった経験を持っています。
その時の悔しさは、もう二度と忘れたくない記憶です。
「何のために高いSSDを買ったんだ」という怒りとも、やりきれなさとも言えない感情に襲われました。
だからこそ、取り付けスロットの選び方ひとつで快適さが変わるのだと強調しておきたいのです。
今の大型タイトルの容量は見過ごせないほど増えています。
100GBを超えるのはもうめずらしい話ではなく、エーペックスレジェンズもアップデートの積み重ねで確実にサイズを膨らませています。
私は実際に1TBを買った後、半年ほどで「やっぱり2TBにしておけば良かった」と思わされたこともありました。
その時は本気で後悔しましたね。
今後も長くゲームを楽しみたい人ほど、容量選びに妥協してはいけないと強く伝えたいです。
信頼できるメーカーのGen.4 NVMe SSDを、容量は1TB以上、できれば2TB。
これが最も現実的で安心できる構成です。
ロード時間を気にせずにプレイや配信を両立できる環境を築くなら、この選択以外は考えにくいと私は思います。
趣味の時間を心から楽しむために、そして余計な後悔を抱えないために、この構成を選んで損はありません。
結局、ここに投資することが未来の自分を救うのですから。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
初めてのBTOでも失敗しにくいパソコン選びのチェック項目


ショップを選ぶときに確認したいサポートと保証内容
性能が高ければそれに越したことはありませんが、本当に重視するのは購入後のサポート体制と保証内容なんです。
以前、不具合が出て焦りながらサポートに電話した経験が何度かあります。
だから私は、これから買う方に伝えたい。
HPを例に挙げれば、大手メーカーらしい落ち着いた安心感が漂います。
電話やチャットの返信も素早いので、トラブルが起きたときに「メールで返事を数日待つ」というあの気持ちの沈む時間が少ないんですよ。
延長保証もしっかり揃っていて、長く安心して使いたい私のような人にとってありがたい仕組みです。
しかもこれまで積み上げてきたサポート実績があるから、不意のトラブルでも「大丈夫」と自然に思える。
頼もしさというのは、そうした何年もの積み重ねからにじみ出るものだと実感しています。
やっぱり歴史と実績は裏切らない。
一方でDellの魅力は何といっても「翌営業日のオンサイト修理」。
これは実際に私も体験していますが、本当に助かりました。
あるとき、仕事で使っていたPCの不具合が業務を完全に止めてしまったことがあったんです。
冷や汗かきましたよ。
すぐに連絡したら翌日には技術者が家まで来てくれ、その場で部品を交換して問題解決。
そのスピード感に救われたんです。
心の底から「ありがたい」と思いました。
壊れたPCの前で待つ無力感を味わわずに済む。
あれほど心強いことはありません。
それとは対照的にパソコンショップSEVENは、自分好みに細部までカスタマイズできる点が光ります。
国内生産で検品体制も整っていて、昔ながらのショップの信頼感が今も続いています。
私は数年前に購入した一台を使い続けていますが、一度も故障していません。
静かに、しかし力強く動き続けているんです。
冷却方式をこだわって選んだり、ケースのデザインを吟味したり、自分の使い方に合わせてオーダーした一台はやはり格別です。
価格はやや高めですが「納得感」という言葉がしっくりきます。
自分だけの特別感があるんです。
ただ、どのメーカーにも一長一短があります。
延長保証が標準でつくのか、それとも追加費用が必要なのか。
私は以前、修理に一週間かかってしまい仕事の進行が滞るという大失敗をしました。
あのときほど「保証とサポートを甘く見てはいけない」と痛感したことはありません。
苦い経験です。
今の時代はスピードが当たり前になりつつあります。
スマホ業界では即日対応がよくあることですが、その流れが確実にPC業界にも広がってきています。
昔は「直るまで一週間は見ておけ」と半分諦めていましたが、今は違います。
翌日修理が珍しくない。
ユーザーの事情が多様化したことが背景にあるのでしょう。
配信活動やゲーム大会に参加する人にとっては、たとえ一日でもPCが動かないことは致命的です。
だからこそスピードは大きな価値を持ちます。
では、どうやって選ぶのがいいのか。
私の考えはシンプルです。
自分の優先順位をまず決めること。
そのうえで、HP・Dell・SEVENの三つを基準にして考えると選択はぐっと分かりやすくなると思います。
配信や大会で絶対に止まれないならDell。
長期安定性を重視するならHP。
自分らしさを反映させたいならSEVEN。
大切なのは「そのPCが自分にとってどんな役割を果たすのか」を真剣にイメージすることなんです。
どれだけ慎重にスペック比較をしても、役割とサポート体制が合わなければ後悔しか残りません。
壊れて慌てる前に、備えておく。
壊れてからでは遅すぎる。
だから私は購入を検討するとき、まず保証とサポートを確認します。
性能や価格だけの比較では出てこない満足があります。
信頼して使える、その安心こそが価値です。
安心できる毎日。
信頼できる相棒。
ゲーミングPC おすすめモデル4選
パソコンショップSEVEN ZEFT R64N


| 【ZEFT R64N スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 7700 8コア/16スレッド 5.30GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal North ホワイト |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60FS


| 【ZEFT R60FS スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9060XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z59M


| 【ZEFT Z59M スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra9 285K 24コア/24スレッド 5.70GHz(ブースト)/3.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Corsair FRAME 4000D RS ARGB Black |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47CC


最新のパワーでプロレベルの体験を実現する、エフォートレスクラスのゲーミングマシン
高速DDR5メモリ搭載で、均整の取れたパフォーマンスを実現するPC
コンパクトでクリーンな外観のキューブケース、スタイリッシュなホワイトデザインのマシン
クリエイティブワークからゲームまで、Core i9の圧倒的スピードを体感
| 【ZEFT Z47CC スペック】 | |
| CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 ROG Strix B760-I GAMING WIFI |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
将来のアップグレードを考慮したケース選び
これまで私は幾度となくパーツを組み替えてきましたが、コンパクトなケースを選んでしまったせいで、あとから苦労したことが少なくありません。
冷却不足で熱がこもるとか、大型のグラフィックカードが物理的に入らないとか、そうした小さなボトルネックが後々大きな後悔を生むんです。
だから今では多少場所を取っても、懐の深いケースを選ぶのが一番安心だと身をもって知っています。
家に置いてみれば意外とすぐに存在に慣れるし、結局は「余裕のある中身」が心の余裕になるんですよね。
数年前、私は配信とゲームプレイの両面を意識したマシンを10万円台で構築しました。
そのとき予算の関係でCPUやGPUはミドルレンジにとどめましたが、「数年以内により高性能なGPUを載せ替えたい」と強く思っていたので、筐体の余裕を軽視するわけにはいきませんでした。
見た目が洗練されていてもスペースが窮屈なケースでは未来の拡張性を犠牲にすることになります。
だからこそ、私の候補からは最初に外れたんです。
結局、ケースは器ではなく土台。
ここを軽く考えると取り返しがつかなくなるんです。
デザイン性を重視したガラスパネルやピラーレスのモデルも最近は人気ですよね。
確かに内部の様子が把握しやすく、ケーブルマネジメントを工夫すればインテリア的にも美しい。
その魅力は分かります。
ただ本当に大切なのは、RTXの三連ファン仕様の大型カードやRadeonの長尺モデルを問題なく収められる空間があるか。
それが足りないと、結局泣きを見るのは自分です。
一度小型ケースを買ったとき、GPUと電源が干渉してしまって入らず、泣く泣くケースごと買い替えた経験があります。
その出費と落胆は忘れられません。
だから今の私は、多少大げさに聞こえても「ケースは大きめに限る」と声を張って言いたいんです。
小さな失敗を繰り返すより、最初に少し広さを買う方が確実に合理的。
冷却性能も、後で必ず効いてきます。
配信をしながら何時間もApexのような重いゲームを走らせると、CPUやGPUがぐんぐん発熱します。
前面の吸気口に余裕があるか、ラジエーターを増設できるか、実はこういう条件が後の安定性を左右するんです。
BTOでマシンを買う人はつい外観に惹かれがちですが、内部設計の甘さが結局パフォーマンスを台無しにします。
しかも冷却は単に温度だけでなく静音性に直結するので、環境全体の快適さすら変えてしまう。
正直に言うと、近年の木目調パネルや個性的なデザインケースを見ると「ちょっと欲しいかも」と心が揺れる瞬間はあります。
ですが冷静に「実用に耐えるだろうか」と自問すると、結局は拡張性と冷却を優先する判断に戻ることばかりです。
ケースは少なくとも5年は使い続けるもの。
その時間を考えれば、流行りに流された選択より、地道で堅実な選択に価値が出てくる。
見た目よりも地に足が着いた機能を重視する判断こそ、大人の選び方だと私は思っています。
それにしても、静音性は軽んじてはいけません。
私は配信を行うので、ファンの回転音ひとつで視聴者に不快を与えてしまう可能性があります。
だからファンのエアフローがきちんと確保されていて、余計な突起や制約が少ないケースを必ず選ぶようにしています。
些細に思えても、こうした工夫が最終的には作業環境の快適さに直結するんです。
安くてデザインがよければ良いという考えで選んでしまうと「なぜもっと考えなかったんだ」と後悔するのがオチ。
静音対策まで見越してケースを選ぶのは、配信者としての必須条件なんですよ。
実用本位。
PC自作はどうしても派手なパーツや最新のパーツに意識が向きがちです。
でも、結局はそれらを支える土台が貧弱なら、せっかくの性能も発揮できない。
私は何度もその罠にかかりながら学んできました。
だから、安心感と冷却性能、そして未来の拡張余地をバランスよく持つケースを選ぶこと。
それが後悔を避ける唯一の道筋です。
そして気づくのです。
ケースは単なる箱じゃない、未来を繋ぐ基盤なんだと。
余裕のある選択さえしておけば、数年後にパーツを取り替える時にも頭を抱えることはありません。
むしろ、「ああ、あのとき大きめにしておいてよかった」と笑える。
それが最も健全で、長続きするPCライフだと私は思います。
だから今日も私は、大きめで堅実なケースを選ぶのです。
静音環境を目指すなら押さえたい空冷クーラー事情
配信しながらゲームをすると、あっという間にパソコンの中は灼熱状態になります。
CPUもGPUも全力で働いて息を切らしているような感じで、気がつけばケース内部はサウナのよう。
正直、最初は温度の上昇そのものよりも、そこから派生する耳障りなファンの騒音に悩まされました。
せっかく静かに楽しみたい時間が、ブーンブーンと響きわたる音に塗りつぶされると本当にげんなりします。
だから私は自然と空冷クーラーに注目するようになったのです。
視聴者にとって一番の敵は「雑音」です。
どんなに華麗な映像を見せても、その背後で耳障りな音が混じれば、すっと冷めてしまうのです。
だからこそ、快適な配信には冷却性能と静音性、この二つを同時に追い求める必要があるのだと痛感しています。
耳から来る不快感は、目で感じる不満よりもずっと早く心に刺さるのですから。
最近のCPUは昔と比べてずっと安定していて、かつてのように「熱暴走」と常に戦っているというイメージは薄れました。
ただ、それでも冷却をおろそかにしていいわけではありません。
昔は「水冷こそ唯一の解決策」と盲目的に信じていた私ですが、今ではそうではないと実感しています。
Noctua製の静音クーラーを実際に購入して取り付けてみた日のことは今でも鮮明に覚えています。
配信だけでなく日常の作業環境まで澄んだ静寂に包まれ、心の余裕まで取り戻した気がします。
空冷の最大の強みは「安心感」ではないかと私は思います。
水冷のようにポンプの音が気になったり、数年先の寿命を心配したりする必要がない。
基本はファンの掃除だけで十分で、必要であれば交換すればいい。
それだけでずっと使い続けられるのです。
だから私は胸を張って空冷を選びます。
余計な心配をしなくて済む。
ただ、ここで一つ落とし穴があります。
クーラーそのものの性能だけに注目しても意味が薄いのです。
重要なのはケース全体の空気の流れ。
高性能な空冷を載せても、ケースの吸気と排気の仕組みが悪ければ、内部の空気が滞留し、結果としてうまく冷えない。
だからフロントがメッシュ構造で空気を取り込みやすいケースを選ぶのが鉄則になります。
クーラー単体で考えずケース全体の設計と合わせて捉える。
その意識の有無が最終的な快適さを決めてしまうのです。
最近のBTOパソコンの中には、この考えをきちんと反映しているモデルが出てきています。
私が確認した一台では、Ryzenと大型空冷クーラーに加え、フロントから背面まで空気の通り道が整えられていました。
その結果、負荷をかけても40デシベル前後の静けさを実現していたのです。
正直、仕様を見ただけでは「本当にいけるのか?」と半信半疑でしたが、実際の音を耳にしたとき、思わず「やるな」と呟いていました。
夜中でも安心して使えるレベル。
想像してみてください。
夜遅くにゲームを終え、ヘッドセットを外した瞬間、部屋は静まり返り、余韻を楽しもうとしたところに「ブーン」とファンの唸りが割り込んでくる。
その瞬間の不快感は本当に耐えがたいものです。
だから私は声を大にして訴えたい。
CPUクーラーとケース、この二つの選び方を軽くみるなと。
静音性を犠牲にしてしまえば、せっかくの楽しみまで削がれてしまいます。
これは配信に限らず、日常的にPCを使う人すべてに当てはまることです。
静音性に配慮されたパソコンは、快適さが圧倒的に違います。
大型空冷クーラーと空気が抜けやすいケース、それさえしっかり押さえれば、不安定な温度とも耳を塞ぎたくなる騒音とも無縁になれます。
集中できるし、気持ちも楽になる。
それによって配信の質も自然と上がり、視聴者にとっても心地よい空間を提供できるのです。
これは何度も試行錯誤を重ねた私の肌感覚であり、机上の空論などではありません。
最終的に私がたどり着いた答えは明快でした。
無理に水冷へ行く必要なんてない。
配信を本気でやりたいなら、静音を重視した空冷クーラーを選ぶべき。
私はこれを自信を持って断言します。
静けさがあるからこそ。
集中できるからこそ。
かつて水冷信者だった私ですが、今ははっきりと言えます。
40代の自分が素直に選んだのは空冷です。
これは机上の理屈ではなく、日常の配信と作業を通じて手に入れた私自身の確かな実感なのです。
エーペックスレジェンズ用ゲーミングPC購入前によくある質問


10万円台のPCで配信も快適にこなせる?
10万円台のゲーミングPCでも配信を快適に楽しめるのか、最初は正直なところ疑っていました。
価格だけを聞くと「きっと中途半端で、実際には不安定なんじゃないか」と半分構えていたのです。
しかし実際に手にしてプレイと配信を同時に試してみたとき、その先入観は大きく覆されました。
拍子抜けするほどスムーズに動き、戦闘中でも映像が乱れず、自分が思っていたハードルの高さが幻だったように思えて、ちょっと照れ笑いしたくらいです。
とくに印象に残ったのは、Apex Legendsを高フレームで動かしながらOBSで配信しても、ほとんどカクつきがなかったことです。
これまで私は20万円近いPCを何度か使ってきましたが、そのときですら配信中にフレームが落ちて、視聴者に「今日も重そうですね」と言われることがあったのです。
その経験があるだけに、10万円台でこの安定感。
思わず「いや、これはすごいな」と声が出てしまいました。
ただ、正直に言えば多くの配信者にとって本当に必要なのは、視聴者が違和感なく楽しめる安定感です。
フルHDで60fpsを維持できる段階で、求められる基準はほぼ満たされているはずです。
この部分を強調したいのは、私自身が安定しない配信に何度も悩まされ、気づけばゲームよりも「配信が止まらないか」という不安にばかり意識を割かれていたからです。
あの頃と比べたら今の世代のGPUとCPUは本当に頼もしい相棒です。
実際に使い込んでみると、静音性や放熱設計の進化が非常に大きいことに気づきます。
昔は夏場になるとファンが爆音で回り、マイクにノイズが乗ってしまったり、CPUの温度が上がって処理が落ちたりしました。
あの「ジリジリと嫌な音」に悩まされていたのが嘘のように、今のモデルは静かに、しかも安定して動いてくれます。
これもまた「見えない安心感」なんですよね。
さらに忘れてはならないのがメモリとストレージの快適さです。
私は32GBを選びましたが、これが大正解でした。
裏でブラウザを開いて情報を確認しながら、録画をしつつ動画編集ソフトをちょっと動かしても配信が安定するのです。
メモリ不足でイライラした経験がある人には、この安心感がどれほど大きいかわかっていただけると思います。
そしてSSDも1TBを搭載しておけば、アップデートや録画で容量がひっ迫して慌てることがありません。
データの整理で余計な時間をとられずにすむのは、精神的な余裕にもつながります。
温度も静音も快適さも、全部が当たり前のように整っているとき、そのありがたみは逆に忘れがちになります。
けれど少し前までは、この水準を実現するために20万円以上を出さなければならなかったのです。
たとえば私は以前、旧世代のRyzenと当時のハイエンドGPUを組み合わせて配信していました。
性能的には高かったのに、どうしてもエンコードの処理が不安定で、戦いに集中するどころではなくなることも多々ありました。
これを電気自動車の進化になぞらえる人もいます。
ゲーミングPCの進化には、それと似た風景を私は感じるのです。
技術の恩恵がいつの間にか生活に溶け込んで、「十分だ」と心から満足できる瞬間。
ただし、もちろん向上を追求する道もあります。
例えばもう一段階上のGPUを選べば4K配信に近づきますし、将来的な安心感も増すでしょう。
画質かフレームか、その調整を自分の嗜好に合わせる余裕が生まれるレベルで動いてくれるのですから、もう文句はありませんね。
そして何よりも感じたのは「配信を楽しむとき、必要なのは極端なスペックではなく、むしろ無理をしない安心感」だということです。
これは私自身が長年仕事でもPCを使いつづけ、世代交代を重ねてきたからこそ説得力を持って伝えられる実感だと思います。
時代の進化を見届けてきただけに、10万円台でこの水準を実現できるのは感慨深く、また新しい一歩を踏み出す勇気を与えてくれます。
安心して挑戦できる。
私は今そう断言できます。
迷っている人には「大丈夫、まずはこのクラスで試してみてほしい」と素直に背中を押したい気持ちです。
配信を始めようとする自分自身の過去の姿を思い出しながら、もしそのときにこの環境があれば、きっともっと気楽に挑戦できただろうと考えずにはいられません。
だからこそ、ここまで進化した現実を前に、嬉しさと同時にちょっとした誇らしさを感じるのです。
まさに今、その真ん中に立っている実感があります。
グラボはRTXとRadeon、どちらを選ぶのが安心?
グラフィックボードの選択について私が強く伝えたいのは、安心して長く使える環境を望むなら、最終的にはRTXを選んだ方が良いということです。
パソコン歴が二十年を超える私にとって、どれほど高い性能をうたっていても安定性が伴わない機材は結局ストレスの種になり、仕事や趣味の時間を台無しにすることを何度も経験してきました。
その積み重ねから学んだのは、数字で示されるスペック表よりも「何時間動かしても不安を覚えないこと」が価値になるという事実です。
最初は私も、正直どちらを選んでも大差はないだろうと思っていました。
しかし実際にApexのような反応速度と安定したフレームレートが重要になるゲームを本気でやってみると、その差が結果として如実に出てしまう。
RTXのドライバ更新の速さ。
そしてメーカーとゲーム会社との協業体制。
これらが積み重なって「妙な挙動で試合を壊されない環境」を作り上げていると気づいたとき、この安心感こそ投資の価値だと心から思いました。
プレイ中に無駄な不安を感じない。
それがどれほど大きいか。
もちろんRadeonが弱いと言っているわけではありません。
最新世代を触ったときには「お、かなり良くなったな」と心底驚かされました。
昔持っていた「ドライバが安定しない」という印象は確かにもう古いもので、RX 9070XTをWQHDで144Hz駆動させたときは予想外にスムーズで、思わず声が出るほどでした。
あの瞬間、「ここまで来たんだな」と素直に感心したのです。
過去のイメージに縛られていると今のRadeonの進化を見落とす、それを身をもって知った経験でした。
ただ、配信を絡めて使うとなるとやはりRTXに軍配が上がると感じます。
独自のNVENCエンコーダーはCPUに無理をかけず、安定して高画質の映像を配信してくれるので、私のように仕事帰りに友人と雑談しながら配信を楽しむスタイルには欠かせません。
映像が乱れる心配をせずに済み、音ズレも気にせず安心して会話に集中できる。
小さなことのようで、毎回の配信を続ける大きな支えになるんです。
一方でRadeonのFSR4には正直感心しました。
フレームをAIで補うことで負荷を抑えながらも滑らかさを確保する仕組みは、まさに「なるほど!」と唸らされた技術です。
RTXのDLSSに比べれば映像の細かさでやや差を感じる場面も確かにありますが、タイトルによってはほとんど違いを気にしないレベルまで迫っている。
ものによってはRadeonが勝っていると感じることもあり、こうした意外性や尖った部分があるのはRadeonならではの魅力だと思っています。
とはいえ、最終的に私が重視するのはコストと満足感のバランスです。
10万円台でゲーミングPCを構築する場合、グラフィックボードの選択が全体の方向性を左右するのは事実で、RTX 5060Tiあたりを中心にすると「性能と価格のほどよい落としどころ」が自然に見えてきます。
Radeon側のRX 9060XTも同価格帯に収まりますが、数年先を想像したとき「崩れにくい選択肢」としてどうしてもRTXを手に取りたくなる。
私は趣味にしろ仕事にしろ、できるだけ長期的に安心できる環境を優先しているんです。
ただし、人によっては「とにかくコスパ重視」という考え方も確かにあります。
私も独身時代に限られた小遣いでパーツを組み合わせ、夜中に電気を消してスペック表をじっと見比べながら頭を抱えたことが何度もありましたから、その気持ちは痛いほど理解できます。
けれど一方で、たとえばApexで撃ち合いの最中にほんの一瞬フレームが落ちて敗北につながることがある。
正直、撃ち合いの瞬間に画面が一瞬止まる。
あれは本当に腹立たしい。
私も何度机を叩きたくなったことか。
それ以来、もし誰かに聞かれたら迷わずこう答えます。
「勝ちたいならRTXだ」と。
精神的な保険ですね。
滑らかさと予測できる挙動を買うことは、結局プレイを安心して楽しむための保険料だと割り切っています。
社会人としての生活でもトラブルを避けるために余分なお金や時間を投資するのは当然のことですし、それと同じでプレイ環境においても「備え」にお金をかけるのはむしろ建設的な判断だと思うのです。
全体として見れば、Apex専用の10万円台のPCを考えるなら、やはり私自身の答えは「RTXを選ぶ」です。
それでも私が譲れないのは「迷いなく勝負に集中できること」であり、その一点でRTXに分があるのは確かだと感じています。
今までの試行錯誤や悔しい体験を経て、そうはっきり断言するのです。
安定こそ最良の武器。
信頼できる環境。
ゲーミングPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60CL


| 【ZEFT R60CL スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9700X 8コア/16スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.80GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal Design Pop XL Air RGB TG |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (内蔵) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60FS


| 【ZEFT R60FS スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9060XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z54Y


| 【ZEFT Z54Y スペック】 | |
| CPU | Intel Core Ultra7 265K 20コア/20スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.90GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5050 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | intel B860 チップセット ASRock製 B860M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z55ED


| 【ZEFT Z55ED スペック】 | |
| CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) |
| ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II White |
| マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
アップグレードするなら最初に手をつけたいパーツは?
ゲームをしていて一番ストレスになるのは、画面がカクついたり反応が遅れたりする瞬間だからです。
CPUを後回しにしてでもGPUを先に換えるだけで、まるで別物の体験になることを、私は実際に肌で感じてきました。
古いGPUを使っていた頃は、敵を見つけても描画が遅れて撃ち負けることが多く、悔しさのあまり机を叩いたことすらありました。
だから最初はグラフィックボード、これは間違いないと思っています。
フルHD環境の時代に思い切ってGPUを新調した時のことを、今でもよく覚えています。
ガクガクと引っかかっていた画面が不思議なくらい滑らかになり、弾を撃つたびに反応が即座に返ってくる。
その瞬間、「あぁ、これが本来のゲーム体験なのか」と思わず声が出ました。
スマホを最新機種に替えて、その快適さに驚くあの感じにとても近かったです。
やってみなければ分からない強烈な差でした。
最近のGPUの進化は本当に目を見張るものがあります。
中位からやや上のモデルを選ぶだけで、200fpsを安定して出せる時代になりました。
WQHDが高嶺の花だったのは昔の話で、今では144Hz以上の環境も十分手の届くところにあります。
配信を同時に走らせても重さを感じにくい場面も増えました。
余裕があるって、気持ちまで前向きにするものです。
もちろん、GPUだけですべてが完結するわけではありません。
次に考えるべきはメモリです。
16GBで何とかやりくりする時代は、そろそろ終わりに近づいています。
配信や複数のアプリを同時に使うことを考えれば、32GBは自然な選択です。
それほど違いがあったのです。
小さなストレスが消えるたびに集中が増していき、それが結果につながる。
実はそれが一番大きな意味を持っているのだと思います。
ストレージに関しても、昔の「とりあえずHDDに積む」という発想はもう通用しません。
エーペックスのように頻繁に更新が入るゲームをHDDで扱うのは、効率が悪すぎます。
小さな積み重ねですが、長い時間プレイする人には大きなアドバンテージです。
ロードの速さは単なる利便性にとどまりません。
集中を切らさない武器なのです。
CPUについては、多くの人が「最新にしなきゃ」と思いがちです。
しかし、エーペックス単体で見ればGPUの方が圧倒的に影響が大きく、CPUだけでは勝率を変える要素になりません。
そのタイミングで冷却や静音性も一緒に考えると良いと思います。
深夜プレイ時にファンの音が静かなだけで、環境の心地よさは想像以上に違うんです。
そして最後にケースや電源。
これを軽く扱う人も多いですが、私は真っ先に大事にするようになりました。
昔、大会中にエアフロー不足が原因でGPUが熱暴走し、いきなり試合が止まったことがあったのです。
あの絶望感は二度と味わいたくありません。
だから以降は、風の通り方と電源の安定性を必ず確認するようにしています。
高性能パーツほど熱に弱い。
車内に放置したスマホが熱で落ちるのと同じことが、ゲームPCでも起こるわけです。
弱点対策を軽視してはいけません。
順序を整理すると、まずGPUで基盤を固め、次にメモリを拡張し、ストレージをSSDで整え、最後にCPUや冷却とケース電源を仕上げる。
この流れを守って進めれば、中途半端な迷走に陥ることなく確実に環境が育っていきます。
大事なのは優先順位を間違えないこと。
それだけでゲーム体験は見違えるものに変わります。
効率よく揃えること。
これが押さえておくべき要点です。
私が本当に伝えたいのは、パーツを換えて数値が上がること自体よりも、そのときに自分が感じる安心感や満足感の方がずっと価値があるという点です。
スペック表の数値よりも、レスポンスの速さや静かさに包まれた安心感こそ、長時間のプレイを支える力になるんです。
それを少しずつ積み重ねていくことこそが、結局は最も大切な投資なんだと、私は強く感じています。
SSDは1TBで足りるのか、それとも2TBが安心か?
なぜなら1TBでは最初は問題なくても、結局のところ「足りない」と感じて容量を整理することに追われ、その度に楽しさが薄れてしまうからです。
実際、私は以前1TBで運用していた際に、ゲームをする前にまず「今日はどのデータを消すか」ということを考える時間が増えてしまいました。
本来ならワクワクしながら起動するはずなのに、ああまたか、とため息をつく瞬間の多さに疲れがじわじわと積もったのです。
もちろん、コストを考えれば1TBは魅力的です。
導入の段階で出費が抑えられるのは明らかなメリットだと思います。
数分だから大したことないと割り切れる人もいるのでしょうが、私はその「チリツモのストレス」が思った以上に重くのしかかりました。
この時間でゲームを一本でも多く遊べたかもしれない、そう考えたときの損失感はなかなか拭えません。
特に私が強く2TBを推すようになったのは配信を始めてからです。
録画データがあっという間に膨れ上がり、気づけば外付けHDDに逃さざるを得ない状況になりました。
外付けを使えば一応対応はできますが、やはりロード時間や安定感では内蔵SSDには到底かないません。
ロード待ちのあの間延びした時間に、しびれを切らした経験のある人はわかるはずです。
余裕のある内蔵SSD環境は、結局のところパフォーマンスだけでなく精神的な快適さをもたらします。
やっぱり内蔵が一番なんです。
さらに最近の傾向を見ても、NVMe SSDの2TBは性能とコストのバランスがかなり良く、速度や安定性で安心できる製品が増えています。
容量が異なると挙動も変わるため、ベンチマーク以上の違いを実際に感じるのです。
私はこれを実機で体験してから確信しましたが、やはり2TBクラスには余裕の「強さ」があると。
結果として、費用と安心感を両立するなら自然に2TBが有力候補になります。
動画編集に少し手を出した方ならわかるのではないでしょうか。
そこに加えてゲームデータや追加コンテンツを乗せると、1TBはすぐに枯渇します。
外付けを増設すれば物理的に対応はできますが、その瞬間から運用の面倒さが始まります。
別ドライブに振り分ける環境管理は、一見便利なようでいて長い目で見るとリスクばかり増えるんですよね。
そう、落とし穴です。
価格について触れると、Gen4 SSDの2TBモデルはようやく手の届きやすい価格帯に落ち着いてきました。
しかも現行の主流規格なので、多くのユーザーに支持されている安心感もあります。
誤解のないように言っておきますが、Gen5 SSDも確かに最先端です。
ただ、発熱やコストを考えると、全員にすすめられる選択肢ではありません。
ヒートシンクやエアフローを詰めて調整する環境作りは、かなりマニアな人向けの領域です。
私は正直そこに時間を割けない。
だからGen4の2TBで十分、いや十分すぎると感じています。
ただ、もちろん予算が限られている方もいます。
その場合は1TBでスタートし、後から拡張する道もゼロではありません。
ただしそのときには、追加で取り付ける余裕がPCに残っているか、特にM.2スロットの有無は必ず確認しておいた方がいい。
ここを見落として後悔している人を、私は何人も見てきました。
これ、本当にありがちな失敗なんです。
また、ゲームだけでなくOSや各種ドライバ、キャッシュファイルが予想以上にじわじわと容量を食ってきます。
これは私自身の痛い体験なのですが、最初から余裕を持っておかないと、後から立て直すのは結構しんどいのです。
気分的にも落ち込みますしね。
スマートフォンの容量選びにも似ています。
契約するときには「64GBで十分」と思っていても、写真や動画を撮りためるうちにすぐ窮屈になり、買い替えの欲求に押されるあの感覚です。
パソコンのSSDもまさに同じ。
だからこそ、先を読んで選択することの価値が際立ちます。
ただ、この差額を「安心料」と考えるなら話は違ってきます。
私は仕事柄いろいろな機材投資をしてきたので実感していますが、余裕を見込んだ投資で後悔することはほとんどありませんでした。
後悔するときはいつも、ギリギリで妥協したときでした。
あの悔しさはどうしても尾を引きます。
だから私は胸を張って言います。
Apexのように長く続くゲームを楽しむなら、2TBを選ぶべきです。
確かに1TBでも遊べます。
しかし、余裕がない環境は気持ちまで削っていくのです。
快適でストレスの少ない運用を本気で望むなら、最初から2TBを構えておくこと。
この判断が最終的に一番効率的で満足度の高い選択肢になることは間違いありません。
安心感が全然違うんですよ。
冷却方式は空冷と水冷のどちらが扱いやすい?
特に配信を同時に行う環境ではCPUやGPUへの負荷が非常に大きく、その熱処理を軽視するとパフォーマンスが一気に崩れることを、これまでの経験でいやというほど実感してきました。
長時間安定して稼働する環境を整えるには、冷却の方式をいい加減に選んではいけないのです。
だからこそ、私が出した答えは「やはり空冷に分がある」というものです。
取り付けが比較的容易で、日常的に大きなトラブルが出にくいという点は、仕事でも長年PCを使ってきた自分にとって非常に大きな安心要素です。
小さな不具合が続けば集中力もそがれますし、そのたびに時間を奪われることになります。
仕事でも趣味でも「安定して動くこと」が第一なのは変わらない。
だから私はどうしても空冷を選びたくなるのです。
一方で、水冷にも惹かれる瞬間はあります。
数年前に簡易水冷を導入したとき、熱処理の心配をほとんどせず、静かに稼働するPCに「これは理想の形かもしれない」と感動した記憶があります。
あのときのすっきりしたケース内部、静寂の中で淡々と動き続ける姿には夢を見るような気持ちになった。
ただし時間が経つと、耳に残るポンプ音が心の中で少しずつ積もっていき、「空冷に戻したほうがいいかもしれないな…」と独り言を漏らしてしまったのを今でも覚えています。
水冷は年々進化し、静音性や耐久性が向上してきたのも事実です。
しかし、完全にメンテナンス不要とまでは言えません。
ポンプや冷却液といった部品は必ず寿命がありますし、突発的なトラブルは避けられません。
ビジネスの現場で最優先されるのは「止まらないこと」。
その価値観をそのまま趣味のPC環境に重ねるなら、やはり安定性に優れる方式が必要だと思うのです。
見た目に寄せるか、実用を選ぶか。
これは単純なようでなかなか悩ましい問いです。
そのため大型空冷クーラーを組み込んでも以前より快適な冷却環境が作れますし、ファンの追加や交換での調整も容易になりました。
長く使うことを考えたときに、保守のやりやすさや交換部品のコストも見逃せません。
限られた予算でしっかりした性能を維持する。
そこに空冷の実力があると思っています。
では最終的にどちらを選ぶべきか。
これははっきりしています。
もし10万円台でエーペックスレジェンズを配信込みで快適に遊びたければ、私は空冷を推します。
コストパフォーマンスの良さ、扱いやすさ、そして不安の少なさ。
この三拍子を重視すれば、おのずと答えは空冷に行き着くはずです。
もちろん水冷は、高解像度や高フレームレートを追い求め、とことん突き詰めたい方にはふさわしい手段です。
配信環境でどうしても静音を突き詰めたいという人にとっては、水冷が応えてくれる場面もある。
それでも、「本当にそこまで必要だろうか?」と自問すると、答えは多くの場合「今はまだ空冷で十分」なのです。
それでも水冷の最新モデルを見ると、心が揺れる瞬間があります。
NZXTやCorsairのクーラーを見たときのあの高級感、緻密で洗練されたデザインに「また触ってみたい」と思わされる。
自作PCの楽しみをくすぐる誘惑がそこにはあるのです。
ただ、そこで冷静になって考え直すと現実が迫ってきます。
もしトラブルが起きたとき、修理や交換にかかる手間、パーツ寿命による影響、不測の停止リスク――それを抱え込む余裕が今の私にあるか。
結局そう自問して「いや、やっぱり空冷でいいや」と落ち着くのです。
派手さより安定。
これです。
見た目の良さを追いかけるより、確実に長く使えて安心できる選択をしたい。
これはビジネスにもそのまま通じます。
40代になってからは時間や手間に対する感覚が大きく変わってきて、多少格好悪くても安心できるものを優先したいと強く思うようになりました。
「無駄な心配をするぐらいなら、地味でも安定したやり方を取る」。
そんな思考が自然と根を下ろしました。
だからこそ、私が導いた結論はごくありふれたものです。
エーペックスレジェンズを安心して配信まで楽しみたいなら、まずは空冷クーラーをしっかり選ぶこと。
水冷は特別なこだわりを持つ人に残しておく選択肢です。
余計な不安を抱えない。
予期せぬトラブルに頭を悩ませない。
私はそこに大きな意味を見いだしています。
安心感が欲しい。
何より大切にしたいのは、結局この二つなのです。
人気PCゲームタイトル一覧
| ゲームタイトル | 発売日 | 推奨スペック | 公式 URL |
Steam URL |
|---|---|---|---|---|
| Street Fighter 6 / ストリートファイター6 | 2023/06/02 | プロセッサー: Core i7 8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: RTX2070 / Radeon RX 5700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter Wilds
/ モンスターハンターワイルズ |
2025/02/28 | プロセッサー:Core i5-11600K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce RTX 2070/ RTX 4060 / Radeon RX 6700XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Apex Legends
/ エーペックスレジェンズ |
2020/11/05 | プロセッサー: Ryzen 5 / Core i5
グラフィック: Radeon R9 290/ GeForce GTX 970 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| ロマンシング サガ2
リベンジオブザセブン |
2024/10/25 | プロセッサー: Core i5-6400 / Ryzen 5 1400
グラフィック:GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| 黒神話:悟空 | 2024/08/20 | プロセッサー: Core i7-9700 / Ryzen 5 5500
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700 XT / Arc A750 |
公式 | steam |
| メタファー:リファンタジオ | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i5-7600 / Ryzen 5 2600
グラフィック:GeForce GTX 970 / Radeon RX 480 / Arc A380 メモリ: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Call of Duty: Black Ops 6 | 2024/10/25 | プロセッサー:Core i7-6700K / Ryzen 5 1600X
グラフィック: GeForce RTX 3060 / GTX 1080Ti / Radeon RX 6600XT メモリー: 12 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンボール Sparking! ZERO | 2024/10/11 | プロセッサー: Core i7-9700K / Ryzen 5 3600
グラフィック:GeForce RTX 2060 / Radeon RX Vega 64 メモリ: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE | 2024/06/21 | プロセッサー: Core i7-8700K / Ryzen 5 3600X
グラフィック: GeForce GTX 1070 / RADEON RX VEGA 56 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ファイナルファンタジーXIV
黄金のレガシー |
2024/07/02 | プロセッサー: Core i7-9700
グラフィック: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5600 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Cities: Skylines II | 2023/10/25 | プロセッサー:Core i5-12600K / Ryzen 7 5800X
グラフィック: GeForce RTX 3080 | RadeonRX 6800 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ドラゴンズドグマ 2 | 2024/03/21 | プロセッサー: Core i7-10700 / Ryzen 5 3600X
グラフィック GeForce RTX 2080 / Radeon RX 6700 メモリー: 16 GB |
公式 | steam |
| サイバーパンク2077:仮初めの自由 | 2023/09/26 | プロセッサー: Core i7-12700 / Ryzen 7 7800X3D
グラフィック: GeForce RTX 2060 SUPER / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| ホグワーツ・レガシー | 2023/02/11 | プロセッサー: Core i7-8700 / Ryzen 5 3600
グラフィック: GeForce 1080 Ti / Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| TEKKEN 8 / 鉄拳8 | 2024/01/26 | プロセッサー: Core i7-7700K / Ryzen 5 2600
グラフィック: GeForce RTX 2070/ Radeon RX 5700 XT メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| Palworld / パルワールド | 2024/01/19 | プロセッサー: Core i9-9900K
グラフィック: GeForce RTX 2070 メモリー: 32 GB RAM |
公式 | steam |
| オーバーウォッチ 2 | 2023/08/11 | プロセッサー:Core i7 / Ryzen 5
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 6400 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Monster Hunter RISE: Sunbreak
/ モンスターハンターライズ:サンブレイク |
2022/01/13 | プロセッサー:Core i5-4460 / AMD FX-8300
グラフィック: GeForce GTX 1060 / Radeon RX 570 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| BIOHAZARD RE:4 | 2023/03/24 | プロセッサー: Ryzen 5 3600 / Core i7 8700
グラフィック: Radeon RX 5700 / GeForce GTX 1070 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |
| デッドバイデイライト | 2016/06/15 | プロセッサー: Core i3 / AMD FX-8300
グラフィック: 4GB VRAM以上 メモリー: 8 GB RAM |
公式 | steam |
| Forza Horizon 5 | 2021/11/09 | プロセッサー: Core i5-8400 / Ryzen 5 1500X
グラフィック: GTX 1070 / Radeon RX 590 メモリー: 16 GB RAM |
公式 | steam |