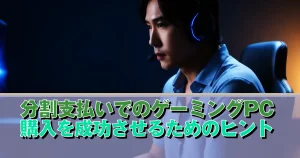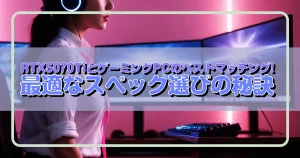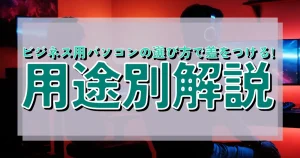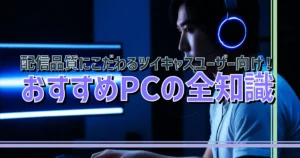Ryzen 9800X3D ゲーミングPCを予算別にどう組むか考える

10万円台でそこそこ快適に遊ぶためのパーツ選び
そのジレンマと長年付き合ってきたからこそ、この構成に落ち着いたのです。
だからこそ「10万円台でそこそこ快適」、これ以上に現実的で納得のいくテーマはない。
肝心のGPUについて。
やはり全体のゲーム体験を左右する最も重要なパーツです。
これまで長いことGeForceを軸に組んできた私は、RTX5070くらいが一番肩ひじ張らずに性能を楽しめると感じています。
RTX5060Tiも試しましたが、軽いゲームは問題なくても最新の重量級タイトルではややモタつく印象が強かったのです。
画面がカクつくと正直気持ちが萎えるんですよね。
だから今回は妥協せず5070。
もしくはRadeonのRX9060XT。
初めて使ったときは、そのフレームの滑らかさに思わず「おお、ここまで自然に進化したのか」と声が漏れました。
ここはRTX5070かRX9060XT、この二択で間違いなし。
自分の経験から強くそう言えます。
Ryzen 9800X3Dです。
以前使っていた9700Xでは、CPU負荷が重い場面で足を引っ張られてしまい少々ストレスが溜まっていました。
それを9800X3Dに切り替えた瞬間、あまりの余裕っぷりに「やっと本領発揮だな」と思わずつぶやいてしまったほどです。
何も工夫をしなくても安定してパワーを出せる。
その安心感は格別です。
しかも価格帯もGPUとのバランスを考えれば十分射程圏内。
このCPUはまさに頼れる相棒。
メモリは今回32GBにしました。
でもそのたびに数年後には動作が窮屈になって再投資を強いられた。
もうあの苦労はごめんです。
DDR5-5600あたりなら価格と性能のバランスも上々で、余裕をもった動作が期待できます。
経験上、ここはケチってはいけない。
ストレージはどうするべきか相当悩みました。
容量を減らして価格を抑えたい誘惑に何度も負けそうになりながらも、最終的に1TBのGen.4 NVMeを選択しました。
確かに2TBならさらに余裕がありますが、まだ高い。
Gen.5も魅力的です。
ただし本体価格に加えて発熱対策など見えないコストが増えていく。
ここは空冷を選びました。
9800X3Dは極端な発熱をするわけではないし、ミドルクラスの空冷で十分安定します。
もちろん水冷も見栄えが良くて格好いいですが、メンテナンスに時間を取られるのは嫌なんですよ。
だから迷いなく選択。
ケース選びは最後まで心が揺れました。
透明なガラス張りや派手なRGBのケースは確かに気持ちをくすぐるんです。
でも現実的に見れば冷却性能と内部の整理のしやすさが何より大事。
結果、強化ガラスでスタンダードなモデルに落ち着きました。
このパーツを選べば10万円台の範囲できちんと収まるし、最新のゲームも胸を張って楽しめます。
安心してプレイできる。
正直に言えば、この構成からさらに一歩上を狙えば一気に20万円になる。
それでも逆に安さを追って削ってしまうと、日常的に小さな妥協の連続になるでしょう。
10万円台で遊びたいなら、この構成以外は考えづらい。
身の丈に合った一台。
20万円前後なら長く安心して使える構成にまとめる
私もこれまで何度も構成を考えては自作を繰り返してきましたが、正直言って派手さや一時の性能に惹かれて高価なパーツを選んだときほど、後々の後悔が残るんですよね。
冷静に見れば、数年先を見据えて無理のないパーツを選んでおくほうが、結局はお金も時間も無駄にせず、落ち着いてゲームを楽しめる形になります。
心からそう感じています。
CPUについては、Ryzen 9800X3Dを選んだときに「とにかく周辺とのバランスを崩さないこと」が一番大事でした。
ベンチマークで一瞬見栄えの良い数値を追うよりも、これから出てくるゲームを問題なくプレイできるだけの余裕を残しておく方が後々の快適さにつながります。
派手さよりも安定性、若い頃なら考えなかったかもしれませんが、今は迷わずそう結論づけますね。
そしてグラフィックボード。
ここはお金全体の軸になる部分です。
私は結局RTX 5070Tiを選んだのですが、その瞬間「ああ、やっぱりこれだよな」と思いました。
4Kでの新作タイトルもストレスなく動きましたし、熱暴走でゲーム中にイライラすることも少なかった。
正直、これ以上上位のカードを選んでしまうと生活費や貯金に響く。
20万円前後という枠を守りながらちょうど良い贅沢に落とし込む、ここが大事なんです。
だから5070Ti。
この選択には今も納得しています。
メモリに関しては、32GBを積んでおくのが現実的で安心です。
昔は16GBで十分な時代もありましたが、最近はさすがに厳しい。
RPGを遊びつつ配信し、その裏でブラウザを複数開いて調べ物をする、そんな日常的なスタイルだともう16GBでは窮屈すぎるんです。
正直それ以上積んでも費用対効果は薄いと感じます。
だから欲張らず32GB。
これが経験から得た一番納得できる数字です。
ストレージは2TBのGen.4 NVMe SSD。
ここは強くこだわりたいところです。
私も昔は「1TBで十分」と思い込んでいました。
けれど実際にはAAAタイトルを3、4本入れただけで容量が限界に達してしまい、結局外付けHDDを買い足す羽目になった。
そのときの徒労感たるや、二度と味わいたくないですね。
最近のゲームは1本で100GB越えなんて当たり前なので、最初から2TBを選んでおく方が絶対に楽です。
容量不足に怯えずに済む安心感、これは本当に大きい。
正直なところ水冷の格好良さには今でも惹かれます。
大型の空冷クーラーなら冷却性能も十分で静音性も確保できますし、実際に使うとゲーム中でも心に余裕が生まれるんです。
ケースも流行のピラーレス構造ではなく、風通しの良い定番のガラスパネルタイプを選んでいます。
派手さは控えめでも、結果的に日々の掃除や熱管理のしやすさが効いてくる。
ここはあえて地味で良い。
いや、むしろ地味な方が気楽です。
全体を俯瞰すると、「突出しすぎない選択」が20万円前後のラインで理想的な答えになると私は考えます。
最高性能を求めたければ素直に30万や40万を投じればいい。
でもこの20万円ラインには身の丈に合った満足感がしっかり宿るんです。
だからバランスを取る。
これが一番大切な鉄則です。
私も過去にGPUとCPUの釣り合いを無視した構成を組んだことがあります。
そのときのことは今でも悔しく思い出します。
せっかくのCPUが力を発揮できず、宝の持ち腐れになってしまった。
あの哀愁は二度と味わいたくありません。
だからこそ今回は9800X3Dと5070Tiを軸にする。
この組み合わせであれば、CPUもGPUも互いの強みを引き出し合い、無駄のないマシンに仕上がります。
そこに32GBメモリ、2TB SSD、そして頼れる空冷クーラー。
これで構成はしっかり固まります。
20万円前後で安心して長く付き合えるPC。
これ以上を望む必要はないのだろうと胸を張って言えます。
つまり、私にとっての「最適解」は明快です。
安定したCPU、堅実なGPU、余裕を持たせたメモリとストレージ、そして丁寧に選んだ冷却とケース。
この組み合わせこそが後悔のない投資になります。
派手さで見栄を張るよりも、日々心地よくゲームを楽しめる余裕が欲しい。
無理のない形で手に入った安心感。
それが私の答えです。
背伸びしない喜び。
40代の私がようやくたどり着いた、本当に暮らしに馴染む一台。
30万円を超えるなら画質もフレームレートも妥協しない
30万円を超えるゲーミングPCを組もうとするとき、私が最も大切にしているのは「後から後悔しない」ことです。
安く抑えたつもりでも、いざ動かして不満が出はじめると、その不満がずっと積もっていきます。
だから高額を投じるならこそ、妥協なしの構成で固めるべきだと強く思うのです。
Ryzen 9800X3Dを軸にする場合、その性能を中途半端に引き出すのはもったいない。
いわば高級な車のエンジンを手に入れながら、足回りを安物で誤魔化すようなものです。
私はそんなアンバランスだけは避けたい、そう感じています。
RTX 5070TiやRadeon RX 9070XTといった上位モデルを避けると、結局4Kや高リフレッシュレートでのプレイが成立しません。
以前、私は一つ下のモデルで我慢したのですが、新作のタイトルで画質設定を落とした瞬間のあの虚しさは今も記憶に残っています。
「どうしてあの時に投資しなかったんだ」と、後になって後悔する。
だから今は迷わずGPUに力を注ぐ。
そう決めています。
メモリの容量についても、32GBから64GBへと切り替えた時の変化は衝撃的でした。
配信しながら、動画編集ソフトを開きながら、さらにゲームを走らせるような状況では32GBでは引っかかりが出て、集中力が途切れることが多かったのです。
64GBにして以降、そのわずらわしさが完全に消え、作業の流れが途切れなくなりました。
単なる数字の倍増ではなく、心の余裕まで変わる。
まさに「大は小を兼ねる」を肌で実感しましたね。
Gen.5 SSDを導入したときの、読み込み速度の体感は本当に段違いでした。
特にRPGなどでロード画面を待つ時間が半分ほどに短縮された瞬間は、正直言って笑ってしまったほどです。
毎日積み重ねるプレイだからこそ、わずかな時間差が精神的な快適さを大きく左右するのだと思います。
小さな差ではありません。
CPUクーラーも軽視してはならない部分でした。
初めの頃は「ハイエンド空冷で十分だろう」と思い込んでいたのですが、夏場にファンが全力で回り始めたときの轟音には本当に参りました。
ゲームどころかその場にいるのも嫌になるレベルでした。
その後、思い切って水冷に切り替えると静音性がまるで別物で、とても落ち着いた気分で夜でも作業に集中できました。
導入の手間は確かにありましたが、その満足感は比べ物になりません。
静けさは強い味方です。
ケース選びでは過去に失敗した経験があります。
デザイン重視の安いケースを買った結果、内部配線がしづらく、空気の流れも悪く、夏にはPC内部の温度が上がってしまい、本来の性能を発揮できなかったのです。
その経験から、いまはデザインと機能を両方確認せずに購入しません。
最近ではガラスパネルやピラーレス構造のケースが増え、美しさと整備性、冷却性を兼ね備えた選択肢がそろっています。
そうした製品を導入したときに感じるのは、ただの道具ではなく「所有する喜び」でした。
私はこうした一つ一つの選択を経て、ようやく自分の答えにたどり着きました。
30万円を超えるなら、中途半端な構成はしない方が良いと。
Ryzen 9800X3Dのパフォーマンスをフルに引き出すため、GPUには現行の上位モデルを、メモリは64GB、ストレージはGen.5 SSD、水冷クーラーを採用し、ケースも冷却性能を重視する。
この組み合わせこそが、性能と静音性、デザインまでを揃えた理想的なマシンを作り上げる唯一の方法だと確信しています。
正直、この構成で組んだPCを目の前にしたとき、自分のお金の使い方にやっと納得できた気がしました。
圧倒的なパフォーマンスが常に待機している安心感。
静かに力強く回り続ける頼もしさ。
ゲームも仕事も、自信を持って向き合える環境が目の前に整ったのです。
それまで悩み続けてきた時間が一気に報われる瞬間でした。
ああ、これが本当の正解なんだと心から感じました。
そうした思いから、もしこれから30万円を超えてPCを組もうとしている方がいるなら、私は遠慮せず言いたいのです。
「どうせここまで投資するなら、最高の構成を狙った方がいい」と。
将来、「あの時なぜ妥協したのだろう」と後悔するのは本当に辛いことです。
だから後になって振り返ったときに胸を張れるように、今できる最善を形にすべきだと心の底から思います。
胸を張れる一台。
それこそが、本当に価値のあるゲーミングPCです。
学生向け Ryzen 9800X3D ゲーミングPC パーツの選び方

CPUと冷却 ― 空冷で十分か、水冷にすべきか
Ryzen 9800X3Dを購入してから、まず真っ先に考えたのは冷却方式でした。
正直なところ、このクラスのCPUなら空冷で十分にいけると私は思っています。
実際に使ってみて、動作が不安定に感じたり、処理落ちに悩まされたことはほとんどありません。
それでも冷却にまつわる話題は、性能だけでなく快適さや安心感に直結するだけに、人によって捉え方がバラバラです。
ある人にとっては多少の騒音は我慢できますが、別の人にとっては「静けさ」そのものが価値になります。
つまり、単純な数値ではなく、ライフスタイルに大きく左右される要素なのです。
9800X3DのTDPは120W。
この水準なら、正直それほど手強い相手ではありません。
私自身、長時間のゲームプレイでも温度は70度前後に収まり、パフォーマンスが落ちることもほとんどありませんでした。
ファンが急に唸り声を上げて集中が削がれる心配もほぼなし。
安心感というのは、やはり使う側の余裕につながりますね。
ただし盛夏の真っ只中、締め切った部屋で何時間も動かすとなると、さすがの空冷でも少し苦しい。
そういう場面での水冷の強さは認めざるを得ません。
水冷なら温度をぐっと下げられますし、ファンの回転を抑えられるおかげで静音性もワンランク上に感じられます。
静けさ。
これを大事にするなら水冷の選択は十分ありだと思います。
ただし導入の敷居が高いことと、メンテナンスの不安は常につきまといます。
水漏れやポンプトラブルに出会うリスクを想像すると、正直私は二の足を踏んでしまうのです。
かつてNZXTの簡易水冷を導入した経験があります。
ゲーム中は驚くほど静かで、温度は申し分ありませんでした。
けれど夜中ふと気になってしまうポンプの微妙な振動音や、あの太いホースの取り回しの厄介さ。
それを毎日のように扱ううちに、小さな積み重ねが気持ちを揺さぶるのです。
結局のところ、便利さと不便さは表裏一体なんですよね。
その反動もあって、私は9800X3Dでは空冷がベストだと確信しています。
近年の空冷クーラーは進化が著しく、大型の製品を選んでおけば冷却力は十分、しかも騒音も驚くほど抑えられています。
数年前の空冷のイメージしか持っていない方は「本当にそれで足りるのか」と不安を抱くかもしれません。
水冷でなければ性能が発揮できないという発想は古い常識になりました。
空冷にもきちんとした価値があるのです。
もちろん、PCに見た目の華やかさを求める方もいるでしょう。
RGBライティングや大きなラジエーターの存在感は、確かに視覚的な満足感を与えてくれます。
特に学生さんや、組んだPCそのものを「見せて楽しむ」ことを意識するユーザーにとって、水冷の美しさは間違いなく魅力的です。
一方で、私のようにシンプルで機能的な安定稼働を重視する人間にとっては、少し仰々しすぎるのも事実。
その差こそが人の価値観なのでしょう。
実際に私は、空冷で冷却不足に困った経験はほぼありません。
長時間のゲームや動画編集でも安定して動き続けてくれるので、ストレスを抱えたことがありません。
それは単なる「十分」ではなく「適している」とさえ言っていい。
安定しているからこそ安心して趣味や仕事に没頭でき、余計な不安を感じないという点は非常に大きな差になります。
最終的に冷却方式をどう選ぶかは、その人の優先順位の問題に帰着します。
見た目や静音性、パフォーマンスのピークをとことん追求したいなら水冷。
その一方でコストを抑えて快適に長く使いたいなら空冷。
ライフスタイル次第。
そういう話です。
特に学生や初めて組む方なら、空冷であっさり満足できるはずですし、不安要素が少ないというのは思った以上に大きなメリットになります。
Ryzen 9800X3Dなら空冷で十分。
そして、どうしてもデザインや静けさにこだわりたい人だけが水冷を導入すれば良い。
どちらを選んでも基本的な性能は十分引き出せるので、冷却不足を心配しすぎる必要はありません。
選択はもっと肩の力を抜いていい。
そこに気づいたとき、PCづくりの楽しみ方そのものが少し楽になりました。
最終的には「自分に合うかどうか」それだけなのだと、私は実感しているのです。
最新CPU性能一覧
| 型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 42923 | 2462 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42678 | 2266 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 41712 | 2257 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 41007 | 2355 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38483 | 2075 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38407 | 2046 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37176 | 2353 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265KF | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37176 | 2353 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 9 285 | 24 | 24 | 2.50GHz | 5.60GHz | 35552 | 2194 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35411 | 2232 | 公式 | 価格 |
| Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33667 | 2205 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32811 | 2235 | 公式 | 価格 |
| Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32445 | 2099 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.50GHz | 32334 | 2190 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29174 | 2037 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265 | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28462 | 2153 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 7 265F | 20 | 20 | 2.40GHz | 5.30GHz | 28462 | 2153 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25380 | 0 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 245KF | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25380 | 2172 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 23022 | 2209 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8 | 16 | 4.70GHz | 5.40GHz | 23010 | 2089 | 公式 | 価格 |
| Core Ultra 5 235 | 14 | 14 | 3.40GHz | 5.00GHz | 20797 | 1857 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19452 | 1935 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17682 | 1814 | 公式 | 価格 |
| Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 16001 | 1776 | 公式 | 価格 |
| Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15246 | 1979 | 公式 | 価格 |
グラボ選びで迷ったら RTXとRadeonの特徴をどう見るか
Ryzen 9800X3DでPCを組むと決めた時、一番頭を悩ませたのはやはりグラフィックボードの選択でした。
CPU性能に関しては十分すぎるほどで、心配する余地はほとんどありません。
むしろGPUの選定こそが快適性を左右する要因になる、と強く感じていました。
最終的に私がたどり着いた答えは、長期的に安定性と高い解像度を重視するならRTX、コストを抑えながら実用性を重んじるならRadeonという二択になる、ということです。
DLSSの進化によって負荷の高いタイトルでも余裕が生まれ、4K画質でもフレームレートが安定します。
以前の世代では処理落ちして苛立っていた場面で、今ではサクサク進むことに正直感動しました。
さらに入力遅延の低減機能はFPSを遊ぶ際に「遅れを取らない」と思わせてくれる大きな安心材料でした。
競技性のあるタイトルでこの差は無視できませんね。
一方で、Radeon RX 90シリーズの良さは別のところで光ります。
FSRの対応幅が非常に広いので、わざわざ互換性を心配せずに使える気楽さがあります。
私はRX 9060XTを導入した際、正直な感想は「価格を考えればすごく優秀」でした。
突出した派手さはありませんが、毎日のようにWQHDで遊ぶ私にとって、ストレスなく付き合える存在なのです。
堅実さ。
これがRadeonの本質だと改めて感じました。
検証を続けると、両者の違いが数字だけでは見えない部分に現れてきます。
RTXはどうしても発熱が強めで、ケース内の冷却対策を甘くすると途端に不安になる瞬間がありました。
それに対して、Radeonはかつて不安定さが目立っていたドライバが数年で大きく改善され、フリーズのリスクに怯える必要がほとんどなくなっています。
長くPCを組んできた私からすると、この進化は想像以上に大きい意味を持っていました。
また、ゲーム以外で考えると配信での安定性も選択の要素になりました。
一方でRTXは動画エンコード能力が突出していますが、私の用途からすると少し余り気味に感じられました。
用途によってはオーバースペック、というのが正直なところです。
予算面ではさらに悩みました。
RTXを選ぶとGPUだけでかなり資金を消費するので、電源やケースに多少の妥協をせざるを得ません。
その結果、全体のバランスに小さな不満が残ったのも事実です。
逆にRadeonを選んだ際には予算が浮き、その分をメモリに回して64GBまで増強できました。
快適なマルチタスクと高速ロード。
これは日常使いでもすぐ体感できる効果でした。
近年のゲーム動向を考えると、AI技術や高度なレイトレーシングが当たり前になりつつあります。
その流れに備えるにはRTXの技術力が有利に働くことは疑いようがありません。
未来を見据えて長期的に使いたい人にとって、RTXは安心できる投資先になるでしょう。
しかし、今この瞬間に快適さを求め、確実にコストに見合った満足を得たいのならRadeonに軍配が上がります。
結局のところ、自分の生活リズムや遊び方に照らして最適な選択をすることが大切なんです。
一方で、費用を抑えながらも安定した実用性を優先したいならRadeon。
まさにこの二つの選択基準に尽きるのです。
天井を突き抜けたいのか、それとも堅実に満足を積み上げたいのか。
その見極めが、Ryzen 9800X3Dを核に据えたPC構築を後悔なく仕上げる最後の分岐になる、と私は思います。
考え続ける時間が長かった分、最終的にどちらを選んでも納得ができるのが不思議です。
むしろ、この葛藤こそが自作PCの面白さを際立たせているのでしょう。
この瞬間のために、私は今日もパーツの選択に迷い続けています。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
| GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 32GB | 48533 | 101751 | 575W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5080 | 16GB | 32047 | 77933 | 360W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 XT | 16GB | 30055 | 66640 | 304W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 29978 | 73293 | 355W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 Ti | 16GB | 27075 | 68805 | 300W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9070 | 16GB | 26420 | 60131 | 220W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5070 | 12GB | 21879 | 56698 | 250W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19855 | 50392 | 263W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 16GB | 16507 | 39301 | 145W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 16GB | 15942 | 38131 | 180W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 8GB | 15805 | 37909 | 180W | 公式 | 価格 |
| Arc B580 | 12GB | 14592 | 34857 | 190W | 公式 | 価格 |
| Arc B570 | 10GB | 13699 | 30804 | 150W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 5060 | 8GB | 13160 | 32303 | 145W | 公式 | 価格 |
| Radeon RX 7600 | 8GB | 10787 | 31685 | 165W | 公式 | 価格 |
| GeForce RTX 4060 | 8GB | 10617 | 28534 | 115W | 公式 | 価格 |
9800X3D搭載PC搭載ゲーミングPC おすすめ5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R61GS

| 【ZEFT R61GS スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H6 Flow White |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61BM

| 【ZEFT R61BM スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61BO

| 【ZEFT R61BO スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P20C ブラック |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R65WH

| 【ZEFT R65WH スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H9 FLOW RGB ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ NZXT製 水冷CPUクーラー Kraken Plus 360 RGB White |
| マザーボード | AMD X870 チップセット ASRock製 X870 Steel Legend WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60AL

| 【ZEFT R60AL スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX4060 (VRAM:8GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Micron製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S200 TG ARGB Plus ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD B650 チップセット ASRock製 B650M Pro X3D WiFi |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| 光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
メモリは16GBか32GBか ― 実際どれくらい必要か
私はRyzen 9800X3Dでゲーミング環境を作るなら、最終的には32GBメモリを選んでおく方が精神的にも楽だと強く感じています。
実際に自分で試し、16GB環境との違いを体験したからこそ言えることですが、容量の不足はゲームや作業の快適さにダイレクトで響くんですよね。
数字上は16GBでも動く。
しかし、実際にやってみると「あと少し余裕があれば」と痛感する場面に出くわすことが多いのです。
私が16GBでテストをしていた時、フルHDの軽量なタイトルでは特に不満はありませんでした。
でも、ある夜に4Kで最新のタイトルを起動し、レイトレーシングを入れ、そのうえで裏でVoiceチャットやブラウザを立ち上げたら、もう動作にぎこちなさを感じてしまったんです。
その瞬間の「やっぱり足りないか」という胸の奥の小さな溜息は、今でもよく覚えています。
一方、32GBに切り替えた時の感覚は驚くほど違いました。
正直世界が変わったと言ってもいい。
ブラウザのタブを大量に開いても気にしなくていいし、SSDに余計な負荷がかかることもほぼない。
ストレスがスッと消えて、CPUやGPUが本来の力を存分に発揮している実感が湧いてきました。
いや、本当に快適なんですよ。
とはいえ、誰だって最初から余裕のある選択ができるわけではありません。
学生や若手社会人にとって、数万円の差は本当に大きいものです。
私も若い頃なら迷わず一旦16GBで始めて、後から増設で対応していたと思います。
ただここで大切なのは、最初にメモリスロットや構成をきちんと考えておくこと。
将来増やせる準備をしておけば、その安心感が心を軽くしてくれるんです。
「後から何とかできる」と思えるかどうか。
これ、思っている以上に気持ちの余裕に直結します。
現在主流のDDR5-5600のモジュールをどう揃えるかと迷う人も多いでしょう。
16GB×2で始めるのか、あるいは最初から32GB×2に振り切るのか。
私は最近GSkillのメモリを選びましたが、ヒートスプレッダのデザインが想像以上に良くて、ケースを閉じる時にちょっとした満足感が残りました。
40代になった今でも、不思議とそういうところで気分が上がるんですよ。
機械なのに、なぜか愛着が湧くんです。
ゲームの進化は容赦がありません。
最新のAAA級タイトルではキャラクターロード時に一気に15GB近いメモリを要求されることがあり、その瞬間に裏で配信ソフトや常駐アプリが動いていたら、もうカツカツ。
そういう場面でNVMe SSDへのスワップが走ると、体感的にすぐ分かるラグが発生する。
だからこそ、動画編集や画像加工を同時にこなすとなったら、32GBはほぼ必須です。
CPU性能やGPU性能にばかり目がいってしまい、メモリを軽く見てしまう気持ちは分かります。
昔の私もそうでした。
経験してようやく気付く。
ちょっと悔しい。
でもその経験が次の選択を賢くしてくれるわけですから、悪いことばかりでもないですね。
よく聞かれる質問です。
確かに余裕を持たせるという点では間違っていません。
ただ、普通の学生や社会人がそこまで必要とするケースはまだ少なく、映像制作や特殊な研究用途の一部に限られます。
だから、16GBか32GBで迷っている人が一足飛びに64GBを検討するのは現実的ではない。
選ぶ段階を飛ばしてしまうのは、無駄が多いと思います。
私はこれから先のゲーム開発の方向性を考えると、テクスチャはもっと重くなり、オープンワールドはさらに広大になり、データの事前読み込みも増えていくのは明らかだと感じています。
その流れを考えれば、16GBはすでに最低限にすぎません。
私も40代になって、これまでパソコンだけでなく色々なモノの選択に悩み、後になって後悔したこともあれば、逆に自分を褒めたくなるような決断もありました。
小さな投資の違いが、長い時間の中で気分や効率に大きな差を生む。
だからこそ財布事情と利用シーンの両方を見ながら決めることが大事だと思います。
16GBで始めるのも悪くない。
ただほんの少し余裕があるなら32GBを選び、長い時間を安心して過ごせる方がいい。
用途別 Ryzen 9800X3D ゲーミングPCおすすめ構成

フルHD中心に遊ぶならコスパ重視の組み方
フルHDでゲームを楽しむ環境を考えるとき、私が一番大切だと実感しているのは「性能とコストの釣り合い」です。
新しいパーツが登場すると、どうしても心が揺さぶられますし、もっと上を見れば際限なく欲しくなってしまう。
ですが、実際に使う場面を思い浮かべれば、冷静にバランスを取る方が長く満足できるんですよね。
私はRyzen 9800X3DとミドルレンジのGPUを中心にした構成こそ、フルHDのゲーム環境を整える上で最適な解だと確信しています。
必要以上の出費をせずに、安心してゲームを楽しめる現実的な答え。
これが一番の魅力です。
GPU選びはやはり最大の焦点になります。
性能のグラフやレビューを目にすれば、誰だってハイエンド製品に惹かれてしまうのは自然なことです。
そのため私はRTX5070やRadeon RX 9060XTクラスのGPUを推しています。
実際、私自身RTX5070を搭載したPCで重めのタイトルを動かしましたが、フルHD設定なら100fpsを軽く超えて快適でした。
余計な支出を避けて満足感を得られる、この感覚は体験して初めて腑に落ちるんです。
メモリの話も外せません。
これは何度も迷ったところですが、DDR5-5600の32GBに落ち着きました。
16GBでは同時作業や軽い配信をしようとしたときに不足が目立ち、逆に64GBは余らせてしまいます。
つまり、32GBが最善の落としどころ。
私は一度だけ16GB構成で試したことがあるのですが、複数のアプリを開いた途端カクつきを感じて「やっぱり足りない」と思い知ったものです。
32GBなら安心感がある。
考える時間を減らせる。
潔く選び切ることで、日々の快適さに直結すると断言できます。
ストレージについては、ここも冷静な選択が物を言います。
Gen.5のSSDは数値上ものすごい性能ですが、実際フルHDゲーミングでどれほど意味を持つかを考えると疑問です。
私は最終的に2TBのGen.4 NVMeに決めました。
起動やロード時間は体感的に十分速く、発熱やコスト面での不安も少ない。
その分の予算をほかのパーツに回した方が良いことを身をもって感じたからです。
使ってからさらに強く思いましたが「分相応の速さこそ日常的に快適」ということですね。
余裕が心地いい。
CPUクーラーも私の中では一度大きく考えが変わった部分です。
昔は水冷に強い憧れを持っていました。
ですが実際に組んでいくうちに、冷却性能とコスト、それにメンテナンスのしやすさを比較して、空冷が最善だと気づきました。
9800X3Dは思っていた以上に発熱が抑えられていたため、NoctuaやDEEPCOOLの信頼できる空冷ファンで十分余裕がありました。
水冷を試したこともありますが、手入れの面倒さやリスクを考えれば私はもう戻りません。
「もう水冷はいらないな」と思うまでに至ったのは、失敗と学びの積み重ねがあってこそです。
静音性の高さも実際の生活環境では思った以上に重要でしたね。
そして意外と悩むのがPCケース選びです。
私は派手に光るデザインに惹かれたこともありましたが、結局行き着いたのは落ち着いた黒ベースのシンプルなケースでした。
派手さがなくても、数年にわたって隣に置くには馴染む方がいい。
オフィスにも家庭の一角にも溶け込む。
通気性さえ確保できていれば性能面で不満もない。
数年後にケースを見て「やっぱり落ち着いた選択で良かった」と思えたことは、私自身の経験の中で強く残る学びでした。
ここまでを振り返れば、私の中で答えは明確になっています。
Ryzen 9800X3DとミドルレンジクラスのGPU。
そこに32GBメモリ、Gen.4 NVMe SSD 2TB、堅実な空冷クーラー、そしてシンプルで冷却性能を備えたケース。
この構成ならたとえ最新の重量級タイトルであってもフルHD環境で滑らかに遊べますし、同時に配信や作業を進めても大きな不満はありません。
全体としての満足度がとても高く、コストの面でも余裕を持った運用ができます。
私はいつも「過剰投資はしない」という鉄則を意識しています。
もちろん高みを目指す行為そのものは悪くありません。
しかし実際の用途を見誤ると、せっかくの投資に見合った満足感を得られなくなる。
後から振り返って「なんでこんなにお金をかけてしまったんだろう」と後悔するのが一番もったいない。
だから私は自分の環境に必要なラインを見極め、そこに自信を持って投資する姿勢を貫いてきました。
それによって無駄のない選択ができ、最終的には自分に合ったベストな環境を手に入れることができたのです。
だからこそ、フルHD前提でゲーミングPCを組むなら、性能とコストのバランスを優先してほしい。
無理に上を追わず、身の丈に合った選択を取ること。
それが最終的に一番の満足につながります。
背伸びしない快適さ。
これが大人の買い物。
最後に強く言いたいのは、Ryzen 9800X3DとミドルレンジGPUが持つ「ちょうどよさ」です。
それ以上を追う必要はない。
安心して楽しめる環境。
それこそが私が求めていたものなんです。
WQHDで学業も配信もこなすための構成
もちろん「最新・最強」という言葉は魅力的ですが、実際に毎日使う道具としてのパソコンは、派手さよりも息の長い信頼感が重要なのです。
40代になった今だからこそ、華やかさに目を奪われた若い頃の自分を少し恥ずかしく思い返すときすらあります。
結局、一番力を入れるべきは「安定した使い勝手」と「自分に合った堅実な構成」だと断言できます。
CPUについては、Ryzen 7 9800X3Dの実力があればまずは十分です。
しかし正直なところ、FHDからWQHDへと解像度を上げれば負荷の質が変わり、CPU単体では力不足を意識する瞬間が必ず出ます。
だからと言って焦る必要はありません。
パソコンは総合力で動く機械。
心臓がいくら丈夫でも、支える血流が滞れば体は動かないし、GPUをしっかり整えない限り快適さは守れません。
私は以前、友人から「CPUだけよければ大丈夫でしょ?」と相談され、「いや、むしろGPUの方が長い目で効いてくるんだ」と答えたことを覚えています。
その選択肢として落ち着くのがGeForce RTX 5070TiやRadeon RX 9070XTクラスのGPUです。
この辺りならコストもまだ現実的な範囲で、同時に配信の安定性を手に入れることができます。
フレームレートが途切れる瞬間に味わうストレス、あの嫌な冷や汗は私自身も体験しました。
配信ソフトが一瞬固まっただけで視聴者が減ってしまい、気持ちが折れてしまうことが本当にあるんです。
そう確信しています。
次にメモリです。
私は学生に相談されたとき、必ず32GBを推します。
そのたびに彼が「やばい、止まった…」と顔を青ざめさせる姿を見ながら、作業効率が気づかぬうちに削られていく現実を目の当たりにしました。
そこから32GBに切り替えた後の安心感の変化は、本当にわかりやすいものでした。
「やっと余裕ができた」と本人が笑顔を見せた瞬間、あの選択が正しかったと心底思ったのです。
64GBももちろん魅力ですが、学生生活に求められる現実的な用途を考えれば、そこまでは不要です。
ストレージについては、PCIe Gen.4対応のNVMe SSDを1TBか2TBにするのが理想的だと思います。
確かにGen.5という響きは最新の魅力に満ちていますが、正直言えばその熱管理の難しさと価格の高さは学生には荷が重すぎると感じます。
私は以前、Gen.5を導入して夏場に処理落ちを繰り返した経験があります。
冷却不足を甘く見てはいけないと心から痛感しました。
結果的にGen.4へ切り替えた瞬間からストレスは消え、それ以来は不具合知らず。
やはり発熱と価格、そして信頼性のバランスを加味したらGen.4が正解です。
冷却面で言えば、私は空冷をおすすめします。
水冷の見た目のカッコよさに惹かれる気持ちは理解できますが、メンテナンスや万一のトラブル時の不安を考えると、学生の方には勧めにくいです。
昔、ある学生から「どうしても水冷がいい」と言われましたが、私は「見た目を取るか安定を取るか、よく考えて」と伝えました。
結局空冷に落ち着いた彼は数年ノートラブルで過ごし、安心した表情を見せてくれました。
その顔を見たとき、「やっぱりシンプルが正義だ」と私も心の奥で納得しました。
ケース選びも甘く見るべきではありません。
私は昔、剛性の高いシンプルなケースを選んだことがあります。
余計な装飾や派手さはなかったけれど、手に持った瞬間から「これを長く使える」と直感しました。
振り返ればあの選択は本当に正しかった。
ガラス張りで一見おしゃれなケースは映えますが、熱で不具合を呼び込んだら結局続きません。
最後に一つ大切なことを伝えたいと思います。
それは「長く安心して使えることこそ、最高のコストパフォーマンスだ」ということです。
派手さではなく、信頼性。
短期間のスペック競争よりも、日々の安定。
私は以前、深夜に締め切り直前の課題を仕上げながら、裏で配信ソフトを動かしていました。
余裕のある構成。
ストレスのない作業環境。
学生生活を支えるのに必要なのは「豪華な最上位機種」ではなく「安心して日常をこなせる頼れる相棒」なのです。
Ryzen 7 9800X3DにRTX 5070TiもしくはRadeon RX 9070XT、32GBのメモリとGen.4 SSD、信頼できる空冷クーラーに堅牢なケース。
この組み合わせを私は心から勧めます。
学業と配信を無理なく両立させ、時には課題も趣味も同じ机の上で進めていける。
そんな安心できる構成こそが、学生にとって最良の選択だと私は確信しています。
4K解像度で最新ゲームを楽しみたい人向け構成
私の答えは、Ryzen 9800X3Dを搭載した構成が最も安心できる選択だと思っています。
なぜならこのCPUは3D V-Cacheを備えていて、GPUに負荷が高まる4K環境でもCPU側の足並みが乱れず、結果としてゲームが驚くほどスムーズに動くからです。
実際に自分で試した際、CPUの心配をせずプレイに集中できる安心感に、思わずうなずいてしまった記憶があります。
つまり、CPUをどう選ぶかが4KゲーミングPCの基盤を形作るのです。
一方で重要なのは、やはりグラフィックボードです。
私はRTX 5070Tiを実機で試し、「Cyberpunk 2077」を強化レイトレーシングとDLSS 4を有効にしてプレイしましたが、そのなめらかさは想像以上のものでした。
その瞬間、長年PCゲームを追いかけてきた自分の胸にも「ついにここまで来たか」と震えるような感情が走ったのです。
RadeonのRX 9070XTもFSR 4を有効にすると特定の場面ではむしろRTXを上回るほどの体感になり、人によってはそちらに強く魅力を感じるでしょう。
結局のところ、このクラスを選べばどちらでも満足できるので、自分のプレイスタイルに合う方を選べばよいのです。
メモリ構成は軽視されがちな部分ですが、4Kで快適さを失わないためには欠かせません。
表面的には16GBで動くゲームも多い一方で、配信や録画、マルチタスクを絡めると途端に苦しい場面が見えてきます。
その時、「ここは節約してはいけない」と強く学びました。
だから32GBは必須と考えていますし、余裕を持たせたい人には64GBをおすすめしたい。
結局のところ、性能の余力が心の余裕につながるのです。
ストレージ選びも地味に大切です。
性能面の数字に目を奪われGen.5 SSDに手を伸ばしたくなる気持ちも理解できますが、現実を見れば発熱対策の難しさや高価さが厄介です。
私はあえてGen.4の2TB SSDを選びました。
Gen.5を追う余裕がある人なら止めはしませんが、今バランスの良さを考えるならGen.4が最適解だと納得しています。
数字より実用、それが大人の選び方です。
CPUクーラーにも人それぞれの価値観が出るところです。
9800X3Dは発熱が穏やかなので高性能な空冷で問題はないのですが、私は静音性を重要視するタイプなので簡易水冷を選ぶことも検討しています。
やり過ぎかなと思いつつも、「冷却に余裕がある」という安心を手に入れると、不思議とゲーム中の没入感が増すんです。
騒音に邪魔されずに深夜の静けさの中でゲームに没頭できるあの時間。
心から満足できます。
PCケースについても触れたいと思います。
若い頃はLEDで光らせるタイプを好んで選んでいましたが、最近は落ち着いた雰囲気を選ぶことが多くなりました。
特に先日触れた木製パネルのケースは感動ものです。
部屋に置いた瞬間、ただの機械ではなく家具の一部として溶け込み、「これなら生活空間に自然に馴染む」と実感しましたよ。
正直、そのとき妻から「悪くないじゃない」と言われたのが嬉しくてたまりませんでした。
やっぱりデザインの力は大きい。
実用性以上に、家庭での存在感を変えるのです。
そして電源ユニット。
軽視してはいけない。
私はこれまで安価な電源で何度か痛い目を見ました。
ある時、突然のシャットダウンでプレイ中のデータを失った悔しさは今でも覚えています。
それ以来、850W以上のゴールド認証を備えた電源を選ぶようになり、ようやく「これなら大丈夫だろう」と安心できるようになりました。
安定こそが全てです。
最終的に、4KゲーミングPCを組む上で揃えておくべき要素は明確です。
Ryzen 9800X3Dに、RTX 5070TiまたはRX 9070XT。
そして適切な冷却機構と納得できるケース、さらに余裕ある電源ユニット。
これだけ揃えた構成が、4Kで最新のゲームを全力で楽しむための答えだと私は実感しています。
もちろん個人の予算や好みで微調整はありえますが、この枠組みを押さえておけば「このゲームは動くのか」と不安を抱えながら遊ぶようなことはもうありません。
本気でやるなら徹底的に整えること。
それが結局は長い安心へつながる。
安心感がある。
Ryzen 9800X3D 自作PCで気をつけたい部品選び


SSDはGen4で十分か、それともGen5を狙うべきか
SSD選びについて迷うことは誰にでもあると思います。
私自身もかつてはそうでしたし、後輩から相談を受けるたびに思い出すのですが、結局行き着いた答えは「ゲーミング用途ならGen4で十分」だということです。
これは理屈だけではなく、私が実際に自分のPC環境で試してきた経験から言えることです。
カタログに並ぶ派手な数値に目を奪われた時期もありましたが、冷静に振り返るとその差が生活の質やゲーム体験をどこまで向上させるのか、そこには必ずしも直結しない現実がありました。
以前、私はGen5 SSDを導入し、自分でも笑ってしまうほどベンチマークを繰り返して数値の伸びに喜んでいました。
しかし同時に、ケース内部の熱対策に手を焼き、ヒートシンクを追加し、エアフローを考え直し、さらには温度計まで導入した経験があります。
わかりやすく言えば「速いけれど扱いが面倒」でした。
ゲーム中に体感できるロード時間の短縮は確かにありましたが、数秒の違いのためにここまで苦労する価値があったのかと、何度も自問しました。
正直、無理してでも最上位を選んでいた若い頃の私に、「落ち着け」と声をかけたくなったんです。
それに比べると、Gen4 SSDは本当にちょうどいいんですよ。
スムーズに動いてくれるし、値段も現実的。
それでいて不安定さを感じたことはほとんどありません。
仕事で毎日使うPCでは「安定して動くこと」が一番の価値だと、この年齢になって本当に実感するようになりました。
トラブルが少ないだけで、心の余裕までつくられるんだと気づいたのです。
学生や若いゲーマーに対して特に伝えたいのは、SSDのグレードにこだわりすぎなくてもいいということです。
Ryzen 9800X3Dのような性能の高いCPUと安定したGPUを組み合わせるほうが確実に効果がわかりやすいし、体感としての満足度が高い。
SSDをGen5にしたからといって、フレームレートが上がるわけではありません。
あくまでデータのやり取りが速くなるだけで、それは一部の用途に限られるのです。
もちろん例外はあります。
私の知り合いで動画編集を仕事にしている人がいますが、その人は本当にGen5をフルに活かしています。
4Kやそれ以上の解像度の映像を同時に何本も扱う場合、転送速度の差が仕事の効率に直結する。
クリエイティブ職には価値があります。
だからといって、私のようにゲームを楽しむ程度の人間が手を出す必要はまったくないのです。
宝の持ち腐れ。
そう心底思いました。
発熱問題も無視できません。
Gen5 SSDは性能が高い分、驚くほど熱を発し、標準クーラーでは到底追いつかないことがあります。
そのせいで速度低下を招くのでは、笑い話にもなりません。
私はその対策に何時間も費やした結果、「ここまでやる意味があったか?」とげんなりしました。
面倒さと出費の増加。
やる気まで奪われかねない。
それに比べてGen4 SSDは静かで手間もかからない。
落ち着きがあるんです。
特に価格面では大容量のGen4 SSDが手頃になってきましたから、2本組み合わせてRAIDを組むといった工夫も可能です。
こうすることで速度も十分に稼げるし、コストパフォーマンスは抜群です。
私も過去に試したことがありますが、この方法は期待以上に快適でした。
使いやすさが全然違うんですよ。
現在のAAAタイトルでGen4以上を前提とするものは出始めてはいますが、Gen5でなければ動かないという話は聞きません。
業界全体を見ても「普及帯で動くこと」を前提にゲーム設計はされています。
ならば、無理して最新規格を追いかける必要はないでしょう。
まだまだGen4で十分に戦えます。
では、最終的にどうするべきか。
私自身の答えは明確です。
もしRyzen 9800X3DでゲーミングPCを組むのならば、Gen4 SSDを容量大きめで確保しておく。
それでいいんです。
その確信があります。
Gen5を選ぶ意味がまったくないとは言いません。
しかし、自分の使い方と照らし合わせることが必要です。
欲を出して見た目のスペックだけで選ぶのは、結局あとで苦労や出費に跳ね返ってくる。
パーツ選びは身の丈に合わせることが大切だと痛感しました。
最適解はシンプル。
Gen4で決まり。
声を大にして伝えたい言葉です。
ゲームを快適に遊ぶ環境とは、余計な心配ごとを取り除いて「ただ楽しめる状態」にすることだと、私は心の底から思います。
自分の体験を通して得たメッセージは一つ。
Gen4 SSDを選んでおけば失敗はしない。
そして残りの予算で、自分が心から楽しいと思える部分に投資する。
SSD規格一覧
| ストレージ規格 | 最大速度MBs | 接続方法 | URL_価格 |
|---|---|---|---|
| SSD nVMe Gen5 | 16000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen4 | 8000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD nVMe Gen3 | 4000 | m.2 SSDスロット | 価格 |
| SSD SATA3 | 600 | SATAケーブル | 価格 |
| HDD SATA3 | 200 | SATAケーブル | 価格 |
9800X3D搭載PC搭載ゲーミングPC おすすめ5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R61FA


| 【ZEFT R61FA スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | INWIN A1 PRIME ピンク |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850I Lightning WiFi |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R64M


| 【ZEFT R64M スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9070XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Fractal North ホワイト |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 DIGITAL WH |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60TB


| 【ZEFT R60TB スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5080 (VRAM:16GB) |
| メモリ | 64GB DDR5 (32GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | LianLi O11D EVO RGB Black 特別仕様 |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
パソコンショップSEVEN ZEFT R66T


| 【ZEFT R66T スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5060Ti 16GB (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5000Gbps/3900Gbps KIOXIA製) |
| ケース | LianLi A3-mATX-WD Black |
| CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー ML 240 Core II Black |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 650W 80Plus BRONZE認証 電源ユニット (COUGAR製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61AR


| 【ZEFT R61AR スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 192GB DDR5 (48GB x4枚 Gskill製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7400Gbps/7000Gbps Crucial製) |
| ケース | Antec P10 FLUX |
| CPUクーラー | 空冷 サイズ製 空冷CPUクーラー SCYTHE() MUGEN6 BLACK EDITION |
| マザーボード | AMD X870 チップセット GIGABYTE製 X870M AORUS ELITE WIFI7 ICE |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Pro |
電源ユニットの容量と認証 ― どのくらいを選べば安心か
Ryzen 9800X3DのようなCPUと最新のGPUを組み合わせようと考えているなら、電源は単なる部品ではなく、安定稼働を左右する屋台骨そのものです。
失敗談を踏まえてお伝えすれば、余裕のある容量と信頼できる効率認証を持つ電源を選べば、いらぬトラブルを回避し、長期的に安心して使えるというのが私の結論です。
派手さはありませんが、痛い目を見てきた私には、電源ユニットは実感をもって「過小評価してはいけない存在」だと断言できます。
私が若いころは、知識不足もあって定格ギリギリの電源を使っていました。
ある日、動画配信中にPCが突然リセットされ、その瞬間の心臓が凍りつくような焦りは今でも記憶に残っています。
視聴者に謝る自分の声が震えていたのを思い出しますよ。
正直、安物に飛びついた浅はかさを恥じました。
悔しさと後悔が入り混じった夜。
まさに「安物買いの銭失い」そのものでした。
そこで学んだのは、数千円を節約した代償はあまりにも大きいという事実です。
それ以来、容量に関してはどんなに予算を削る必要があっても絶対に妥協しないと心に決めました。
例えばRyzen 9800X3DにミドルハイのGPUを組み合わせるなら750Wクラス。
さらにハイエンドGPUを加えるなら850W以上が必要です。
確かに750W以下でも「動いた」と言えるケースはあるでしょうが、瞬間的な消費電力の跳ね上がりを吸収できず、フリーズや強制再起動につながるリスクを何度も目にしました。
あんな不安定な環境に身を置くのは無駄なストレスでしかありません。
だから私は言い切ります。
効率認証についても、数字やラベルだけの問題ではありません。
それがゴールド認証電源に変えただけで、静音性が高まり、発熱も抑えられ、心身ともにラクになったのです。
ただの省エネ商品だと思っていたのに、ここまで日常の生活感に影響するとは思いませんでした。
効率が高いということは、電気代の節約どころか、快適な居住環境にも直結するという学びでした。
最近、私はRTX 5070TiクラスのGPUを導入しました。
CPUの使用率が跳ね上がる場面では特に顕著で、750Wぴったりでは不安定になるのが見えてしまいました。
そこで850Wを選んでいた私は、初めて「数値上の最低条件」ではなく「実体験に基づいた余裕」が必要だと腹に落ちたのです。
数字はあくまで参考。
身をもって学んだ現場感です。
ケーブルの構造や扱いやすさも同じく無視できません。
フルモジュラータイプを使って配線を整理したときのスッキリ感は、パソコンを単なる機械から「自分で手をかけて育てる道具」に変えてくれます。
エアフローが良くなればホコリも溜まりにくく、冷却効果も上がり、結果としてすべてが安定へとつながります。
昔なら「別に見えない部分だし…」と軽視していたのに、今は毎回清掃するたびに「ここをきちんとやってよかった」と思わず口に出すほどです。
年齢を重ね、細部への目配りが生活に直結することを知りました。
「結局どれを選べばいいの?」と友人に聞かれたら、私ははっきり答えます。
Ryzen 9800X3DにミドルレンジGPUなら750W以上、ハイエンドGPUなら850W以上。
そして必ずゴールド認証以上。
たったそれだけでトラブルに悩まされる確率は大きく減少します。
これは私の経験から出てきた、誤魔化しのない答えです。
今では私も850Wのプラチナ認証モデルを使っています。
「ここまで要る?」と言われるかもしれません。
でも実際は逆で、「この余裕があったからこそPCの安定が手に入った」と確信しています。
ゲーム中に不意に電源が足りなくなる心配がゼロになり、妙なトラブルに時間を奪われる生活からようやく解放されました。
これからGPUの消費電力はさらに増していくでしょう。
だから私は次の組み換え時には1000Wクラスを見据えています。
人によっては「さすがに余裕を持ちすぎじゃないか」と笑うかもしれません。
それでも私は払う価値がある保険料だと思います。
後悔するくらいなら前もって守りを固めたほうがいい。
そう信じています。
大切なのは一つ。
Ryzen 9800X3Dを使うなら必要容量を守り、効率認証の高いモデルを選び、配線管理まで考える。
これさえ意識すれば、PCは安定し、自分の投じた金額と時間に見合う成果を返してくれるのです。
逆に妥協すれば、せっかく高いCPUもGPUも本領を発揮せず、結局は自分が損をする。
電源を甘く見てはいけない、と。
安心できる選択。
信じてよかったと心から言える瞬間。
そのすべてを支えているのが電源なのです。
これが、40代になった私がようやく手にした揺るぎない答えです。
PCケース選び 静音性か冷却重視かで分かれるポイント
PCケースを選ぶときにまず最初に頭を悩ませるのは、冷却性を重視するべきか、それとも静音性を優先するべきか、この二択だと私は思います。
Ryzen 9800X3Dのような高性能なCPUを搭載した場合、真っ先に感じるのは熱の上昇が早いことです。
しかし逆に冷却にこだわりすぎると、今度は常にファンの音が耳に入り込み静かな作業環境を壊してしまう。
そのため、最終的には自分がどうPCを使いたいのか、そこで必要な要素が冷却か静けさかを判断するしかありません。
これが結局のところ私が行き着いた考え方です。
日常的な資料作成や動画視聴においても、大きな問題は全くなかった。
特にテレワークが中心になった時期、一日中パソコンの前に座る環境では「やっぱり静かさは正義だな」と痛感しました。
静かな環境だからこそ書類と向き合う集中力が増し、頭の中の整理もスムーズになる。
これは実際に体験してみて初めて理解できる利点でしたね。
一方で、冷却重視のケースはまた違った安心感を与えてくれます。
フロントパネルを思い切ってメッシュにしたモデルや、派手さを抑えて風の流れを最優先に設計されたケースは、CPUやGPUの温度を驚くほど安定させます。
まさにスポーツ選手が試合終了までスタミナを維持し続けるような安定感を感じました。
集中してプレイしているときに余計な不安が一切頭をよぎらないのは、ゲーマーにとってまさに理想の環境です。
静けさと冷却。
どちらも取捨選択が難しいのが現実です。
最近ではデザイン性を高めながら冷却効率もある程度確保できるケースも出てきました。
例えばウッドパネルを採用したものや、内部の気流設計を工夫して両立を目指す製品も登場しています。
しかし正直に言えば、どちらの性能も本気で満足できるレベルで両立しているケースはまだ少ない。
特にRyzen 9800X3Dを軸にハイエンドGPUを搭載する場合は、夏場の長時間稼働で冷却をないがしろにすることが致命傷になりかねません。
だから私は「冷却重視が安全策」と断言します。
それでも、もし静かな環境での集中作業が中心ならば、迷わず静音ケースへ投資するべきです。
ここでの選択が、体験を大きく左右する分岐点なのです。
使用する前はケースの違いが日常をこんなに変えるなんて想像もしていませんでした。
CPUやGPUの性能差は分かりやすい一方で、ケースは軽視されがちです。
しかし実際に長い時間を過ごしてみると「なるほど、私にはこっちのタイプが合っているのか」と腑に落ちるのです。
環境そのものが作業や余暇に直結する以上、PCと長く付き合う大人にはケース選びこそ慎重に行ってほしいと心から思います。
私は冷却を優先するスタイルです。
理由は明確で、ゲーム体験に妥協したくないからです。
ちょっとしたフレーム落ちや映像の引っ掛かりが積み重なると、楽しさは一気になくなります。
だからこそ冷却性能に優れたケースを選ぶのが私にとっては必須でした。
これが私の考えであり、仕事後の楽しみでもあるゲームをきちんと支えてくれる安心の要素です。
静音を選べば生活そのものが落ち着き、冷却を選べば性能維持に不安がなくなる。
用途の違いに応じて正解は変わるのです。
これが一番合理的な決め方ですし、最終的に納得感のある選択につながると思います。
私の場合は冷却を選んだことで安心感が得られました。
これは「自分のPCをどんな時間に使い、どう過ごしたいか」を意識した結果でした。
だからこそ一人ひとりが、自分にとって手放せない要素を問い直さなくてはならない。
そこに本当の正解があるのです。
集中力が高まると仕事もはかどる。
冷却が安定していればゲームは快適に続けられる。
それぞれに確かな利点があります。
私が経験から学んだキーワードは、この二つに尽きます。
静けさか、冷却か。
この分岐点が未来の満足度を決めてしまう。
だから迷う時間すら意味があるのです。
安心感。
信頼感。
最終的に私が辿り着いた答えを一言で言えば、この二つの大切さでした。
Ryzen 9800X3D 搭載PCに関するよくある疑問


学生が自作PCに挑戦するのとBTOで買うのとではどちらが得か
学生が初めてゲーミングPCを買うなら、私はやはりBTOパソコンを強く勧めたいと思います。
自作に興味がある気持ちも理解できますが、それ以上に「安心してすぐ使える」という利点は、限られた時間とお金しかない学生にとって非常に価値があることだと感じるのです。
私自身、これまで何度も同僚や後輩が自作でつまずき、結局コストも時間も想定以上にかかってしまった事例を見てきました。
そうした経験を踏まえると、一台目はBTOで確実にスタートを切った方がいいと心の底から思うのです。
しかし実際にやってみれば、ケースサイズを間違えたり、CPUクーラーの取り付けで手こずったり、しまいには新しい部品を買い足す羽目になったりと、慣れない人ほど余計なお金がかかります。
さらには運悪くパーツを壊してしまえば、出費はどんどん膨れ上がります。
現実には「安く済むはずが逆に高くついた」というパターンが少なくないんです。
恐ろしくもあり、そして不思議とよくある話です。
この点、BTOパソコンには保証とサポートがついてきます。
私は以前、仕事で使っていたPCが急に電源を入れてもまったく反応せず、頭を抱えたことがありました。
慌てて販売元の窓口に連絡したら、すぐに修理対応してくれて「ここなら任せても大丈夫だ」と心底安心したのを今でもはっきり覚えています。
心配せずに使えるという安心感、これが一番大きい。
もっとも自作にも、唯一無二の楽しさがあるのは確かです。
私も学生時代に初めてGPUを選ぶときのワクワク感や、ケース内のエアフローを工夫して試行錯誤した記憶は、今でも宝物のように残っています。
電源を入れて画面がついた瞬間の達成感、それは他のなににも代えがたい体験でしたね。
だから「挑戦してみたい」という学生の気持ちを否定するつもりはありません。
むしろ、強い想いがあるなら挑むのも良い選択肢だと思います。
しかし冷静に考えてみてください。
自作は挑戦の場であると同時にリスクの場でもあります。
授業やゼミのレポート提出、あるいはオンライン講義など、絶対にPCを使わざるを得ない局面は学生生活に確実に訪れます。
そのときに「電源が入らない」「ブルースクリーンが出る」という状況に直面したら、目も当てられません。
将来の勉強や進路に関わる以上、最初の一台では冒険しない方が無難だと私は思うのです。
最近のBTOパソコンは驚くほど進化しています。
冷却性能と静音性のバランスがとれた設計が最初から組み込まれており、内部のケーブル取り回しやファン配置なども専門家が手を入れているため、使い始めから快適さを実感できます。
デザイン性の高いケースを選ぶこともでき、透明パネルでLED演出を楽しむようなモデルも増えています。
つまり、余計な苦労をせずに見た目も性能も満たされたPCを手にできるわけです。
この「すぐに満足できる環境」が揃うことは、本当にありがたいことです。
私自身も経験がありますが、自作の時にはネジ穴が合わなくて「おい、どこに刺すんだよ!」と一人でぶつぶつ文句を言いながら格闘する時間がありました。
時間だけが過ぎていくあのストレスは、今思い返しても苦笑いするほどです。
学生は勉強やアルバイトなど、やることが山ほどあります。
その限られた時間を「組み立ての苦労」に費やしてしまうのは本当にもったいない。
効率重視で行くべきです。
もちろん、情熱を胸に抱いて自作へ挑む学生もいるでしょう。
その場合は最新のCPUやGPUを調べ、相性をきちんと確認して、ケースの大きさや電源容量も慎重に選ぶことで、大きな失敗は避けられると思います。
実際、適切な手順さえ踏めば問題はほとんど防げますし、学びの効果も絶大です。
手を動かした分だけ知識が身につきますし、トラブルを自力で解決できたときの喜びも格別です。
ただし、それは二台目、あるいは余裕がある時期に取り組むべき挑戦ではないでしょうか。
だからこそ私は声を大にして言いたい。
最初の一台はBTOにするのが正解です。
そして自作は次のステップとして楽しめばいい。
安全にスタートを切れる安心感と、その後に自分の手で作る面白さを段階的に味わう。
この流れこそ、学生にとって一番ふさわしい選び方だと私は確信しています。
これが現実的な道筋だと、何度も経験を重ねてきた私の胸から自然と出てくる言葉です。
失敗の少ない選択をして生活を守り、その上で新しい挑戦を楽しむ。
これ以上に満足度の高い方法はないと私は思いますね。
安心できる第一歩。
Ryzen 9800X3Dは大学のレポートや研究用途にも活かせるか
Ryzen 9800X3Dを学生が使う意味を考えると、私は「十分に学業や研究に活かせる」と断言します。
一見するとゲーミングに特化したCPUというイメージが強いかもしれませんが、実際にはその枠だけでは収まらない力を秘めています。
私は以前、夜遅くまで統計データを処理しながら「どうしてこんなに時間がかかるんだ」とイライラした経験がありました。
大学生活を振り返れば、PCを使うのはレポート作成だけでは終わりません。
研究室に配属されると、多くの学生がプログラムを走らせたり解析をしたり、膨大な実験データを処理したりすることになります。
私自身も学生時代、何度も回したシミュレーションが夜明けまで終わらず、結局寝不足で授業に向かったことがありました。
正直、その時に高性能なCPUがあったなら、余計な不安や焦りを感じずに済んだはずです。
能力の高さは時間の余裕に直結します。
これは学びの質に直に影響するのです。
最近の学生が直面している課題は、さらに難易度が上がっています。
ドローン撮影した膨大な動画を処理したり、AIを用いて画像診断のモデルを動かしたり、研究内容が高度化している現実があります。
その中で9800X3Dの大容量キャッシュは確実に役立ちます。
集中し続けられる環境。
これはとても重要な価値です。
さらに大事なのはGPUとの連携です。
多くの学生がゲーミング用に憧れる高性能GPU、実は研究にもそのまま役立ちます。
特にディープラーニングのフレームワークを走らせるとき、GPUの力と同時にCPUがいかに効率よく支えられるかが肝になります。
私はGPU計算を研究室だけに依存していた頃、利用時間を奪い合う状況に何度も苦しみました。
自宅で自由に回せる環境があること。
用途は学業や研究に限りません。
大学生活の実態はもっと幅広いのです。
ゼミや学会での発表資料作成、デザイン系ソフトの活用、共同研究で必要なデータ整理といったタスクが次々に押し寄せてきます。
私は性能不足のノートPCで資料を作ろうとして固まった経験が何度もあります。
スライドの修正だけでこんなに時間がかかるのかと頭を抱える場面は本当に多かった。
余裕ある性能があれば、その苛立ちから解放され、気持ちもぐっと楽になります。
余裕。
そして忘れてはならないのが静音性と安定性です。
深夜に作業するとき、ファンの騒音で集中力が途切れる。
私は過去にその音が気になって、仕事がまったく進まなかった経験があります。
この静けさが作業効率に直結するという点は決して小さなことではありません。
落ち着いた環境は、心を守ってくれるものなんです。
ストレージの選び方も軽視してはいけません。
私は2TB以上のNVMe SSDを搭載する構成を強く推奨します。
ストレージに余裕があることは、見えにくいけれど確実に作業の安心感へとつながります。
将来に備えて拡張できる仕組みを整えておくことも大事です。
そして長期的な視点。
今は生成AIや高解像度の動画処理が当たり前になっています。
学生のうちから「できる環境かどうか」で学びの幅が変わります。
9800X3Dを贅沢だと感じる人もいるでしょうが、私は逆にコスト以上のリターンを見込める投資だと考えます。
長く使える環境を整えば、余計な買い替えコストや不満を抱かずに済みます。
長期的に見て無駄のない選択なのです。
だから私は言います。
このCPUは間違いなく大学生活のパートナーになります。
学びも、研究も、遊びも、一台で全部支えられる。
その安心感は学生の成長に大きく貢献するでしょう。
9800X3D搭載PC搭載ゲーミングPC おすすめ5選
パソコンショップSEVEN ZEFT R60HT


| 【ZEFT R60HT スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (32GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット MSI製 PRO B850M-A WIFI |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R60WH


| 【ZEFT R60WH スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070Ti (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H9 FLOW RGB ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ NZXT製 水冷CPUクーラー Kraken Plus 360 RGB White |
| マザーボード | AMD X870 チップセット ASRock製 X870 Steel Legend WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R63Q


| 【ZEFT R63Q スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9070XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) SSD SSD 2TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Antec P10 FLUX |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット GIGABYTE製 B850 AORUS ELITE WIFI7 |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (CWT製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R65D


| 【ZEFT R65D スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | Radeon RX 9070XT (VRAM:16GB) |
| メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | NZXT H9 FLOW RGB ホワイト |
| CPUクーラー | 水冷 360mmラジエータ NZXT製 水冷CPUクーラー Kraken Plus 360 RGB White |
| マザーボード | AMD X870 チップセット ASRock製 X870 Steel Legend WiFi |
| 電源ユニット | 850W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT R61GE


| 【ZEFT R61GE スペック】 | |
| CPU | AMD Ryzen7 9800X3D 8コア/16スレッド 5.20GHz(ブースト)/4.70GHz(ベース) |
| グラフィックボード | GeForce RTX5070 (VRAM:12GB) |
| メモリ | 16GB DDR5 (16GB x1枚 クルーシャル製) |
| ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:7250Gbps/6900Gbps WD製) |
| ケース | Thermaltake S100 TG |
| CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ASRock製 B850M-X WiFi R2.0 |
| 電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
| BlueTooth | BlueTooth 5 |
| OS | Microsoft Windows 11 Home |
配信や動画編集に使うなら、どれくらいの性能が必要か
仕事でも趣味でも使うパソコンは、最初に多少余裕を持って構成を考えておいた方が圧倒的に安心できると、私は強く感じています。
後から「しまった」と思ってパーツを買い足すよりも、最初から備えをしておいた方が結果的に出費も手間も抑えられることが多いのです。
特に動画編集や配信のように負荷の高い用途を想定するなら、CPUはもちろんですが、メモリやストレージ、GPUにもしっかりと力を入れるべきだと思っています。
結局、バランスを無視して一つの要素にだけ頼ろうとすると、思ったような快適さは得られない。
それを身をもって経験してきました。
ところが、実際に配信と並行して4K動画編集を始めてみると、あっという間にメモリが枯渇してしまったのです。
その瞬間に画面がカクカクと重くなり、作業が全然前に進まない。
あのときの焦りは今もはっきり覚えています。
「なるほど、そんなに違うのか」と半ば呆れるくらいの落差でした。
だから今では最低でも32GBを積むのが自分の中での常識になっています。
妥協したら痛い目を見ると分かっているからです。
動画編集をしていると、大量のキャッシュを扱うため、あっという間に空き容量が消えていきます。
私も初めは1TBのSSDで何とかなるだろうと思っていたのですが、あるとき作業途中で容量が尽き、保存もレンダリングも進まなくなって呆然としました。
それから思い切って2TBのNVMe SSDを導入したのですが、それ以来プレビューの再生が途切れないし、レンダリング時のストレスも見事になくなったのです。
PCIe Gen.5のSSDも試してみたい気持ちはありますが、どうしても価格と発熱が気になります。
毎日の作業環境として考えれば、私は今のところGen.4で十分だと判断しています。
無茶して背伸びする必要はない、と自分に言い聞かせています。
そしてGPUの存在。
これを軽視すると痛い思いをします。
私はRTX5070Tiを導入してから初めて、配信中の映像がここまで安定するのかと実感しました。
画面の乱れも減り、フレーム落ちもほとんど気にならない。
正直「もっと早く買っておけばよかった」と思いました。
グラフィックス性能だけでなく、配信のためのエンコード性能も十分に備わっていると、最終的に仕上がる映像の品質に確実に直結する。
やっぱり機材は嘘をつきません。
これは強く断言できます。
ただ、性能ばかり追い求めても落とし穴があります。
長時間の作業を続けると、冷却不足が浮き彫りになってくるのです。
私の場合、ある日長時間レンダリングをしていたら、CPU温度がじわじわと上がり続け、最終的にソフトが落ちてしまいました。
あのときは冷や汗をかきました。
本当に怖かったです。
それがきっかけで空冷から水冷に切り替えましたが、結果的に温度が落ち着いて静音性も高まり、ようやく安心して作業に集中できるようになりました。
集中力は環境に左右される。
これは痛感しましたね。
ケース選びも大事です。
私は以前、見た目に惹かれてガラス張りのケースを使っていたのですが、どうしてもエアフローが貧弱で熱がこもりました。
音もうるさくなり、正直嫌になった記憶があります。
そこで次は木製パネルタイプのケースを思い切って選んでみたのですが、これが驚くほど快適で落ち着いた雰囲気を作ってくれたのです。
デザイン性も大事ですが、使っていてホッとできることが一番の価値なのかもしれません。
意外な発見でしたが、私にとっては宝物のような気づきでした。
CPUが高性能であることは間違いありません。
ただ、それを活かすためには全体の調和が必要だというのが、今私が持っている考えです。
メモリを32GB以上、2TBのSSD、そしてRTX5070Ti以上のGPUを用意する。
これらをそろえたときに初めて、Ryzen 9800X3Dの持つ力をフルに引き出せる。
私はこう思います。
パソコンの環境作りは車の整備に似ていると。
エンジンだけが立派でも、タイヤやブレーキ、サスペンションが貧弱ならまともに走れない。
それと同じで、CPUがいくら優秀でも、メモリや冷却が伴っていなければ宝の持ち腐れです。
そう思ったときに「なるほど、そういうことだったのか」と心底納得しました。
きれいな映像を届けたい。
スムーズに編集をしたい。
そうした願いを叶えるためには冷却やエアフローに余裕を持ち、ストレージも潤沢にしておく。
妥協すれば作業のたびに不満が積もってしまう。
だから私は声を大にして言いたい。
環境に投資することが、長く快適に使い続けるための唯一の正解なのだと。
これからも私は、パソコンの性能と同じくらい周辺環境が大切だということを人に伝えていきたいです。
派手さや一時的な話題性よりも、長く寄り添ってくれる安定感。
ここに尽きるのです。
安心できる環境が欲しい。
信じられる一台に出会いたい。